
胸椎とは?「背中の中心」の骨の構造と役割
胸椎の位置・骨の数(12個)・肋骨との関係・可動性の特徴
「背骨」と聞くと腰や首を思い浮かべる方が多いですが、実はその真ん中あたりにあるのが**胸椎(きょうつい)**です。胸椎は全部で12個あり、背中の中心から腰にかけて縦に並んでいます。肋骨はそれぞれ胸椎と関節を作り、胸郭(きょうかく)というかご状の構造を形づくるため、呼吸のたびにわずかに動く仕組みになっていると言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/back/back-spine-pain/)。
首の骨(頸椎)や腰の骨(腰椎)に比べて、胸椎は可動性が小さい特徴があります。これは肋骨と連動しているためで、背中全体の安定性を高める役割を担っているとされています。その一方で、動きが少ない分、硬さやこりが生じやすい部分でもあるのです。
胸椎の役割(姿勢維持・呼吸との関係・背骨全体の連動性)
胸椎の一番大きな役割は、体をしっかり支えることだと言われています。首から腰までの背骨全体がスムーズに連動することで、姿勢をまっすぐに保ちやすくなるのです。もし胸椎がずれると、首や腰にも負担がかかることが多いと説明されています。
さらに、胸椎は呼吸とも深く関わっています。肋骨と一緒に胸郭を広げたり縮めたりすることで、肺が十分に膨らみやすくなるのです。つまり、胸椎の柔軟性は呼吸のしやすさにも影響している可能性があると考えられています。
胸椎が固まることで生じる影響(肩・腰・呼吸など)
では、胸椎が固まってしまうとどうなるのでしょうか。よくあるのは、背中の張り感や肩の重さにつながるケースです。胸椎が動きづらくなると、肩甲骨や腰に負担がかかりやすいと指摘されています。
また、胸椎と肋骨の動きが制限されると、胸が十分に広がらず、呼吸が浅くなることもあるそうです。その結果、疲れやすさや集中力の低下を感じる方も少なくないと聞きます。普段から胸椎を意識して柔軟に保つことが、体全体の快適さにつながると言われています。
引用元:
#胸椎 #背中の痛み #姿勢改善 #呼吸と背骨 #体のしくみ
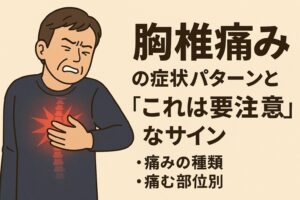

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています






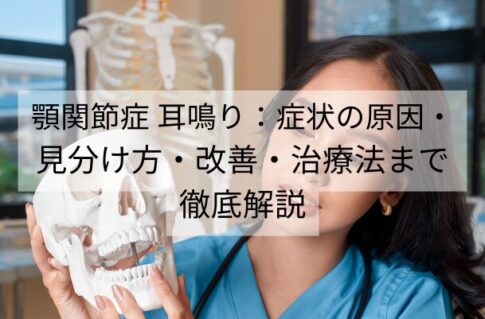
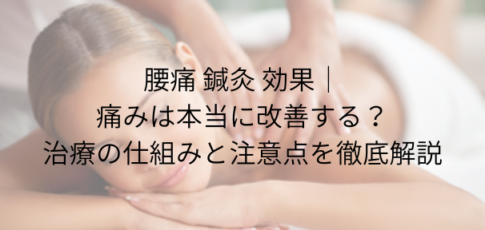
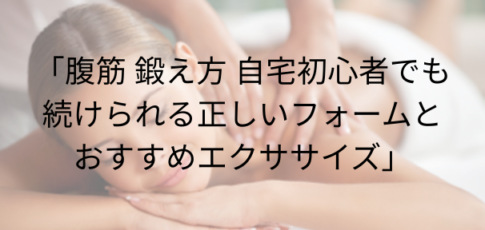
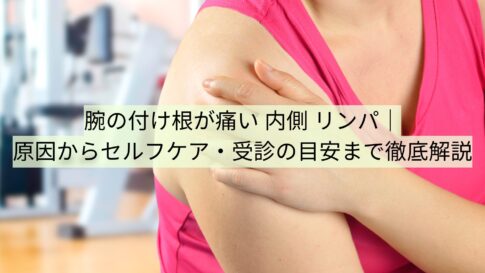


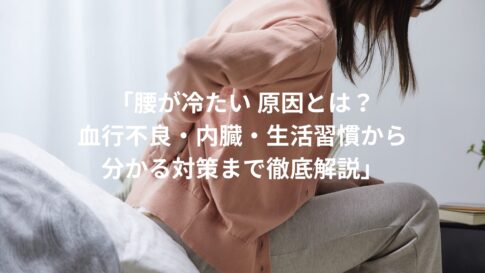




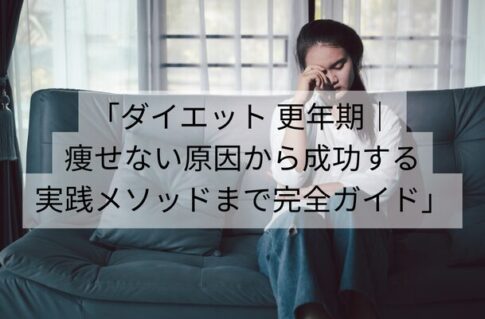
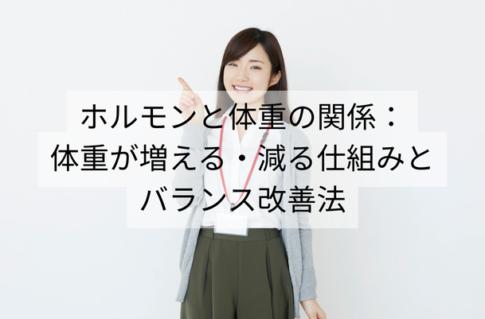
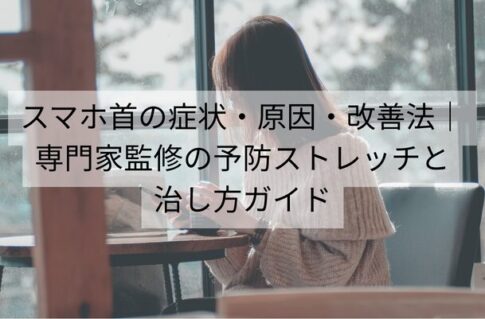
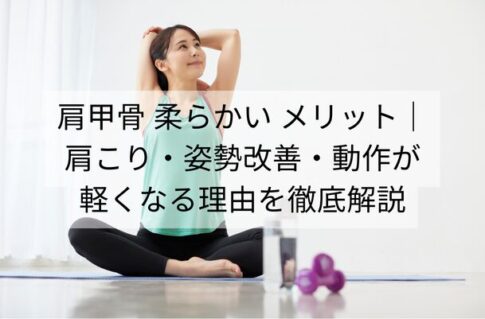
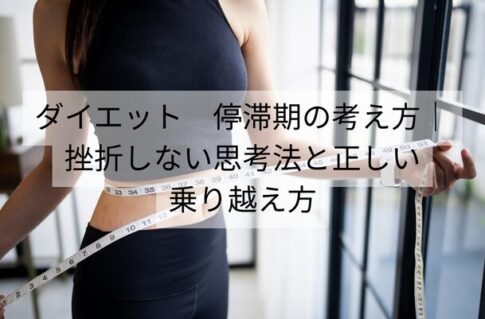




コメントを残す