1.休養の本質を理解する:なぜ「休むだけ」では十分でないのか
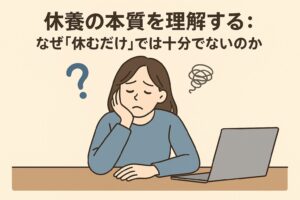
「ちゃんと寝てるのに、なんでこんなに疲れてるんだろう…」
こんな風に感じたこと、ありませんか?
実は、「休養=寝ること」と思い込んでいる方はとても多いようです。でも、それだけでは疲れが取れないケースがあるとも言われています(引用元:https://stretchex.jp/5863)。
というのも、人の疲れには「体の疲れ」だけでなく、「心の疲れ」や「頭の疲れ」、さらには「人間関係による気疲れ」など、さまざまな要素があるからです。
本当に必要なのは“多面的な休養”だった
「じゃあ、どうすればちゃんと疲れが取れるの?」
こう思った方もいるかもしれません。
実は、休養には “体を休める休養” だけでなく、“心や感情、感覚を整える休養” も含まれるとされています。これは「7つの休養」という考え方にも見られるもので、単に寝る・横になるだけでは回復できない、というのが最近の見解です(引用元:https://stretchex.jp/5863)。
たとえば、寝ても寝ても疲れが取れないという人は、「感情の疲労」や「情報の過多」によるストレスが原因になっていることもあるそうです。
休養は“引き算”だけじゃない
「休む=何もしない」だけではないって、ご存じでしたか?
じつは、積極的に散歩をしたり、自然の中で深呼吸したり、人と話して心が軽くなったりするのも、立派な休養の一つなんです。これを「積極的休養」と呼ぶこともあります。
つまり、休養とは「活動を止める」だけでなく、「心地よい刺激を与えることで整える」ことでもあるというわけです。
自分に合った休養を見つけることがカギ
休養にも“個人差”があると言われています。
ある人には音楽が癒しになっても、別の人には静かな時間の方がリフレッシュになることも。
だからこそ、自分の疲れ方やストレスの傾向を知って、それに合った休養スタイルを見つけることが重要なのです。
まとめ
「休んでいるのに疲れが取れない」と感じるときは、「休養の質」が合っていないサインかもしれません。
ただ眠るだけではなく、心や感情、感覚、さらには社会的なつながりまで意識した休養をとることが、根本的な回復につながると考えられています。
まずは「自分にとっての本当の休養って何だろう?」と見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。
#休養の本質
#疲れが取れない
#睡眠以外の休養
#7つの休養
#積極的休養
2.7つの休養タイプとその具体的アプローチ
「休養って、ただ寝るだけじゃないんですね」
こんな言葉をよく耳にします。確かに、ぐっすり眠ることも大切ですが、それだけで疲れが取れないと感じる人も多いようです。実際には、休養にはさまざまな“種類”があると言われており、「7つの休養タイプ」という考え方が注目されています(引用元:https://stretchex.jp/5863)。
7つの休養とは?それぞれのタイプと実践アイデア
では、その7つの休養とは何でしょうか? それぞれに合ったアプローチを見ていきましょう。
1. 身体的休養(Passive & Active)
これは多くの人がイメージする休養ですね。
・質の良い睡眠
・ストレッチや軽い運動(アクティブレスト)
どちらも体の疲労回復に役立つとされています。
2. 精神的休養
「何も考えたくない…」というときは、脳や思考の疲れかもしれません。
・深呼吸
・5分間の瞑想
・スマホから離れる「デジタルデトックス」も効果的と言われています。
3. 感覚的休養
現代人は光・音・画面の刺激を受けすぎているとも言われています。
・静かな空間でぼーっとする
・アロマや自然音でリラックスする
このような方法で感覚のリセットを目指します。
4. 創造的休養
何かを「作る」「感じる」ことで、心が満たされるタイプの休養です。
・絵を描く、音楽を聴く
・自然の景色を見る
刺激を受け取ることで“心の栄養”になるとされています。
5. 感情的休養
誰かに気を使いすぎていませんか?
・信頼できる人に本音を話す
・感情を日記に書き出す
感情を溜め込まないことがポイントのようです。
6. 社会的休養
「1人の時間」が必要な人もいれば、「誰かと過ごすこと」で安心する人も。
・気心の知れた人との会話
・SNSから離れてみる
自分にとって心地よい関係を見直すことが休養になるとも言われています。
7. スピリチュアル休養
「生きがい」や「つながり」を感じられる瞬間ってありませんか?
・自然の中に身を置く
・価値観の合うコミュニティに参加する
内面と向き合う時間が回復につながることもあります。
自分に合った休養を“選んで”取り入れる
「どれが自分に合ってるのか、正直わからない…」という方も安心してください。
大切なのは、“全部やらなきゃ”ではなく、今の自分に足りていない休養を見つけて、1つずつ試していくことです。
たとえば、頭がパンパンなら「精神的休養」を、周囲に気を使いすぎて疲れたなら「感情的休養」から取り入れてみましょう。
#7つの休養
#休養の種類
#感情的休養
#感覚的休養
#積極的休養
3.今日から使える休養の取り方:短時間〜長期プラン別ガイド

「忙しくて休む時間なんてないよ…」と思っていませんか?
実は、ほんの数分でも“正しく休む”ことで、心と体が軽くなると言われています(引用元:https://stretchex.jp/5863)。ここでは、働きながらでも使えるミニ休養から、休日のリセット方法、そして長期的な習慣づくりまで、実践しやすい形で紹介します。
スキマ時間で使える“ミニ休養”
「5分も休めない」と感じる人ほど、ミニ休養の効果を実感しやすいとも言われています。
-
目を閉じて深呼吸するだけ
-
首や肩を回すストレッチ
-
好きな香りを嗅ぐ
-
トイレついでに背伸びする
たった数十秒でも、交感神経の高ぶりをゆるめる時間になるそうです。会議の前や移動中でも取り入れやすく、「切り替えの儀式」として使っている人もいるようです。
週末・休日におすすめの“中休養”
「寝だめしたのに疲れが残る…」という声も多いですが、休日の休養は“回復+刺激のバランス”が鍵だと言われています。
例えばこんな過ごし方があります:
-
自然の中を散歩する
-
カフェで読書や手帳タイム
-
温冷交代浴やサウナでリセット
-
料理や手仕事で“無心になれる時間”をつくる
もちろん、何もしない時間も悪くありませんが、「スマホを見続けて終わっちゃった…」という休日は疲れを残しやすいとも指摘されています。
1〜3か月単位で整える“長期ルーティン”
一時的な休養だけでは、蓄積疲労が抜けにくいこともあるようです。そこで、長期的に疲れを溜めにくくする習慣づくりが役立つと言われています。
例としては:
-
就寝前30分はスマホを触らない
-
週1回はノープランデーを確保
-
月1で一人時間や趣味の日を設定
-
カレンダーに「休養枠」を先に入れておく
「自分の余白時間を守る」意識が、気力の回復につながるとも言われています。
休養は“時間の長さ”じゃない
「まとまった休みが取れた時に考えよう」ではなく、短時間・中規模・長期習慣を組み合わせるほうが心身にはやさしいようです。大切なのは“時間を作る”よりも、“今の状態に合った休養を選ぶこと”かもしれません。
#休養の取り方
#ミニ休養
#休日リセット
#ルーティン作り
#疲労ケア
4.避けるべき “休み方の誤り” とその改善策
「せっかく休んだのに全然疲れが抜けない…」こんな経験はありませんか?
実は、休んでいるつもりでも“逆に疲れをためてしまう休み方”があると言われています(引用元:https://stretchex.jp/5863)。ここではありがちな誤りと、すぐ試せる改善アイデアをセットで紹介します。
① 寝だめは逆効果になることも?
「休日くらい好きなだけ寝たい!」という気持ちはよくわかります。ところが、長時間の寝だめは生活リズムを崩しやすく、夜に眠れなくなったり、月曜にダルさを引きずる原因になるとも言われています。
✅ 改善策の一例
・起床時間は普段と1〜2時間以内のズレにする
・昼寝は20分前後にとどめる
・眠気が強いときは横になる前にストレッチを挟む
「短く質を整える」ほうが結果的にスッキリしやすいそうです。
② ゴロゴロしっぱなしは“疲れを固定”しやすい?
「今日は何もせず横になっていたい…」という日は誰にでもありますよね。ただし、長時間同じ姿勢でいると血行が滞り、かえって疲労感が増すとも言われています。
✅ 改善策の一例
・1時間に1回は立って伸びをする
・座ったまま足首や肩を回す
・5分の散歩や深呼吸をセットにする
“完全に止まる休養”より“ゆるく動く休養”のほうが回復しやすいという考え方も広がっています。
③ スマホ時間が休養をジャマすることも
SNSや動画をダラダラ見ていたら半日消えていた…という声は多く聞かれます。画面からの光や情報量は脳に負荷を与えやすく、“休んだつもり疲れ”につながるとも言われています。
✅ 改善策の一例
・ベッドやソファにスマホを持ち込まない
・タイマーをかけて区切る
・見るより「聴く」コンテンツに変える(ラジオ・音声配信など)
「触らない時間を先に作る」ほうが気持ちの切り替えもしやすくなります。
④ “何もしない罪悪感”で心が休めていないパターン
「休んでる場合じゃない」と思いながらゴロゴロしていると、頭の中では仕事や家事のことがグルグルしがちです。これは精神的な疲労を引きずる原因になるとも言われています。
✅ 改善策の一例
・最初に「今日は○○だけ休む」と宣言する
・やらないことリストを書き出す
・10分だけ片付け→残りは休む、という区切りを作る
“気持ちまで休める余白”をつくることがポイントです。
まずは「やめる」のではなく「置き換える」
休養のミスは怠慢ではなく、“習慣のクセ”と言われています。いきなり全部を変えようとせず、今の行動に「ひと工夫」加えるところから始めるほうが現実的です。
#休み方の改善
#寝だめ対策
#スマホ疲れ
#だらだら休日防止
#正しい休養
5.自分に合った休養モデルを設計しよう:チェックリスト+実践プラン例

「自分なりに休んでいるつもりなのに、なぜか疲れが抜けない…」
そう感じる人は少なくありません。実は、休養は“量”より“質”が大事だと言われていて、自分に合ったパターンを作ることで回復しやすくなるとも考えられています(引用元:https://stretchex.jp/5863)。ここでは、簡単なチェックリストとモデルプランを使って、自分仕様の休養スタイルを作る方法を紹介します。
まずは“今の自分”を知るチェックリスト
以下の項目を読んで、当てはまるものに丸を付けてみてください。数が多いところが、今不足している休養タイプのヒントになります。
✅よくある疲れのサイン例
【体の疲れ】
・朝起きてもだるい
・肩や首のコリが取れづらい
・長時間同じ姿勢になりがち
【頭・感覚の疲れ】
・スマホやPCを見続けてしまう
・寝る直前まで画面を触っている
・情報に振り回されて休めていない感覚がある
【感情・人間関係の疲れ】
・本音を話せる相手が少ない
・何となく人付き合いがしんどい
・「何かあった?」と言われるほど表情が固い
【精神的・内面的な疲れ】
・考え事を止められない
・気づけばため息が出ている
・やる気が続かない、理由が分からない
多くチェックがついたところが“整えるべき休養タイプ”だと考えられています。
タイプ別・実践プランの例
「何から始めればいいの?」という方に向けて、取り入れやすいプラン例を3パターン紹介します。
◆ 平日・短時間プラン(すきま休養向け)
-
朝の3分ストレッチ
-
通勤中はイヤホンなしで歩く
-
昼食後に目を閉じて深呼吸
-
帰宅後はスマホを充電スペースに置く
「ながら休養」にすると負担が少ないと言われています。
◆ 休日リカバリープラン(半日〜1日)
-
午前:散歩やカフェなど“外の刺激で回復”
-
昼:スマホOFFで食事
-
午後:好きな音楽・読書・昼寝
-
夜:湯船にゆっくり浸かる
「寝だめより活動休養が有効なこともある」と紹介されるケースも多いです。
◆ 1週間ルーティン化プラン
-
月:夜は照明を落として過ごす
-
水:ノーSNSデー
-
金:軽い運動 or サウナ
-
土日:1〜2時間“誰にも邪魔されない時間”を確保
“続けられる休養”が疲労の蓄積を防ぐと言われています。
完璧を目指さず“足す・引く・選ぶ”から
最初からフルセットを目指す必要はありません。
「今の生活に1つ足す」「逆に減らす」「無理なく続けるものを選ぶ」これだけでOKです。
休養は“がんばるもの”ではなく、“整える習慣”としてゆるく組み込んでいくことがポイント、とも言われています。
#休養チェックリスト
#自分に合う休み方
#休養モデル設計
#ルーティン休養
#疲れタイプ別ケア
ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。




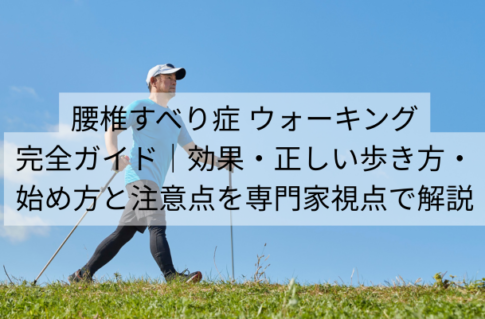
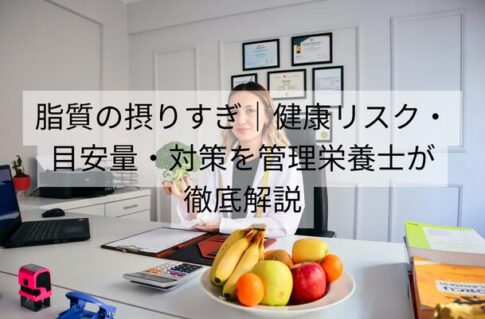
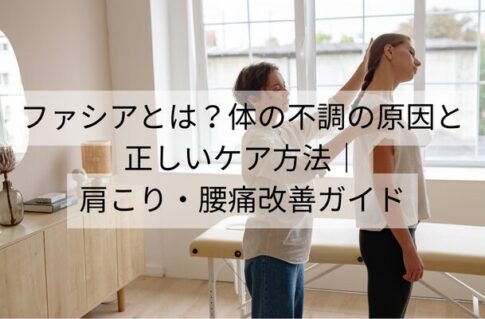
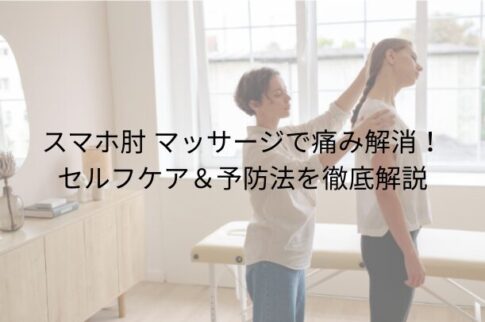
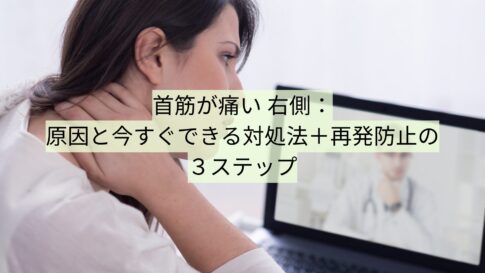


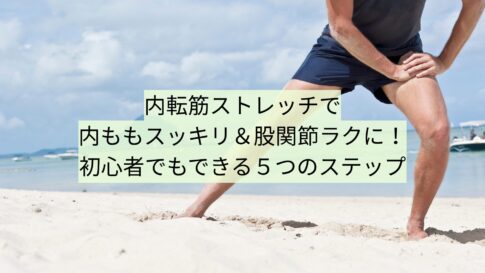
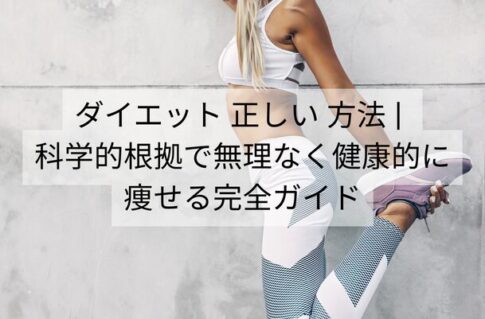
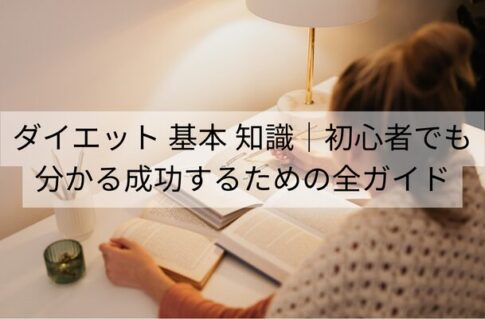
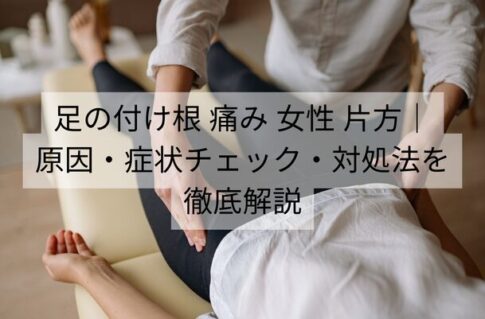
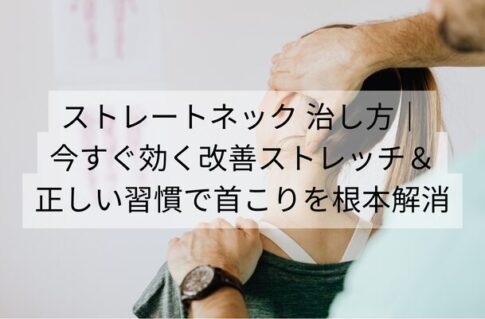
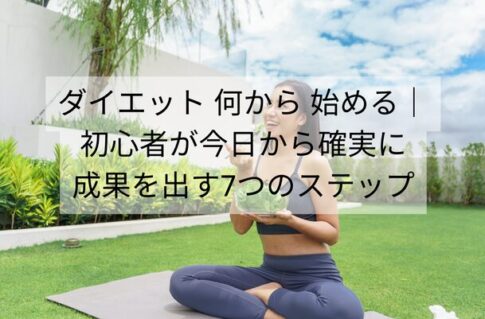




コメントを残す