
捻挫とは何か?まず知っておきたい構造と段階
捻挫という言葉はよく耳にしますが、実際のところ「どんな状態なのか?」と聞かれると、案外あいまいなまま過ごしている人が多いように思います。ざっくり言うと、関節を支えている靭帯や周りの組織に負荷が加わり、本来の可動範囲を超えてしまった時に起こるものと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5755/)。
ただ、「ただのひねり」だと軽く見ると、後で思った以上に長引くことがあるとも言われているので注意が必要です。
捻挫の定義/靭帯・関節の関係
関節は骨同士が集まってできていて、その安定性を靭帯という硬い組織が支えています。ジャンプの着地、段差の踏み外し、スポーツ中の急な切り返しなど、瞬間的に力がかかると靭帯が耐えきれず、伸びたり一部が傷ついたりすることがあると言われています。
「捻挫」はその状態をまとめて呼ぶ言葉で、骨折ほどの大きな損傷ではない場合も多いのですが、靭帯が関係するため、軽度でも腫れや痛みが出ることがあります。特に足首の捻挫は日常でも起こりやすく、一度ひねった場所を再び痛めやすいとも言われています。
軽度〜重度の分類と見分け方
捻挫には段階があり、一般的には「靭帯が軽く伸びた程度」「部分的に損傷している」「しっかりと損傷している」というように分けられると言われています。
軽い場合は違和感や軽度の腫れで済むこともありますが、重度になるほど腫れが強くなり、足をつくのがしづらいことも多いです。
ただ、外から見ただけでは判断しづらいことがあるため、痛みが強い、腫れが急に広がる、しびれが出るなどの場合は、専門家に相談することがすすめられています。
捻挫が「やってはいけないこと」を知るべき理由
捻挫をした直後は「少し痛いだけだから、そのうち改善するだろう」と思って動いてしまう人が多いのですが、これが後で困る原因につながることがあると言われています。
例えば、すぐに温めたり、無理に歩き続けたりすると、腫れが増えたり、靭帯の回復を妨げる可能性があると考えられています。
また、初期対応を誤ると、関節が不安定なままクセになってしまうケースもあるとされています。
だからこそ、「やってはいけないこと」を知ることは、早期の改善や再発予防につながる大切なポイント、と言われています。
#捻挫とは
#捻挫の基礎知識
#靭帯と関節の関係
#捻挫の段階
#捻挫でやってはいけないこと
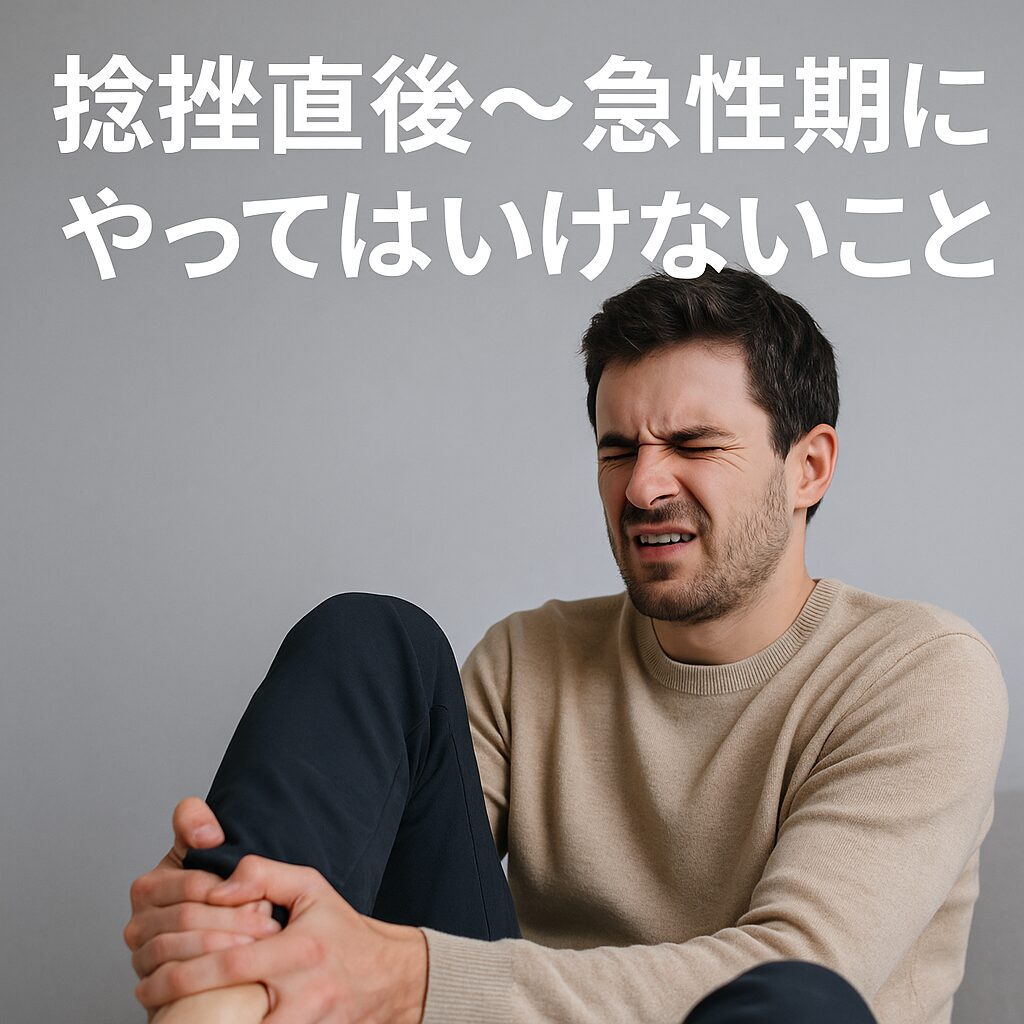
捻挫直後〜急性期にやってはいけないこと
捻挫をした直後は、痛みや腫れに気づきながらも「少し休めばそのうち改善するだろう」と思って動いてしまう人が少なくありません。ただ、急性期は靭帯や周囲の組織がデリケートな状態になっているため、刺激が重なると後の回復に時間がかかると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5755/)。
ここでは、日常でやってしまいがちなNG行動を、会話形式も交えながら分かりやすく整理していきます。
無理に歩く・関節に荷重をかける
「少しくらいなら歩けるし、大丈夫そうだな…」と思ってしまいがちですが、急性期は特に負荷をかけない方が良いと言われています。靭帯が伸びたり傷ついたりしている可能性があり、重心をかけると炎症が強くなることもあるそうです。
友人から「我慢すれば歩けるよ」と言われても、無理に動くと腫れが広がるケースがあるため、いったん負担を減らすことがすすめられています。
すぐに温める(浴槽・サウナ・ホットパック)
「冷やすのか温めるのか、どっちなんだろう?」と迷うこともあると思います。
急性期は血流が一時的に高まりやすく、温めると腫れが増えやすいと言われています。お風呂やサウナ、ホットパックなども早い段階では避けた方が良いとされています。
「ぬくめた方が楽になる気がする」と感じることもありますが、ひとまず落ち着くまでは冷却が無難と言われています。
飲酒・マッサージ・自己流テーピング
「夜にお酒を飲んだら少しは気が紛れるかな」と思うこともありますが、飲酒は血流を促して腫れを強める可能性があるとされています。
また、マッサージも「コリが取れそう」と感じても、急性期は逆に刺激が強すぎることがあると考えられています。
さらに、自己流のテーピングは圧が偏ったり、動きを制限しすぎたりするリスクがあり、専門的な方法と比べて不均一な固定になりやすいとも言われています。
強すぎる圧迫固定/長時間の湿布・塗布薬乱用
「しっかり固定した方が良いよね?」と思って締めすぎてしまうと、血行が悪くなったり、痛みが増えたりすることがあると言われています。
湿布や塗り薬も「貼れば貼るほど良い」というものではなく、長時間の使用は皮膚トラブルにつながることもあるため、注意が必要とされています。
#捻挫急性期
#捻挫やってはいけないこと
#捻挫のNG行動
#捻挫の初期対応
#捻挫の悪化予防

中期〜回復期で見落としがちなNG行動
捻挫は、急性期を抜けると「もう大丈夫そうだし、そろそろ動けるかな」と思えてしまう時期があります。
ただ、この“痛みがひいた頃”が一番気をつけたいタイミングと言われています。回復途中の靭帯は、まだ負荷に弱く、見落としやすいNG行動が積み重なると再発につながりやすいそうです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5755/)。
ここでは、よくやってしまいがちなポイントを、なるべく日常の会話に近い形でまとめてみました。
痛くないからとすぐ運動再開・ジャンプ・ランニング
「もう痛くないし、軽く走ってみてもいけるかも?」
ついそんな気分になることがありますよね。ただ、痛みが落ち着いても靭帯が完全に安定しているとは限らない、と言われています。
特にジャンプやランニングは関節に急な負荷がかかるため、炎症が再び出てしまうケースもあるそうです。
“痛みがひいた=戻っていい”ではなく、段階的に強度を上げる方が安心と言われています。
完全安静のまま動かさず筋力低下・関節硬化
反対に、「怖いからしばらく触らないでおこう…」と完全に動かさずにいると、関節が硬くなりやすいと言われています。
友達に「しばらく使わない方がいいよ」と言われることもありますが、実際には軽い可動や筋力トレーニングを少しずつ取り入れた方が、回復がスムーズなことも多いようです。
もちろん、無理のない範囲で徐々に、が大前提です。
靴・足元環境を軽視して履き替えない
「まあ、いつもの靴でいいか」と思ってしまいがちですが、この時期の足元環境は surprisingly 大事だと言われています。
クッション性の低い靴や、ぐらつきやすい靴を履いていると、本来より負荷がかかりやすく、回復の妨げになることもあるそうです。
仕事や生活のなかで長時間歩く人ほど、靴選びを見直すことがすすめられています。
違和感を放置して「クセ」になる(再発リスク)
「まぁ大丈夫だろうし、このまま様子見でいいかな…」と違和感をそのままにしてしまうことがあります。
ただ、捻挫がクセになるのは、この“違和感放置”が積み重なるためとも言われています。
特に足首は再発しやすい部位なので、グラつく感覚や不安定さが続く場合は、早い段階で専門家へ相談する方が安心だと言われています。
#捻挫回復期
#捻挫のNG行動
#捻挫の再発予防
#捻挫のリハビリ
#捻挫でやってはいけないこと
やってはいけないことを避けるための “正しいケア”
捻挫をした時、「何をしちゃいけないか」だけでなく、「どうケアするのが自然なのか」も知っておくと安心だと言われています。
痛みがあると動揺しやすいですが、流れさえつかめれば落ち着いて対応しやすくなりますよ。
ここでは、応急処置からリハビリの入り口、そして相談すべきサインまで、会話のようなテンポでまとめてみました。
応急処置「RICE」の使い方と注意点
「とりあえず冷やせばいいんでしょ?」とよく言われますが、実はRICEには順番と考え方があると紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5755/)。
Rは安静、Iは冷却、Cは圧迫、Eは挙上のことで、急性期の腫れや炎症を落ち着かせるための手順とされています。
ただ、強すぎる圧迫は血流を悪くすることがあるので、軽めに、がポイントと言われています。
「少しきつい方が効きそう」と思う人もいますが、そこは控えめの方が安心みたいです。
冷却から温熱へ切り替えるタイミング
「いつまで冷やして、いつから温めていいの?」という質問は多く聞きます。
一般的には、腫れや熱感が落ちついてきた頃から、じんわり温める方向へ切り替えることがすすめられています。
ただ、痛みがまだ鋭い時や、触ると熱を感じる時は温めを避ける方が良いとも言われています。
会話の中でも「もう湯船入っていいかな?」と悩む場面がありますが、無理のない範囲で様子を見るのが自然です。
サポーター・テーピングの正しい使い方
サポーターは「つけておけば安心」という声が多いですが、実は固定力が強すぎたり弱すぎたりすると負担をかけやすいと言われています。
特にテーピングは、自己流だと圧が偏ることがあるため、最初は専門家に相談する方が分かりやすいかもしれません。
「巻いてみたけど逆に痛い…」という声も耳にするので、慣れないうちは慎重さが大切です。
リハビリ・筋力・バランス訓練の始め方
急性期が過ぎて動けるようになってきたら、軽いリハビリを入れることがすすめられています。
例えば、タオルを引き寄せる足指の運動や、座ったまま行う可動域の確保など、負担の少ないものから始めることが多いようです。
「ちょっとだけなら立って運動してもいい?」と相談されることもありますが、その日の痛みや腫れ具合を見ながら調整していく、と言われています。
専門家(整形外科・整骨院など)に相談すべきサイン
次のような状態は、無理せず相談した方が安心と言われています。
-
腫れが急に強くなった
-
足をつくのがしづらい
-
しびれや感覚の変化が出てきた
-
数日経っても不安定感が続く
「このまま様子見でもいいかな?」と迷う気持ちもわかりますが、長引かせないためにも早めの相談が安心と言われています。
#捻挫ケア
#RICE処置
#捻挫のリハビリ
#捻挫の正しい対応
#捻挫でやってはいけないこと
再発防止・後遺症を防ぐためにやってはいけないことをもう一度見直す
捻挫は「痛みが落ち着いたら終わり」と思われがちですが、実はそこからの管理がとても大切だと言われています。
特に足首の捻挫は再発が多いと紹介されており、日常のちょっとした油断が積み重なると、後々の不安定さにつながるケースもあるそうです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5755/)。
ここでは、慢性化を防ぐために改めて見直しておきたいポイントを、できるだけ日常の会話に近い形でまとめています。
「またひねったけど大丈夫」の放置リスク
「さっき軽くひねったけど、まぁ平気かな…」
そんな場面は意外と多いですよね。ただ、この“放置”こそ再発の入り口になると言われています。
靭帯は一度ゆるむと元の安定性をすぐに取り戻しにくいことがあり、「小さな捻挫の繰り返し」がクセ化の要因になるとも紹介されています。
少しでもグラつく感じがある時は、早めの対応が安心だと言われています。
関節のぐらつき・慢性不安定症につながるケース
捻挫後に「何となく不安定」「着地が怖い」という声はよく聞かれます。
この状態が続くと、足首が本来の動きをサポートしづらくなり、慢性的な不安定さへつながることもあるようです。
特に片足立ちで揺れてしまう、階段で怖さを感じる、方向転換で踏ん張れないなどは、注意したいサインと言われています。
放置するより、軽めの筋力トレーニングやバランス訓練を始めた方が良いケースもあります。
足元・靴・日常動作(段差・方向転換など)の見直し
日常の中には思いがけない“つまづきポイント”が潜んでいます。
例えば、底が薄くてグラつく靴、摩耗したスニーカー、かかとの固定が弱いサンダルなどは、再発のリスクを上げることがあると言われています。
また、段差の登り降りや方向転換のクセが強いと、足首に余計な負担がかかりやすいとも紹介されています。
「歩き方なんて気にしたことなかったな…」という人ほど、一度見直す価値があります。
遂に「クセになってしまった」人のための対策+当院のアプローチ紹介
「もうクセになっちゃって、またひねりそうで怖い…」
そんな状態でも、段階的なケアを重ねることで安定感を取り戻せるケースがあると言われています。
主な対策としては、
-
足首まわりの筋力強化(特に腓骨筋)
-
バランス訓練や片足立ち練習
-
可動域の調整
-
日常動作のクセの修正
などが挙げられています。
当院では、足首の状態に合わせて靭帯まわりの緊張を整え、必要に応じてサポート用テーピングやバランス指導を併せて行うアプローチを採用しています。
「何をしたら良いか分からない」という人でも、段階的に取り組めるようにサポートしていく形が多いです。
#捻挫再発予防
#捻挫のクセ化防止
#足首の不安定さ
#捻挫の後遺症対策
#捻挫でやってはいけないこと

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

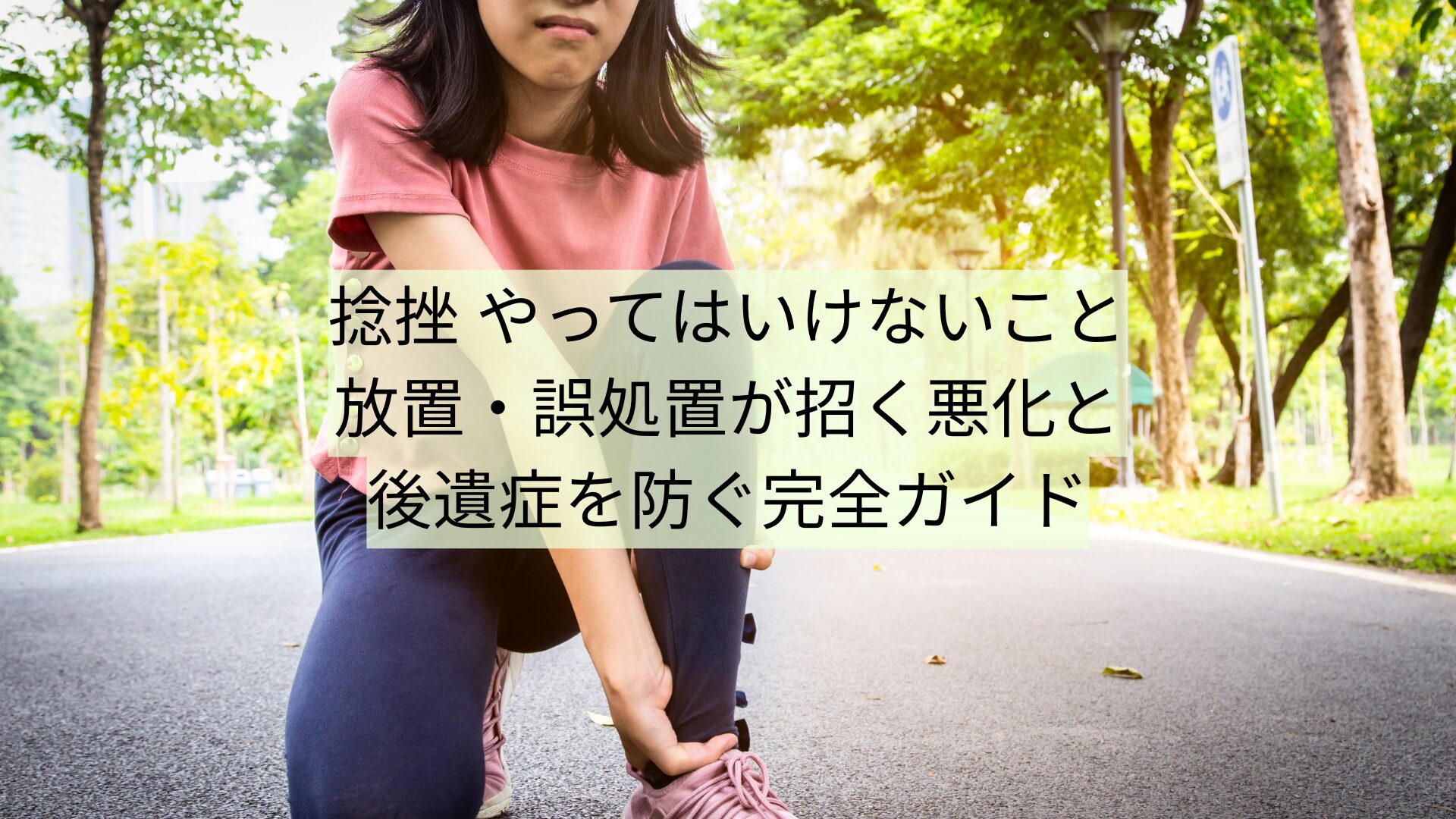

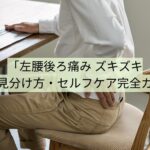
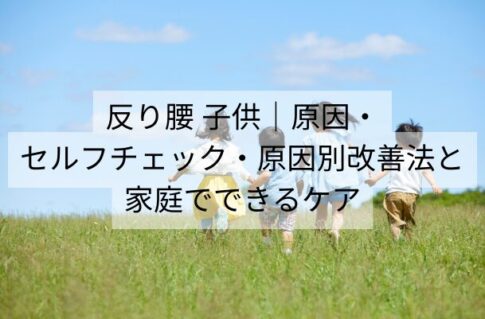
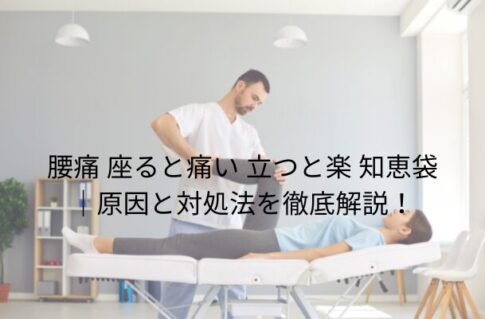
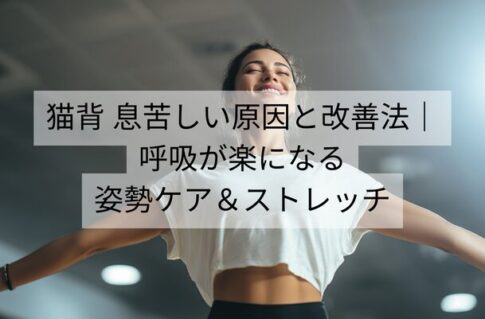
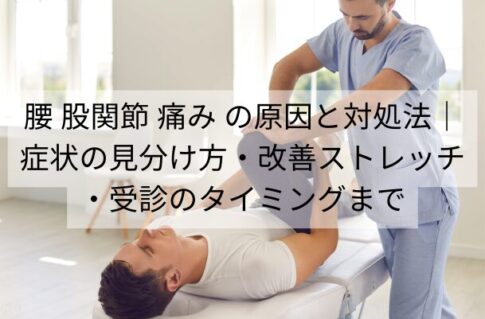
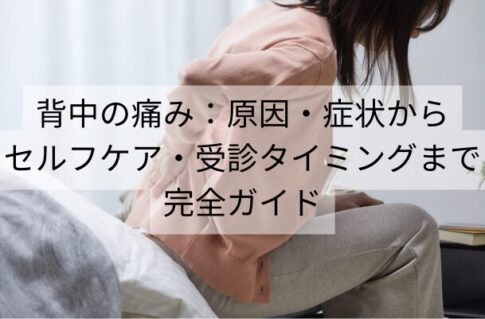
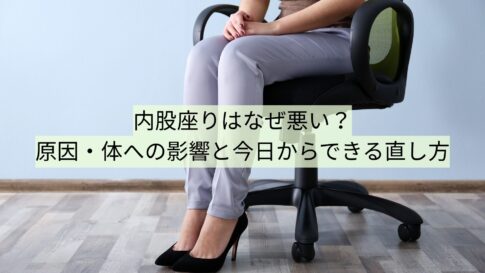
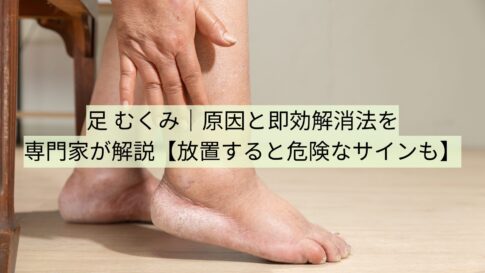
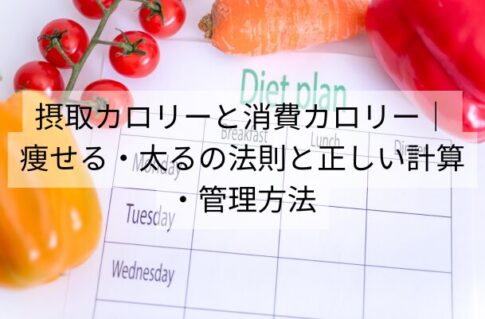








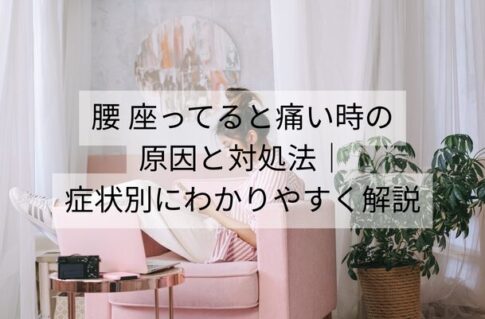




コメントを残す