1.肩甲挙筋とは?/痛みを感じる仕組み

肩甲挙筋の解剖・役割(肩甲骨と首をつなぐ筋肉としてのポイント)
「肩甲挙筋」は、首の第1〜第4頸椎あたり(C1〜C4横突起)から起こり、肩甲骨の上角および内側縁上部へとつながる細長い筋肉と言われています。 リハビリのセミナーなら 療法士活性化委員会-
この筋肉の主な役割は、肩甲骨を上方へ引き上げ(挙上)、また肩甲骨をやや下方に回す動作(下方回旋)にも関与しており、加えて首の横倒し(側屈)や回旋動作の補助を担っていると言われています。 n-p-t.com
つまり、肩甲骨と首を「つなぐ」ように走っているため、このエリアに負担がかかると「肩甲挙筋が痛い/こる」と感じることが少なくないわけです。
なぜ「痛い」「こる」状態になるのか(姿勢、デスクワーク、スマホ首など)
では、なぜ肩甲挙筋が痛んだり、常に張るような感覚になるのでしょうか。ひとつの原因として、長時間のデスクワークやスマホ操作で首が前に出たり肩がすくんだりする「すくめ姿勢/前かがみ姿勢」が挙げられます。このような姿勢では肩甲挙筋が常に少しばかり縮んだ状態に置かれ、その疲労・血流低下・筋膜の癒着が生じやすいとされています。 マイナビコメディカル
また、重い荷物を片肩にかける、肩をすくめて緊張状態が続く、首・肩甲骨まわりの可動性が低下して肩甲挙筋に過剰に働きかけてしまう、というパターンもよく見られます。 rehatora.net
こうした状態が続くと、肩甲挙筋内に「こり」や「張り」が生じ、痛みとして自覚されやすくなります。
痛み・違和感の典型的な症状(肩甲骨上部〜首筋、腕へのしびれ感など)
肩甲挙筋が過度に緊張すると、典型的には「肩甲骨の上部 – 首の付け根あたり」にかけて重だるさや張り、鋭い痛みを感じることが多いと言われています。 n-p-t.com
さらに、肩甲骨内縁付近から腕にかけての「しびれ」や「違和感」を訴える方も少なくありません。これは、筋肉の緊張により近接する神経・血管が圧迫されることで起こる可能性があります。
また、首を横に向いたり、肩をすくめた姿勢を取ると痛みが増す・動きが制限されるという方も多く、「あれ、首を振り向くとつっぱる」「肩甲骨を寄せると痛い」という感覚が出るケースがあります。 rehatora.net
注意すべき痛みのサイン(神経症状、手のしびれ、急激な痛みなど)
ただし、肩甲挙筋の張りや痛みだけで済まされないサインも出ることがあります。例えば、手のしびれが強い/腕の動きが悪い/急に強い痛みが出た/夜間に痛みが増すといった症状は、神経が関わっている可能性が高いため注意が必要です。 rehatora.net
また、むち打ち後や事故後に痛みが出ている場合、単なる筋肉のコリではなく頸椎・神経・血管などに障害が及んでいるケースもあり、その場合はセルフケアだけに頼らず、専門家による検査・施術を検討することが勧められています。 teito-mc.com
つまり、「いつもと違う痛み」「しびれが増す」「改善しない違和感」が続くときは放置せず、早めに対応することがギモン回避につながると言われています。
#肩甲挙筋 #肩こり #首こり #デスクワーク対策 #肩甲骨ケア
2.肩甲挙筋が痛い・こるときの主な原因
日常生活での姿勢・習慣による負担(前かがみ、PC作業、スマホ操作)
「最近、肩甲挙筋が痛い・こる感じがして…」という方、多いのではないでしょうか。実は、長時間の前かがみ姿勢や、パソコン作業・スマホ操作で首が前に突き出る「スマホ首」状態は、この筋肉に大きな負担をかけると言われています。
例えば、PCの画面が目線より低い位置にあると、首を前に出しながら作業するため、肩甲挙筋が無意識に「縮んだまま」働き続ける可能性があるのです。あるいは、肩をすくめた姿勢で荷物を片側にかけて歩く習慣も、肩甲挙筋を過度に使う一因として挙げられています。トリガーポイントネット
このような「繰り返し・長時間の負荷」が蓄積すると、筋肉が休まる暇なく張り、こり・痛みへと発展する流れができやすいと言われています。rehatora.net
筋肉疲労・筋膜張り・血流不良・神経圧迫などのメカニズム
では、実際にどうして「こる」「痛い」状態になるのか。主なメカニズムとしては、筋疲労→筋膜張り→血流不良→神経圧迫の順で悪化していくと言われています。例えば、筋肉が長時間緊張したままだと、その中にトリガーポイントと呼ばれる硬いしこりが発生しやすくなります。やまだカイロプラクティック
この硬結部分では血管や毛細血管が圧迫され、酸素や栄養の供給が落ち、代謝産物(疲労物質)が溜まりやすくなります。すると、いわゆる「こり」「張り」「痛み」という自覚症状が出やすい状態になるのです。やまだカイロプラクティック・鍼灸院
さらに、その筋肉に近い神経が局所的に圧迫されたり、引っ張られたりすることで、「腕のしびれ」「肩から首にかけての違和感」などの神経症状を伴うこともあります。トリガーポイントネット
他の筋肉/関節との関連(例えば僧帽筋、大菱形筋、肩甲骨の可動域低下)
この肩甲挙筋ひとつだけが悪くなるわけではありません。実際には、例えば僧帽筋上部や大菱形筋、さらには肩甲骨自体の可動域低下などが「セット」で起きやすいと言われています。トリガーポイントネット
つまり、肩甲骨がうまく動いていない(例えば下がったままだったり、内側に寄ったままだったり)と、肩甲挙筋が代わりに動きを補おうとして過剰に働くことがあります。その結果、肩甲挙筋が余計に負担を受けてしまうのです。ある研究では、僧帽筋と肩甲挙筋が同時にトラブルを起こして「衛星トリガーポイント」になるケースもあると報告されています。rehatora.net
痛み・こり以外に出やすい合併症(首の可動域低下、頭痛、肩甲骨の動き悪化)
そして、肩甲挙筋のこり・痛みを放っておくと、痛みだけで済まず様々な“合併症”的な症状が出る可能性があります。例えば、首を左右に回す・後ろを見るなどの動きが制限されて、「首の可動域低下」を自覚する方も多いと言われています。rehatora.net
また、肩甲挙筋のトリガーポイントがある人では、肩甲骨の上部から首筋にかけての痛みが、頭痛やめまい、肩甲骨の動きの悪さとしても現れるケースがあります。トリガーポイントネット
さらに、肩甲骨の可動域が落ちることで、腕を上げる動作がしづらくなったり、背中側に肩甲骨を寄せるのが難しくなったりするため、肩こり・首こりが慢性化するリスクも高まると言われています。癒し人 |
#肩甲挙筋ストレッチ#肩こり解消法#首こり対策#デスクワーク疲労ケア#スマホ姿勢改善
3.症状別・痛みのタイプ別セルフケア&ストレッチ

軽い「張り・だるさ」向けケア:温め・軽いストレッチ・姿勢リセット
「最近ちょっと肩が重いな…」「首まわりがだるい気がする」という程度の軽い症状なら、温めとストレッチによる血流促進が効果的だと言われています。(co-medical.mynavi.jp)
まず、蒸しタオルや温熱パッドを肩甲骨まわりに当てて温めます。筋肉がゆるんだ状態で、ゆっくりと「首を左右に倒す」「肩を後ろに回す」ような軽めのストレッチを行うと、血流がスムーズになりやすいとされています。(rehatora.net)
また、長時間同じ姿勢が続いたときは「1時間に1回、席を立って深呼吸+肩回し」を意識するだけでも、張りの悪化を防げると考えられています。(triggerpoint-net.vitacain.co.jp)
「痛み・こりが出ている」向けストレッチ:肩甲挙筋をターゲットにした具体的方法
痛みやこりを感じる場合は、肩甲挙筋そのものを意識したストレッチがポイントになります。
-
背筋を伸ばして座る
-
痛みのある側の腕を背中の後ろに回す
-
反対側の手で頭を軽く斜め前に倒す
-
首の横〜肩甲骨の上角あたりに伸びを感じたら、20秒キープ
このストレッチは筋肉を無理に引っ張らず、「気持ちいい」と感じる範囲で止めることが大切だと言われています。(athletic.work)
「温め→ストレッチ→姿勢を戻す」の流れをセットに行うと、緊張緩和の効果がより出やすいと考えられています。
「首〜肩甲骨にかけてしびれ・神経症状あり」向けの注意点とケア方法
しびれや神経的な違和感がある場合、過度なストレッチは避けたほうが良いと言われています。(teito-mc.com)
まず、冷やさずに温めることで血流を促し、神経圧迫を緩めることが推奨されています。また、姿勢を変えた瞬間に「ビリッ」とくる場合は、無理に動かさず、安静を保つことが重要です。(rehatora.net)
症状が続くときは、筋肉以外の原因(頸椎・神経・関節)も関与していることがあるため、理学療法士や整体師など専門家のアドバイスを受けるのが良いとされています。
日常習慣でできる「こりにくい体づくり」の簡単習慣(休憩の取り方、椅子・モニターの高さ、スマホ操作)
「肩甲挙筋のこり」は、毎日の姿勢と習慣が大きく関係しています。
デスクワーク中は、椅子の高さを調整して背もたれに深く座り、モニターの上端を目線の高さに合わせると良いとされています。(co-medical.mynavi.jp)
また、スマホを操作するときは、顔を下げずに腕を上げて目線を水平に保つだけでも、首への負担を減らす効果があると言われています。(triggerpoint-net.vitacain.co.jp)
さらに、1時間ごとに軽く立ち上がって体を動かすことで、血流の滞りを防ぎ、“こりにくい体”をつくることができると考えられています。
#肩甲挙筋ストレッチ #肩こり解消 #デスクワーク疲れ #スマホ首対策 #姿勢リセット
4.専門的ケア・治療が必要なケースとその選び方
自分でケアをしても改善しないとき:どんな場合に病院・整体・理学療法を検討すべきか
「肩甲挙筋がずっと痛い/こりが取れないな…」と感じたら、“セルフケアだけでは改善が難しいサイン”と言われています。例えば、数週間以上続いている痛み・首〜肩〜腕へのしびれ・夜間に悪化する痛み・頭痛やめまいを伴う場合には、専門的な検査・施術を検討すべきだとされています。 〖三軒茶屋〗ADVANCE世田谷鍼灸整骨院
また、「マッサージしても2~3日で戻る」「両肩で差が出てきている/動きにくさまで出てきた」といったときは、楽だからとそのまま放置すると慢性化するリスクが高まると言われています。 step-kisarazu.com
ですから、セルフケアで“ちょっとずつ改善してきた”と思えなければ、早めに専門機関を検討するのが理想と言えそうです。
整体・マッサージ・理学療法それぞれのメリット・デメリット
整体・マッサージ・理学療法(リハビリ的アプローチ)には、それぞれ特徴があります。
-
整体・マッサージ:筋肉をほぐしたり、関節の動きを整えたりすることで“即効性”を感じやすいと言われています。一方で、根本原因(姿勢・使い方・筋バランス)を変えないと再び硬くなりやすいというデメリットも指摘されています。 整体oasis
-
理学療法(理学療法士によるアプローチ):関節や神経・筋肉の機能を評価し、運動+動作指導+日常的な使い方の改善を含めるため、長期的な改善につながりやすいと言われています。一方、料金や通院の頻度が増える/即効感が薄いというケースもあるようです。
-
どちらを選ぶかは「痛み・しびれの程度」「日常生活・仕事への影響」「改善のペース」などを基に、専門家と相談するのがおすすめです。
診察・治療を受ける際のポイント(筋電図や姿勢分析などの検査、保険適用の可否)
来院・来院時には、まず問診+触診・動作テストが行われ、必要に応じて「筋電図」「姿勢・動きの分析」「神経伝達の検査」などが実施されることがあります。これらの検査は“ただ揉むだけ”では見えてこない根本原因を明らかにするために有効だと言われています。 整体oasis
また、保険適用となるかどうかも重要なチェックポイントです。例えば病院・整形外科での診察・理学療法は保険が使える場合がありますが、整体・マッサージでは自費となるケースが多いと言われています。来院前に「どこまで費用がかかるか」「検査・施術内容はどうか」を確認すると安心です。
そして、最も大切なのは「一度施術を受けたら終わり」という考えではなく、施術後に自身での日常ケア・姿勢改善・運動習慣の継続を併用することが、再発を防ぐ鍵となると言われています。 〖三軒茶屋〗ADVANCE世田谷鍼灸整骨院
治療後にも重要な「再発予防」とセルフケアとの併用の理由
施術で一時的に筋肉の緊張がゆるんでも、姿勢や動きクセ・使い方を変えなければ、また「肩甲挙筋が痛い・こる」状態に戻りやすいと言われています。 kubi-kori-rakuraku.com
だからこそ、「施術+自身でのケア」の両輪が必要です。たとえば、姿勢を整える、定期的にストレッチをする、肩甲骨まわりの筋肉を使う習慣をつける、デスク環境を見直す…などが挙げられます。こうした習慣が“再発のサイクル”を断つ手助けになると言われています。 step-kisarazu.com
さらに、施術をきっかけに「自分の体の使い方に意識を向ける」ことが、長期的に“痛み・こりが出にくい体づくり”につながるわけです。なので、専門的なケアを受けた後も“自分メンテナンス”を続けることを大切にしましょう。
ハ#肩甲挙筋ケア #肩こり改善 #専門ケア選び方 #姿勢改善 #再発予防メンテナンス
5.長期的に肩甲挙筋の痛み・こりを防ぐための3つの生活習慣
①定期的なチェック&メンテナンス(ストレッチ・ほぐし習慣化)
「肩甲挙筋が痛い」と感じる人の多くは、知らないうちに筋肉が硬くなり、慢性的なこりに発展しているケースが多いと言われています。だからこそ、**“痛くなる前のメンテナンス”**が大切です。
たとえば、朝起きたときや仕事の合間に首をゆっくり回したり、肩甲骨を引き寄せるようにストレッチをするだけでも、筋肉の血流を保つ効果があると考えられています。(co-medical.mynavi.jp)
「肩こりって仕方ないものじゃない?」と感じる人もいますが、数分の“ほぐし習慣”を取り入れるだけで、肩甲挙筋の柔軟性や回復力を保ちやすくなると言われています。(rehatora.net)
② 正しい姿勢・動作の習慣化(モニター位置、椅子の角度、スマホ閲覧時の工夫)
肩甲挙筋の負担を軽減するうえで、“姿勢の見直し”は欠かせません。特にデスクワークでは、モニターの高さが低いと首が前に出やすく、筋肉が常に緊張してしまう傾向にあります。
理想的なのは、モニターの上端が目の高さになる位置で、椅子の背もたれに深く座り、骨盤を立てた姿勢です。また、スマホを見るときは、顔を下げずに画面を目線の高さに近づける意識が重要だと言われています。(triggerpoint-net.vitacain.co.jp)
こうした小さな姿勢の工夫を重ねることで、肩甲挙筋だけでなく首や背中全体への負担も減らせると考えられています。
③ 筋肉・可動域(肩甲骨まわり・首・背中)のバランスを整える運動(肩甲骨まわし、軽い体幹トレーニング)
肩甲挙筋の痛みやこりを予防するには、筋肉の柔軟性だけでなく「使う力のバランス」も大切です。
肩甲骨まわしや軽い体幹トレーニングなど、全身の連動を意識した運動を取り入れることで、肩甲挙筋への一方的な負担を減らせると報告されています。(athletic.work)
特に「背中が硬い」「肩が動きにくい」という方は、肩甲骨の動きをサポートする僧帽筋や菱形筋を同時に使う運動を取り入れると、首・肩全体のバランスが整いやすいと言われています。(tokyo-iyashibito.com)
日常的に“ちょっと肩を回す”“背伸びをする”だけでも、筋肉の動きがリセットされ、慢性化の防止につながると考えられています。
痛み・こりを繰り返さないために知っておきたい“慢性化”プロセスとその防止法
肩甲挙筋の痛みが慢性化する背景には、**「痛み→使わない→血流低下→さらに硬くなる」**という悪循環があると言われています。(rehatora.net)
このサイクルを断つためには、「動かす・温める・姿勢を整える・リラックスする」の4つをセットで行うことが重要だとされています。
特に仕事や家事などで長時間同じ姿勢を取る人は、1時間に1回の軽い肩回しや深呼吸を習慣にすると良いと言われています。体を動かす“ちょっとした意識”が、慢性的なこりを防ぐ第一歩になるのです。
#肩甲挙筋 #肩こり予防 #ストレッチ習慣 #姿勢改善 #デスクワークケア
ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

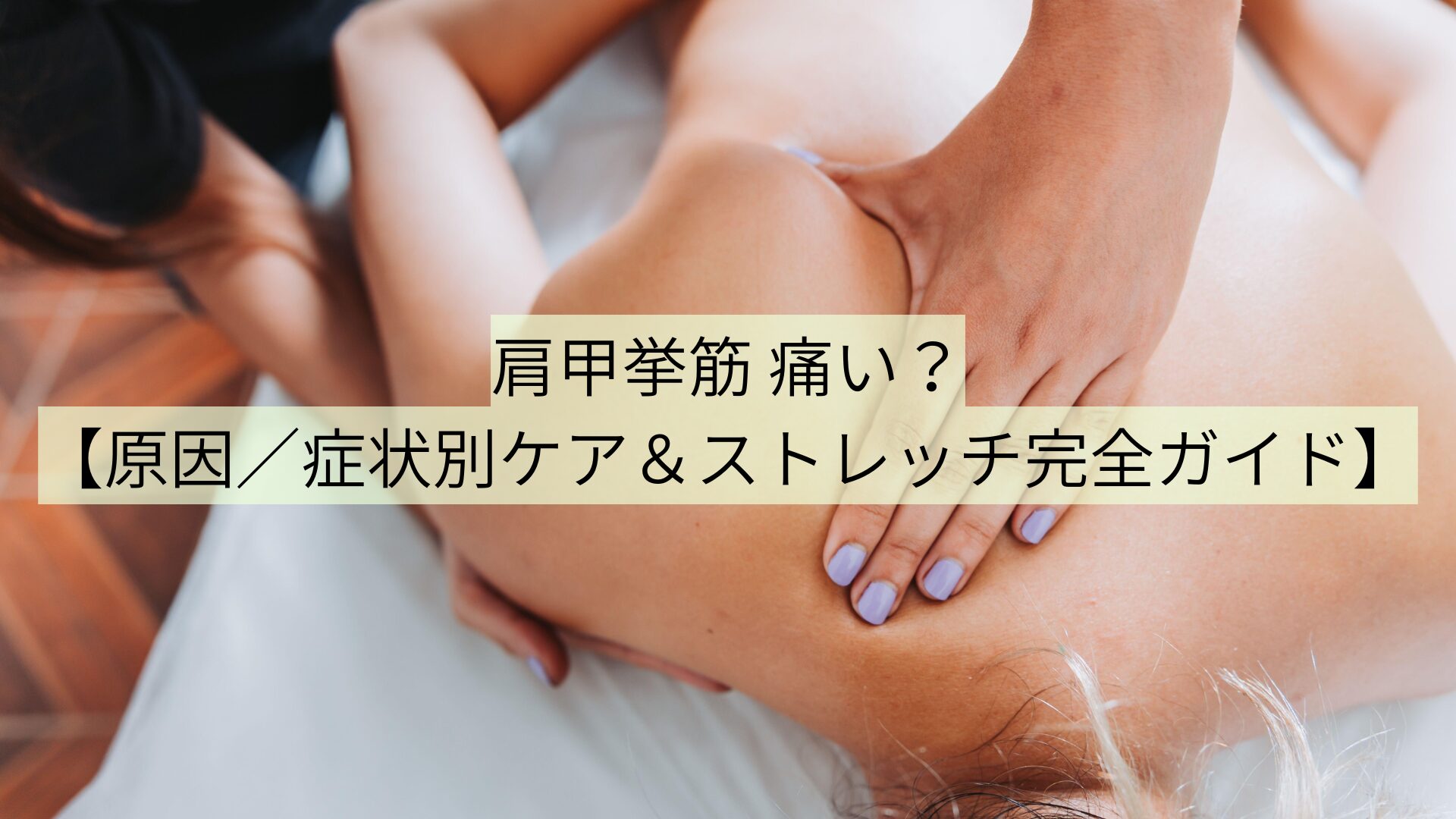

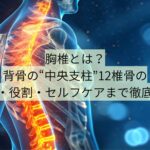
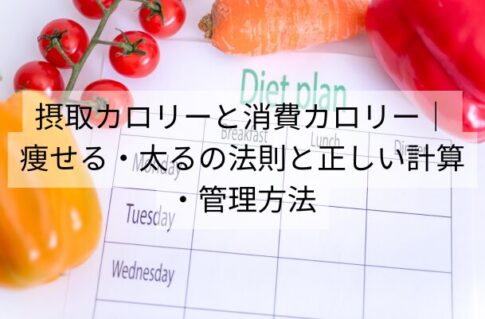

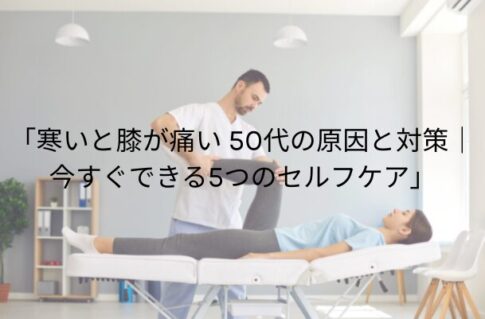

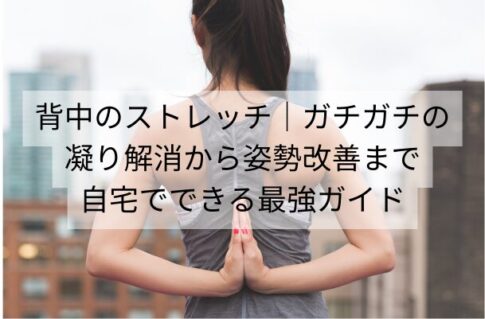
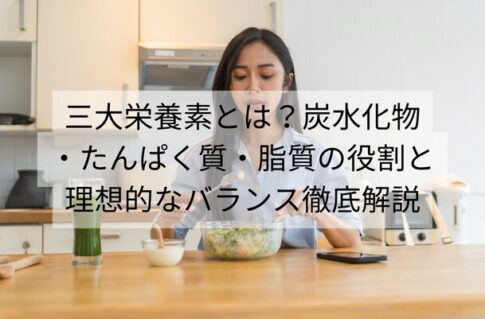











コメントを残す