3.「ツボ押し・筋膜ほぐしでピンポイントケア」
肩中兪のツボ押し+フォームローラーで血流アップ
背中の血流を良くする方法の中でも、ピンポイントで実践しやすいのがツボ押しや筋膜リリースです。特に肩甲骨の内側にある「肩中兪(けんちゅうゆ)」と呼ばれるツボは、血行の改善やこりの軽減に役立つとされています(引用元:くまのみ整骨院)。さらに、テニスボールやフォームローラーを使った筋膜リリースも背中の血流をサポートすると言われています(引用元:yotsuya-blb.com)。
肩中兪のツボ押しでじんわりケア
肩中兪は、肩甲骨の内側・背骨のやや外側に位置すると言われています。押すと心地よい圧を感じやすい箇所で、指や親指で3〜5秒ほどかけてゆっくり押すのがポイントとされています(引用元:くまのみ整骨院)。これを数回繰り返すことで、背中の筋肉がほぐれ、血流のサポートにつながる可能性があるそうです。
フォームローラーで背中の筋膜リリース
ツボ押しだけでなく、フォームローラーやテニスボールを使った筋膜リリースも効果的とされています。背中の下にフォームローラーを置き、仰向けになって体をゆっくり前後に動かすだけで、硬くなった筋膜が緩み、血液やリンパの流れが促されることがあると言われています(引用元:yotsuya-blb.com)。
セルフケアで大切なこと
ツボ押しや筋膜リリースを行う際は「強すぎない圧」が大切だとされています。押しすぎや長時間の刺激は逆に筋肉を緊張させる場合があるため、心地よいと感じる範囲で取り入れるのが安心です。また、日常的に軽い運動や姿勢改善と組み合わせることで、より血流サポートにつながると考えられています。
まとめ
肩中兪のツボ押しやフォームローラーを使った筋膜リリースは、背中の血流を良くする方法として有効とされるシンプルなケアです。ツボを3〜5秒ほどじんわり押したり、フォームローラーで背中を転がすことで、こりの軽減やリラックスを感じる人も多いと言われています。無理のない範囲で取り入れることが、セルフケアの継続につながるでしょう。
#ツボ押し
#筋膜リリース
#フォームローラー
#背中ケア
#血流アップ
4.「姿勢・日常習慣で血流をサポート」
5.「生活習慣と栄養で体の内側からケア」

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。










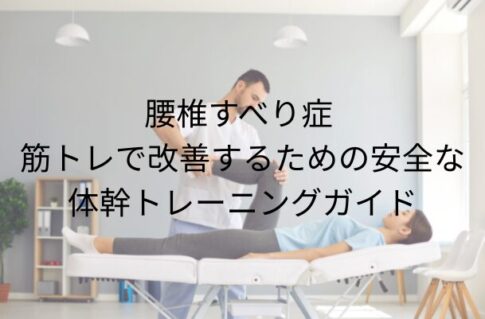

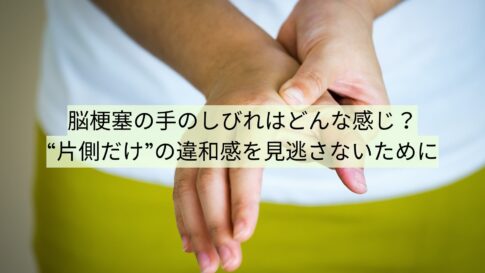
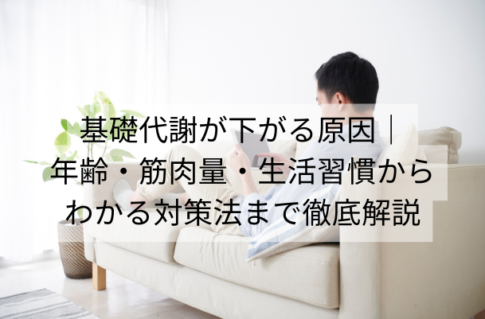
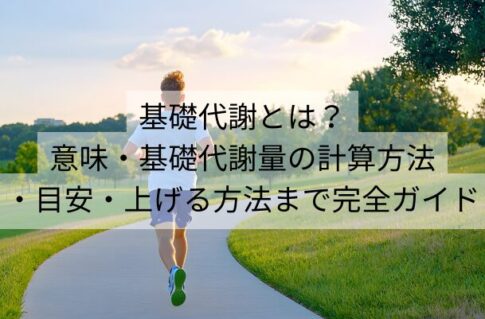
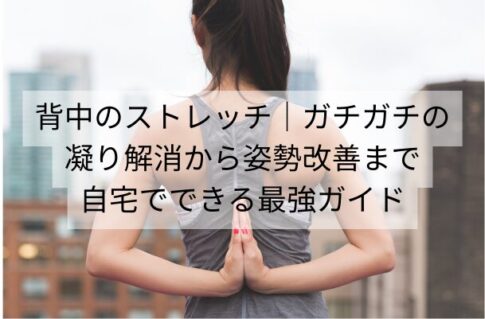
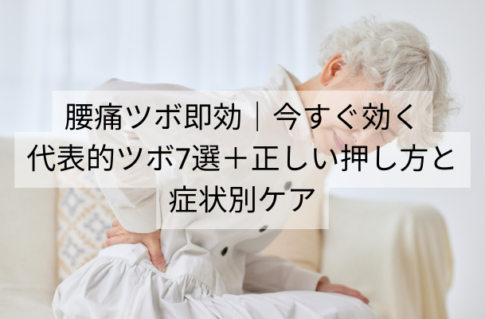
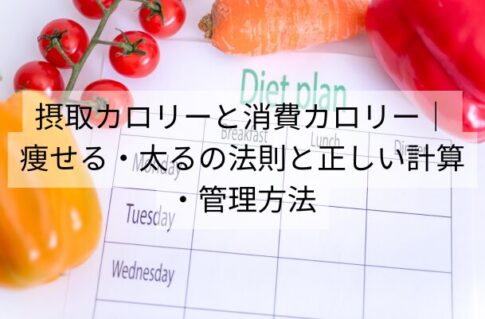




コメントを残す