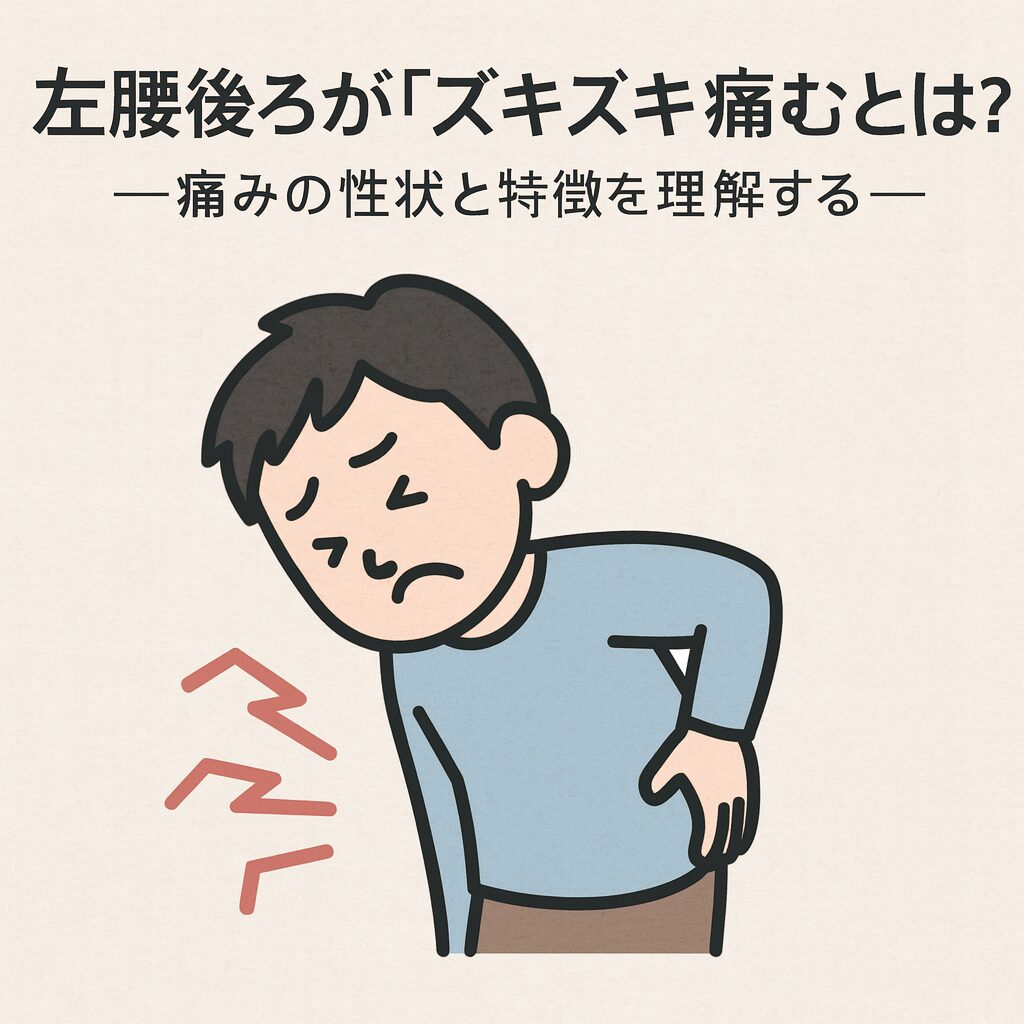
左腰後ろが「ズキズキ」痛むとは?—痛みの性状と特徴を理解する
「左腰の後ろがズキズキ痛むんですけど、これってよくあるんですか?」
そんな声をよく聞きます。まずは、この“ズキズキ”という言葉がどんな痛みを指すのかから整理していきますね。
「ズキズキ」という表現が示す痛みの質
「ズキズキ」は拍動するような痛みや、同じ場所が繰り返し主張するような感覚を指すと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。
たとえば「じっとしていても痛みが気になってくる」「夜になると余計につらい」といった声も多く、体が疲れているときに強まりやすい傾向もあるようです。
僕自身も施術中に相談を受けることがありますが、ズーンとした重さとは違って、どこか“拍つくような痛み”と表現される方が多いですね。
左側に症状が出ることの意味
「なんで左側だけなんですか?」
この疑問もよく聞きます。左腰にズキズキした痛みが偏って出る場合、日常動作の偏りが影響すると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。
たとえば
・無意識に左側へ体重を乗せる癖
・バッグを左肩にかけやすい
・骨盤の左右差
・利き手の影響
こうした積み重ねが、左の筋や関節に負担をかけやすくしてしまうようです。
「そういえば思い当たるかもしれない…」という方、意外と多いんですよ。
痛みが出るタイミングや動作
左腰後ろのズキズキした痛みは、特定の動作の後に感じる人が多いと言われています。
たとえば、
・朝起き上がるとき
・寝返りをうつ瞬間
・長時間のデスクワーク後
・車の運転後
(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)
日常のちょっとした姿勢や負担が、筋肉のこわばりや関節のズレにつながり、ズキズキ感へ影響することがあるようです。
「この動きのあと痛いかも…」という気づきは、改善の第一歩になりますよ。
#左腰後ろの痛み
#ズキズキ痛む理由
#腰痛の気づき
#腰のケア
#痛みの特徴理解

主な原因5パターンと見分け方
筋・筋膜性(腰方形筋・多裂筋など)/姿勢・骨盤の歪み
「左腰の後ろがズキズキして…動くと余計に気になるんですよね」と相談されることが多いのが、この筋・筋膜タイプです。
腰方形筋や多裂筋に負担がかかると、前かがみや体をひねる動きで痛みが強まりやすいと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。
姿勢のクセや骨盤の左右差があると、片側に疲労がたまりやすく、朝の起き上がりで「ズキッ」と感じることも珍しくありません。
実際、「長時間同じ姿勢だったあとに左側だけ重だるい」という声も多く、日常生活の積み重ねが影響しているようです。
椎間関節・椎間板・仙腸関節など関節由来
「反る動きがしづらい」「立ち上がる瞬間にズキッと来る」
こんな特徴があると、関節の影響が疑われると言われています。
特に椎間関節や仙腸関節まわりは、左右どちらかに偏って負担がかかると痛みが出やすい場所です。
デスクワークや車の運転が続いたあとに痛みが出やすい方は、このタイプが当てはまるケースが多い印象ですね。
神経圧迫(坐骨神経痛・椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症)
「腰だけじゃなくて、お尻や脚にも違和感が出る」「しびれっぽい感じがある」
そんな場合は、神経への圧迫が関係していることがあると言われています。
特に椎間板ヘルニアは前かがみ動作で痛みが強まりやすく、脊柱管狭窄症は歩くとつらくなり、休むと楽になるという特徴がよく語られます。
もし脚の力が入りづらい感覚があれば、早めに相談したほうが安心です。
内臓・泌尿器・婦人科由来(腎臓・膵臓・子宮・卵巣など)
「動かなくてもズキズキする」「体勢を変えても痛みが変わらない」
こうしたケースは、内臓や泌尿器の影響があると言われています。
特に腎臓は背中側に近いため、左側に違和感を感じる方もいます。
さらに女性の場合は、子宮や卵巣まわりの影響で腰にズーンとした痛みが出やすいという話もあります。
熱・吐き気・排尿の変化がある時は、早めの来院が安心です。
慢性化・生活習慣・血流低下型(冷え・運動不足・長時間座位)
「座りっぱなしのあとだけ痛む」「冷えてくるとズキズキする」
こんな場合は、血流低下や筋のこわばりが影響していると言われています。
特に冬場やエアコンの効いた室内では、筋が固まりやすく、同じ姿勢が続くことで痛みが増しやすくなります。
軽く動くと楽になる感覚があるなら、このタイプが関係していることがよくありますね。
#腰痛の原因
#左腰のズキズキ
#原因別チェック
#日常動作と痛み
#腰のセルフケア
自宅でできる/今すぐ始めたいセルフケアと生活習慣の改善
安静時・寝姿勢・椅子に座る時の工夫
「横になっている時だけ楽なんですよね…」という話をよく聞きます。左腰の後ろのズキズキを和らげたい場合、まずは寝姿勢を見直すことが大切と言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。
膝の下にタオルを入れると腰の緊張がゆるみやすく、仰向けがしづらい時は横向きで軽く膝を曲げるだけでも楽になる方がいます。「椅子に座ると痛みが気になる…」という方は、体を少しだけ前に倒し、骨盤を立てる意識を持つと負担が分散しやすいようです。
ストレッチ・軽い体操(腰方形筋・中臀筋・腸腰筋など)
左腰後ろのズキズキは、腰方形筋や中臀筋、腸腰筋がこわばっている場合に感じやすいと言われています。
「立ち上がるときに重い感じがする」「歩き始めで違和感が出る」といった方には、軽めのストレッチが役立つ場面もあります。
特に、中臀筋のストレッチは腰回りの余計な緊張が和らぎやすく、腸腰筋のストレッチは姿勢の安定につながりやすいとされています。
温める vs 冷やすの使い分け
「温めた方がいいの?それとも冷やすの?」と質問を受けることも多いです。
一般的には、筋のこわばりや冷えを感じる場合は温めるほうが楽になりやすいと言われています。一方、動いた直後にズキッとした痛みが出たときは、少し冷やすほうが落ち着くケースもあるようです。
どちらも長時間行う必要はなく、短い時間で様子を見ると安心ですね。
姿勢・骨盤バランスの調整
バッグをいつも同じ肩ばかりに掛けている、足を組むのが癖、長時間同じ姿勢で作業している——こうした習慣が積み重なると、左側の腰に偏った疲労が出やすいと言われています。
ちょっとした行動でも、左右を交互に使うだけでバランスが変わりやすく、結果的にズキズキ感の軽減につながるケースがあります。
日常動作の見直し
重い荷物を片側だけで持つ、車の運転で同じ姿勢が続く、パソコン作業で前のめりになる。
これらは腰に負担をかける動作としてよく挙げられています。
「少し姿勢を起こす」「荷物を左右交互に持つ」など、小さな意識でも負担が分散しやすくなり、ズキズキした痛みの予防につながると言われています。
#腰痛セルフケア
#左腰ズキズキ
#生活習慣改善
#姿勢調整
#腰をいたわる習慣
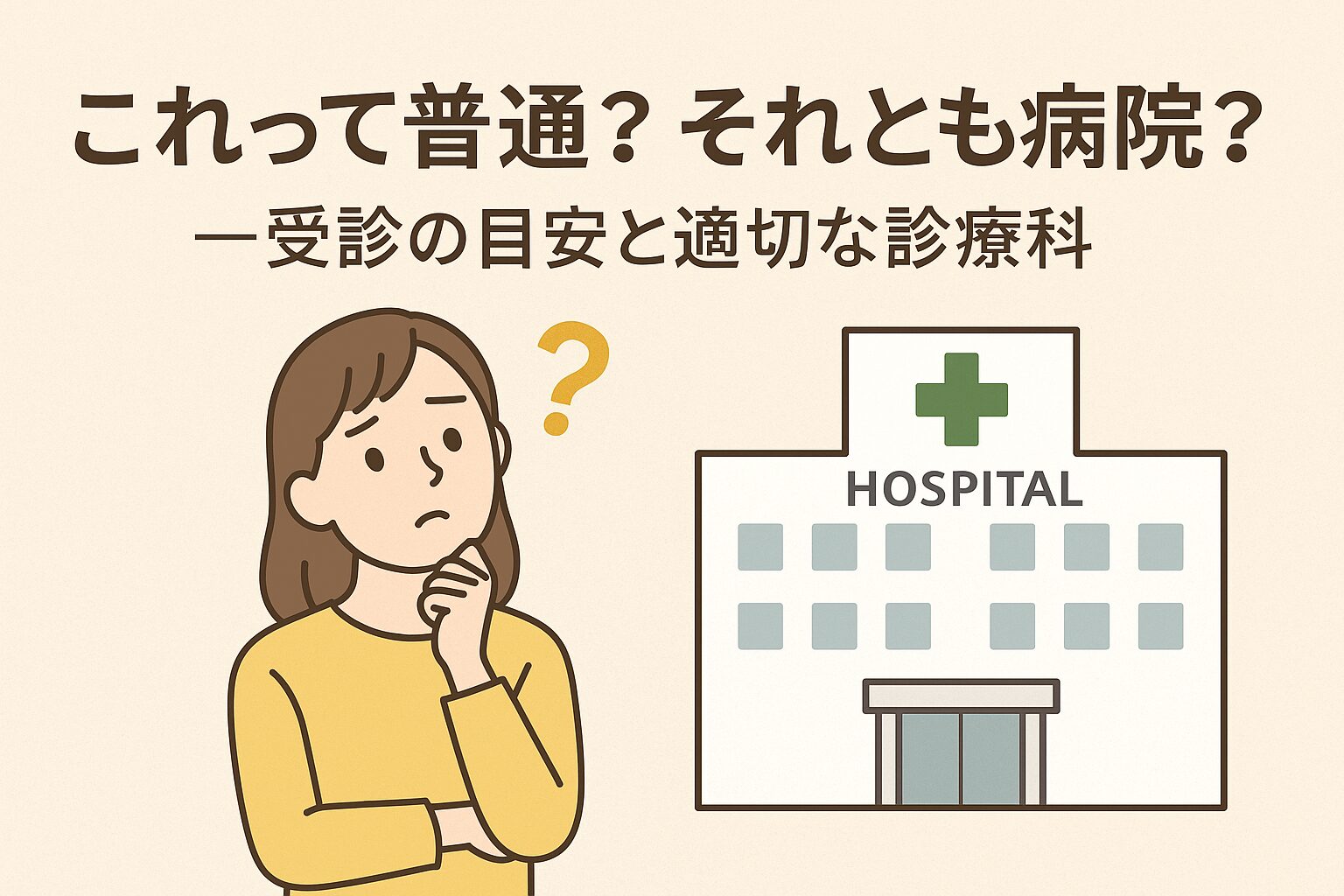
「これって普通?それとも病院?」—来院の目安と適切な相談先
筋・関節由来なら整形外科・整骨・整体などの目安
「動くとズキッとするけれど、じっとしていれば落ち着いてくる」
こんな場合は、筋や関節の影響が考えられると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。
特に、前かがみや反る動作で痛みが変わるときは、整形外科や整骨・整体での触診・姿勢チェックが参考になることがあります。
「とりあえず専門家に体のバランスを見てもらいたい」という時の相談先として選ばれることが多い印象です。
神経症状(しびれ・脚の痛み・力が入りづらい)なら整形外科/脊椎専門医
「左腰だけじゃなくて脚の方まで広がってくる…」
「なんだか力が入りづらい気がする」
このような症状は神経の関与があると言われています。
坐骨神経痛や椎間板の問題が関係するケースもあり、整形外科や脊椎を専門とする医師に相談すると安心です。
歩いている途中で休みたくなる感覚がある場合も、神経系の評価が大切になるとよく言われています。
内臓・泌尿器・婦人科由来なら内科・泌尿器科・婦人科の可能性
「体勢を変えてもズキズキが変わらない」
「熱っぽい・排尿が変な感じがする」
そんな時は、腎臓や泌尿器、婦人科の影響が腰に出るケースがあるとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。
特に左の腎臓付近は腰の後ろ側に近いため、腰痛と間違われやすいようです。
不安な症状がある時は、内科や泌尿器科、婦人科での検査が安心につながります。
来院を急ぐべきサイン
・夜中に痛みで目が覚める
・安静にしてもズキズキが引かない
・脚のしびれが強い
・排尿時の違和感・血尿
・発熱がある
これらは「早めに相談されたほうがいい」と言われるケースです。
痛み以外のサインが出ているときは、無理せず医療機関に問い合わせたほうが良いですね。
来院時に聞かれやすい問診と検査の流れ
整形外科や内科では、まず「どんな時に痛むのか」「いつからか」を詳しく聞かれることが多いです。
その後、必要に応じてレントゲンやMRI、血液検査、尿検査などを組み合わせて、痛みの背景を確認すると言われています。
整体や整骨院では、姿勢・動きの癖・筋の硬さなどを触診し、日常生活のアドバイスや施術の提案が行われる流れが一般的です。
#腰痛の相談先
#左腰ズキズキ
#受診目安
#神経症状チェック
#内臓由来の可能性
再発を防ぐための長期ケア・痛みにくい体をつくる習慣
体幹筋・インナーマッスルを鍛える簡単エクササイズ
「また左腰の後ろがズキズキするようになったらイヤだな…」
そう感じる方にまずおすすめされるのが、腹横筋や多裂筋といったインナーマッスルを使う動きです。
大げさな運動ではなく、ゆっくりとお腹をへこませるドローインや、四つ這いで手足を伸ばすエクササイズは、腰まわりを安定させやすいと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。
「運動が苦手」という方でも、1日1〜2分から始められるので取り入れやすいですよ。
ストレッチ習慣と血流促進(ウォーキング・ラジオ体操)
腰方形筋やお尻まわりが固まってくると、同じ姿勢が続くだけで痛みが出やすくなると言われています。
軽めのストレッチやウォーキングは血流が上がりやすく、ズキズキ感の予防にもつながりやすいようです。
「ラジオ体操ぐらいならできるかも」
そんな気持ちで始めてみると意外と続きやすく、習慣的なケアとして取り入れやすいですね。
寝具・寝姿勢・マットレス・枕の見直し
実は、寝ている間の姿勢が腰の負担に影響するケースもあると言われています。
柔らかすぎるマットレスや、高さの合わない枕は体が沈みやすく、腰が反りやすい状態を作りがちです。
仰向けだと腰が浮く感覚がある場合は、膝の下にタオルを入れたり、横向きの姿勢で膝を軽く曲げると楽になる方が多いです。
定期的なセルフチェックリスト
・足を組むクセが出ていないか
・左右の重心が偏っていないか
・長時間座りっぱなしになっていないか
・疲れが溜まっているサインが出ていないか
こうした点をこまめに確認するだけでも、痛みの再発を防ぎやすいと言われています。
「気づいたときに直す」という小さな積み重ねが大事ですね。
生活習慣と“腰を大切にするマインドセット”
運動量・水分・栄養・睡眠・ストレス——これらは腰の状態に影響しやすいと言われています。
特に水分が不足すると筋がこわばりやすいとも言われており、こまめな水分補給は意外と大切です。
「腰をいたわる意識」を持つだけで、自分の体の変化に気づきやすくなり、痛みにくい体づくりにつながります。
#腰痛予防習慣
#左腰ズキズキ対策
#インナーマッスルトレ
#生活習慣でケア
#再発予防ケア

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

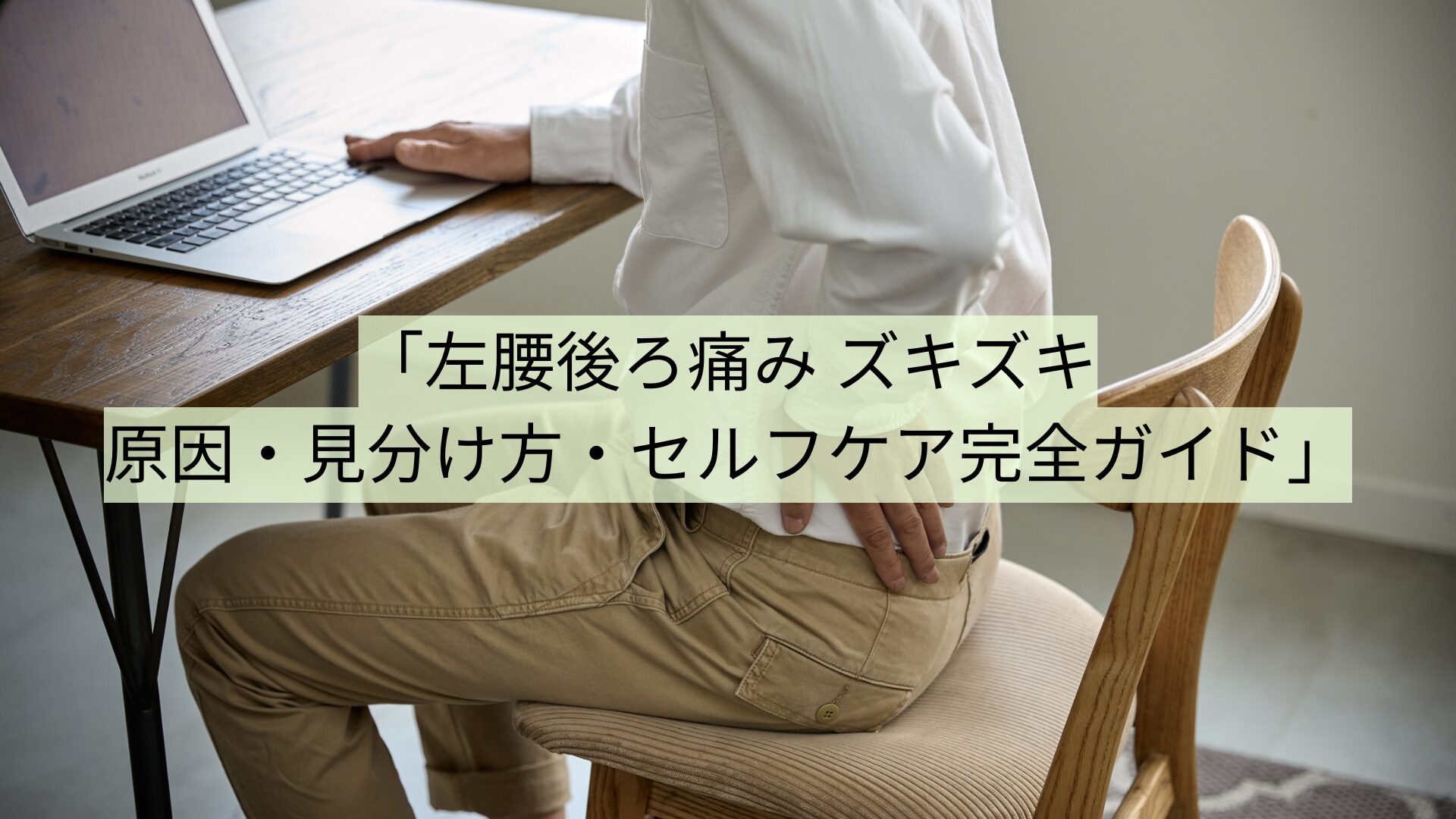


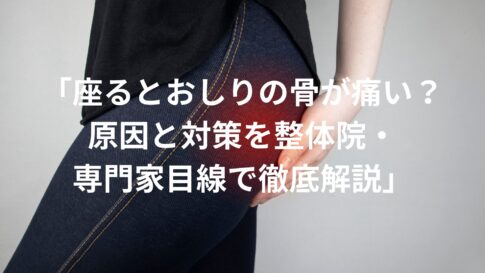
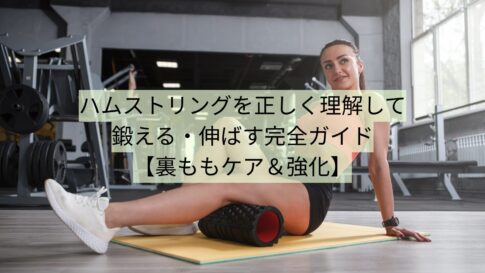
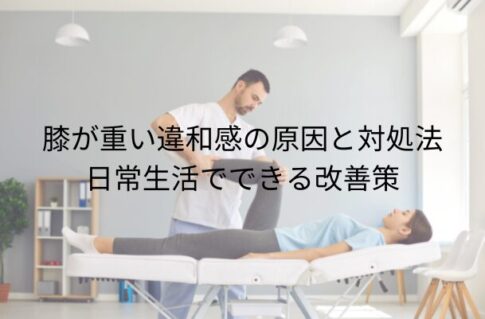


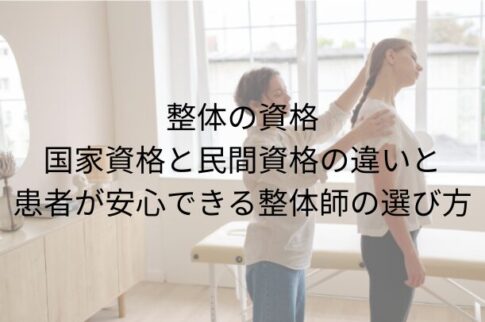
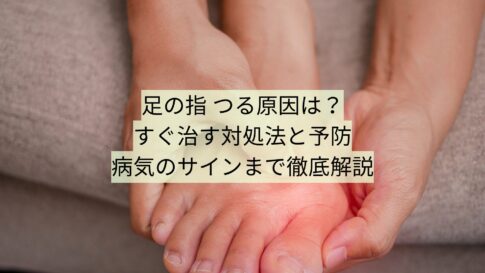














コメントを残す