妊婦 お腹つるとは?症状の特徴と安心ポイント
「お腹がつる」という表現は、妊娠中の方がよく口にする症状のひとつです。これは、急にお腹の筋肉がキュッと硬くなり、動けなくなるほどの違和感や痛みを伴うことが多いと言われています。特に、夜間の寝返りや朝起き上がるとき、立ち上がった瞬間など、急な動作のタイミングで起こりやすい傾向があるようです。「同じ経験をしている人が意外と多い」という事実は、不安を和らげる材料にもなります。
どんな痛み?そしていつ起こりやすいのか
実際の感覚は「ふくらはぎのこむら返り」に似ており、腹部の奥がキュッと縮こまるような感覚だと表現されます。多くの場合、数十秒から数分で落ち着くことが多いと言われていますが、強い張りを感じる場合もあります
起こりやすいのは、以下のような場面です。
-
夜、寝ているときに寝返りを打った瞬間
-
起床してベッドから起き上がるとき
-
長時間同じ姿勢を続けたあと急に立ち上がったとき
-
重い荷物を持ち上げようとしたとき
妊娠中はホルモンの影響で筋肉や靱帯が柔らかくなりやすく、姿勢の変化や体重の増加も相まって、お腹の筋肉に負担がかかりやすくなると言われています
「痛みがあると心配になるけど、多くの妊婦さんが同じような経験をしている」という事実を知るだけでも、少し気持ちが楽になるかもしれません。もちろん、頻度が多かったり痛みが強い場合は、無理せず専門家に相談することが大切です。
#妊婦お腹つる
#妊娠中の症状
#夜間の腹部痙攣
#寝返り時の痛み
#マタニティケア
(引用元:https://rehasaku.net/magazine/lower/sciatica-pregnantwoman/)
(引用元:https://oasisseitai.com/pregnant-abdominal-cramp/)

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

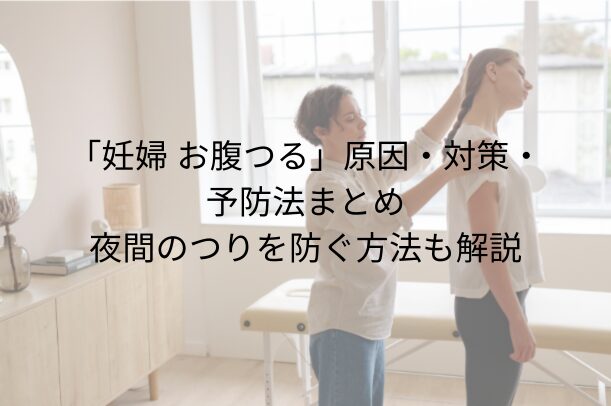

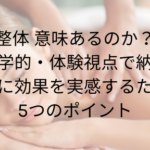


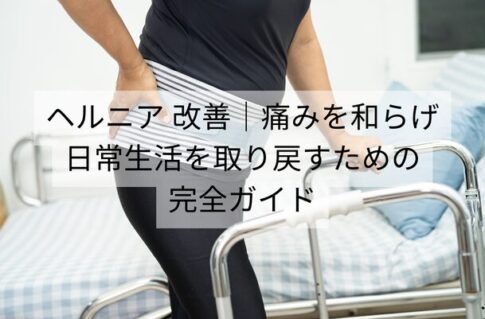




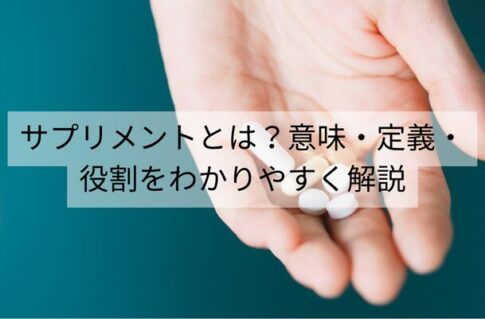













コメントを残す