「股割り」とは?o脚との関係を知る
股割り(左右開脚・開脚ストレッチ)の定義と目的
「股割りって、そもそも何のためにやるの?」と聞かれることがよくあります。股割りは、左右に足を開いて股関節まわりをゆっくり伸ばす開脚ストレッチのことで、主に内ももの柔軟性を高め、骨盤を安定させるために使われる方法と言われています。
開脚をするときのポイントは、無理に広げるのではなく、骨盤を立てたまま前に倒していくことなんですね。これだけでも股関節まわりの動きがスムーズになりやすいと言われています。
「じゃあ、これがどうしてo脚と関係するの?」と疑問に思いますよね。実は、o脚の方は内ももがうまく使いづらく、太ももの外側ばかり緊張する傾向があるとされています。このバランスの崩れが、脚のラインの乱れにつながると言われているんです。
o脚のメカニズム・なぜ股関節・骨盤が関係するのか
o脚は、膝だけの問題ではなく、股関節と骨盤の位置が大きく関わるとされています。例えば座り方の癖や歩き方の特徴によって骨盤が後ろに傾いたり、股関節がねじれた状態が続くと、膝の向きにも影響が出ると言われています。「膝が外に向きやすい感じがする…」という方は、この股関節のクセが関係することもあるとされています。
実際、「股関節が硬くて、お尻が後ろに倒れやすいんだよね」と相談されることも多いのですが、この状態だと脚全体の軸が安定しづらく、結果としてo脚の見た目が強まりやすいと言われています。(引用元:https://stretchex.jp/5032)
なぜ「股割り」がo脚ケアに有効と言われるのか(メリット・根拠)
股割りがo脚ケアに使われる理由として、内もも(内転筋)や股関節の柔軟性が高まると、脚の軸が整いやすいと言われているためです。柔らかくなることで膝とつま先の向きがそろいやすく、骨盤も立ちやすくなるため、日常動作のクセが変わっていく可能性があると言われています。
もちろん、股割りだけですぐに脚がまっすぐに「改善する」とは断言できませんが、姿勢や脚の使い方を整える土台づくりとして役立つと言われています。実際に、「続けていたら脚が使いやすくなった気がする」という声はよくあります。
(引用元:https://stretchex.jp/5032)
#股割りの基本
#o脚と股関節の関係
#骨盤のバランス
#内転筋ストレッチ
#脚の軸を整えるケア
o脚チェック&原因をセルフ診断しよう
自分の脚の形(膝・太もも・ふくらはぎの隙間など)を確認する方法
「私って本当にo脚なのかな?」と感じたとき、まずは今の脚の状態をざっくり把握しておくと分かりやすいです。壁にかかと・お尻・背中をつけて立ち、膝や太もも、ふくらはぎのどこにどれくらい隙間があるか確認してみてください。
実際、多くの方が「思ったより膝が開いて見える…」と気づくことがあるようです。膝の位置だけでなく、つま先の向きや体重がどちらにかかりやすいかも見ておくと、自分の癖がつかみやすいと言われています。
また、左右差が大きいタイプもあり、「右だけ膝が外に向きやすい」などの特徴がある場合もあるとされています。数値で測る必要はなく、まずは立ち姿勢のクセをざっくり把握するのがコツですね。(引用元:https://stretchex.jp/5032)
o脚になりやすい生活習慣・姿勢
話していると、「座る時に気づいたら足を組んでるんですよね…」という方が本当に多いです。足を組むクセや、ぺたんこ座り(W座り)、骨盤が後ろに傾いた姿勢は、股関節のねじれや筋肉バランスの偏りにつながりやすいと言われています。
「長時間スマホをいじって気づいたら背中が丸まってた」なんて経験、ありますよね。この姿勢も骨盤が後ろに倒れやすく、その状態が続くと膝の向きにも影響が出ると言われているんです。
歩き方にもクセが出やすく、つま先が外に向きやすい人は、股関節の外旋が強まりやすいと言われています。こうした小さな習慣が積み重なることで、結果的に脚のラインに表れやすいと考えられています。
股割りを始める前に知っておきたい注意点(構造的o脚 vs 機能的o脚)
股割りはo脚のケアとして使われることがありますが、始める前に知っておきたいのが「構造的o脚」と「機能的o脚」の違いです。
構造的o脚は骨の形によるもので、ストレッチだけで大きく変化しづらいタイプと言われています。一方、筋肉の硬さや使い方のクセが原因の機能的o脚は、股関節まわりが動きやすくなると、見た目が変わりやすいと言われています。
「自分はどっちなんだろう?」と思ったら、無理のない範囲で股割りを試しながら、股関節が動きやすくなる感覚があるか確認してみるのが良いかもしれません。
ただし、痛みが強い場合や股関節の動きに不安がある場合は、専門家の触診を受けて状態を見てもらうのもひとつの方法と言われています。(引用元:https://stretchex.jp/5032)
#o脚セルフチェック
#脚の隙間確認
#生活習慣と姿勢
#構造的o脚と機能的o脚
#股割り前の注意点
股割りでo脚を改善するための正しいやり方
準備動作:ウォームアップ・太もも外側・内もものストレッチ
「いきなり股割りをすると、どうしてもうまく開かないんですよね…」という声はとても多いです。股関節まわりが固い状態だと前に倒れづらくなるため、最初は軽いウォームアップを入れておくと良いと言われています。例えば、骨盤を左右にゆらす動きや股関節の曲げ伸ばしを繰り返すだけでも体が温まりやすいです。
続いて、太ももの外側と内ももを順番に伸ばしておきましょう。外側は横向きのストレッチ、内ももは片足ずつ伸ばすと入りやすいです。「これだけでも前より動きやすい感じがする」という方も多いと言われています。(引用元:https://stretchex.jp/5032)
股割りのフォーム&ポイント(骨盤を立てる・腰を丸めない・内ももを意識)
実際に股割りの姿勢に入る時は、開脚の角度よりも「骨盤が立っているかどうか」が大事だとされています。「どれくらい開けば正解ですか?」と聞かれることがありますが、無理に開くよりも、背筋を伸ばして骨盤をまっすぐ保つ意識がまず大切です。
腰が丸まると内ももに伸び感が入りにくくなるので、お腹を軽く前に引き上げるようにすると姿勢が保ちやすいです。内ももがじわっと伸びる感覚が出てきたら、そのまま呼吸を繰り返しながら少しずつ前に倒してみてください。
「これで合ってるのかな…?」と不安になる時は、太ももとつま先の向きがそろっているかを見ると分かりやすいです。
初心者向けバリエーションとステップアップ例
初心者の場合、両足を大きく開いて座るのが難しいことがあります。その場合は、片足ずつ開くハーフ開脚から始めると動きが取りやすいと言われています。
慣れてきたら、クッションやヨガブロックをお尻の下に入れると骨盤が立ちやすくなり、前屈がしやすくなることがあります。また、上体を左右に倒すストレッチを組み合わせると、太もも内側の細かい部分に刺激が入りやすくなると言われています。
ステップアップとしては、呼吸を使いながらゆっくり前に倒す「静的ストレッチ」をベースに、股関節の可動域を広げる軽い動きを追加してみるとバランスが取りやすいです。
よくあるNG動作とそのリスク(反動をつける・無理に180度を目指す)
「開かないから勢いをつけちゃうんですよね…」という方もいますが、反動を使う動きは筋肉を痛めやすいとされています。特に太もも内側は繊細なので、急に引き伸ばされる動きは負担が大きいと言われています。
また、180度の開脚を目指す必要はありません。むしろ、無理に広げることで骨盤が後ろに倒れ、逆に内ももが伸びにくくなると言われています。
「痛気持ちいいくらい」で止めておく方が継続しやすく、結果として股関節が動きやすい状態になりやすいと言われています。(引用元:https://stretchex.jp/5032)
#股割りのやり方
#ストレッチ準備
#骨盤を立てるフォーム
#初心者バリエーション
#NG動作とリスク
よくある質問と安全に継続するためのヒント
「どれくらいで効果が出る?」「180度開かないと意味ない?」などFAQ形式で
股割りについて相談を受けると、「どのくらい続ければ変化を感じられますか?」という質問がよくあります。これは個人差が大きいのですが、股関節まわりが少しずつ動きやすくなる感覚は、続けていると出やすいと言われています。
ただ、「1週間で絶対こうなる」といった決めつけはできませんので、まずは無理のない範囲で続けることが大切ですね。
次に多いのが「180度まで開かないと意味ないんですか?」という質問です。これも心配しなくて大丈夫で、180度を目指す必要はないと言われています。むしろ、無理に広げようとすると骨盤が後ろに倒れ、内ももにうまく刺激が入らなくなることもあるとされています。(引用元:https://stretchex.jp/5032)
大切なのは角度ではなく、内ももがじわっと伸びる感覚があるかどうかなんですね。「思ったより気持ちよく伸びた」という感覚があれば、それだけでも目的に近づきやすいと言われています。
ケガ・股関節変形・痛みがある場合の注意点と専門家相談の目安
「やってみたいけど、痛みがある時はどうすればいいですか?」という相談も多いです。股割りは無理のない範囲で行うことが前提と言われていますが、鋭い痛みが出る場合はやめておいた方が安心です。
股関節に変形がある可能性が心配な場合や、動かすと強い違和感を伴う時は、整形外科での触診を受けて現在の状態を確認してもらうことも検討してみてください。痛みを我慢して続けるのはおすすめされていません。
また、筋肉痛のような軽い張りであれば、ウォームアップを丁寧に行うことで動きやすくなる場合もあります。いずれにしても「痛いけど頑張ろう」という方向ではなく、体と相談しながら取り組む方が安全と言われています。
続けるためのモチベーション維持/記録の取り方/効果のチェック方法
股割りを続けるコツとして、「記録を残すと楽しくなる」と言われています。例えば、週に1回でいいので開脚の角度を写真に残したり、膝の隙間がどれくらいあるかをメモしておく方法があります。
「前より骨盤が立てやすくなった気がする」「足が軽い感じがする」など、数字以外の体感を書いておくのもモチベーション維持に役立ちます。
効果のチェックには、壁に背中とお尻をつけた状態で立ち、膝の隙間を確認するだけでも十分と言われています。日々の変化は小さくても、継続していくことで「続けてよかった」と感じやすくなるはずです。(引用元:https://stretchex.jp/5032)
#股割りFAQ
#180度開脚は不要
#痛みがある時の注意
#記録のコツ
#効果のセルフチェック

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

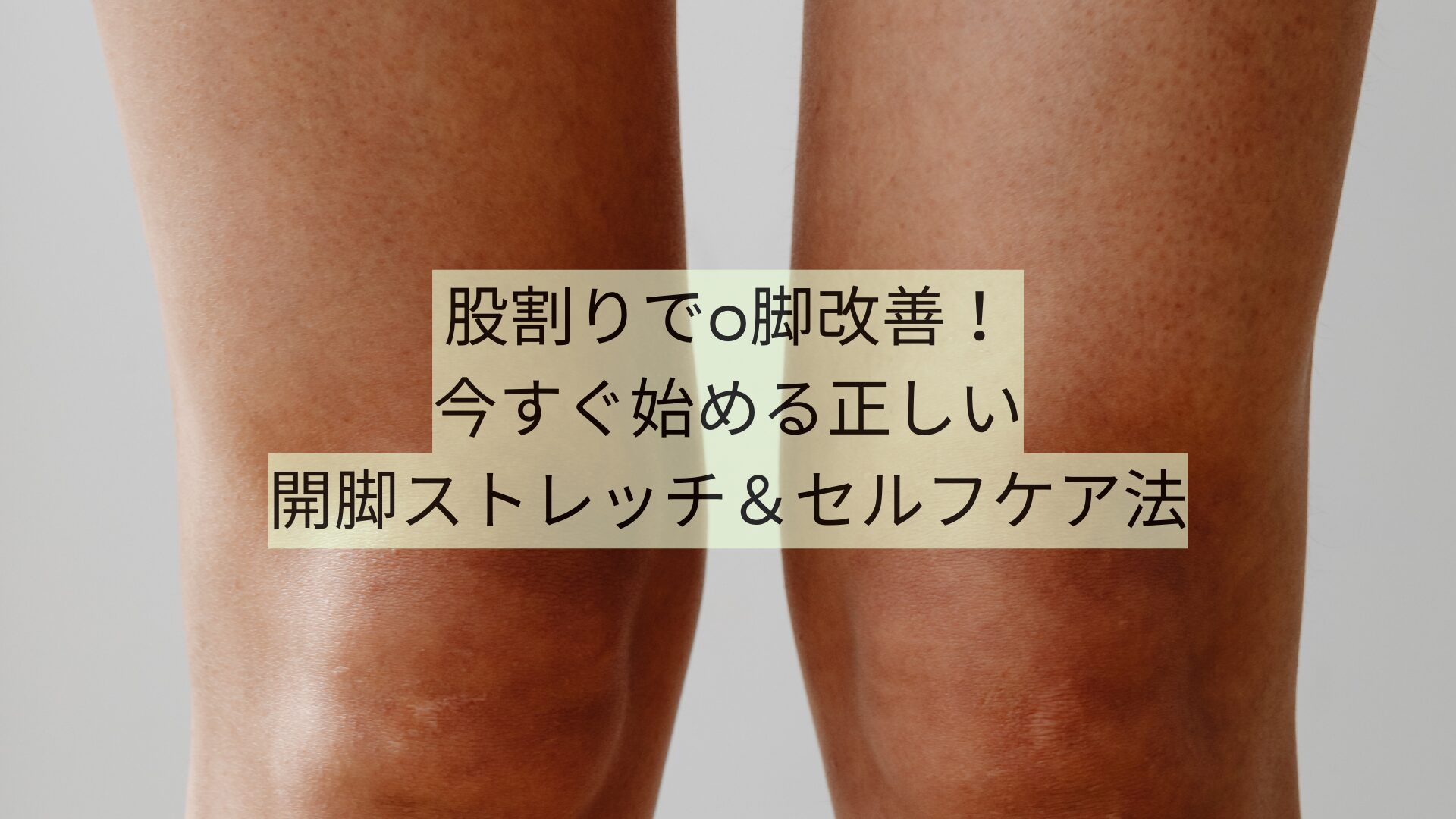


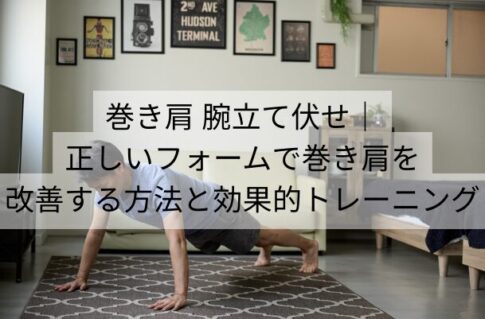





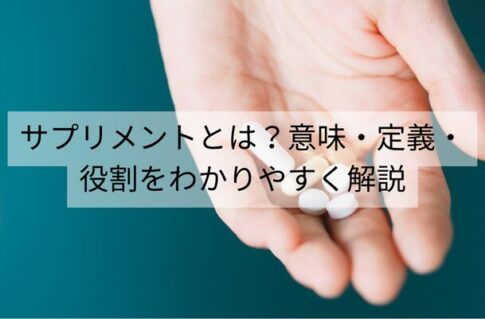














コメントを残す