1.ぎっくり腰って何?
「ぎっくり腰」という言葉はよく耳にしますが、医学的には「急性腰痛症」と呼ばれるものです。突然腰に強い痛みが走り、動けなくなることが多いと言われています。多くの場合、腰の筋肉や靭帯、筋膜といった組織に急激な負担がかかり、炎症が起こることで痛みが生じると考えられています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog)。
ただし、骨がずれたり大きな異常があるわけではないケースが多く、「魔女の一撃」とも表現されるように、ある瞬間に強烈な痛みが走るのが特徴です。
なぜ起こるのか?ぎっくり腰のメカニズム
ぎっくり腰は、重い荷物を持ち上げた時や体をひねった瞬間、あるいはくしゃみや咳などの小さな動作でも発症することがあります。これは、腰の周辺組織が疲労や柔軟性の低下によって弱っている状態で、急激なストレスが加わることが原因とされています。
たとえば、普段から同じ姿勢で長時間作業していたり、運動不足で筋肉が硬くなっていると、腰のバランスが崩れて小さなきっかけでも炎症が起きやすくなると言われています(引用元:https://hitomiru-clinic.com/blog/post-536/)。
痛みの正体と体の反応
痛みの強さには個人差がありますが、炎症によって周辺の筋肉が硬直し、さらに体を動かしにくくなることが多いです。体が「これ以上動かすと危険だ」と判断して防御反応を起こしていると考えられており、その結果として動作が制限されてしまいます。
「少し休めばよい」と軽く見られることもありますが、実際には日常生活に大きな支障をきたすため、適切な対応が求められるとされています(引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-393/)。
誤解されがちな「骨がずれた」説
「ぎっくり腰になると骨がずれる」と思う人も少なくありませんが、実際には骨がずれるケースはほとんどなく、炎症や筋肉の緊張による痛みが主体だと言われています。これは整骨院や医療機関でも繰り返し説明されている点で、正しく理解しておくことが予防や改善にもつながります。
まとめ
ぎっくり腰は「急性腰痛症」という名前が示す通り、急に起こる腰のトラブルです。その背景には筋肉や靭帯、筋膜の炎症が関係していると考えられています。無理な動作や日常の体の使い方のクセが引き金になることが多いため、発症の仕組みを知ることが再発予防の第一歩になると言えるでしょう。
#ぎっくり腰
#直し方
#急性腰痛症
#腰痛予防
#原因とメカニズム

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

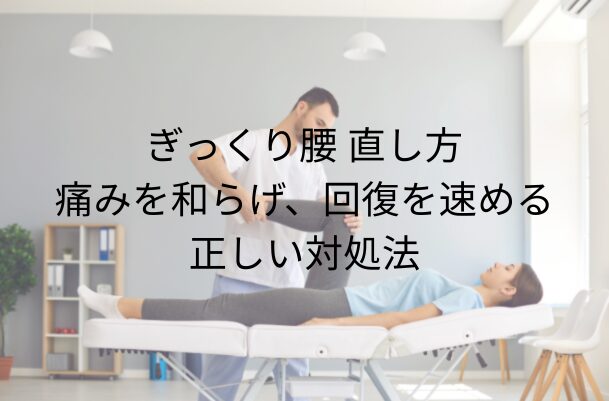








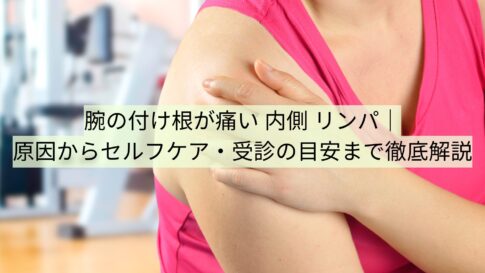
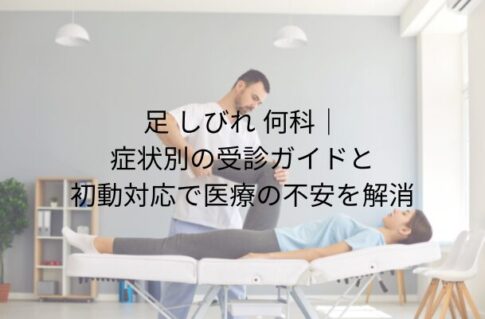










コメントを残す