
ギヨン管症候群とは?原因・症状をやさしく理解
ギヨン管と尺骨神経の仕組み
手首の小指側には「ギヨン管」と呼ばれる細いトンネルのような部分があります。この中を通るのが尺骨神経で、指先の感覚や筋肉の働きに関わっていると言われています。もしこの部分が圧迫されると、神経がスムーズに働かなくなり、小指や薬指のしびれが出たり、手の筋肉がうまく動かなくなることがあるようです。特に、細かい動作がしづらいと感じる方もいるとされています(引用元:miyagawa-seikotsu.com)。
主な症状と見られる特徴
ギヨン管症候群の代表的な症状は、小指や薬指のしびれです。さらに進行すると、指の間の筋肉が少しずつ痩せてきたり、力が入りにくくなることもあると言われています。例えば、ペンを握る動作や細かい手作業が不便に感じるケースもあるそうです。こうした症状は人によって差があり、軽度の違和感から日常生活に影響が出る場合まで幅広いのが特徴です(引用元:ぎの整体院 ginoseitaiin.jp)。
原因として多いもの
原因はさまざまですが、よく見られるのは「手首への圧迫」や「繰り返し動作による負担」だと言われています。たとえば、自転車のハンドルを強く握る、パソコンのキーボードやマウスを長時間使うなど、日常的な習慣がきっかけになりやすいそうです。スポーツや仕事で手首を酷使する方にも起こりやすいと報告されています(引用元:miyagawa-seikotsu.com, shimoitouzu-seikotsu.com)。
似た症状との違い
ギヨン管症候群と間違われやすいのが「手根管症候群」や「肘部管症候群」です。手根管症候群は親指から中指にかけてのしびれが特徴で、ギヨン管症候群とは指の範囲が異なります。一方で、肘部管症候群は肘の内側で神経が圧迫されるもので、小指側のしびれは似ていますが、原因となる部位が異なると言われています。このように見極めが必要なケースも多いため、症状が長引く場合は早めに専門家へ相談することが大切とされています(引用元:shimoitouzu-seikotsu.com)。
#ギヨン管症候群
#ストレッチと症状
#小指薬指のしびれ
#手首の圧迫原因
#似た症状との違い


皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています





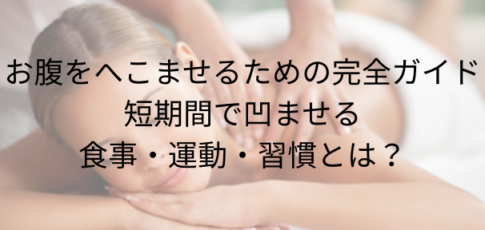
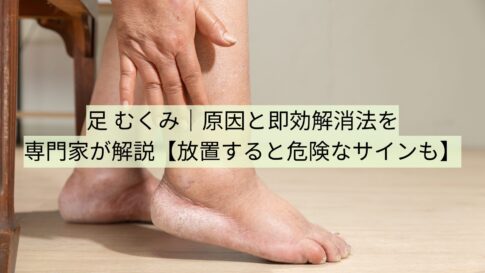

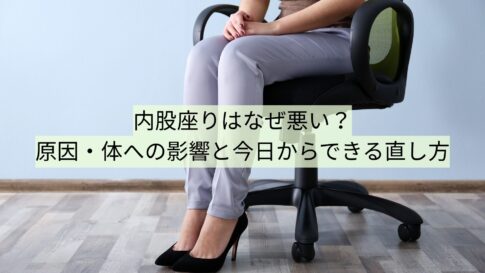


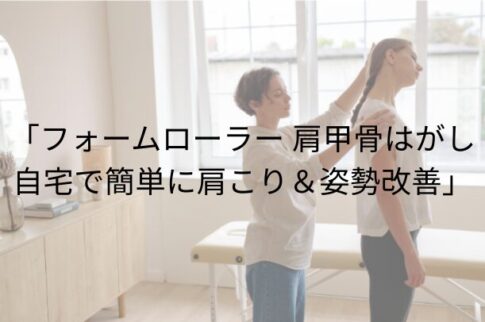
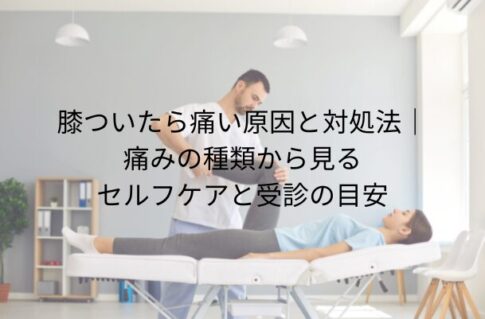




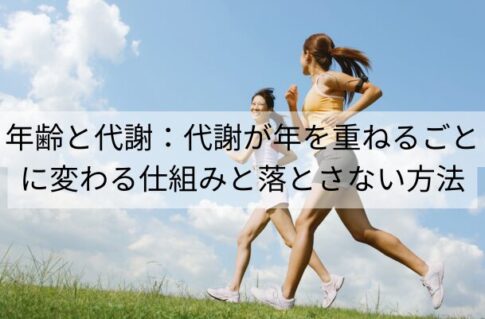
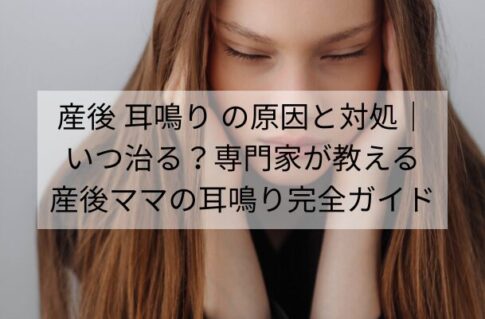
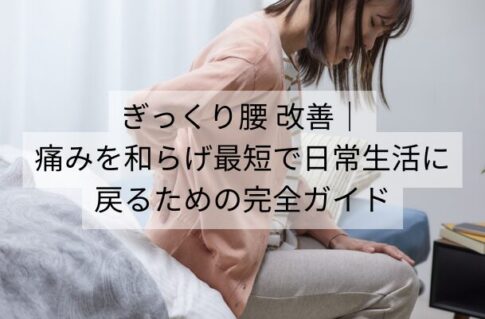
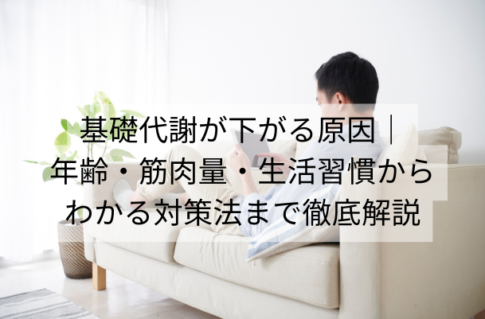
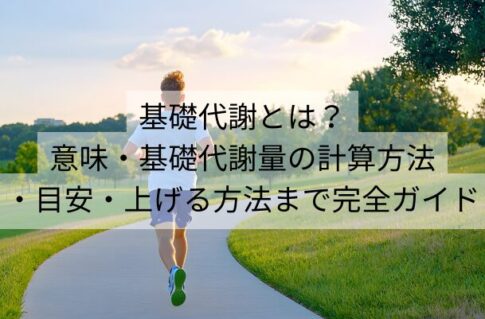




コメントを残す