ランナー膝とは?湿布でできること・できないこと
腸脛靭帯炎の基本知識とランナー膝のメカニズム
「ランナー膝」という呼び名は一般的ですが、正式には**腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)**と呼ばれています。太ももの外側を走る腸脛靭帯が、膝の外側で大腿骨とこすれることで炎症が生じると考えられています。走る距離が長いランナーや、フォームに偏りがある人に起こりやすいとされ、「膝の外側がズキッと痛む」「走り始めは平気でも距離が延びると痛みが強まる」といった特徴があると言われています(引用元:みやがわ整骨院, https://miyagawa-seikotsu.com/blog/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E8%86%9D%E3%81%AB%E6%B9%BF%E5%B8%83%E3%81%AF%E5%8A%B9%E3%81%8F%EF%BC%9F%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%A8%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%99)。
湿布による痛み・炎症の一時的緩和の役割
膝の外側に炎症や痛みが出ている時、湿布を貼ることで「ズキズキ感が和らぐ」といった一時的な効果を感じる方も多いようです。特に炎症が強い初期には、冷湿布で熱感や痛みを落ち着かせることができると言われています。逆に、慢性的にこわばりを感じるような時には、温湿布で血流を促し、動かしやすくする方法もあります(引用元:ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院, https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/5856)。
ただし、湿布の効果はあくまで「対症的なケア」であり、炎症の根本原因を取り除くものではないと説明されています。つまり、痛みを一時的に抑えてくれるサポート役ではあるものの、湿布だけで改善に直結するわけではない、と考えられています(引用元:みやがわ整骨院, https://miyagawa-seikotsu.com/blog/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E8%86%9D%E3%81%AB%E6%B9%BF%E5%B8%83%E3%81%AF%E5%8A%B9%E3%81%8F%EF%BC%9F%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%A8%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%99)。
湿布でできないことと注意点
「湿布を貼っているから大丈夫」と思って走り続けると、炎症が長引いたり慢性化してしまうリスクがあるとも言われています。根本的な改善のためには、ランニングフォームの見直しやストレッチ、筋力バランスの調整といったセルフケアが必要です。湿布はあくまで「痛みを和らげる補助的な手段」として捉え、無理を重ねないよう意識することが大切だと考えられています。
#ランナー膝
#湿布の役割
#腸脛靭帯炎
#スポーツケア
#セルフケア
冷湿布 vs 温湿布:使い分けガイド
痛みの初期(熱感・ズキズキ)には冷湿布を
ランナー膝による痛みが出たばかりの時期、膝の外側に「ズキズキするような鋭い痛み」や「熱っぽい感じ」がある場合には、冷湿布がよいと言われています。冷湿布にはメントールなどの成分が含まれており、貼った部分がひんやりと感じられます。この冷感によって、炎症が強くなっている部位の違和感を和らげることができるとされています。特に走った直後や、膝が腫れぼったいように感じるときは冷湿布を選ぶ方が多いようです。あくまで痛みを鎮める一時的なケアとして使うことが推奨されているため、貼り続ければ改善するというわけではない点に注意が必要です(引用元:四ツ谷BLBはり灸整骨院, https://yotsuya-blb.com/blog/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E8%86%9D-%E6%B9%BF%E5%B8%83%EF%BD%9C%E8%B2%BC%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%83%BB%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9%E3%82%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6)。
慢性的なこわばり・違和感には温湿布を
一方で、膝の外側に「じんわりした違和感」や「こわばり感」が続くような場合には、温湿布の方が合うと言われています。温湿布は血流を促す目的で使用されることが多く、慢性期にありがちな筋肉や腱の緊張感をやわらげるサポートになると考えられています。実際に、膝が固まったように動かしづらい時や、長時間座った後に走ると痛みが戻るようなケースでは、温湿布で温めてからストレッチを行うと動きやすいと感じる人もいるようです(引用元:四ツ谷BLBはり灸整骨院, 同上)。
感覚重視の選び方と注意点
ただし、湿布は薬効そのものよりも「冷感」「温感」といった体感を得ることが中心であると説明されています。そのため、冷やしたほうが楽に感じるか、温めたほうが心地よいかといった“感覚”を目安に選ぶのも一つの方法とされています。注意点としては、長時間貼りっぱなしにしないこと、肌のかぶれやすい人は短時間の使用にとどめること、そして痛みが数日以上続く場合は専門家へ相談した方がよいと言われています。湿布だけに頼らず、ストレッチやランニングフォームの調整をあわせて行うことが、改善のためには欠かせないポイントになると考えられています(引用元:四ツ谷BLBはり灸整骨院, 同上)。
#ランナー膝
#冷湿布と温湿布
#腸脛靭帯炎
#セルフケア
#スポーツ障害
湿布の正しい貼り方・タイミング・注意点
“圧痛点”に合わせる貼り位置
ランナー膝で湿布を貼るとき、大切なのは「どこに貼るか」です。なんとなく膝の周りに広く貼るよりも、**圧痛点(押したときに特に痛みを感じる場所)**を目安にするのがよいと言われています。膝の外側、腸脛靭帯が大腿骨とこすれる部分が代表的なポイントです。痛みが出ている位置に合わせてピンポイントで湿布を当てると、効率的に冷感・温感を感じられると考えられています(引用元:四ツ谷BLBはり灸整骨院, https://yotsuya-blb.com/blog/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E8%86%9D-%E6%B9%BF%E5%B8%83%EF%BD%9C%E8%B2%BC%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%83%BB%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9%E3%82%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6)。
入浴後・運動後、肌の状態に配慮したタイミング
湿布を貼るタイミングも意識したいポイントです。一般的には、入浴後や運動後に皮膚が清潔な状態で使うのがよいとされています。汗や皮脂が残ったままでは密着しにくく、かぶれの原因にもなるため注意が必要です。また、運動直後の熱感が強い時期には冷湿布を、こわばりやすい夜間には温湿布を選ぶなど、状況によって貼り分けると快適に感じられることもあるようです(引用元:四ツ谷BLBはり灸整骨院, 同上)。
使用時間・頻度、肌トラブル・光線過敏などの注意点
湿布は便利ですが、長時間の貼りっぱなしはNGとされています。一般的には数時間〜半日程度を目安にし、かゆみや赤みが出た場合はすぐに外すことがすすめられています。特に光線過敏(紫外線に当たると皮膚トラブルを起こしやすい状態)を引き起こす成分を含む湿布もあると言われているため、日中に貼る場合は直射日光に気をつけることが必要です。また、毎日同じ場所に貼り続けると肌に負担がかかりやすいため、部位や使用頻度にも配慮することが望ましいと説明されています(引用元:みやがわ整骨院, https://miyagawa-seikotsu.com/blog/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E8%86%9D%E3%81%AB%E6%B9%BF%E5%B8%83%E3%81%AF%E5%8A%B9%E3%81%8F%EF%BC%9F%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%A8%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%99)。
湿布はあくまでサポート的な手段であり、貼り方・タイミング・注意点を守ることでより快適に使えると言われています。うまく活用しながら、必要に応じてストレッチやフォーム改善などのセルフケアも取り入れていくことが大切です。
#ランナー膝
#湿布の貼り方
#腸脛靭帯炎
#セルフケア
#スポーツ障害

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

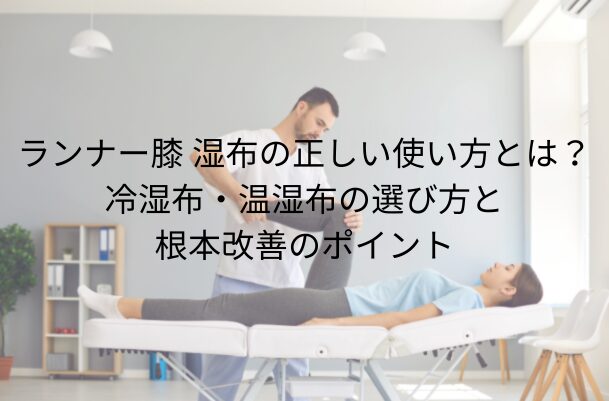


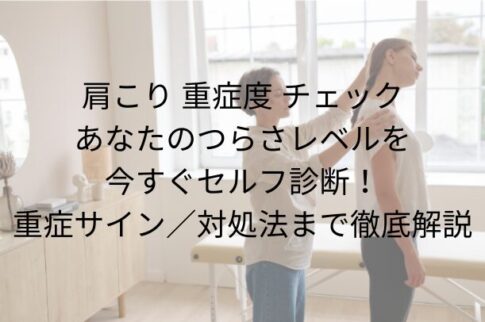
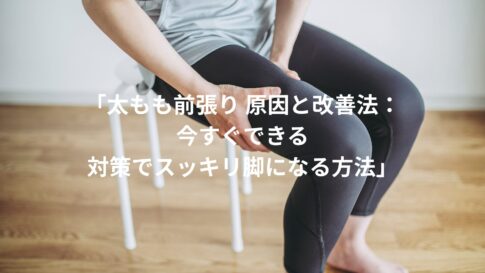



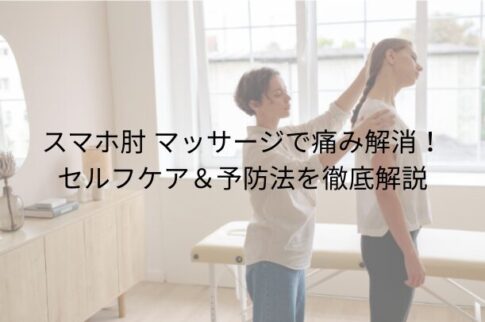

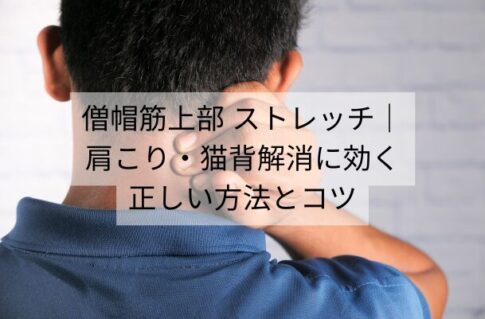














コメントを残す