
肩甲骨が“ほぐれていない”とどうなる?
不調のメカニズム
「最近、肩が重い…」「首がつっぱって回しづらい」そんな感覚、心当たりはありませんか? もしかすると、その原因は“肩甲骨の硬さ”にあるかもしれません。
肩甲骨は、背中の上部に位置し、腕や肩の動きをスムーズにするための“土台”のような役割を担っています。肩甲骨は肋骨の上を滑るように動くことで、腕を上げたり、背中に回したりといった複雑な動きを可能にしています。さらに、僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋といった首や背中の筋肉と密接につながっており、日常の姿勢や動作に大きく関わっていると言われています(引用元:https://stretchex.jp/5827)。
では、この肩甲骨が硬くなるとどうなるのでしょうか。まず、肩甲骨の可動域が狭くなり、腕を上げる・後ろに回すといった動作で違和感を覚えるようになります。筋肉が引っ張られることで血流が滞り、肩こりや首こりが起こりやすくなるとも言われています。特にデスクワークが多い方は、長時間同じ姿勢が続くことで筋肉がこわばりやすく、結果的に肩甲骨の動きが制限されやすい傾向があります。
さらに、肩甲骨の動きが悪い状態を放置すると、姿勢が前かがみになり、猫背が定着しやすくなるとも考えられています。これが首や背中の筋肉に余計な負担をかけ、慢性的なこりや張り、さらには頭痛や腕のだるさにつながるケースもあるそうです。
実際、「肩甲骨が硬い=肩や首の不調が出やすい」というのは、整形外科や整体の現場でもよく知られている考え方です。日常生活では「なんとなく動きづらい」「背中が重い」といった軽い違和感で済むことが多いですが、放っておくと運動のパフォーマンスや姿勢維持にも影響すると言われています(引用元:https://yogajournal.jp/16439)。
つまり、肩甲骨をやわらかく保つことは、肩や首の不調を予防するだけでなく、毎日の動きをラクにするための重要なポイントなんです。自分では意識しづらい部分だからこそ、日々のケアがカギになってきます。
#肩甲骨ほぐし #肩こり対策 #首こり予防 #姿勢改善 #ストレッチ習慣


皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています





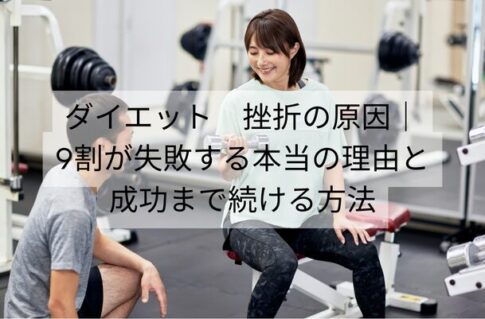





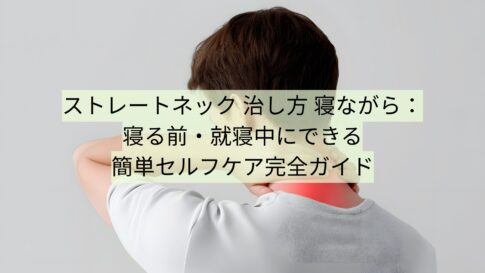
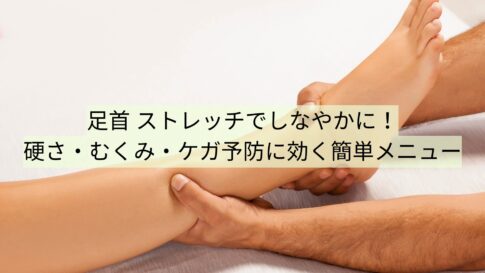













コメントを残す