1.肩こりの主な原因を把握しよう:腕の使いすぎ・目の酷使・姿勢の悪化

肩こりは、日常生活の中にあるちょっとした習慣や姿勢の積み重ねから起こることが多いと言われています。原因を理解しておくと、自分に合ったケア方法を見つけやすくなります。ここでは、特に多くの人が当てはまりやすい「腕の使いすぎ」「目の酷使」「姿勢の悪化」の3つについて紹介します。
腕の使いすぎによる肩こり
長時間のパソコン作業やスマホ操作、荷物の持ち運びなどで腕を酷使すると、肩から首にかけての筋肉が緊張しやすくなります。筋肉の緊張が続くと血流が滞り、コリやだるさを感じるようになると言われています。
「仕事終わりに肩がズーンと重い」「腕を上げるのがしんどい」と感じる場合は、このパターンかもしれません。日常でこまめに肩や腕を回したり、重い荷物を左右交互に持つなどの工夫が役立つと言われています。
目の酷使による肩こり
パソコンやスマホの画面を長時間見続けることで、目の周りや首の筋肉に負担がかかります。目を酷使すると、首の後ろから肩にかけての筋肉も緊張しやすくなるため、肩こりの引き金になることが多いとされています。
「夕方になると目の奥が重い」「首筋がガチガチ」という感覚がある方は、休憩時間に遠くを見る、蒸しタオルで目を温めるなどのセルフケアが効果的と言われています。
姿勢の悪化による肩こり
猫背や前かがみの姿勢は、首や肩に余計な負担をかけます。特に長時間同じ姿勢を続けると、肩周辺の筋肉が硬直しやすくなると言われています。
仕事中に背中が丸くなっていると感じたら、深呼吸をして背筋を伸ばす、椅子の高さを調整するなど、日常の中での姿勢改善を意識することが大切です。
まとめ
肩こりの原因は人によって異なりますが、腕の使いすぎ・目の酷使・姿勢の悪化は特に多くの人に共通しています。まずは自分の生活習慣を振り返り、どの原因が当てはまりそうかを知ることが、改善の第一歩と言えるでしょう。
#肩こり
#マッサージ
#姿勢改善
#セルフケア
#目の疲れ
(引用元:https://www.naturaltime.co.jp/column/selfcare/katakori-massage)
(引用元:https://plusseikotsuin.com/katakori/8786.html)
2.原因別おすすめマッサージ方法
「ねえ、ちょっと肩がしんどい…」なんて思っている人、多いですよね。そこで、腕の使いすぎ・目の酷使・姿勢の悪さに分けたセルフマッサージ方法をご紹介します。銀座ナチュラルタイムさんでも“原因別のアプローチが近道”と言われています。
腕の使いすぎ → 指・腕をさすり上げるマッサージ
「最近、パソコンばっかりで腕がパンパン…」って感じたら、まずは指先からのケアがおすすめ。
「やり方は簡単ですよ」って言われてるんですけど、親指から小指まで反対の手の親指と人差し指でつかみながら根元までずらして押していく。これを1分くらい行ってから、手のひらを上にして手首から脇の下に向けてさする…これがまたいいんですよね。両腕交代でどうぞ。
目の使いすぎ → 首の横・後ろを押す・さするケア
「目を酷使してて肩も首もガチガチ…」なんてときには、首まわりのマッサージがぴったりです。
例えば、手のひらを首の横にあてて、頭の重みを少しかけながらじわっと押す方法があると言われています。その後、こぶしをつくって第二関節あたりで耳下から肩先へ、首の後ろまでさすり下ろす…というのもおすすめです。じんわりほぐれてくる感覚、実際ありますよ。
姿勢の悪さ → 鎖骨・肩甲骨周りをさする流れ
「猫背や背中丸まり気味で…」って自覚ある人も多いでしょう。そんなときは、姿勢改善に繋がるケアとして、鎖骨の上と下を交互にさするのが良いとされています。少し体をひねるようにするとさらに効果あり。
さらに、背筋を伸ばして肩甲骨間を意識しつつ、背中の高い位置に両手をあてて、左右交互に腰までさすり下ろすのもポイントです。
#肩こりマッサージ
#腕の疲れ解消
#目の疲れケア
#猫背対策セルフケア
#原因別アプローチ
(引用元:https://www.naturaltime.co.jp/column/selfcare/katakori-massage)
(引用元:https://plusseikotsuin.com/katakori/18849.html)
3.肩こりに効くツボ紹介と押し方のポイント
「ツボってちょっと難しそう…」なんて思うかもしれません。でも、知っておくと自分のケアにすごく役立つんですよ。plusseikotsuin.comさんでも「肩こりに効果的な代表的なツボ」として肩井、天柱、風池を紹介されていて、これはセルフケアにすごく向いていると言われています。
肩井(けんせい)— 肩の頂点で見つけやすい定番ツボ
「え、肩の頂点?」って思ったそこのあなた、その通りです! 肩井は左右の乳頭をまっすぐ上へたどった先、最も盛り上がった肩の頂点にあります。
押すと響く感じがして、これがまた気持ちいいんですよね。でも、強く押しすぎないのがポイントで、「肩こりに効果的なツボである反面、急所のひとつでもあるので注意」とも言われています(引用元:同上)。だから“ほどよい圧”でじっくり押すのがいいと言われています。
天柱(てんちゅう)と風池(ふうち)— 後ろからのケアにぴったり
「後頭部のここ?」って思いません?天柱と風池は、頭の付け根の生え際、首の両サイドあたり、そこが疲れてる時にやさしく押すと“すーっと深まる感じ”があると言われています。
天柱はうなじ、風池はその少し外側で、目の疲れや頭痛にも効果が期待できるツボとも紹介されています(引用元:同上)。指の腹で軽く押して、ゆっくり深呼吸しながら行うのがおすすめです。
経絡・スジに基づいた深めのツボアプローチ
「東洋医学っぽい話も欲しいな」って人向けに、Fukurowでは経絡(スジ)のラインに沿ったアプローチも紹介されていて、ツボを刺激するだけじゃなく、スジに沿って流れを促すようなマッサージが望ましいと言われています。
これは、「肩こりをほぐすにはツボとスジへの的確な施術が重要」と語られている東洋医学の考え方に沿っていて、ただ押すだけでなく“気の滞りを流す意識”もプラスできるという深みがあるんです(引用元:同上)。
#肩こりツボ
#肩井
#天柱風池
#経絡アプローチ
#セルフマッサージ
(引用元:https://plusseikotsuin.com/katakori/18849.html)
(引用元:https://www.fukurow.jp/katakori/kata-massage/)
4.肩甲骨周辺・背中のセルフケア(ストレッチやマッサージ)
「背中がバリバリで、肩甲骨のあたりがやばい…」って感じてませんか?理学ボディでは、この肩甲骨はがしが「セルフでもできる」と理学療法士さんが推奨していると言われています。加えて、銀座ナチュラルタイムでは、リンパの流れを促すケアも大事だとされていて、両方を取り入れると効果的だと言われています。
セルフ「肩甲骨はがし」の手順
「セルフで肩甲骨をはがすってどうするの?」って声が聞こえてきそうですが、意外とシンプルです。まずはこんなストレッチから。
両手を背中で組んで胸を張り、そのまま腕を後ろに「ぐーっと」伸ばします。背中の筋肉がギュッと縮む感覚のところで10〜20秒キープするといいと言われています(引用元:理学ボディ)。
さらに、腕を肩の高さまで上げて、肘を広げながら肩甲骨の内側を縮めて、その後肘を前に寄せて今度は肩甲骨を広げる…という動きを10回。これで「肩甲骨が背中からめくれるイメージ」が自然にわいてきます。
リンパの流れを促す簡単マッサージ
「リンパも滞ってる気がする…」という方には、銀座ナチュラルタイムで紹介されている方法がおすすめ。肩甲骨の内側上端(背骨から指4本分くらい外側)にあるツボ「肩外兪」をやさしく押してから、肩甲骨を意識してさすってリンパを流すように促すのがポイントだと言われています。日頃デスクワークで動きが少ない人には、これが意外と効果あるんですよね。
#肩甲骨はがし
#セルフストレッチ
#背中ケア
#リンパマッサージ
#デスクワーク対策
(引用元:https://kabushikigaisya-rigakubody.co.jp/seitai/blog/fascia-release-scapula-peeling/)
(引用元:https://www.naturaltime.co.jp/column/selfcare/lympha-massage-of-shoulder-blade)
5.症状に応じた対処法の使い分け:セルフ vs 専門家の施術
「肩こりって、自分でケアすればいいの?それとも整体に行くべき?」と悩む人は少なくありません。理学BODYの視点では、「症状の軽さや改善したい目的で使い分けるのがいい」と言われています。
まずはセルフケアで軽い疲れにアプローチ
「ちょっと肩が重いな…」という軽度の肩こりには、まずセルフケアが役立つと言われています。例えばストレッチやツボ押し、軽く肩を回すだけでも血の巡りがよくなって、気持ちが少し楽になることがありますよね。その日の疲れは、その日に緩める感覚、すごく大事と言われています。
ただし、「肩の張りが強くなってきた」「しびれや鈍痛を感じるようになった」など変化があるときは、セルフだけに頼るのはおすすめしづらいと言われています。早めに専門家に相談するのが安心な役割を果たしてくれるようです。
慢性的なコリや姿勢の乱れには専門家も視野に
「ずっと凝りが取れない…」「猫背も気になるなあ」という場合は、整体や整骨院の施術が効果的だと言われています。理学BODYでも、骨格のバランスや筋膜の硬さなどにアプローチすることで、原因に根本から対処する効果が期待できると説明されています。
慢性化した症状には、自己流ケアだけでは取り切れない部分もあるようです。だからこそ、定期的な専門家の施術を組み合わせて、根本改善を目指すのが大切な選択肢だと言われています。
#肩こり対処法
#セルフケア優先
#整体併用
#根本改善目指す
#使い分けがコツ
(引用元:https://kabushikigaisya-rigakubody.co.jp/seitai/blog/stiff-shoulders-chiropractic-massage/)

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

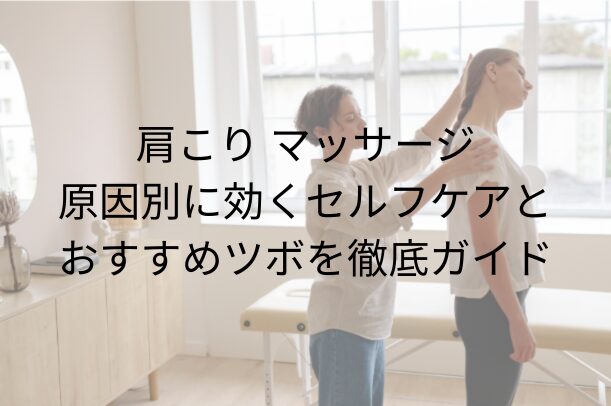
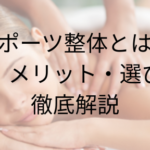
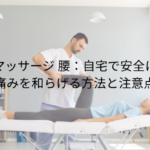
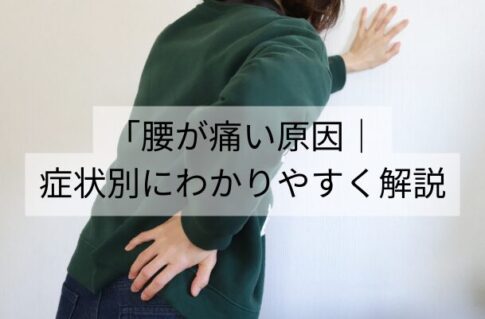
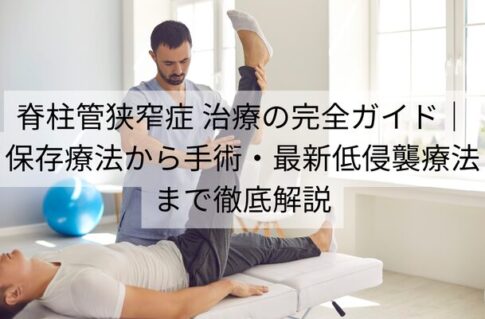
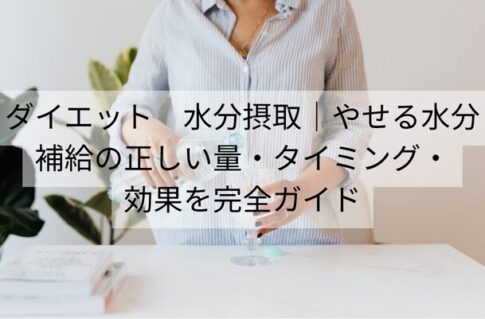

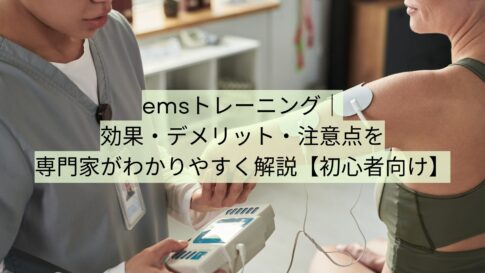
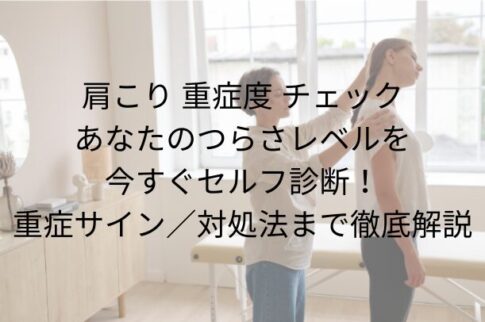
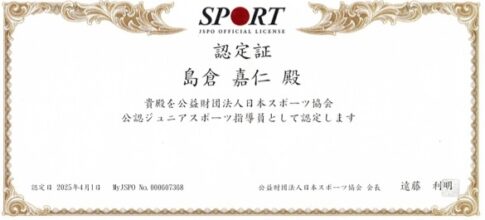
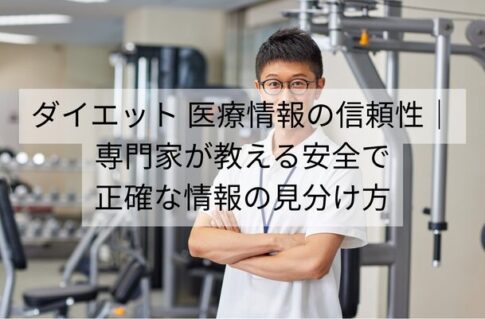









コメントを残す