
なぜマッサージで腰が楽になるのか?
科学的メカニズムの視点
「腰がだるい…」そんなとき、マッサージを受けるとスッと軽くなる感覚がありますよね。これは筋肉がほぐれて血流が改善すると言われており、滞っていた酸素や栄養が届きやすくなることで、こわばりや疲労感がやわらぐとされています
また、筋肉の緊張がやわらぐことで神経の圧迫も軽減されやすくなり、結果として痛みの感覚が落ち着くケースもあるそうです。いわば「固く縮こまっていたゴムが、ゆるやかに元の状態へ戻る」ようなイメージですね。
ただし、この効果は一時的なものであり、慢性的な腰痛や構造的な異常がある場合は、マッサージだけでの改善は難しいとされています
東洋医学的な視点
一方で、東洋医学では腰の不調は「気」や「血」の流れが滞ることで起こると考えられています。コリは単なる筋肉の硬さではなく、エネルギーの通り道が詰まってしまったサインとされ、マッサージでツボや経絡を刺激することで、この滞りを解消へ導くと言われています
例えば、腰周辺だけでなく足やお腹周りのツボを刺激することで、全身の巡りが整いやすくなるという考え方です。こうしたアプローチは単に「ほぐす」だけでなく、体全体のバランスをととのえることを目的にしています。
つまり、西洋医学が「筋肉と血流」に注目するのに対して、東洋医学は「体のエネルギーの流れ」に着目していると言えるでしょう。どちらの考え方も一長一短があり、実際には組み合わせて取り入れることで、より快適な状態を目指しやすくなると考えられています。
#腰マッサージ
#血流改善
#筋肉緩和
#東洋医学
#セルフケア
(引用元:https://yotsuya-blb.com、引用元:https://www.fukurow.jp)
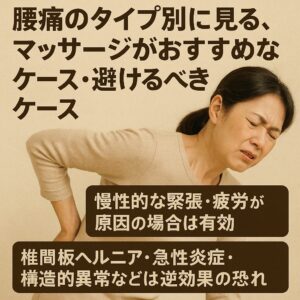
正しいマッサージのやり方:強すぎる刺激はNG
強すぎる力による「揉み返し」リスクと炎症悪化への注意
マッサージは心地よい刺激が魅力ですが、力任せに押しすぎると「揉み返し」と呼ばれる反応が起こることがあります。これは、筋繊維や周囲の組織が過度な圧迫を受けて微細な損傷を起こし、その修復のために炎症反応が強まる現象だと言われています
特に急性の腰痛や炎症がある場合は、強い刺激が痛みや腫れを悪化させることがあるため注意が必要です。受けている最中に痛みが鋭くなる、終わったあとにだるさが長く続くといった場合は、圧の強さを見直すサインかもしれません。
マッサージは「痛ければ効く」というわけではなく、体が心地よく感じる範囲で行うことが大切だと考えられています。
ゆるめて圧す、ツボや筋の起始停止を意識する施術法
正しいマッサージの基本は「ゆるめてから圧す」ことです。まず表層の筋肉を軽くほぐし、緊張を和らげてから徐々に深部へアプローチすると、筋肉や神経への負担が少なくなると言われています。
また、ツボや筋肉の起始部(筋肉が始まる部分)と停止部(筋肉が終わる部分)を意識して施術することもポイントです。この方法は筋肉の走行に沿って刺激が入りやすく、効果が出やすい傾向があるとされています。
例えば腰まわりの場合、脊柱起立筋や大腰筋のラインを意識しながら、押す位置や角度を変えるとより心地よい刺激になります。こうした工夫を取り入れることで、無理のない施術をしながらも十分なリラックス感が得られると考えられています。
#腰マッサージ
#揉み返し注意
#炎症予防
#ツボ刺激
#正しい施術方法
(引用元:https://yotsuya-blb.com)
(引用元:https://www.fukurow.jp)
セルフケア完全ガイド:ストレッチ・温冷・生活習慣
腸腰筋・大腰筋など、直接触れない腹部の筋肉を伸ばすストレッチ
腰痛ケアでは、腰そのものを揉むだけでなく、深部にある腸腰筋や大腰筋をゆるめることが大切だと言われています。これらの筋肉は腰椎と大腿骨をつなぐ重要な役割を持ち、デスクワークや座り姿勢が長いと短縮して硬くなりやすい部位です。
ただし、腸腰筋や大腰筋は直接手で触れられないため、ストレッチが効果的とされています。例えば、片膝立ちで骨盤を前に押し出す「ランジストレッチ」や、仰向けで片足を抱えて反対側の足を伸ばす方法がよく使われます。ポイントは、呼吸を止めずにゆったりと伸ばすこと。急に強く伸ばすと筋肉や腱を痛める可能性があるため、無理のない範囲で行うことが重要です。
温めと冷やしの判断、日常の姿勢・運動習慣
腰を温めるか冷やすかは、痛みの状態によって判断が分かれると言われています。
急性期(ケガやぎっくり腰直後など)には炎症が強いため、冷やすことで腫れや熱感を抑えることが推奨される場合があります。一方で、慢性的なこわばりや疲労感が中心の腰痛では、温めて血流を促す方が筋肉がゆるみやすいとされています。
さらに、普段からの姿勢や生活習慣も大きな影響を与えます。長時間の同じ姿勢を避け、こまめに立ち上がって軽く動くことや、日常的にウォーキングや軽いストレッチを取り入れることが予防につながると考えられています。椅子やデスクの高さを調整するだけでも、腰への負担を減らせる場合があります。
#腰痛セルフケア
#腸腰筋ストレッチ
#温冷療法
#生活習慣改善
#腰痛予防
(引用元:https://yukishiatsuseitai.com、引用元:https://yotsuya-blb.com)

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

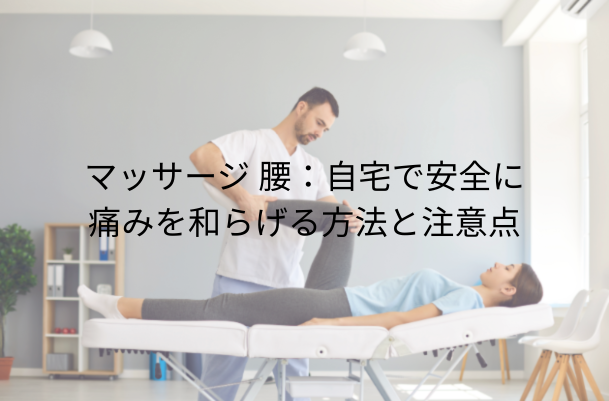



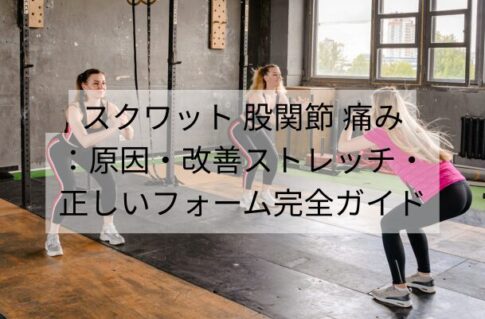
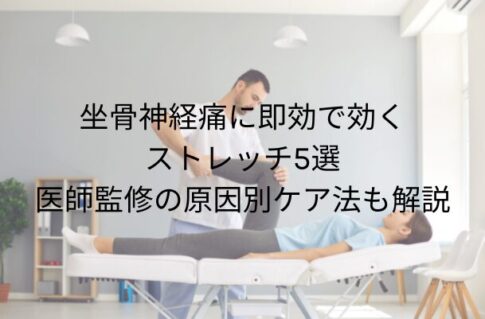



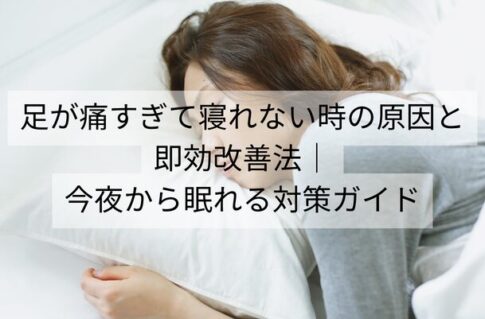
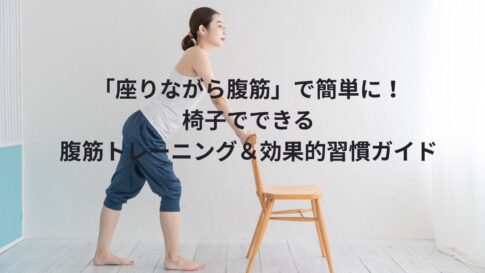













コメントを残す