1.首筋コリの正体とは?〜関係する筋肉とメカニズムを分かりやすく解説
首筋コリに関わる代表的な筋肉
首のコリを感じるとき、多くの場合「僧帽筋(そうぼうきん)」「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」「肩甲挙筋(けんこうきょきん)」といった筋肉が関与していると言われています(引用元:くまのみ整骨院)。
僧帽筋は肩から首、背中の広い範囲を覆う大きな筋肉で、重たい頭を支え続ける役割を担っています。胸鎖乳突筋は耳の後ろから鎖骨にかけて伸びる筋肉で、首を左右に回したり傾けたりする働きがあります。肩甲挙筋は肩甲骨を持ち上げる筋肉で、姿勢の崩れや肩の緊張と直結する部位です。これらの筋肉が過度に緊張すると「首筋の張り」や「重だるさ」といった不快感につながると考えられています。
首筋コリが引き起こすメカニズム
首筋の筋肉がこわばると、血流が悪くなり、老廃物や疲労物質がうまく流れにくい状態になると言われています。その結果、首周辺だけでなく頭部にも影響が及び、頭痛やめまい、時には吐き気といった症状につながることがあるようです(引用元:くまのみ整骨院)。また、筋肉の緊張は神経を圧迫しやすく、ピリピリとしたしびれ感や集中力の低下を招くケースも指摘されています。
さらに、姿勢不良や長時間のスマホ操作などで僧帽筋や胸鎖乳突筋に過度な負担がかかると、慢性的なコリが続きやすくなると考えられています。特に「デスクワークで下を向く時間が長い人」や「眼精疲労を抱えている人」は、首筋の筋肉に強いストレスがかかりやすい傾向があるようです。
こうした一連の流れは、単なる首のコリにとどまらず、全身の不調につながる入り口になると言われています。そのため、コリの正体を理解し、早めに対策することが大切だと考えられています。
#首筋コリ
#僧帽筋
#胸鎖乳突筋
#肩甲挙筋
#頭痛めまい
2.首筋コリの主な原因5つ〜日常の“クセ”を見直そう

姿勢の悪さ(スマホ首/猫背・巻き肩)
長時間スマホやパソコンを使うと、自然と首が前に突き出た姿勢になりやすいと言われています。いわゆる「スマホ首」や「猫背」「巻き肩」は、首から肩にかけての筋肉へ負担をかけ、コリを慢性化させる要因になると考えられています(引用元:nikkori-sinkyuseikotsu.com)。
眼精疲労
画面を凝視し続けると、目の筋肉が緊張しやすく、首筋にも負担がかかると言われています。特に胸鎖乳突筋や僧帽筋といった首回りの筋肉は、目の疲れとも関係が深いと考えられており、眼精疲労が続くと首のコリが強く出やすいとされています(引用元:kumanomi-seikotu.com、nikkori-sinkyuseikotsu.com)。
ストレス・自律神経の乱れ
ストレスは筋肉を緊張させ、自律神経の働きにも影響を与えると言われています。リラックスできない状態が続くと、交感神経が優位になり、血流の滞りや筋肉の硬直を招く可能性があります。その結果、首筋コリや頭痛が強まるケースもあるようです(引用元:kumanomi-seikotu.com、nikkori-sinkyuseikotsu.com)。
更年期や加齢による筋肉・頚椎の変化
年齢を重ねると筋肉の柔軟性が低下し、また骨や椎間板も変化していくと言われています。特に更年期にはホルモンバランスの乱れも重なり、首筋に強いこわばりを感じやすくなる方が増える傾向があると考えられています(引用元:kumanomi-seikotu.com)。
運動不足・血行不良・遺伝的要因
体を動かす機会が少ないと、血流が悪くなり筋肉の柔軟性も落ちると言われています。また、家族に慢性的な肩や首の不調を抱える人がいる場合、遺伝的な要因も一因になると考えられています。これらの要素が重なることで、首筋コリが改善しづらくなるケースがあるようです(引用元:kumanomi-seikotu.com、plusseikotsuin.com)。
#首筋コリ
#姿勢改善
#眼精疲労
#ストレスケア
#運動不足

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。


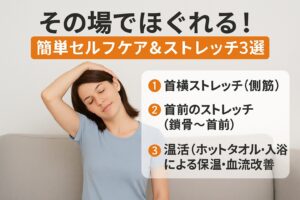



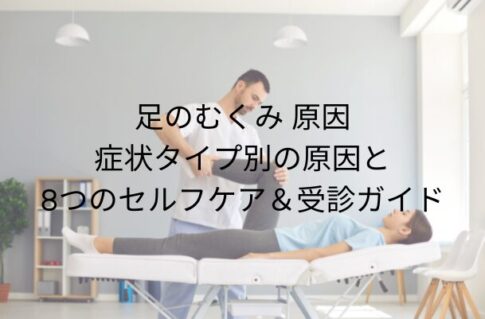

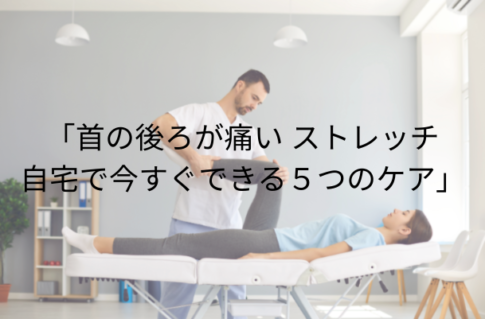
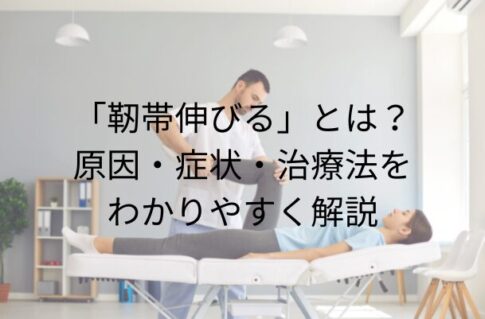


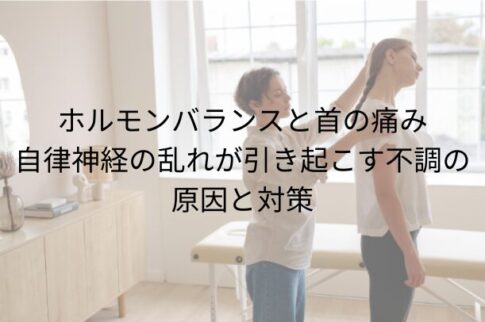
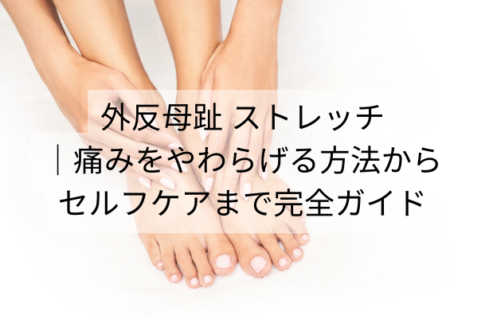
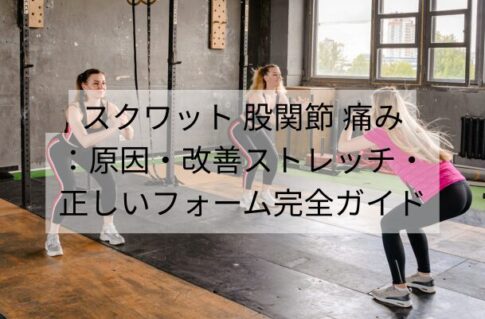
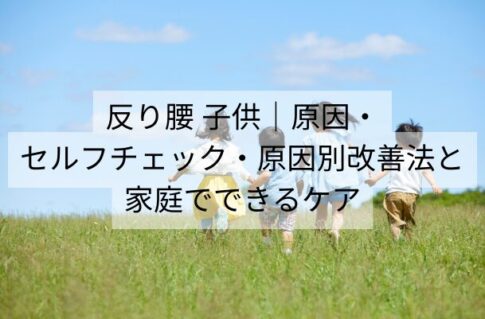
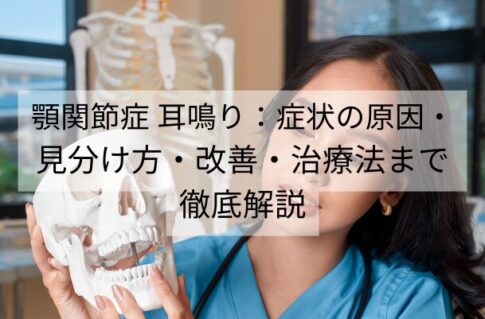
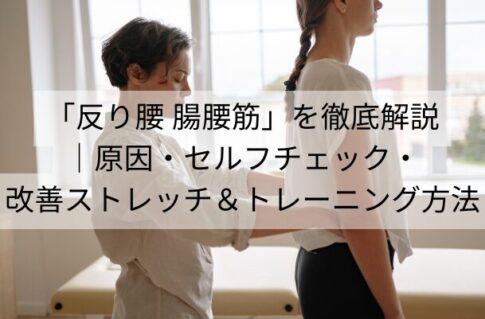




コメントを残す