1.首こりはなぜ起きる?筋トレで良くなる“本当の理由”
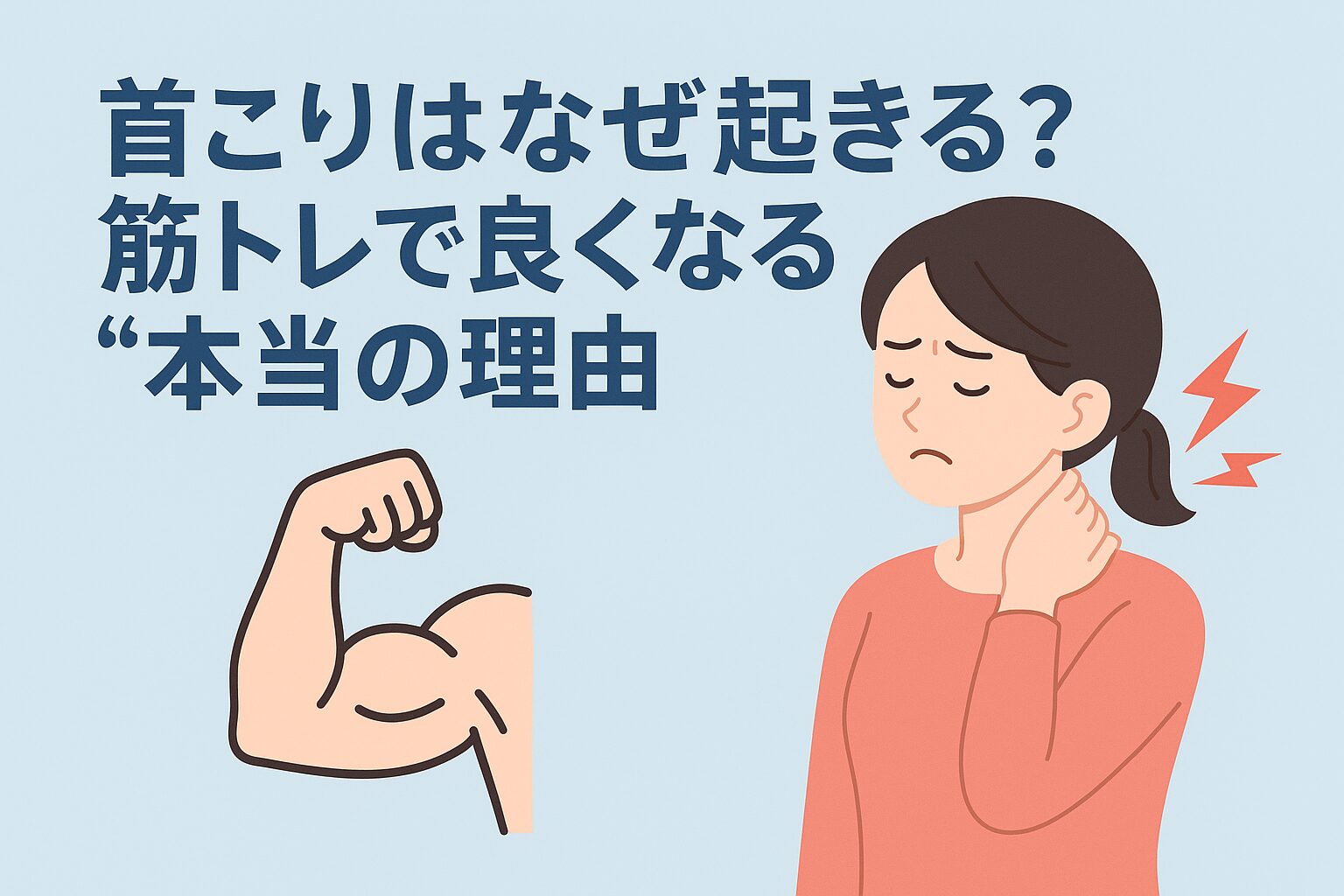
スマホ首・デスクワークで首が固まるワケ
「最近、首がずーんと重い…」って感じる人、多いですよね。スマホをのぞき込む姿勢やPC作業の前かがみが続くと、首や肩の筋肉は動かないまま力を出し続ける“静的緊張”状態になりやすいと言われています。すると僧帽筋や肩甲挙筋など表面の筋がずっと頑張りっぱなしで、血の巡りが落ち、疲労物質がたまりやすくなるそうです。首がこるのは、この「固まったまま支え続ける疲れ」がベースになっているイメージです。
引用元:https://myuseikotsu.com/kubi/kubikori/desk-neck-selfcare/
引用元:https://stretchex.jp/4987
こりの正体は“支える筋のサボり”と“使いすぎ”
じゃあ、なんで揉んだり温めたりだけだと戻りやすいの?――それは、頭の重さ(体重の約1/10とも言われます)を支える首の深い筋肉がうまく働かず、代わりに表面の筋だけが過緊張になるケースが多いから、と考えられています。深層頸部屈筋みたいな“首のインナーマッスル”がサボると、頭が前に出やすくストレートネックや猫背も進みがち、という流れですね。
引用元:https://note.com/regalo_tomo/n/n6820861d416d
筋トレが役立つ理由
ここで筋トレの出番。ゆっくりした首まわりのトレーニングで深層の支える筋を目覚めさせると、表面の筋の負担が分散され、姿勢が安定しやすいと言われています。動かすことでポンプみたいに血流も促されるので、「こりがたまる環境」そのものを変えやすいわけです。つまり、ほぐすケアは“今つらい分のリセット”、筋トレは“つらくなりにくい土台づくり”。この違いを知っておくと、首こり対策の手応えが変わってくるはずです。
#首こり原因
#スマホ首デスクワーク
#深層頸部屈筋
#筋トレで姿勢安定
#血流と負担分散
2.【セルフチェック】あなたの首こりタイプ別・効く筋トレの選び方
まずは30秒、壁と鏡で“今の首”を見てみよう
「首こり 筋トレって、結局なにをやればいいの?」と迷ったら、最初にタイプをざっくり見分けるのがおすすめです。やり方はシンプル。壁にかかと・お尻・背中をつけて立ち、あごを軽く引いた状態で後頭部が壁につくかチェックしてみてください。つきにくい人は、首のカーブが少なくなった“ストレートネック寄り”と言われています。さらに鏡で横から見て、肩が前に出ていたり胸が縮こまっていたら“猫背・巻き肩寄り”のサインかもしれません。こういう姿勢のクセが首こりにつながりやすい、という見方があります。
引用元:https://takeda3.com/2025/09/15/do-you-have-a-stiff-neck-diagnose-your-neck-with-this-easy-self-check-now/
引用元:https://stretchex.jp/4987
タイプ別に“効かせたい場所”がちょっと違う
じゃあ、タイプがわかったらどう選ぶ?ざっくり言うと、狙う筋肉が変わります。
-
ストレートネック型:あごが前に出やすく、後頭部が壁につきづらいタイプ。首の奥で頭を支える筋を目覚めさせる動き(チンタック系)が合いやすいと言われています。
-
猫背・巻き肩型:肩が前、胸が硬いタイプ。首だけでなく、胸を開いて肩甲骨を寄せる筋トレを優先すると首の負担が減りやすい見方があります。
-
僧帽筋ガチガチ型:「気づくと肩をすくめてる…」という人。上の僧帽筋が働きすぎていることが多いとも言われ、肩甲骨を下げる意識や、軽いシュラッグでバランスを取り直すのがポイントになりがちです。
-
眼精疲労・後頭下筋型:目の奥の重さや頭の付け根のコリが目立つタイプ。画面作業で後頭下筋が固まりやすく、首こりや頭の重さに関係することがあるそうです。だから首の奥をゆるめつつ支える筋も動かす、という順番が合うケースがあります。
引用元:https://www.seitai-enjoint.com/suboccipital-muscles-stretch/
#首こりセルフチェック
#ストレートネック型
#猫背巻き肩型
#僧帽筋ガチガチ
#眼精疲労後頭下筋型
3.首こりに効く筋トレ5選(タイプ別の優先度つき/自宅OK)

まずは“首を守る筋”から順番にいこう
「首こり 筋トレって、首をゴリゴリ動かせばいいの?」
「いや、それだと逆に疲れる人もいるみたい。だから順番が大事と言われています。」
首は小さい筋肉で頭を支えているので、いきなり強くやるより“支える力を整えてから動かす”流れが合いやすい、という考え方があります。ここでは自宅でできて、タイプ別に優先度をつけやすい5つを紹介しますね。
引用元:https://stretchex.jp/4987
5つの筋トレと効かせどころ
-
チンタック(深層頸部屈筋)
「ストレートネックっぽい人は?」
「まずこれが最優先と言われています。」
あごを軽く引き、首の奥で頭を支える感覚を作ります。5秒キープ×10回を1日2〜3セット目安。首の後ろを長くするイメージで、力みすぎないのがコツです。 -
ネックフレクション(前側)
うつむき姿勢が多く“支える力が足りないかも”という人向け。仰向けであごを引いたまま頭を少し浮かせ、3秒キープ×8〜10回。首より腹筋に力が入るなら角度を浅めにします。 -
ネックエクステンション(後ろ側)
「頭が重くて背中側がだるい…」そんなときに。うつ伏せでおでこを軽く浮かせる程度にして、3秒×8回。反らしすぎは負担になることがあるそうなので、ゆっくり小さく動かしましょう。 -
ネックラテラルフレクション(側面)
首の片側だけこる、左右差が気になる人に合うと言われています。手で軽く抵抗をかけながら、首を真横に倒すイメージで5秒×左右各6回。肩が上がらない範囲でOKです。 -
シュラッグ/肩甲骨下制系(僧帽筋・肩甲帯)
「肩で頭を支えてる感じがする人は?」
「首じゃなく肩甲帯のバランスを整えるのが近道、という見方があります。」
軽いシュラッグや、肩を下げて胸を開く動きで上部僧帽筋の頑張りを分散。10回×2セットくらいから始めると続けやすいです。
引用元:https://myuseikotsu.com/kubi/kubikori/desk-neck-selfcare/
#首こり筋トレ5選
#チンタック最優先
#前後左右バランス
#肩甲帯で負担分散
#自宅で小さく継続
4.筋トレ効果を倍にするストレッチ&姿勢連鎖ケア
首だけやっても戻るのは“上半身の連鎖”があるから
「首こり 筋トレ、ちゃんとやってるのにまた重くなるんだけど…」
「それ、首だけ頑張りすぎてるサインかも、と言われています。」
首の筋肉って、実は胸椎(背中の上のほう)や肩甲骨、さらに体幹の位置に影響されやすいそうです。猫背になると胸椎が丸まり、肩甲骨が前に流れて、頭も前へスッと出やすくなります。すると首の表面の筋が“頭を引き止める係”をずっとやることになり、こりが戻りやすい…という考え方があります。なので、首トレにプラスして「動きの通り道」を整えると効きやすい、といった流れですね。
引用元:https://stretchex.jp/4987
引用元:https://note.com/cute_fairy9940/n/n1194bb724b8d
最低限入れたいストレッチ&併用エクササイズ
「じゃあ、何を足せばいい?」
「まずは“固まりやすい4か所”をゆるめるのが基本と言われています。」
-
後頭下筋:頭の付け根を軽くほぐすイメージで、あごを引きながら首の後ろを伸ばす。
-
胸鎖乳突筋:斜め上を見るようにゆっくり首を倒して、前側のつっぱりをやさしく伸ばす。
-
肩甲挙筋/僧帽筋:肩をすくめず、首を斜め前に倒して肩甲骨まわりの張りをほどく。
さらに、首こりの土台になる姿勢を整えるために、
-
胸を開く(小胸筋ストレッチ)
-
肩甲骨を寄せ下げる(菱形筋・下部僧帽筋を使う動き)
-
胸椎伸展(背中を反らして猫背リセット)
この3つを軽く入れると、首の負担が散りやすいそうです。首のストレッチと肩甲骨まわりのケアをセットで紹介している記事も多いですね。
最後にタイミング。筋トレ前は“軽く動かす系”で可動域を作り、終わった後は“ゆっくり伸ばす系”でクールダウン、という使い分けがよいと言われています。仕事の合間は、胸を開く・肩甲骨を寄せる・首を小さく回す、のどれか1つでも挟むとリセットしやすいですよ。
#首こり姿勢連鎖
#首だけでなく胸椎肩甲骨
#後頭下筋胸鎖乳突筋ストレッチ
#胸を開く肩甲骨寄せ下げ
#筋トレ前後と仕事合間で使い分け
5.つらい首こりを悪化させない注意点&改善が進まない時の対処

筋トレで悪化しやすいケースと、相談の目安
「首こり 筋トレ、やったほうがいいのはわかるけど、ちょっと怖いんだよね…」
「うん、その感覚は大事。実は“今は慎重にしたほうがいい人”もいると言われています。」
たとえば、首や腕にしびれが出たり、動かした瞬間に激しい痛みが走ったり、めまいが強い場合は、筋トレで負担が増える可能性があるそうです。以前に頸椎の疾患を指摘されたことがある人も、自己流で追い込むより先に専門家へ相談するほうが安心、といった考え方が紹介されています。
危険サインとしては「安静にしても痛みが引かない」「夜間の痛みが増える」「手に力が入りづらい」などが目安になると言われています。気になる場合は早めに来院して、体の状態を見てもらうとよいでしょう。
引用元:https://stretchex.jp/4987
引用元:https://myuseikotsu.com/kubi/kubikori/desk-neck-selfcare/
日常の再発予防と、続けるコツ
「じゃあ、トレーニング以外は何を気をつければいい?」
「ここが実は効きやすさを左右するポイントなんだよね。」
まず、モニターは目線の高さ、スマホは顔の近くに上げる意識が大切と言われています。首が前に出る時間が減るだけでも負担が変わりやすいそうです。さらに、1時間に1回は肩と首を小さく回してリセット。がっつり運動じゃなくてOKで、固まりかけた筋肉をゆるめる目的です。
寝るときは、枕が高すぎると首が曲がりっぱなしになりやすいので、横向きでも首が傾きすぎない高さを目安にするとよいとされています。
最後にひとこと。首こりはタイプによって合うやり方が少し違うと言われています。無理のない範囲で、姿勢とセットでコツコツ続けていけば「首がラクな時間」が増えてくるはず。焦らず、今日できる一歩から始めてみてくださいね。
#首こり悪化サイン
#しびれ痛みめまいは要注意
#専門家相談の目安
#モニター高さと1時間リセット
#枕寝姿勢と継続がカギ
ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。





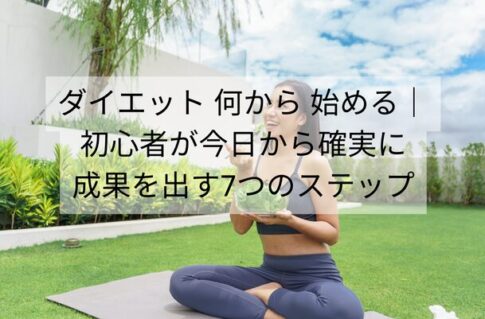
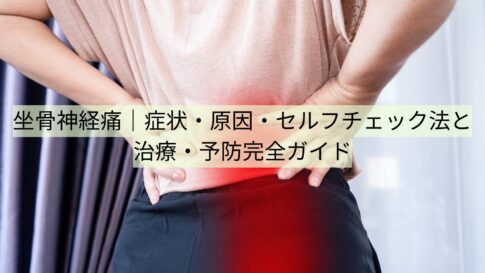
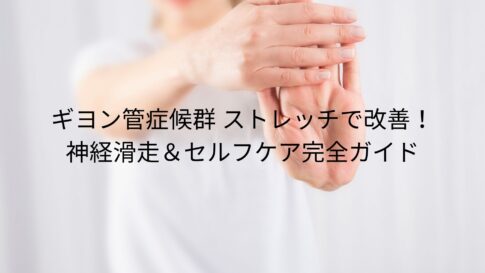

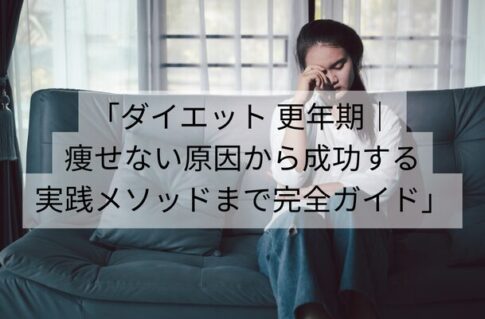
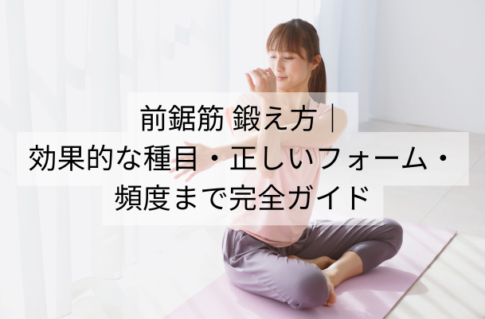
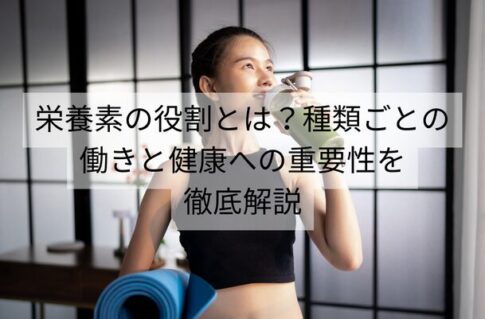
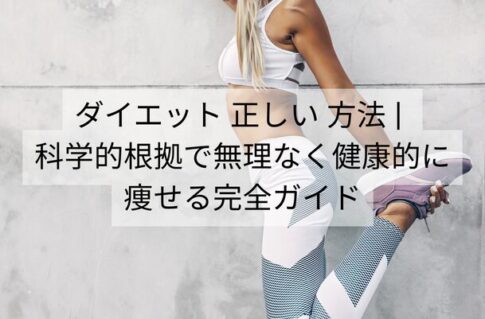
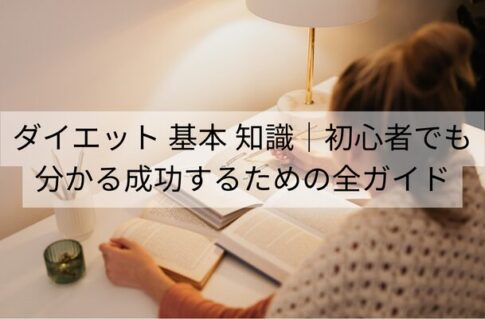
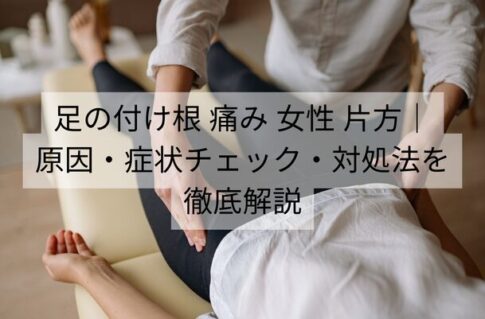
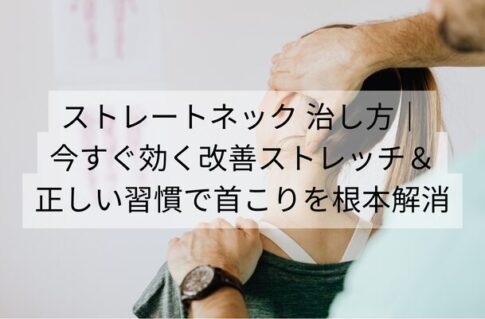




コメントを残す