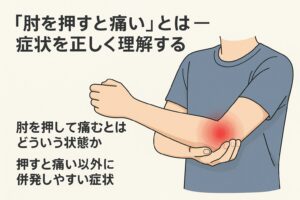
「肘を押すと痛い」とは — 症状を正しく理解する
肘を押して痛むとはどういう状態か
「肘を押すと痛い」と感じる場面は、日常のちょっとした動作で意外と多いと言われています。例えば、机に肘をついた時や物を持ち上げた時に、押した部分にズキッと鋭い痛みが走るケースがあります。また、じんじんとした鈍い痛みや、しびれるような違和感が続く人もいます。これらは肘の周囲にある筋肉や腱、関節に負担がかかっているサインと考えられています。引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/
会話風に言えば、「ただ押しただけなのに、なんでこんなに痛いんだろう?」と不思議に思う方も少なくありません。実際には、その痛みの背景にはいくつかの要因が関わっていると考えられています。
押すと痛い以外に併発しやすい症状
押すと痛むだけでなく、他の症状を伴うことも多いと言われています。代表的なのは腫れや熱感です。肘周辺がぷっくりと膨らんだり、触れると熱を帯びていたりすると炎症の可能性が考えられます。また、動かした時に可動域が狭くなる、いわゆる「曲げづらい・伸ばしづらい」といった不自由さも特徴の一つです。
さらに、長時間デスクワークをしている方やスポーツを続けている方は、しびれや動作痛を感じることもあります。こうしたサインが複数出ている場合は、単なる疲れではなく慢性的なトラブルに発展している可能性があるとされています。引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/elbow-pain/
痛む部位の分類:外側・内側・後側・前腕部との境界
肘といっても、痛みを感じる位置によって関わる組織や考えられる原因は異なると説明されています。
-
外側:テニス肘として知られる症状が代表的で、手首を反らす動作などで負担がかかると痛みが出やすい部位です。
-
内側:ゴルフ肘と呼ばれることもあり、ボールを投げたり物を握ったりする動作で腱に負担がかかりやすい場所です。
-
後側:肘を強く伸ばしたり、体重を支えたりする時に違和感が出やすい部位とされています。
-
前腕部との境界:肘と前腕のつなぎ目に痛みを感じる場合、神経の圧迫や炎症が影響している可能性があると考えられています。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-46/
このように「押すと痛い」症状は一言で片付けられるものではなく、痛む場所ごとに異なる背景が隠れていると考えられています。まずは自分の痛みがどの部位にあたるのかを意識することが、今後の改善につながる第一歩になるでしょう。
#肘の痛み
#押すと痛い
#肘の症状
#セルフチェック
#体ケア
押すと痛む肘の原因(部位別・メカニズム別)
外側(肘の外側を押すと痛い)
肘の外側に痛みが出る代表的なものは「テニス肘(上腕骨外側上顆炎)」と呼ばれる状態です。これは、手首を反らす動作や物をつかむ動作の繰り返しによって腱に負担がかかることで炎症が起こると言われています。また、スポーツや転倒で外側靱帯が損傷する場合もあり、押した時に強い違和感を感じることがあるようです。引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/
内側(肘の内側を押すと痛い)
内側の痛みで多いのは「ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)」と呼ばれる炎症です。物を強く握る動作や投球動作で痛みが出やすいと言われています。もう一つ特徴的なのが「肘部管症候群」で、尺骨神経が圧迫されると小指や薬指にしびれが広がるケースがあるとされています。引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/elbow-pain/
後側/後面(肘の後ろ側を押すと痛い)
後側の痛みは「上腕三頭筋腱炎」が知られています。肘を強く伸ばす動作や、体重を支える動きで腱に負荷がかかりやすいとされています。また、繰り返しの衝撃で肘関節の後方にストレスが集中することもあり、押すと鈍い痛みを感じる方がいるようです。
骨・関節の変化
年齢や使いすぎによって関節に変化が生じ、痛みにつながることもあります。代表的なものは「関節炎」や「変形性肘関節症」で、骨の変形や摩耗によって押した部分に違和感が出ると考えられています。さらに「骨棘(こつきょく)」と呼ばれる小さな突起ができたり、骨硬化が進むと関節の動きがスムーズでなくなり、痛みを感じやすくなることもあるそうです。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-46/
外傷・急性損傷
転倒やスポーツ中のケガで「骨折・裂傷・脱臼」が起こり、その部分を押すと鋭い痛みが出ることがあります。また、靱帯損傷も外傷による代表的な原因の一つです。急性損傷の場合は、腫れや変形を伴うことが多いと言われています。
注意点
ここまで紹介したように、肘を押すと痛む原因は非常に幅広く、複数の要因が重なっている場合も少なくありません。そのため、痛みの特徴や部位を把握しておくことが、改善のための第一歩につながると考えられています。
#肘の痛み
#外側の痛み
#内側の痛み
#骨や関節の変化
#外傷と損傷
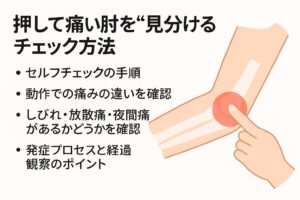
押して痛い肘を“見分ける”チェック方法
セルフチェックの手順
肘を押した時の痛みを確認するには、まず指の使い方がポイントになります。親指や人差し指を使って、肘の外側・内側・後側を垂直に押してみましょう。このとき「強く押しすぎない」ことが大切です。少し押しただけでズキッとしたり、じんじんとした痛みが続く場合は注意が必要と言われています。引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/
動作での痛みの違いを確認
押して痛むだけでなく、実際の動きでどんな変化が出るかもチェックポイントです。手首を曲げる・反らす、物をつかむ、ドアノブを回すなど、日常動作を試しながら痛みの強弱を比べてみましょう。どの動作で一番響くのかを観察すると、自分の肘の状態を整理しやすくなると言われています。引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/elbow-pain/
しびれ・放散痛・夜間痛があるかどうかを確認
ただ痛むだけでなく、しびれが指先まで広がる場合や、腕全体に放散するような痛みがあるケースもあります。また、夜寝ているときに強く痛みが出て目が覚める「夜間痛」があるかどうかも重要です。こうした症状があるかどうかを把握することで、背景にある問題を推測しやすいと考えられています。
発症プロセス(急性型か慢性型か)と経過観察のポイント
痛みが急に出たのか、じわじわと長く続いているのかで原因は異なると説明されています。例えば転んでぶつけた直後に出る痛みは急性型、パソコン作業やスポーツの繰り返しで徐々に強まる痛みは慢性型のことが多いと言われています。時間の経過とともに軽くなるのか、逆に強まるのかを見守ることがセルフチェックでは欠かせません。
図解/イラスト付きで痛むポイント別対応部位マップ
最後に、外側・内側・後側のどの部分が痛むのかを図で照らし合わせて確認するとわかりやすいです。イラストを見ながら自分の痛む場所を当てはめることで、原因の整理や経過観察がしやすくなると言われています。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-46/
#肘セルフチェック
#動作での痛み
#夜間痛の確認
#急性型と慢性型
#肘の痛みの見分け方
応急処置・セルフケアと注意点
RICE 施術(Rest, Ice, Compression, Elevation)の具体的実践方法
肘を押して痛いときの初期対応としてよく紹介されるのが RICE 施術 です。まず「Rest(安静)」は肘を無理に使わず休めること。次に「Ice(冷却)」では、保冷剤や氷をタオルで包み、1回15〜20分ほど冷やすと良いとされています。「Compression(圧迫)」は弾性包帯などで軽く固定する方法で、腫れを抑える効果があると言われています。最後に「Elevation(挙上)」として、心臓より肘を高く上げる姿勢を意識すると腫れや痛みが和らぎやすいとされています。引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/
冷却 vs 温熱の使い分け
「冷やすべき?温めるべき?」と迷う方も多いですが、急性期には冷却が基本とされています。炎症や腫れが目立つ時期は冷却を行い、痛みが落ち着いた後の慢性期には血流改善のため温める方が望ましい場合があるとされています。ただし、症状の進行や体質によって適した方法は変わるため、経過を見ながら調整するのが安心です。引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/elbow-pain/
肘を休ませながら動かす範囲・可動域維持ストレッチ
完全に肘を動かさないでいると関節が硬くなることもあります。そのため「痛みが出ない範囲」で軽く曲げ伸ばしを行うことが推奨される場合があります。ストレッチは無理のない範囲で、回数を少なく始め、徐々に増やしていくのが良いとされています。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-46/
サポーター・テーピング・圧迫具の使い方
スポーツや家事の際にはサポーターやテーピングを利用する方法もあります。これにより肘周囲の筋肉や腱への負担が軽減されるとされています。ただし長時間の使用は血流を妨げる可能性があるため、休憩をはさみながら使うことが大切です。
日常生活で避けるべき動作・姿勢
重い荷物を持ち上げる、肘をひねる動作を繰り返す、長時間肘を曲げたまま作業するなどは、痛みを悪化させる要因になるとされています。日常生活では「肘を酷使しない工夫」を意識すると改善につながる可能性が高いです。
市販薬・湿布の注意点
市販の湿布や外用薬を利用する方も多いですが、使用方法や貼る時間には注意が必要です。特に冷感タイプと温感タイプの選び方を間違えると逆効果になる場合があると言われています。使う際は説明書を確認し、違和感を感じたらすぐに使用を中止するのが安心です。
#肘の応急処置
#RICE施術
#冷却と温熱
#セルフケアの工夫
#日常生活の注意点
受診すべきタイミングと医療的検査
緊急来院が必要なサイン
肘を押して強い痛みが続くとき、腫れや変形が目立つ場合、または指先までしびれが広がるときは早めの来院がすすめられています。さらに、発熱を伴うようなケースでは感染の可能性が考えられるため、医療機関での確認が望ましいと言われています。特に「急に痛みが強まった」「肘を動かせない」といった場合は、自己判断せず専門家に相談することが大切です。引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/
検査で使われる方法
医療機関で行われる検査にはいくつか種類があります。最も一般的なのはレントゲンで、骨折や脱臼の有無を確認できます。MRIやCTでは靱帯や軟骨の状態をより詳しく調べることができると言われています。神経が関わる疑いがある場合には、神経伝導検査が行われることもあります。こうした検査を組み合わせることで、痛みの背景をより正確に把握できると考えられています。引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/elbow-pain/
保存療法(薬物療法・注射・理学療法・運動療法)
多くの場合、まずは保存療法と呼ばれる方法が選ばれると言われています。炎症を抑える薬物の使用や、必要に応じた注射で痛みを和らげます。また、理学療法士によるリハビリや電気刺激、温熱などの施術も組み合わされることがあります。さらに、軽い運動療法を取り入れることで、肘周囲の筋肉バランスを整え再発予防につなげるとされています。引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-46/
手術適応例と手術の種類
保存療法で改善が見込めない場合や、靱帯や骨に大きな損傷があるときは手術が検討されることがあります。関節鏡によるクリーニング、靱帯修復、骨切りなど、症状や年齢、活動度に応じて方法が選択されると言われています。手術後にはリハビリが必須であり、焦らず段階的に回復を目指すことが大切です。
治療期間とリハビリ進行の目安
検査や施術の内容によって期間は異なりますが、保存療法では数週間から数か月の経過観察が必要になることがあります。手術の場合は術後すぐに動かすことは難しく、リハビリを含めると数か月以上かかるケースもあると説明されています。いずれも「無理をせず段階的に」が基本です。
再発予防と生活復帰のガイドライン
日常生活に戻る際は、再発を避ける工夫が欠かせません。重い物を持つ際のフォーム改善、長時間同じ姿勢を避ける、ストレッチや筋力トレーニングを継続するといった工夫が有効と言われています。生活に支障がない範囲から少しずつ活動量を増やすことで、スムーズな社会復帰につながると考えられています。
#肘の検査
#緊急来院のサイン
#保存療法と手術
#リハビリの進め方
#再発予防と生活復帰

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています




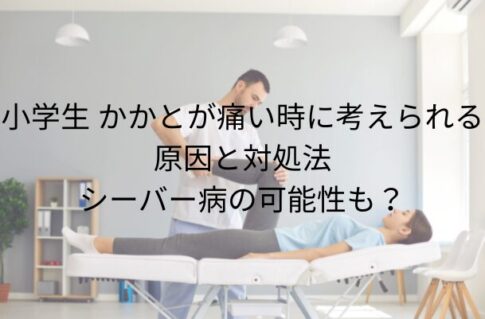
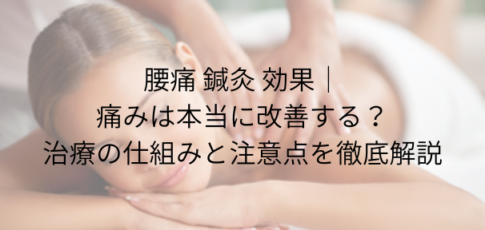

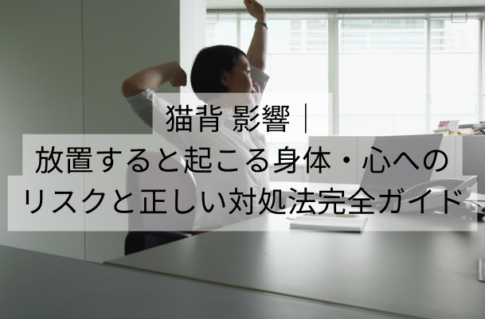
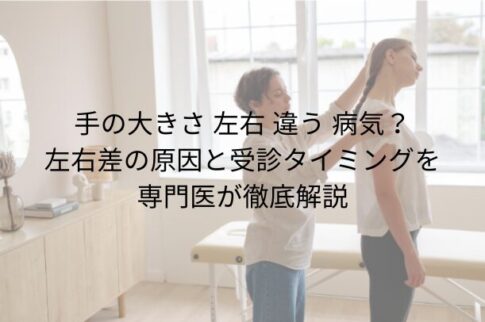


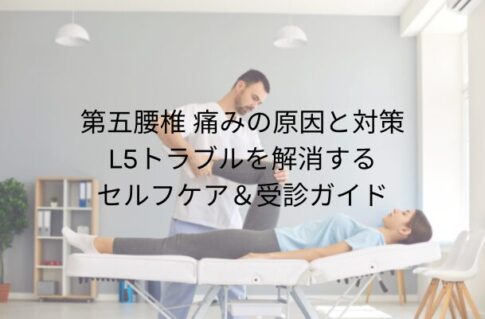













コメントを残す