1.逆腕立て伏せとは?通常の腕立てとの違い

動きや負荷のかかる部位
「逆腕立て伏せって普通の腕立て伏せと何が違うの?」とよく聞かれるのですが、主に体の向きと負荷のかかる筋肉が違うと言われています。一般的な腕立て伏せは胸や上腕三頭筋に刺激が入りやすいのに対して、逆腕立て伏せは肩甲骨周りや背中側の筋肉へ意識を向けやすい動きになっているようです。
体を後方に下げる動作が入るので、肩甲骨を寄せながら支える感覚が自然と必要になります。「腕を使って体を押し上げている」というより、「背中で支える」という印象に近いと言われています。フォームによっては上腕や前腕にも刺激が入るため、姿勢改善を目的に取り入れる人も増えています。
巻き肩との関係性
巻き肩は、肩が体の前側に入りこんでいる状態を指すことが多く、長時間のデスクワークや猫背がきっかけとされています。胸の筋肉が縮まり、背中側の筋肉がうまく使えていない状態が続くと、肩が前に出やすくなると言われています。
逆腕立て伏せでは、肩甲骨を寄せる動きが自然に入るため、胸の前側ばかり使っているバランスを整える役割が期待されているようです。参考記事でも、肩周辺の可動や筋肉の使い方を変えることで、姿勢負担の軽減が見込めると紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/4983 など)。もちろん個人差はありますが、「背中側を起こす感覚」が得られる点が巻き肩との関連ポイントと考えられています。
初心者でもできるか
「体力がなくてもできる?」という不安を持つ方は多いですが、逆腕立て伏せはフォームを調整すれば初心者でも挑戦しやすいと言われています。いきなり床で行うのではなく、椅子やベンチに手をついて体の角度を浅くする形から始める方法もあります。
また、1回の動作をゆっくり行うことで負荷をコントロールできるので、「腕立て伏せが苦手でも試しやすい」という声もあるようです。無理なく始めることで、肩や背中への意識も身につきやすいとされています。もし違和感が出る場合は回数を減らすか、別の姿勢調整ストレッチと組み合わせる方法が紹介されています。
#逆腕立て伏せとは
#通常腕立てとの違い
#巻き肩との関連性
#初心者でも始めやすい
#肩甲骨と姿勢意識
2.巻き肩になる原因と逆腕立て伏せが有効な理由

猫背・デスクワーク・肩甲骨の硬さ
「気づいたら肩が前に出てるんだよね」と悩む人は多いですが、その背景には猫背や長時間のデスクワークが大きく関係していると言われています。特にパソコンやスマホを長く見ていると、首が落ちて背中が丸まりやすくなりますよね。この姿勢が続くことで、胸の前側の筋肉は縮み、反対側の肩甲骨まわりは動かなくなりやすいようです。
さらに「肩甲骨が固まってる気がする」と感じる人も多く、実際に可動域が狭くなると腕の付け根ごと前に巻き込まれる形になりやすいと言われています。意識して動かさない限り、肩甲骨は自然にほぐれないと言われていますし、固まった状態で生活すると姿勢のクセが固定化しやすくなるとも言われています。
胸筋・広背筋へのアプローチ説明
ここでよく話に出てくるのが「逆腕立て伏せがなぜ巻き肩に関係するのか?」という点です。一般的な腕立て伏せが胸筋の強化に偏りやすいのに対して、逆腕立て伏せは背中側の筋肉、特に広背筋や肩甲骨下部への刺激が入りやすい動きだと紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/4983)。
「胸の筋肉が縮むと肩が前に引っ張られるって聞いたことある?」という会話もよくありますが、まさにその逆を狙ったのがこのトレーニングと言われています。胸筋をほぐしつつ、背面の筋肉を使うことで前後のバランスを整えやすくなるのが特徴とされています。
姿勢改善との関連づけ
姿勢の話になると「背中を伸ばせばいいんでしょ?」と考えがちですが、前側・後ろ側のどちらか一方だけでは変化しづらいとも言われています。逆腕立て伏せの動作は、肩甲骨を寄せる感覚を思い出しやすく、その結果として胸のスペースを確保しやすくなるという声もあります。
また、デスクワークの合間に少し行うだけでも「背中が起き上がる感じがする」と言う人もいますが、これは背中側を使う習慣が刺激されるためと考えられています。もちろん無理な回数や負荷で行うのではなく、正しいフォームで少しずつ体に覚えさせることが大切だと言われています。
#猫背と巻き肩の関係
#肩甲骨の硬さが原因
#胸筋と広背筋のバランス
#逆腕立て伏せの有効性
#姿勢改善とのつながり
3.巻き肩解消に効く逆腕立て伏せの正しいやり方
フォーム解説(画像・イメージ想定)
「逆腕立て伏せってどうやればいいの?」と聞かれることがあります。基本的には、椅子やベンチの端に手を置き、足を前に伸ばして腰を少し浮かせる形からスタートすると分かりやすいです。そこから腕を曲げながら体をゆっくり下ろし、肘が90度前後になったら押し戻して元の位置に戻します。
この時に意識したいのは「背中を寄せる感覚」。胸を張ろうとするよりも、肩甲骨を軽く寄せる意識で行うと巻き肩に対してバランスを取りやすいと言われています。腰が反りすぎると負担がかかりやすいので、骨盤をやや立てる意識で行うと安心です(引用元:https://stretchex.jp/4983)。
呼吸法・回数・セット数の目安
呼吸は「体を下げるときに吸う、上げるときに吐く」が基本とされています。リズムよく行うことで無駄な力みを防ぎやすいと言われています。
回数は初心者なら10回前後を目安に、1〜2セットから始めるのがちょうどよいと紹介されていることが多いです。慣れてきたら15回×3セット程度まで増やす人もいますが、あくまでフォームを崩さない範囲で調整することが大切だと言われています。
無理に数をこなすよりも、1回1回を丁寧に行った方が肩まわりに意識を持ちやすいとも言われています。特にデスクワーク後のリフレッシュとして、少ない回数でも効果を感じる人が多いようです。
体勢のバリエーション
「同じ動きばかりだと飽きてしまう」という声もありますが、逆腕立て伏せにはいくつかのバリエーションがあります。たとえば、膝を曲げて足を近づけると負荷が軽くなり、初心者でも行いやすいと言われています。逆に足をまっすぐ伸ばして体を前に出すと、腕や背中にかかる刺激が増えるため、中級者向けになります。
また、足を台に乗せて行う方法もあり、より深い角度で肩甲骨を寄せる動きが入りやすいと紹介されています。ただし、この場合は肩関節に負担がかかりやすいので、違和感があるときは避けた方が良いとされています。
姿勢改善を目的にする場合は、無理なくできるフォームを選ぶのが長続きのコツと言われています。
#逆腕立て伏せフォーム
#呼吸と回数の目安
#初心者向け負荷調整
#肩甲骨を寄せる意識
#体勢バリエーションで工夫
4.自宅でできる応用エクササイズ・ストレッチ
タオルや壁を使った簡単な方法
「道具がないとできないのでは?」と感じる方もいますが、家にあるもので代用できると言われています。たとえばタオルを両手で持ち、頭の上から背中側に引く動作は肩と胸の両方にアプローチできる方法として紹介されています。引っ張りすぎず、肩甲骨を引き寄せる意識で行うと伸ばしたいポイントが分かりやすいと言われています。
壁を使ったストレッチも人気です。片手を壁につけて体を反対側にひねると胸まわりがじんわり伸ばされやすく、「パソコン作業の合間にも取り入れやすい」と話す方もいます。どちらも道具がタオルか壁だけなので、わざわざ準備せずに始められるのが魅力だと言われています。
肩甲骨はがしとの組み合わせ
巻き肩のケアでは「肩甲骨はがし」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これは肩甲骨まわりの筋肉を緩めることで可動域を広げるストレッチの一種として知られています。たとえば腕を後ろに回して肘を軽く引いたり、肩を上下にゆっくり動かしたりするだけでも刺激が入りやすいと言われています。
逆腕立て伏せやタオルストレッチを行う前後に、この肩甲骨まわりの動きを取り入れると、筋肉がスムーズに動きやすくなると紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/4983)。いきなり力を入れるのではなく、ほぐしてから動かすことで体への負担も減らせるという声があります。
女性・初心者向け負荷調整
「腕力に自信がないから不安」という声もありますが、女性や初心者向けの軽めのやり方も多く紹介されています。たとえば正座や膝立ちの姿勢で上体を少し前に傾けるだけでも肩周辺を動かすトレーニングにつながると言われています。
タオルを使う場合も、引っ張る力を弱めたり、肩の高さではなく胸の前で動かしたりするだけで負荷が調整できます。壁ストレッチに関しても、角度を浅くすることで「痛みや張りを避けながら続けやすい」と話す人がいます。
無理なく継続できる形を選ぶことが、巻き肩の予防や改善に役立つと考えられているようです。
#タオルストレッチ自宅ケア
#壁を使った肩伸ばし
#肩甲骨はがしとの併用
#初心者向け負荷調整
#女性でも取り入れやすい
5.効果を高める注意点とNGフォーム

首・肩への余計な力み
「逆腕立て伏せをすると首がつらくなるんだけど…」という声を聞くことがあります。この原因のひとつとして、動作中に首や肩へ無意識に力が入りすぎているケースがあると言われています。本来は肩甲骨を寄せる意識がメインなのに、肩をすくめるような姿勢になってしまうと首回りに負担がかかりやすくなるようです。
「肩に力が入ってる気がする」と感じたら、一度動きを止めて肩をすっと下げるだけでも違いを感じやすいと言われています。呼吸が止まってしまうと上半身に余計な力が入りやすくなるので、吸って吐いてを繰り返しながらリラックスすることがポイントとされています。
腰が反る・肩がすくむパターン
間違ったフォームとしてよく挙げられるのが、腰を反らせすぎるパターンです。お腹の力が抜けると、背中側が反ってしまい、結果的に腰に負担がかかると言われています。特に体を下ろすときに腰が落ちたり反ったりしやすいので、骨盤を立てる意識を持つと安定しやすいと紹介されています。
また、肩が耳に近づくようにすくんでしまう動きもNGフォームの一つとされています。これを続けると、首こりや肩こりにつながると言われています。鏡やスマホで横から姿勢を確認しながら行うと、客観的にチェックできて安心です(引用元:https://stretchex.jp/4983)。
もし痛みや違和感が出た場合の対処法
「ちょっと肩が変な感じがする…」というときは、そのまま続けずに動きを止めるのが基本とされています。無理に回数をこなすより、一旦休んだり別の軽いストレッチに切り替える方が体に優しいと言われています。
痛みではなく“張り”や“違和感”程度の場合は、タオルストレッチや肩甲骨はがしのような緩める動きを挟む方法も紹介されています。どうしても不安なときは、一度回数を減らしたり、角度を浅くするなど負荷調整することで継続しやすくなると言われています。
#NGフォームの注意点
#首肩の力み対策
#腰反りと肩すくみ防止
#違和感時の対処
#無理なく続ける工夫
ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。




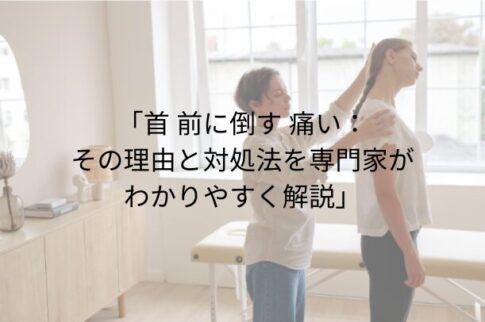
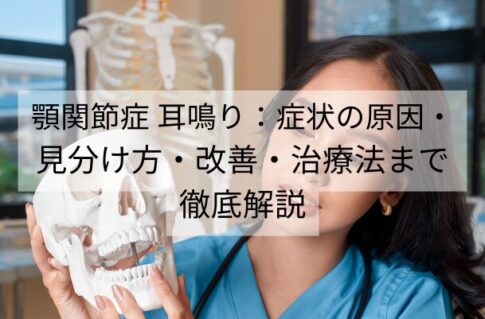
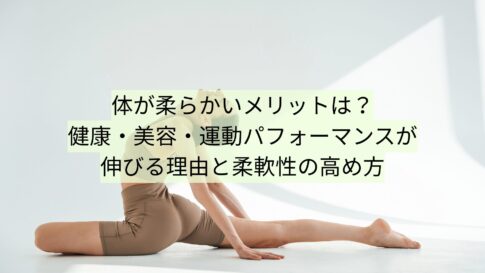
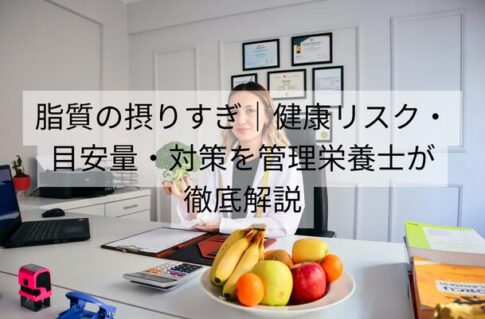


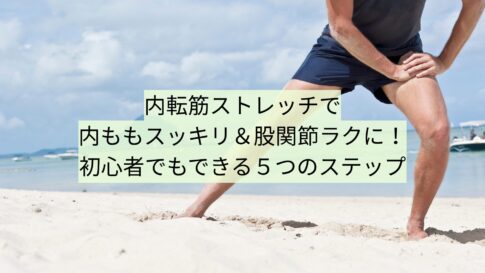
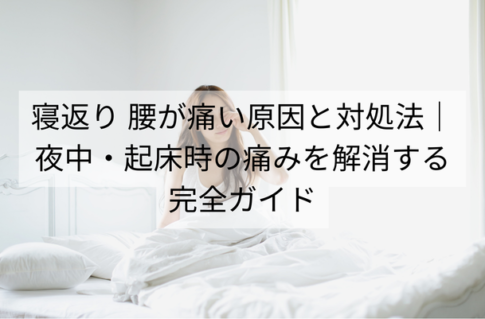
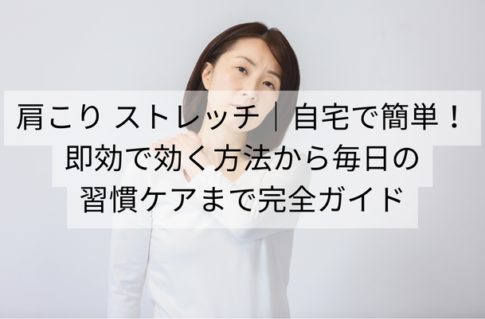

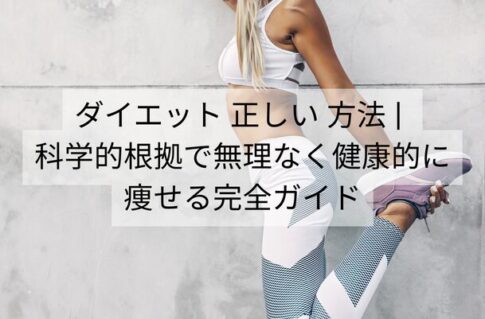
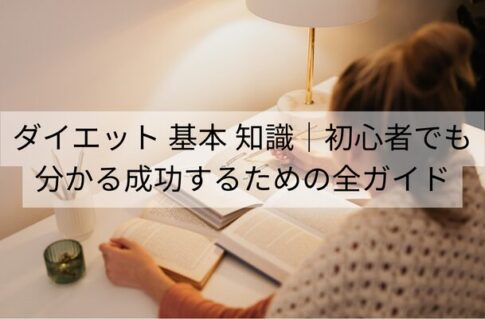
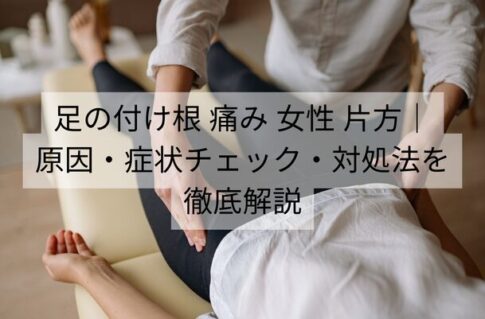




コメントを残す