1.「スタミナとは?基本の意味と使われ方」

「“スタミナ”の語義・定義(例:体力・持久力・精力)」
「スタミナ」という言葉、ちょっと耳にはしていても、「具体的には何を指してるの?」と感じることがありますよね。実は、辞書によればスタミナとは「肉体的な耐久力。精力。体力。また、持久力。」と言われています。 コトバンク
つまり、ざっくり言えば「長く動ける力」「疲れにくい力」ということ。例えばスポーツ選手が「スタミナがある人だ」と表現される時、それは単にパワーがあるとか瞬発力があるというだけでなく、動き続ける力があるという意味合いも含まれています。
また、同時に「精力」という言葉も出てくるので、活動量が高い・持続できる・というニュアンスも含まれていると言えます。コトバンクにも「体力。精力。また、持久力。」とあります。 コトバンク
このように、「スタミナ=持続的に活動できる体の力」という定義を念頭に置いておくと、普段「スタミナ料理」「スタミナつけよう」などという会話で使われている時のニュアンスがクリアになります。
さらに、栄養や健康の文脈では「長期間にわたって体の活動やストレス・病気などに耐えるための活力やエネルギー」の意味でも用いられています。 学校給食の真相
「日常会話・スポーツ・栄養の文脈での“スタミナ”の使われ方」
実は「スタミナ」という言葉、日常会話でもスポーツの現場でも、栄養や健康の分野でも幅広く使われています。たとえば、「明日長距離ランニングだからスタミナつけなきゃ」「このチーム、後半にスタミナ切れしがちだね」というような会話。ここで言う「スタミナ」は「しばらく動き続けられるかどうか」「最後までバテずにいけるかどうか」という意味を含んでいます。
スポーツの文脈では、例えば「スタミナを高めるためには心肺機能を鍛えるべきだ」といった説明も見られ、「スタミナ=心肺持久力」という視点が紹介されています。 大阪体育大学
栄養・健康の場面では、「スタミナ料理」「スタミナ食材」という言い方がされ、「たんぱく質・ビタミンB1・鉄分などがスタミナに関係する栄養素です」という言及もあります。 学校給食の真相
つまり、使われる場面は三つくらいに整理できそうです:
-
日常会話:疲れにくさ・持続力のニュアンス(「スタミナあるね」)
-
スポーツ・運動:長く良いパフォーマンスを維持するための体力/持久力として(「スタミナ鍛えよう」)
-
栄養・健康:体が長く働くために必要なエネルギー・活力源として(「スタミナつける食事」)
そして、なぜこの言葉が浸透しているかというと、私たちの日常生活でも「疲れた」「バテた」など体が持たない感覚をよく経験するからでしょう。ですから、「長く動き続けたい」「途中でへたれたくない」「余裕を持ちたい」というニーズがある時、この言葉が自然に出てくるわけです。
また、競技・仕事・家事・子育てなど、活動が多様化した今の暮らしでは「どれだけ持ちこたえられるか」が評価軸のひとつになっていて、「スタミナ」という言葉がそのままポジティブな評価として使われていると考えられます。
つまり、「スタミナとは何か」を理解することは、スポーツや日常の活動、食事や健康管理において「どんな力をつけるべきか」を見極める第一歩になります。どうですか、少し「スタミナ」のイメージがクリアになってきたでしょうか?
#スタミナとは #持久力 #体力アップ #健康習慣 #運動栄養
2.身体でのスタミナの仕組み:何が“持久力”を決めるのか
生理学的観点から:心肺持久力・最大酸素摂取量(VO₂max)など
「スタミナをつけたいんだけど、どういう仕組みなの?」という声に対して、まず押さえておきたいのが“心肺持久力”という考え方です。例えば、大阪体育大学によれば、スタミナとは「心肺持久力」を指す言われ方があり、心臓と肺を中心に全身の循環系能力が高い状態を指すとされています。 大阪体育大学
具体的には、運動中どれだけ酸素を体内に取り込んで全身に供給できるか、そして筋肉でその酸素を使えるかが鍵となります。この“最大酸素摂取量(VO₂max)”という数値が高いほど、長く動き続ける能力、つまりスタミナが高いと言われています。 大阪体育大学
ここでちょっと会話形式で。
―「じゃあ、走るのが遅くてもスタミナあるって言っていいの?」
―「そうとも言い切れないけど、心肺持久力があれば、速さだけじゃなく“長く動ける”という観点で有利なんだよ」
速さ=瞬発力ではなく、長時間・持続的に体を動かせるかどうか。それが“スタミナ”の重要な構成要素です。ですので、定期的な有酸素運動や心拍数を意識したトレーニングが、持久力を高めるヒントになります。大阪体育大学でも、最大酸素摂取量の50%強度の運動を継続することで毛細血管が発達し、酸素が筋肉に届きやすくなると紹介されています。 大阪体育大学
栄養・代謝・筋肉・血流などの関係性(例:ビタミンB1・鉄分の重要性)
さて、次は運動だけではなく、体の中の“燃料・流通・使う力”という三本柱を見ていきましょう。例えば、鉄分は血液中のヘモグロビンを構成する重要な成分で、酸素を全身に運ぶ役割があります。鉄分が不足すると、酸素が体の隅々に行き渡らず、持久力が落ちると言われています。 グリコ
さらに、ビタミンB1は糖質をエネルギーに変えるために必要な栄養素で、これが足りないと「せっかく動こうとしても燃料がちゃんとエンジンに回らない」という状態になり得るそうです。 エムスタイルホールディングス株式会社
筋肉量やその筋肉が酸素を使う能力、さらには毛細血管の発達・血流の良さ、これらが統合された時に「長く活動できる体=スタミナのある体」という印象につながります。栄養と運動と血流改善が相互に関係しているわけです。
―「つまり、筋トレやランニングだけじゃなくて、食事も睡眠も影響するってこと?」
―「そう、その通り。どれかが欠けると、せっかく運動しても“バテやすさ”が残ることがあるんだ」
ですから、鉄分・ビタミンB1などを含む食材を意識したり、筋肉を維持するためのタンパク質を補ったりすることが、スタミナを支える“内部インフラ”になると言えます。
スタミナを左右する主な要因(年齢・体質・運動習慣など)
最後に、スタミナに影響を与える“背景要因”について整理します。年齢を重ねるごとに心肺機能や筋肉量が低下しやすく、「昔は疲れなかったのに最近すぐバテる」という声も多いです。体質も、人によって酸素取り込み能力や代謝スピードが異なります。運動習慣がある人とない人では、心肺持久力・血流・筋肉の使われ方に差が出ることも言われています。 (※具体データは省略)
―「じゃあ、もう年だから仕方ないのかな?」
―「年だから無理とは限らない。習慣を変えれば“持久力”を改善できる可能性はあるよ」
例えば、日常的に階段を使ったり適度なペースで歩いたりするだけでも、心肺機能の維持・向上に役立つと言われています。上で紹介した大阪体育大学の情報でも、軽めの運動を継続するだけで毛細血管が増える可能性があると紹介されています。 大阪体育大学
ですので、年齢や体質を言い訳にせず、「運動+栄養+休息」の組み合わせで“スタミナを支える基盤”を整えることが大切です。
#スタミナの仕組み #心肺持久力 #最大酸素摂取量 #鉄分とビタミンB1 #運動と栄養の関係
3.スタミナが低い・疲れやすいと感じる原因

運動習慣がない・運動の種類が偏っているケース
「最近、なんだかすぐ疲れちゃうなぁ」「頑張ろうとしても途中で息が切れちゃう」という会話、身近ですよね。これ、実は“運動習慣がない”あるいは“運動の内容が偏っている”ことが原因のひとつと言われています。例えば、ほとんど歩かない・座りっぱなしの時間が長いという生活では、筋肉が使われず基礎代謝が落ち、少し動いただけで疲れやすくなると考えられています。Smart Studio
逆に、運動してるけど「力仕事ばかり」「ランニングばかり」「筋トレばっかり」といった偏った内容も、持久力(=“スタミナ”)を支える心肺機能や血流の改善には十分でないことがあります。言い換えれば、「動いているから大丈夫」というわけではなく、“長く動ける体”を育てるためには、有酸素+筋持久力+動きの多様性が必要と言われています。
―「じゃあ、毎日20分だけウォーキングでもいいの?」
―「はい。少しずつでも動く習慣をつけて、呼吸が少し上がるくらいのペースを取り入れると、持久力改善には有効と言われています」
ですので、運動習慣がまったくなかったり、動きの種類が限られていたりする人ほど「スタミナ不足/疲れやすい」状態になりやすいという構図が生まれるわけです。
栄養バランスの乱れ(例:タンパク質・鉄分・ビタミン不足)
もう一つ、無視できないのが“栄養の偏り”です。「スタミナが低い」「すぐ息が上がる」「疲れが抜けない」というとき、実は“燃料”が十分に供給されていない可能性があります。例えば、鉄分やビタミンB1が不足していると、酸素の運搬やエネルギー代謝が滞ると言われています。
さらに、タンパク質が足りないと筋肉量が落ち、筋肉で酸素を使う“力”そのものが弱くなるという指摘もあります。学校給食の真相
―「例えば、毎日同じものばかり食べてるとまずい?」
―「そうですね。栄養が偏っていると、体は“長く動ける状態”を維持しづらくなると言われています」
つまり、運動しても、その動きを支えるための栄養が整っていなければ、“スタミナ”という持久力を育てる土台が弱くなってしまうのです。
睡眠・休養・ストレスなどからくる影響/年齢変化・慢性疾患などの背景
最後に、見落としがちなのが「睡眠・休養・ストレス」「年齢・体質・慢性疾患」といった背景要因です。例えば、睡眠の質が低かったりストレスが強かったりすると、回復力が落ち、疲労が残りやすくなると言われています。studio8force.jp
また、年齢を重ねることで筋肉量が自然に落ちたり、心肺機能が若干落ちたりすることも“スタミナ低下”の一因として考えられています。運動習慣がないままだと、この影響が顕著になりやすいです。
―「年だから仕方ないって思ってたけど?」
―「年齢は一つの背景ですが、習慣や栄養、休養を整えることで“持久力を改善できる可能性”もあると言われています」
ですので、「疲れやすい」「持久力が無い」と感じたら、運動・栄養・休養・背景(年齢・体質)それぞれに目を向けることが、“スタミナを上げる準備”につながると言えそうです。
#スタミナ低下 #疲れやすい原因 #栄養バランス #運動習慣不足 #睡眠と休養
4.スタミナを高めるための具体的な方法
運動面:有酸素運動・インターバルトレーニング・筋持久力トレーニング
「スタミナを高めたい!」と思ったら、まず”動き方”を見直すのがポイントです。例えば、「毎日ただ歩けばいいんでしょ?」と思いがちですが、実は“有酸素運動+インターバル+筋持久力トレーニング”という組み合わせが効果的と言われています。
―「有酸素運動だけじゃ物足りないの?」
―「そうだね。ゆったり動くだけでも基礎になるけど、『少し頑張る時を作る』ことで持久力が育ちやすくなると言われています」
具体的には、週に2〜3回、例えば30分のウォーキング+5分の早歩き(インターバル)+筋持久力を鍛えるスクワットやプランクなどを取り入れると良いと言われています。こうした運動を継続することで、心拍数がある程度上がる時間を確保し、酸素や栄養の運搬効率がアップし、「長く動ける体」、いわゆる“スタミナのある体”につながると言われています。
始めるなら、「動ける範囲で少しキツめのペース」を意識して、“続けやすさ”と“少しの負荷”のバランスを大事にしてください。
栄養面:スタミナに関係する栄養素と代表食材(タンパク質・ビタミンB群・鉄分など)
運動で体を動かすだけでなく、スタミナを支える“燃料”もしっかり整える必要があります。例えば、鉄分は酸素を体中に運ぶヘモグロビンを作る材料として重要と言われています。
さらに、ビタミンB1・B2などは糖質や脂質・タンパク質からエネルギーを作るために欠かせない栄養素です。
―「じゃあ、何を食べたらいいの?」
―「例えば、豚肉(ビタミンB1豊富)、ほうれん草やひじき(鉄分豊富)、卵や納豆(タンパク質)あたりが手軽でおすすめと言われています」
炭水化物だけでなく、バランスよく「主食+主菜+副菜」で栄養を整えることが、スタミナを育てる食事のコツです。特に運動をしている人、あるいは疲れやすさを感じている人は、この“燃料と材料の両方”を意識すると変化が出やすいでしょう。
生活習慣:睡眠・休息・ストレスケア・定期的な活動/実践のヒント:初心者でも続けやすい運動・食事のポイント
最後に、スタミナを高めるには「動く」「栄養を取る」だけでなく、「休む・ケアする」ことも重要です。睡眠や休息が不足すると、体の回復が追いつかず“動きにくさ”として現れると言われています。ストレスもまた、エネルギーを消費しやすい状態を作り出すため、注意が必要です。
―「でも、忙しくて運動も食事も休息も…って感じなんだけど」
―「そんな時こそ“続けやすさ”重視でいいんだよ。例えば、毎朝5分ストレッチ+夕食に鉄分豊富な食材を1品プラス+夜10分間のリラックスタイムを作るだけでも、習慣化すると変わってくると言われています」
特に初心者であれば、「ハードにやらなきゃ!」と力みすぎると続かないので、まずは“毎日少しずつ”を目指しましょう。また、運動後や週末には“アクティブな休息”(軽めの散歩など)を取り入れると、回復と持久力アップ両方に良いと言われています。
まとめると、スタミナを高めるためには「継続できる運動」「栄養バランス」「休息・ケア」の三つを同時に整えていくことが近道です。
#スタミナアップ #持久力強化 #スタミナ栄養 #有酸素運動 #生活習慣改善

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。


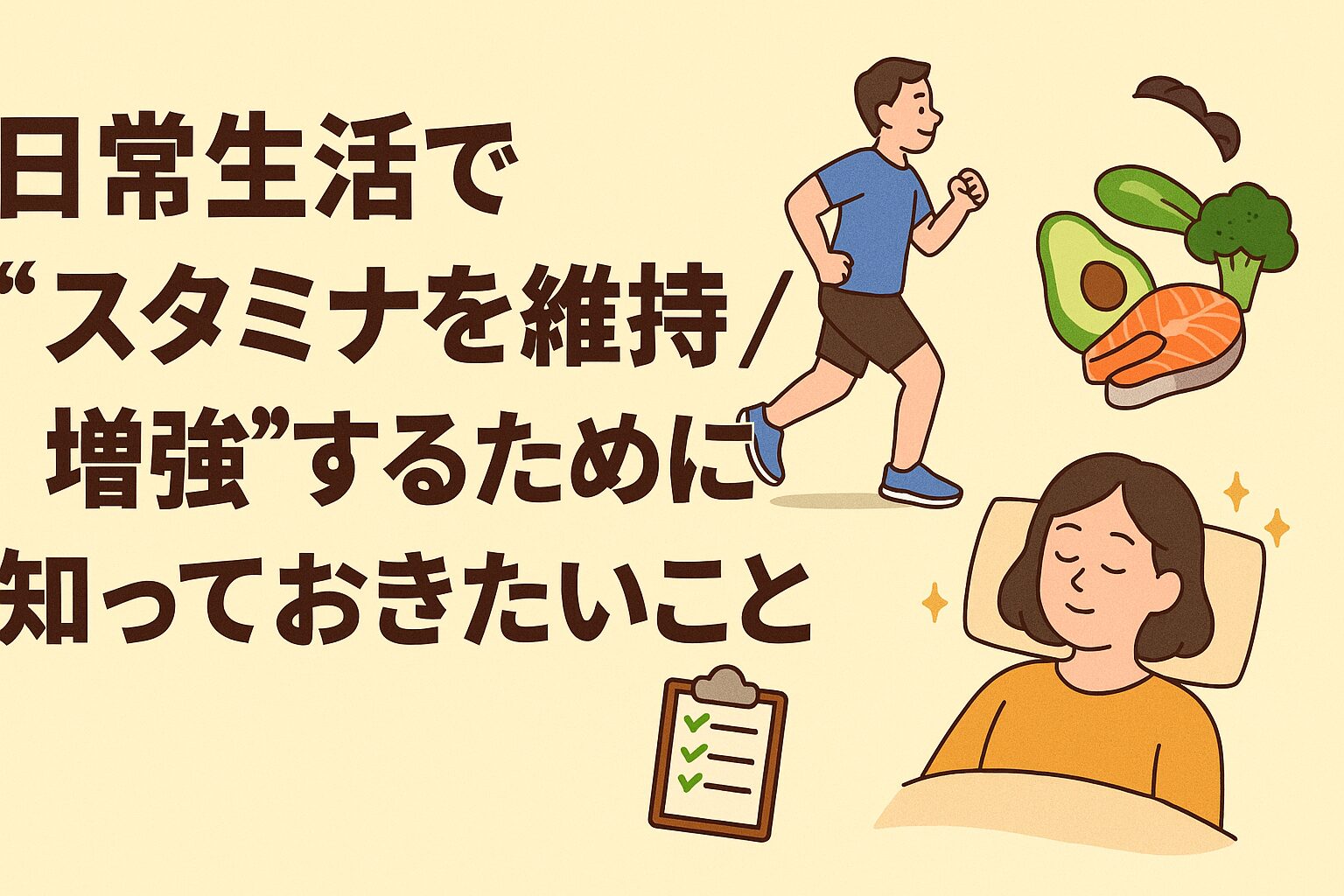
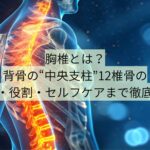

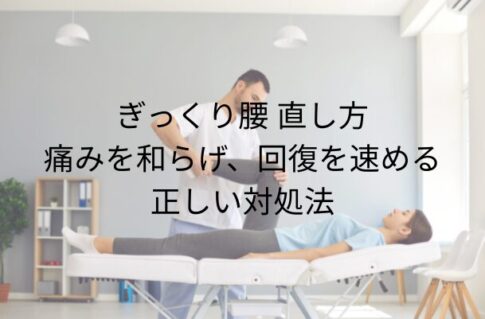


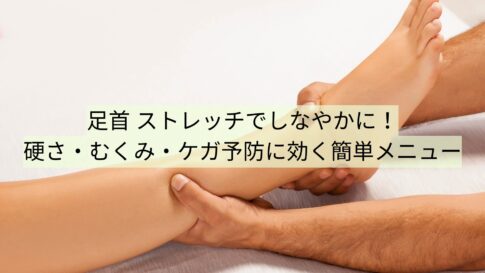
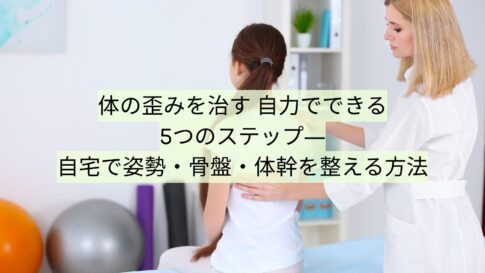
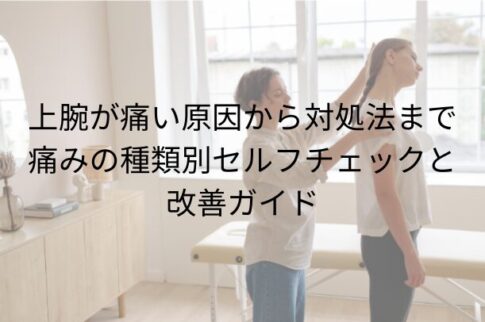

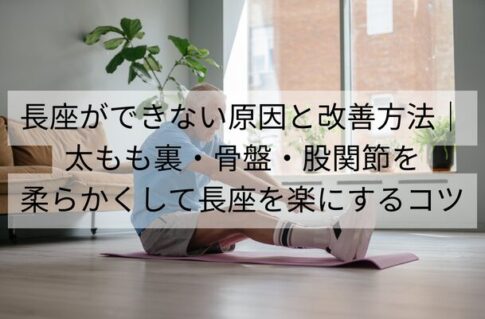
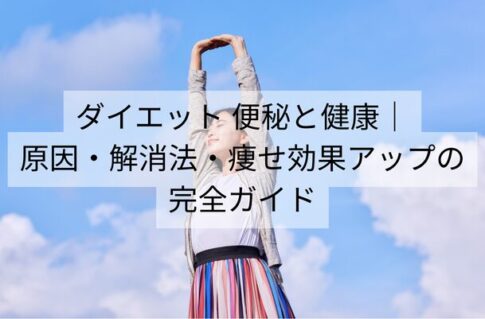
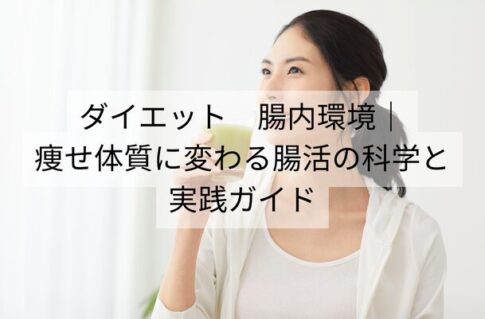
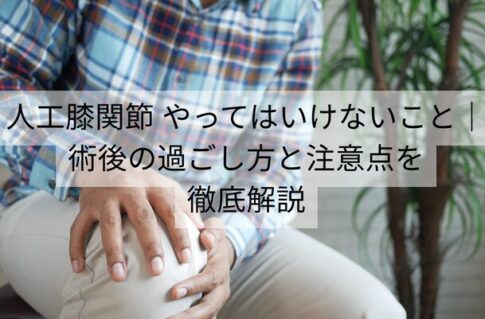
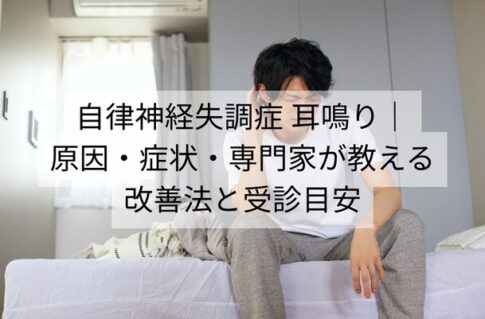
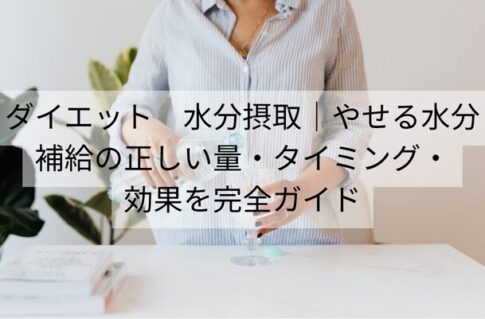




コメントを残す