鼠径部痛の全体像:構造と痛みの特徴
鼠径部とはどの部分か、そのしくみ
「鼠径部(そけいぶ)」は太ももの付け根にあたる部分で、体の中でも多くの組織が集まる場所と言われています。具体的には、内転筋や腸腰筋といった筋肉、靭帯、血管、リンパ節、さらに神経が交差しており、日常の動作や運動時に負担がかかりやすい部位です。特にスポーツをしている人や長時間の立ち仕事が多い人では、筋肉や腱へのストレスが積み重なりやすく、違和感や痛みにつながるケースもあるとされています。
この部分は「体の交差点」のような役割を果たしているため、一つの組織に問題が起きると周囲へも波及しやすいと言われています(引用元:https://inoruto.or.jp/2025/07/groin-hurt/)。たとえば、リンパ節の腫れがあると周囲の血管や神経に圧がかかり、歩行や姿勢に影響が出ることもあるようです。
左側特有の痛みが出る理由
「左だけ痛いのはどうして?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、左右差が生じる背景にはいくつかの要因が考えられています。まず、利き足や姿勢のクセです。無意識に片側へ体重をかける習慣があると、筋肉や靭帯に負担が偏りやすくなります。また、骨盤のバランスや背骨の傾きが影響して片方だけに痛みが集中するケースもあると言われています。
さらに、スポーツ経験の有無も関係するとされています。たとえばサッカーやランニングなど片足を主に使う競技では、左足を軸にして動作を繰り返す人は左鼠径部への負荷が大きくなりやすいそうです。血流やリンパの流れ方も左右でわずかな違いがあり、それが痛みの感じ方に影響する可能性も指摘されています(引用元:https://inoruto.or.jp/2025/07/groin-hurt/)。
こうした背景から、左の鼠径部に痛みを感じるときは「片側だけに負担がかかっていないか」を見直すことが大切だと言われています。普段の姿勢や体の使い方を意識することで、改善のきっかけになる場合もあるようです。
#左の鼠径部が痛い
#鼠径部痛の原因
#姿勢と左右差
#利き足と負担
#体のしくみ
考えられる主な原因と症状の見分け方
筋骨格系の原因
鼠径部の痛みで多いのが、筋肉や腱に関連するものと言われています。特にスポーツをしている方に多いのが**鼠径部痛症候群(グロインペイン症候群)**です。サッカーやランニングなど、繰り返しの動作で内転筋や腸腰筋、恥骨筋に負担がかかり、炎症や損傷を起こすことがあるとされています。動いたときにズキッと痛んだり、股関節を開くと違和感が強まる場合は、このタイプが疑われやすいと言われています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。
骨関節系の原因
次に考えられるのが骨や関節のトラブルです。鼠径ヘルニアは立ったときや力を入れたときに膨らみを感じることが多く、日常生活にも影響が出やすいと言われています。また、変形性股関節症やリウマチ性関節症では、股関節そのものの摩耗や炎症が関係しており、歩行時の痛みや可動域の制限を感じやすいとされています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。
感染・リンパの影響
鼠径部にはリンパ節が多く集まっています。風邪や感染症のあとにリンパ節が腫れて痛むケースもあると言われています。しこりのような腫れを触れることがあり、炎症が強いと熱感を伴うこともあるそうです。この場合は、安静にしていても違和感が続く傾向があるとされています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。
血管・神経・内臓由来の原因
さらに幅広く考えると、血管や神経、内臓からの関連痛が鼠径部に出ることもあるようです。神経の圧迫によってしびれを伴ったり、血管のトラブルで重だるさを感じることもあると言われています。加えて、泌尿器系や消化器系の不調から鼠径部に痛みが響くこともあり、腰やお腹の症状とあわせて出てくる場合もあるようです(引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/7353.html)。
こうしたように、鼠径部の痛みには筋肉や関節だけでなく、リンパや神経、さらには内臓の不調まで多くの要因が関わると考えられています。そのため、自己判断だけではなく「どのような症状が強いのか」を整理することが大切だと言われています。
#左の鼠径部が痛い
#鼠径部痛の原因
#筋肉と関節の不調
#リンパと感染症
#神経と内臓からの関連痛
自宅でできる応急対処とセルフチェック
安静・冷却・湿布の使い方
鼠径部に痛みが出たとき、まず大切なのは「無理をしないこと」と言われています。普段から運動や仕事でよく体を動かす人ほど「少しの痛みなら我慢できる」と思いがちですが、痛みが強くなる前に休むことが重要だとされています。特に急な動作で痛みを感じた場合は、しばらく安静にして筋肉や関節への負担を減らすと良いとされています。
冷却は炎症が疑われるときに役立つと言われています。氷や保冷剤をタオルで包み、15〜20分を目安にあてると、熱感や腫れをやわらげやすいとされています(引用元:https://inoruto.or.jp/2025/07/groin-hurt/)。また、慢性的な違和感であれば、市販の湿布を使うことで痛みの緩和につながる場合もあるようです。
股関節まわりのストレッチと体幹強化
応急対処で少し落ち着いてきたら、簡単なストレッチで股関節の柔軟性を保つことも大切だと言われています。例えば、椅子に座って片足を反対の膝にのせ、股関節を軽く開くように体を前に倒すストレッチは、内転筋や臀部の筋肉をほぐすのに役立つとされています。また、仰向けに寝て両膝を立て、ゆっくりと腰を持ち上げる「ブリッジ運動」も体幹強化につながり、股関節周りの安定性を高める効果があるとされています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/)。
ただし、痛みが強い時期に無理にストレッチをすると逆効果になることがあるため、あくまで違和感が落ち着いてから行うことがすすめられています。
姿勢改善と日常生活での工夫
痛みを再び強めないためには、普段の姿勢や動作を見直すことも大切だと言われています。例えば、立ち上がるときは片方の足に体重をかけすぎず、両足を均等に使うこと。座るときは背もたれにしっかり腰をつけ、骨盤を立てるように意識することがポイントだとされています。また、荷物を持つときは片手だけで持たず、リュックを使うなど両肩に分散させることで鼠径部への負担が減りやすいとされています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/)。
このように、ちょっとした習慣の積み重ねが、痛みを悪化させない工夫につながると考えられています。
#左の鼠径部が痛い
#鼠径部痛のセルフケア
#股関節ストレッチ
#姿勢改善の工夫
#安静と冷却のポイント
受診すべきタイミングと医療機関の選び方
来院を考えた方が良い症状の目安
「少し休めばおさまるかな」と思っていた鼠径部の痛みが、安静にしても続いている場合は注意が必要だと言われています。特に、じっとしている時にも痛む、あるいは腫れやしこり、膨らみが触れるといった症状は自己判断では見極めが難しいことがあるそうです。また、歩くのがつらいほどの痛みやしびれを伴うケース、さらには発熱を伴う場合も、体に炎症や感染が隠れている可能性があるとされています(引用元:https://inoruto.or.jp/2025/07/groin-hurt/、https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。
実際に整骨院や医療機関でも、こうした症状が出ている方は早めに相談をすすめられることが多いようです。放置すると日常生活に支障をきたす恐れがあるため、目安を参考に「このままで大丈夫かな」と感じたら来院を検討すると良いと言われています。
診療科の選び方
鼠径部の痛みでどこに相談したらよいのか迷う方も多いと思います。一般的には、運動や動作に伴う痛みが中心なら整形外科、しこりや膨らみがある場合は泌尿器科、発熱や全身の不調を伴うなら内科に相談する流れが考えられるとされています(引用元:https://inoruto.or.jp/2025/07/groin-hurt/、https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/7353.html)。
例えば、スポーツで痛みが強くなった人は整形外科でレントゲンやMRIなどの検査をすすめられるケースが多いと言われています。一方、リンパ節の腫れやしこりが気になる場合には泌尿器科や内科での触診や血液検査が参考になる場合があるそうです。
どの診療科に行けばよいか迷ったときは、まず整形外科を入り口に考え、その後必要に応じて他科を紹介してもらう流れも選択肢のひとつだとされています。
#左の鼠径部が痛い
#受診すべきタイミング
#整形外科と泌尿器科
#歩行困難と発熱
#医療機関の選び方
再発を防ぐための日常ケアと生活習慣改善
ストレッチと運動で股関節まわりをサポート
鼠径部の痛みを繰り返さないためには、股関節まわりを柔らかく保ち、体を安定させることが大切だと言われています。特におすすめされているのが股関節ストレッチです。たとえば、椅子に腰かけて片足をもう一方の膝にのせ、軽く前に体を倒すストレッチは内転筋や臀部をゆるめるのに効果的だとされています。また、仰向けに寝て膝を胸に引き寄せる動きも股関節の柔軟性を高めるとされています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/)。
さらに、体幹やインナーマッスルの強化も重要です。腰やお腹まわりの筋肉が安定すると、歩行や日常動作で鼠径部に余計な負担がかかりにくくなると言われています。具体的には、ブリッジ運動やプランクといったシンプルな体幹トレーニングが取り入れやすいでしょう。加えて、日常的に軽いウォーキングを習慣にすることで、血流が促されて筋肉や関節の動きがスムーズになりやすいと考えられています(引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/7353.html)。
生活習慣の見直しで体のバランスを整える
運動だけでなく、日常生活の習慣も再発防止に欠かせないポイントだと言われています。まずは体重管理です。体重が増えると股関節や鼠径部への負担が大きくなりやすいため、食生活のバランスを整えることが大切とされています。
また、姿勢改善も効果的です。座っているときに猫背にならないよう意識したり、立っているときに片足に体重をかけすぎないようにすることが、負担の軽減につながると考えられています。骨盤のバランスを保つために、左右均等に荷物を持つ工夫も大切だとされています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/)。
こうした小さな習慣を積み重ねることで、鼠径部にかかる負担を分散させ、再発を予防しやすくなると言われています。「気づいたときに少し意識する」ことが、長期的な体の改善につながるようです。
#鼠径部痛の予防
#股関節ストレッチ
#体幹トレーニング
#姿勢改善と骨盤バランス
#生活習慣の見直し

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

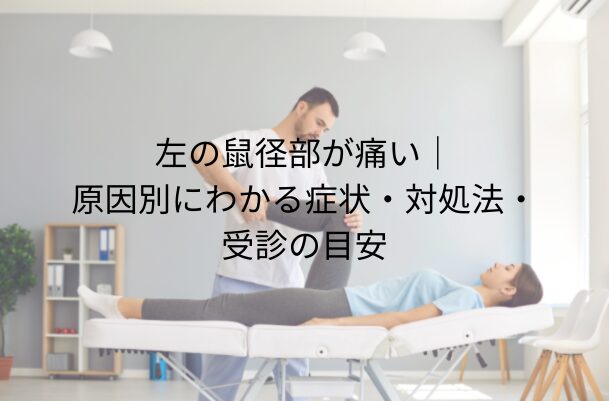


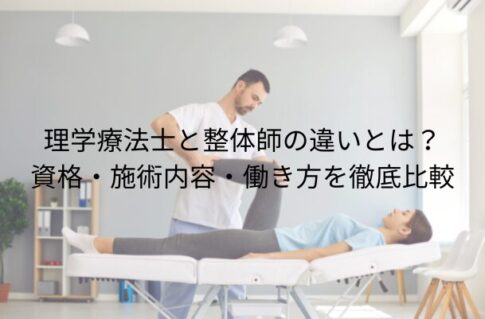

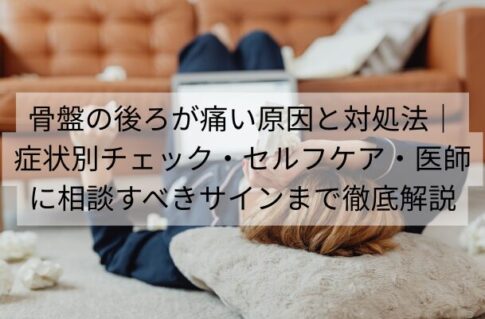
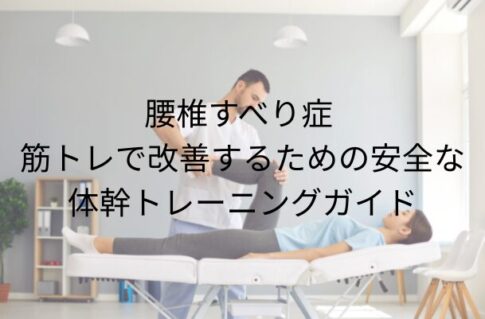

















コメントを残す