なぜ「肩甲骨出し方」が必要?今すぐ知りたい理由
姿勢の乱れがもたらす影響
最近「デスクワークやスマホ時間が長くて肩が重いな」と感じたことはありませんか?私たちの生活習慣は便利になった一方で、長時間同じ姿勢をとることが増えています。特に前かがみの姿勢は肩甲骨の動きを制限しやすいといわれており、その結果として肩こりや猫背につながることが多いそうです(引用元:yotsuya-blb.com, ashiuraya.com, 整体oasis)。
肩甲骨が固まるとどうなる?
「肩甲骨ってそんなに大事なの?」と思う方もいるかもしれません。実は肩甲骨は体の“要”のような存在で、首・肩・背中・腕の動きに深く関わっています。ところが可動性が低下すると、呼吸が浅くなりやすく、血流も滞るといわれています。そのため、肩だけではなく首の重さや頭痛に広がるケースもあると報告されています。当院の整体では、筋膜リリースにより固まった筋肉をほぐしていきます。
日常生活での実感
例えば、長時間パソコン作業をすると「気づけば背中が丸まっていた」という経験はありませんか?また、スマホをのぞき込む姿勢が続くと、背中や肩甲骨の動きが制限されやすくなるといわれています。その状態が習慣化すると、猫背姿勢が定着し、見た目にも疲れた印象を与えてしまうことがあるのです。
今すぐ知っておきたい理由
つまり「肩甲骨出し方」を知ることは、単に背中をすっきり見せるためではありません。姿勢改善や肩こりの予防だけでなく、呼吸や血流の改善にもつながると考えられています。毎日の生活でほんの少し意識を変えるだけで、体の軽さを感じやすくなるといわれていますので、まずは知識として押さえておくことが大切です。
#肩甲骨出し方
#肩こり改善
#猫背予防
#姿勢リセット
#デスクワーク対策

セルフチェック:自分の肩甲骨の状態を知る
壁を使ったバンザイチェック
まず試してほしいのが「壁を使ったバンザイチェック」です。やり方はとてもシンプルで、壁に背をつけて立ち、そのまま腕をゆっくり上に伸ばすだけ。ポイントは、腰や背中を反らさず自然な姿勢を保ちながらどこまで腕が上がるかを確認することです。肩甲骨まわりの柔軟性が十分だと、無理なく耳の横まで腕が上がるといわれています。一方で、腕が途中で止まったり、背中が反ってしまう人は肩甲骨が固まっている可能性があるそうです(引用元:sakaguchi-seikotsuin.com)。
後ろで手を組むチェック
次におすすめなのが「後ろで手を組むチェック」です。これは自分の肩甲骨の可動域や左右差を簡単に確かめられる方法といわれています。やり方は、片方の手を上から背中に回し、もう片方の手を下から背中に回して組むだけ。左右それぞれで行って、指がどの程度触れるか、または組めるかを見てみましょう。片方は組めるのに反対側は難しい場合、左右のバランスが崩れていることが考えられます。日常生活の癖や姿勢の取り方によって、この差が生まれると指摘されています(引用元:ashiuraya.com)。
チェックを通して気づくこと
こうしたセルフチェックを習慣にすると、自分では気づきにくい肩甲骨の動きやすさを客観的に知ることができるといわれています。特にデスクワークやスマホを長時間使う方は、知らず知らずのうちに柔軟性が落ちていることが多いので、まずは“現状を知る”ことから始めるのが大切です。無理なくできる範囲でチェックを行い、気づいたことを今後のストレッチや姿勢改善に生かしてみてください。
#肩甲骨セルフチェック
#肩甲骨出し方
#姿勢改善
#肩こり予防
#柔軟性チェック
自宅でできる短時間ストレッチ5選
「肩甲骨を動かしたいけど、何をすればいいのかわからない…」そんな声をよく耳にします。ここでは、特別な道具を使わずに自宅でできるシンプルなストレッチを5つ紹介します。どれも短時間で取り入れやすいものばかりなので、デスクワークや家事の合間に取り入れてみてください。
肘回しストレッチ(360°回す)
両手を肩に置き、肘で大きな円を描くように前から後ろへ、後ろから前へ回します。360°しっかりと意識しながら動かすと、肩甲骨まわりの筋肉がゆるみやすいといわれています。無理に大きく回そうとせず、気持ちよく動かせる範囲で行うのがポイントです(引用元:kawanaseikotsuin.com, ashiuraya.com, sakaguchi-seikotsuin.com)。
胸を張って肩甲骨を寄せる(10秒×3セット)
椅子に座ったままでもできる簡単な方法です。背筋を伸ばし、両腕を軽く後ろに引いて胸を張ります。そのまま肩甲骨を中央に寄せるように意識して10秒キープ。これを3セット行うと、肩まわりの血流が促されやすいといわれています(引用元:ashiuraya.com)。
壁を使った肩甲骨寄せ
壁に背中をつけて立ち、両腕を「バンザイ」の形で壁につけます。そのまま腕を上下に動かし、肩甲骨が寄る感覚を意識してみましょう。壁を使うことでフォームが安定し、無理なく肩甲骨を動かせるとされています(引用元:からだなび)。
タオルストレッチ(背中で上下に引っ張る)
タオルを両手で持ち、片手を上から、もう片方を下から背中に回して上下に引っ張ります。左右それぞれ行うことで可動域の差も確認でき、背中全体のストレッチになるといわれています。肩甲骨を動かすだけでなく、柔軟性チェックにも役立つ方法です(引用元:ashiuraya.com, kawanaseikotsuin.com)。
背伸びストレッチ or 座ったままストレッチ
立ったまま天井に向かって両手を大きく伸ばす「背伸びストレッチ」は、背中や肩甲骨を気持ちよく広げてくれるといわれています。また、デスクワークの合間には椅子に座ったまま、背筋をまっすぐ伸ばして両手を上に上げるだけでも効果的とされています。呼吸と合わせるとリフレッシュしやすいと感じる方も多いようです(引用元:kumanomi-seikotu.com, ashiuraya.com, 整体oasis)。
これらのストレッチは、毎日1〜2分程度でも続けることで肩まわりが軽くなったと感じる人が多いといわれています。まずはできるものから試して、自分の習慣に合う方法を見つけてみてください。
#肩甲骨ストレッチ
#肩こり予防
#デスクワーク対策
#猫背改善
#簡単エクササイズ

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

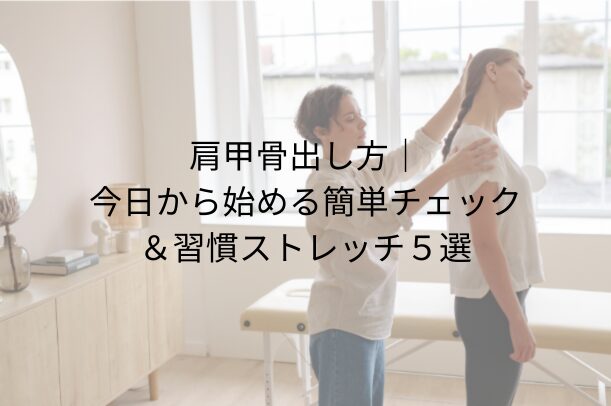




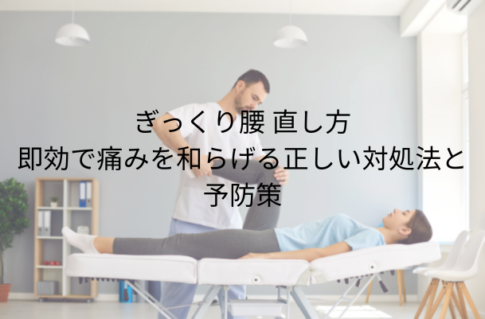

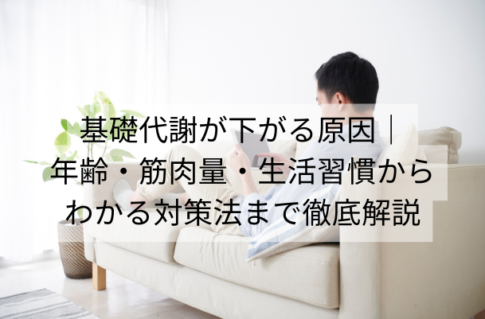
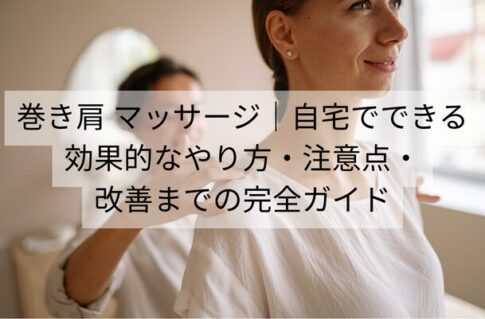
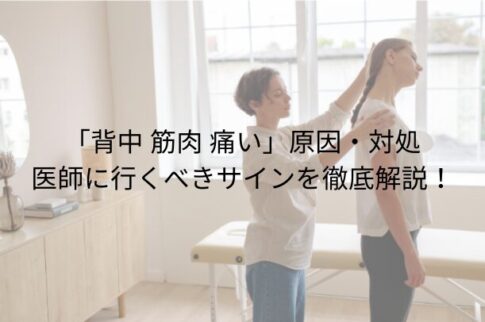
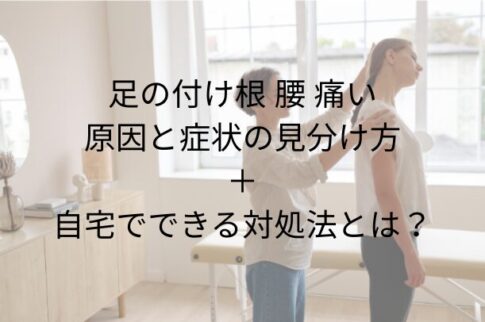






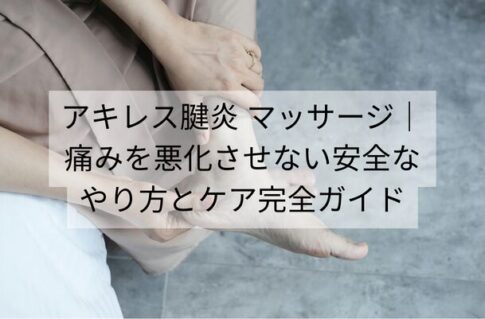








コメントを残す