【原因チェック】膝の皿の下が痛くなる3大原因
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)とは?
「最近、階段を降りるときに膝の下がズキッとするんだよね…」
そんな悩みを抱えていませんか?その症状、もしかしたら**ジャンパー膝(膝蓋腱炎)**かもしれません。
ジャンパー膝は、膝のお皿(膝蓋骨)とすねの骨をつなぐ膝蓋腱に、繰り返し負荷がかかることで炎症が起こるとされているものです。特にジャンプや着地動作が多いバスケットボールやバレーボールなどの競技者に多く見られる傾向があると言われています(引用元:リハサク)。
痛みの特徴としては、動き始めや運動後に膝の下側がズーンと重くなるような感覚があり、ひどくなると運動を続けるのが難しくなることもあるようです。
膝蓋下脂肪体炎の可能性も
「押すとふわっとした部分が痛む気がする…」
それ、膝蓋下脂肪体炎のサインかもしれません。
膝蓋骨のすぐ下にある脂肪組織が刺激を受けて炎症を起こすことで、膝のお皿の下部に痛みを感じると言われています。この脂肪体は関節のクッション的な役割を果たしていますが、膝を深く曲げたり、正座を繰り返すことで圧迫されやすくなるようです。
特に、座りっぱなしやしゃがむ動作が多い方に多く見られ、「膝の奥がじわじわ痛む」「膝の裏側もなんとなく違和感がある」と感じることがあるようです(引用元:Medicalook、まめクリニック)。
オーバーユース(使いすぎ)が根本の原因かも?
スポーツはもちろん、日常生活でも**使いすぎ(オーバーユース)**が痛みにつながるケースがあります。
「運動量を増やしたら急に痛くなってきた」
そんなタイミングはありませんか?
歩く・立ち続ける・階段の上り下りといった何気ない動作でも、膝の下に負担が蓄積されていることがあります。筋力不足やフォームの崩れ、体の使い方の癖が痛みの引き金になることもあるとされています。
一見、たいしたことない痛みに思えても、放置すると長期化することもあるため、早めの対応が大切と考えられています。
#膝の痛み
#ジャンパー膝
#膝蓋下脂肪体炎
#オーバーユース
#スポーツ障害

【症状判断】その痛み、どのタイプ?症状別セルフチェック
あなたの膝の痛み、どこでどんな時に出てますか?
「なんとなく膝の皿の下が痛い気がするけど、原因がわからない…」そんなふうに感じたことはありませんか?
実は、痛みの出るタイミングやシチュエーションを丁寧に見ていくことで、ある程度の目安がわかると言われています。
ここでは、よくある膝痛のパターンを元に、セルフチェックできるようまとめてみました。あくまで参考ですが、ひとつずつ当てはめてみてください。
症状別セルフチェックリスト
✅ 階段の昇り降りで膝の下が痛む
→ジャンパー膝や膝蓋下脂肪体炎が関係していることがあると言われています。階段の昇りよりも、降りる時に強く痛むケースが多いようです(引用元:リハサク)。
✅ スポーツ中や直後にズキっとした痛みが出る
→走る、ジャンプする、方向転換をするなどの動作のあとに痛みが出ると、膝蓋腱炎の可能性もあるとされています(引用元:まめクリニック)。
✅ 座っていて立ち上がった時に痛みを感じる
→長時間同じ姿勢でいた後の動作で痛む場合は、脂肪体炎や筋緊張の蓄積が関係しているケースが考えられるようです。
✅ 膝が腫れている気がする
→膝蓋下に腫れが見られるときは、炎症反応が起こっていることがあるそうです。外から見て明らかでなくても、圧迫感や違和感があれば注意が必要です。
✅ 触ると熱を感じる
→熱感がある場合、組織が炎症を起こしている可能性があるとされています。冷やすことで落ち着くこともありますが、繰り返す場合は注意が必要です。
✅ 膝の曲げ伸ばしがしづらい/引っかかる感じがする
→可動域の制限が出ているときは、内部で滑りが悪くなっていたり、脂肪体の癒着などが影響している場合もあるようです(引用元:Medicalook)。
痛みの強さや出る場所だけでなく、「どんな動きの時に出るのか」も大事なヒントになります。もし複数チェックが当てはまるようなら、一度専門家にみてもらうのも選択肢のひとつかもしれませんね。
#膝の皿の下が痛い
#膝痛セルフチェック
#ジャンパー膝症状
#膝蓋下脂肪体炎
#膝の腫れと熱感

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています









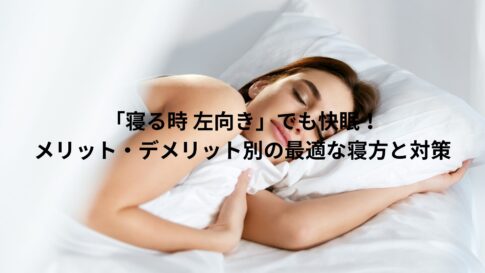

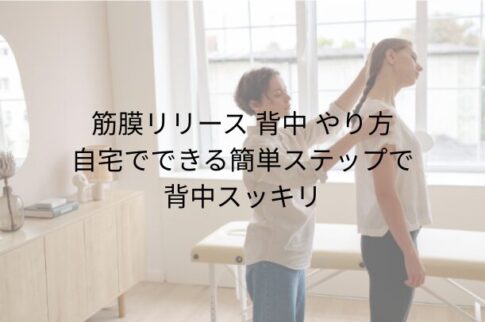




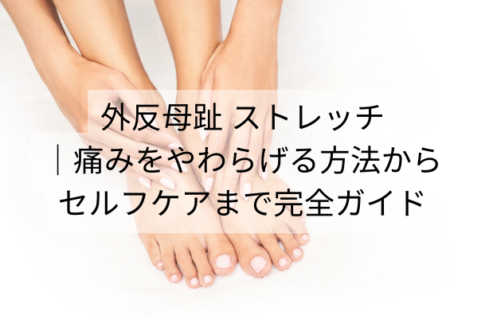
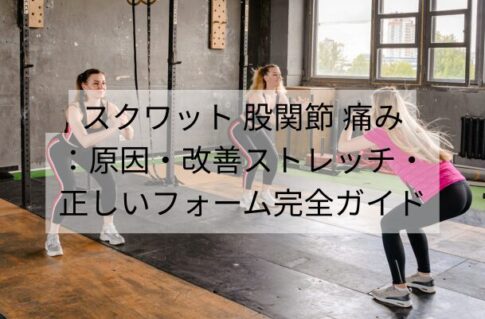
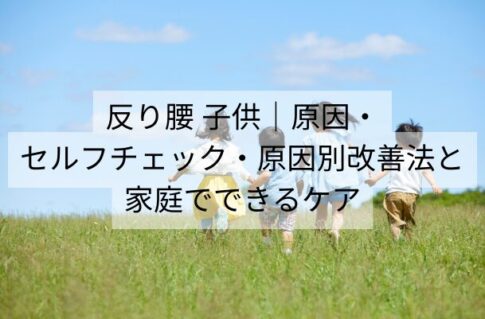
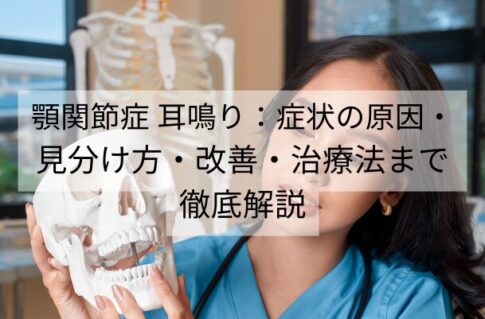
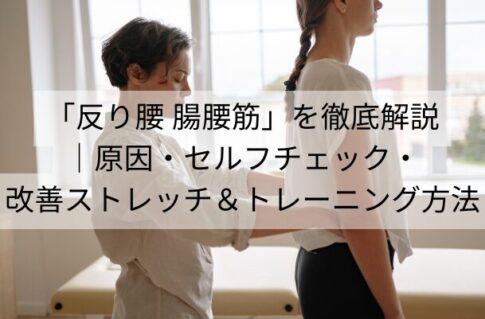




コメントを残す