足首の外側にある代表的なツボと位置
崑崙(こんろん)
「崑崙」というツボは、外くるぶしとアキレス腱の間にあります。座った状態で足首を軽く内側に倒すと、この部分にくぼみができ、その中央あたりが崑崙です。昔から腰や足のだるさに関連があると言われており、指で押すと心地よい刺激を感じる方もいます。あまり力を入れすぎず、ゆっくりと押すのがポイントだそうです
申脈(しんみゃく)
申脈は外くるぶしの真下にあるくぼみに位置しています。足の外側をなぞるように下に向かって触っていくと、骨の際に小さなくぼみがあります。そこが申脈です。体のリズムを整える働きがあると言われ、日常の疲労感やだるさにも関係しているとされます。優しく円を描くように刺激すると、リラックスしやすいという声もあります
丘墟(きゅうきょ)
丘墟は外くるぶしの斜め前方、甲とくるぶしの間あたりにあります。足首を軽く動かすと筋が浮き出ますが、その前側で少しくぼんだ部分が目印です。足の血行促進やむくみケアとの関係が指摘されており、長時間立ち仕事をしている方が押すとスッキリ感を得やすいとも言われています
足臨泣(あしりんきゅう)
足臨泣は足の甲側、薬指と小指の間から足首方向へたどったライン上にあります。外くるぶし寄りで、骨と骨の間に指がスッと入るポイントが目安です。全身の巡りと関わるとされ、冷えを感じやすい方にも注目されています。軽く押すだけでも温かみを感じることがあるそうです。
懸鐘(けんしょう)
懸鐘は外くるぶしの上方、すねの外側に位置するツボです。くるぶしから指3本ほど上にある骨の突起部分の前側を探すと見つかります。足の疲労感やバランス感覚との関わりがあるとされ、スポーツ前後のケアに取り入れる方もいます。
#足首ツボ #崑崙 #申脈 #丘墟 #足臨泣
(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)
(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)
(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)
それぞれのツボが期待できる効果と作用
むくみの軽減
足首外側のツボの中でも「丘墟」や「足臨泣」は、足の血行やリンパの巡りと関係が深いと言われています。特に長時間立ちっぱなしや座りっぱなしで足が重だるく感じる時、このエリアの刺激が水分代謝をサポートする可能性があるとされています。日常のセルフケアとして取り入れる方も多く、足首周辺が温かくなってくる感覚を得やすいそうです
冷えへのアプローチ
「崑崙」や「申脈」は、下半身の冷えと関係しているとされるツボです。東洋医学では、足元の巡りが滞ると体全体のバランスに影響すると考えられています。足首外側をやさしく押すことで、血流が促されて温かみを感じやすくなると言われています。冬場やエアコンの冷えが気になる時期に意識して使う方も少なくありません
疲労回復のサポート
「懸鐘」は筋肉や関節のこわばりと関わりがあるとされ、足の疲労感を感じたときに用いられることがあります。スポーツ後や歩きすぎた日に軽く押すと、足がほぐれるような感覚を持つ人もいるそうです。即効性があるわけではありませんが、繰り返しケアすることで体の調子を整える一助になると考えられています。
腰のだるさとの関係
足首外側の「崑崙」は腰の重さやだるさにも関係すると言われています。東洋医学では、下半身の巡りが腰の負担軽減にもつながるとされており、足元のケアが全身のバランスを取るサポートになる可能性があります。長時間の立ち作業やデスクワークで腰に負担を感じやすい方に向いているとされます
自律神経の調整
「申脈」は体のリズムや睡眠にも関わると考えられており、気持ちを落ち着けたいときに使われることがあります。リラックス状態を作りやすくするため、寝る前に軽く押す習慣を持つ方もいるようです。こうした働きは科学的にすべてが解明されているわけではありませんが、東洋医学的な観点では重要な役割を担っているとされています。
#足首ツボ効果 #むくみケア #冷え対策 #疲労回復 #自律神経調整
(引用元:https://nikkori-sinkyuseikotsu.com)
(引用元:https://nikkori-sinkyuseikotsu.com)
(引用元:https://nikkori-sinkyuseikotsu.com)
自宅でできる正しいツボ押しの手順とコツ
指やツボ押し棒の使い方
足首の外側にあるツボは、指(特に親指)やツボ押し棒を使って刺激できます。親指の場合は腹の部分を使い、やや面で押すようにすると力が均等に伝わりやすいです。ツボ押し棒を使う場合は、先端が丸いタイプを選び、皮膚を傷めないよう注意しながら使うと良いと言われています
実際にやってみると、「あ、ここだな」という心地よい痛みや温かみを感じるポイントが見つかることがあります。
押す強さと呼吸の合わせ方
押す強さは“気持ち良いと感じる程度”が目安です。強く押しすぎると筋肉や皮膚に負担がかかる可能性があるため、軽くから始めて徐々に調整すると安心です。呼吸は、押すときに息を吐き、離すときに吸うリズムがおすすめと言われています。呼吸と合わせることで全身がリラックスしやすくなるそうです。
回数とセット数の目安
1日数回、1セットあたり10回程度を目安にすると継続しやすいです。特に朝起きたときや仕事の合間、夜のリラックスタイムなど、日常に組み込むと無理なく続けられます。1回の刺激時間は1〜2秒押してゆっくり離すイメージで行うと良いとされています。
ベストなタイミング
お風呂上がりは体が温まって血行が良くなっているため、ツボの刺激が届きやすいと言われています。また、寝る前に軽く押すと、心身が落ち着いて眠りやすくなる方もいます。逆に、空腹時や食後すぐ、強い疲労を感じているときは避けた方が良いとされています
効果を感じやすくするコツ
ツボ押しは一度で大きな変化を求めるより、少しずつ習慣化することが大切と言われています。同じツボでも日によって感覚が違うため、強さや時間を調整しながら続けると、体の変化を実感しやすくなるそうです。ストレッチや足首回しと組み合わせると、より巡りが促される可能性があります。
#足首ツボ押し #ツボ押しコツ #セルフケア #むくみケア #冷え対策
(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)
(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)
注意すべきケースとNGタイミング
妊娠中の方
妊娠中、特に安定期前はツボ刺激を避けた方が良いと言われています。足首周辺には子宮やホルモンの働きと関連するとされるツボもあり、刺激が体に負担を与える可能性があるためです。安定期に入ってからも、自己判断せず、必ず専門家や担当医に確認することが大切です
発熱時や体調不良のとき
発熱や強い倦怠感があるときは、体が回復に集中しているため、無理な刺激は避けた方が良いとされています。特に高熱時や感染症が疑われるときは、ツボ押しよりも安静と水分補給を優先した方が安心です。
皮膚炎や外傷がある場合
ツボの位置に湿疹、かぶれ、傷などがあるときは、刺激によって炎症が悪化する恐れがあります。押すのではなく、まずは皮膚の回復を優先することがすすめられています。患部が完治してからセルフケアを再開すると良いでしょう。
糖尿病や神経障害のある場合
糖尿病や末梢神経障害がある方は、痛みや刺激の感覚が鈍くなっている場合があり、知らないうちに押しすぎてしまうことがあります。そのため、必ず専門家の指導を受けたうえで行うことが推奨されています
飲酒後や極端な疲労時
飲酒後や極度の疲労時は血圧や心拍数が不安定になっている場合があり、ツボ押しによる刺激が体に負担を与える可能性があると言われています。こうしたタイミングでは、まず休養や睡眠を取ることを優先した方が良いでしょう。
#ツボ押し注意点 #妊娠中セルフケア #発熱時NG #糖尿病注意 #安全なツボ押し
(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)
(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

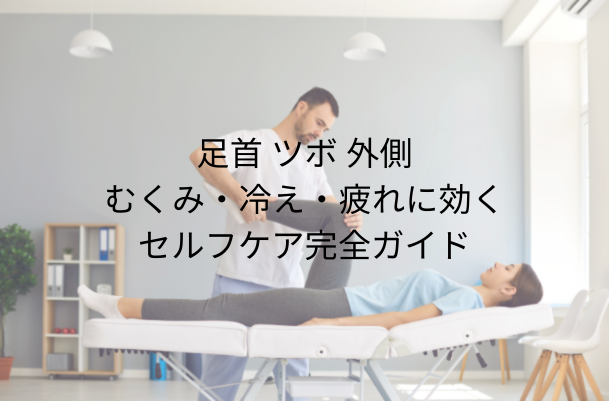

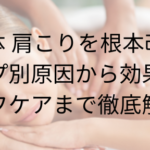
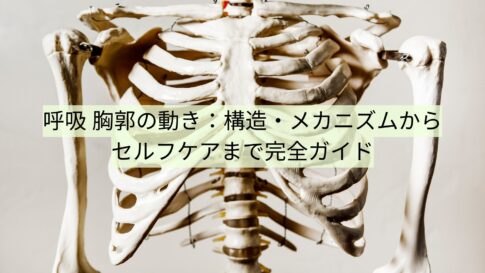
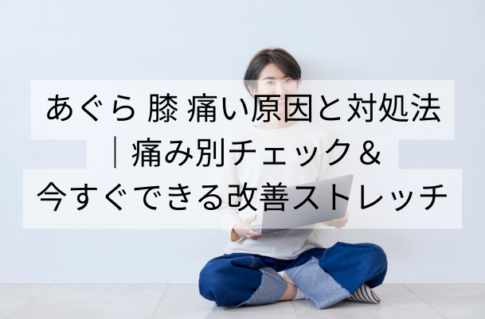

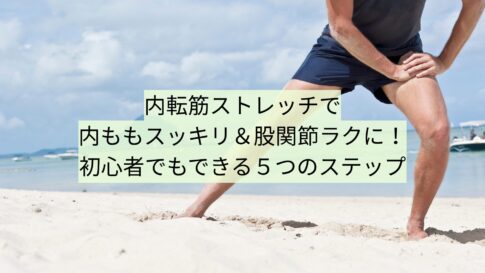

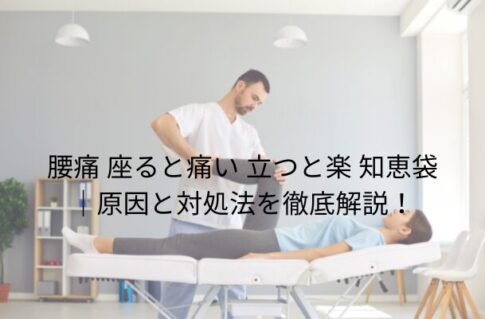
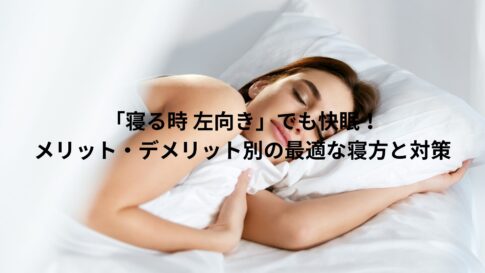






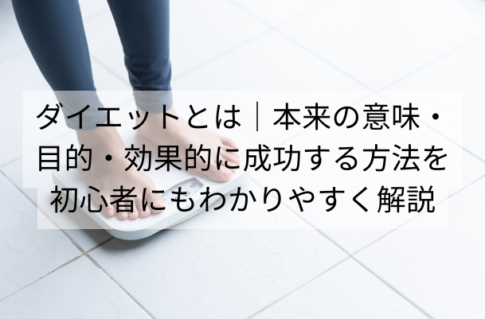
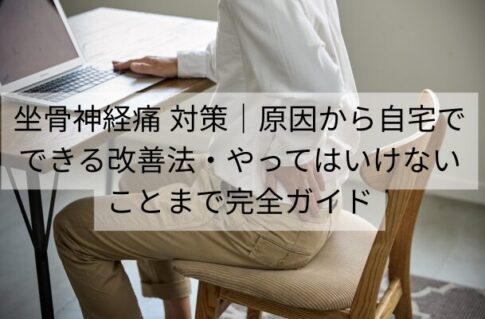
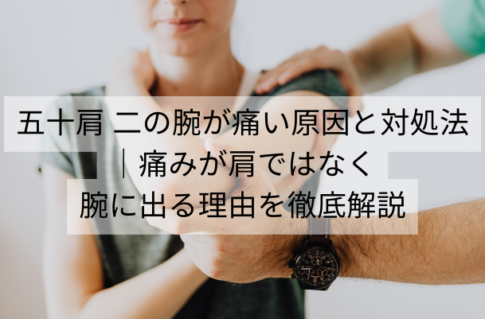
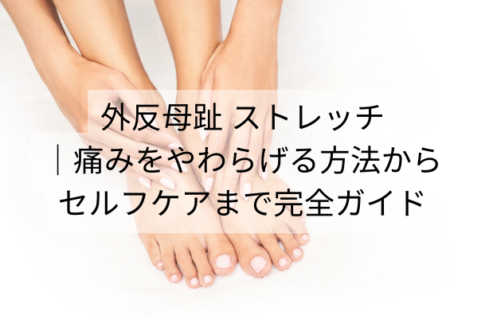




コメントを残す