1.前鋸筋とは?位置・構造・支配神経

「前鋸筋(ぜんきょきん)」って、あまり聞く機会は少ないかもしれませんが、実は肩甲骨まわりの動きや安定に大きくかかわる筋肉と言われています。今回は、「どこにあるのか」「構造はどうなっているか」「支配神経は何か」という点を、できるだけ分かりやすくお話ししますね。
起始・停止・神経支配
まず起始(筋肉が始まる所)と停止(終わる所)から見てみましょう。
-
起始:通常 第1~第9肋骨(外側面) から起こると言われています。 ボディ・モーション・ラボ
-
停止:肩甲骨の 内側縁の前面(前方) 、特に上角・内側縁・下角あたりにかけて付着する構造です。 THERABBY
-
支配神経: 長胸神経(C5~C7) が主にこの筋肉を支配しており、解剖学的な報告でもそのように示されています。 forphysicaltherapist.com
このように、肋骨という「体幹の側面」から肩甲骨という「上肢の土台」となる構造物へと走行しており、「鋸(のこぎり)状」に肋骨にくっついているところから“前鋸筋”という名前が付いたと言われています。
上部・中部・下部筋束の違い
この前鋸筋、一枚の筋肉ではありますが、実は上部・中部・下部の筋束(筋繊維のまとまり)にわけて考えることがよくあります。それぞれ付着部や働きが少しずつ異なるからです。 マイナビコメディカル
-
上部筋束:第1〜2肋骨あたりから起こり、肩甲骨の 上角付近 に付着することが多いです。このあたりは比較的発達していて、肩甲骨の前下方への動きに関与するとも言われています。 マイナビコメディカル
-
中部筋束:第2〜3肋骨あたり起始・肩甲骨内側縁に付着とする報告もあり、外転(肩甲骨を外側へ引く動き)に働くとされた部分です。 ボディ・モーション・ラボ
-
下部筋束:第4〜第9肋骨あたりから起こり、肩甲骨の 下角付近 に付着する構造です。肩甲骨の上方回旋(腕を上げる時に肩甲骨が回る動き)に特に作用すると言われています。 ボディ・モーション・ラボ
このように、前鋸筋は「ひとつの筋肉だけど、部位によって役割が少し異なる」という面白い特徴があります。ですから、肩甲骨まわりの動きが気になる方や、腕をよく使うスポーツ・仕事をしている方は、この筋肉の構造と走行を知っておくことで“どこにアプローチすべきか”が明確になるでしょう。
#前鋸筋とは
#肩甲骨の動き
#筋肉の仕組み
#姿勢改善の基本
#肩甲骨解剖
2.前鋸筋の作用・役割:なぜ重要か
前鋸筋の主な作用・役割
「ねえ、どうしてあの“ 前鋸筋(ぜんきょきん)”って、肩甲骨まわりでそんなに注目されているの?」――そんな疑問、ありませんか?実はこの筋肉、肩甲骨を肋骨としっかりつなぎ、腕をスムーズに動かすための鍵を握ると言われています。
まず、この筋肉の主要な働きについてざっと触れておきましょう。
-
肩甲骨を胸郭(肋骨の外側部分)に“外側・前方に引く(外転)”動きに関与していると言われています。 muscle-guide.info
-
また、腕を上げるためには肩甲骨が「上方回転」する必要がありますが、前鋸筋はこの上方回転を補助する筋肉としても作用するそうです。 The Muscular System
-
さらに、肩甲骨を “肋骨に密着させて安定させる” 役割もあるため、肩甲帯全体の動き・力発揮において重要なポジションなんです。 Physiopedia
-
加えて、固定された肩甲骨のもとでは、肋骨側を引き上げて“呼吸を助ける補助筋”としても働くという報告もあります。 The Muscular System
ですので、前鋸筋がしっかり機能していないと、腕を上げる動作・押す動作・日常動作のスムーズさに影響が出る可能性がある、と言われています。
日常生活・スポーツ動作での登場シーン
「日常で?スポーツで?そんな動きにまで使われてるの?」と思うかもしれませんが、実は結構 “いて当たり前” の場面でこの筋肉が働いています。
例えば:
-
棚の上の物を取り出したり、腕を天井近くまで上げるとき。
-
ドアを押して開けたり、重い荷物を押すような動作をしたり。
-
スポーツではパンチを出すボクサーのような動き、バドミントンやバレーボールのアッパースイング、またプッシュアップ(腕立て伏せ)のロックアウト局面など。 muscle-guide.info
こまめな動作としては、「肘を伸ばして前に押し出す」ような動きにもこの筋肉が一役買ってると言われています。
つまり、“肩甲骨を支える=腕を動かしやすくする土台づくり”として、この前鋸筋が活躍している、ということですね。
前鋸筋の機能不全がもたらす影響
では、「もし前鋸筋の働きが十分でないとどうなるの?」という話です。残念ながら、機能低下や支配神経(例:長胸神経)のトラブルが起きると、次のような影響が出やすいと言われています。
-
肩甲骨が肋骨から浮いてしまい、「 翼状肩甲(よくじょうけんこう)」として肩甲骨の内側縁または下角が背中側から “羽が生えた” ように見えることがあります。 muscle-guide.info
-
腕を上げる・押す・荷物を動かすといった動作が “しづらい” または “ぎこちない” 感覚になる場合があるようです。 サイエンスダイレクト
-
肩甲骨の動きが不安定だと、肩の関節そのものの安定性・機能に悪影響が出る可能性があり、肩こり・痛み・肩関節のインピンジメント(挟み込み)などのリスクが高まると言われています。 Physiopedia
ですので、「なんか肩まわりがスムーズじゃない」「腕を上げたときに肩甲骨がカクッと動く感じがある」など、そんな自覚がある方は、前鋸筋の働きをチェックポイントに入れてみるといいかもしれません。
#前鋸筋の役割
#肩甲骨安定筋
#上方回旋サポート
#日常動作と前鋸筋
#スポーツパフォーマンス向上
3.硬さ・弱さ・機能低下のサインとリスク

前鋸筋が硬くなることで起こる姿勢変化
「ねえ、最近なんか肩が丸まってきたな…」と感じたら、実は 前鋸筋 に“硬さ”が出ているサインかもしれません。例えば、次のような変化が起きやすいと言われています。
-
肩が前に出る「巻き肩」や、背中が丸くなって猫背気味になる姿勢。こういった姿勢は前鋸筋が肋骨から肩甲骨をしっかり引きつけておけない、または走行が短くなっていることが一因と考えられています。
-
呼吸が浅く感じる、胸がうまく使えない感覚。これは前鋸筋が肋骨沿いに走る筋で、緊張状態が長く続くと胸郭の動きが制限され、呼吸効率にも影響を及ぼしうると言われています。
-
肋骨の側面〜肩甲骨内側縁のあたりに「張り」「突っ張り感」を感じることも。これは、前鋸筋が慢性的に短縮・硬化している可能性がある症状です。
このように、“筋肉が硬い”=“動きが制限される”という流れが起きて、姿勢や動作のクセとして現れやすくなります。日々デスクワークが長い人・腕を多く使う仕事をしている人・姿勢をあまり意識できていない人などは、前鋸筋の硬さに注意してみるといいかもしれません。
弱くなる/機能低下すると起こるサイン
では逆に、前鋸筋が “弱い・機能低下” したときに現れやすいサインを見てみましょう。
-
肩甲骨が背中側から “浮く” ように見える「翼状肩甲(ウイングドスキャプラ)」という状態。つまり、肩甲骨の内側縁または下角が肋骨から離れて出っ張って見えるものです。これは前鋸筋が肩甲骨を肋骨側にしっかり貼りつけられなくなったサインと言われています。
-
腕を上げる・押す・荷物を動かすとき、「肩の動きがスムーズじゃない」「ぐらつく感じがある」「肩が引けてしまう」という違和感。前鋸筋が肩甲骨を安定させられないと、肩関節周りの補助筋が過剰に働き、動作制限につながると言われています。
-
肩こり・肩関節まわりの痛み・上腕のだるさなどが慢性的になることも。肩甲骨の位置が崩れることで、神経・筋・関節に過剰な負荷が掛かるリスクが高まると言われています。
こうしたサインに気づいたら、前鋸筋の「働き・構造・付着」などを再度確認して、セルフチェックをしてみるのがおすすめです。
自分でチェックできる簡易セルフテスト・アライメント確認法
「自分でできるかな?」と思うかもしれませんが、前鋸筋の機能低下の有無を簡易にチェックする方法があります。以下のような方法が紹介されています。
-
壁に向かって腕を肩の高さくらいに上げ、手を壁につけて「プッシュアウト(押し出す)動作」をしてみる。肩甲骨が壁から“浮いたり”内側縁が出っ張ったりすれば、前鋸筋の弱さ=肩甲骨の安定低下が疑われると言われています。
-
壁プッシュアップ(壁に手をついて腕立て伏せのような動作)をして、肩甲骨の動きを鏡やスマホでチェック。肩甲骨が滑らかに動けばOK、出てこない・ついてこない・浮くように見えるなら要注意。
-
自分の立ち姿・肩甲骨の位置を見て、「肩甲骨の内側縁が背中から出ていないか」「肩が前に出ていないか(巻き肩)」「腕を上げると肩甲骨がびくっと動く・遅い」といった違和感を感じるかどうか点検する。姿勢のクセとして、前鋸筋の機能低下が隠れている可能性あり、ということです。
こうして“硬さ”“弱さ”“姿勢変化”のサインを事前に知っておくことで、早めに対策を取ることにつながります。もし「これは自分も当てはまるな…」と思ったら、次の段階として「ストレッチ/強化」へと移るのが良い流れでしょう。
#前鋸筋チェック #肩甲骨安定 #巻き肩予防 #肩甲骨ウイング #肩まわりセルフテスト
4.前鋸筋を整える/ストレッチ&トレーニング法
「ねえ、肩まわりがなんだか重い/腕を上げると肩がガチガチ…」という感じがある方は、もしかすると 前鋸筋 が硬くなっていたり、逆に弱くなっていたりするかもしれません。今回はその前鋸筋を “整える”ためのストレッチ&トレーニング法 を、会話口調でわかりやすくご紹介しますね。ポイントや注意点も最後にまとめますので、日常生活に取り入れやすい形で読んでみてください。
ストレッチ — 硬さにアプローチ
「まずは詰まっている感じをゆるめたいな」という時には、ストレッチが有効です。前鋸筋が硬くなると、肩甲骨が動きづらくなって、巻き肩や猫背、呼吸が浅くなるといった変化につながると言われています。引用元: NEIGHBORFIT | 運動で心と身体を整える |
具体的な方法としては次のようなものがあります:
-
壁を使ったストレッチ:壁の前に立って腕を肩の高さまたは少し上に出し、手を壁につけて体を少し前に倒します。肘は伸ばしたまま、肩甲骨が背中から離れて“外に引き出される”感じを意識すると良いです。息を吐きながらゆっくり倒し、20〜30秒キープ。引用元: 湘南カイロ茅ヶ崎整体院
-
フォームローラー(またはストレッチポール)を使った胸郭リリース:脇の下あたりにローラーを当てて横向きに寝転び、腕を上げ下げしながらゆっくり体を転がします。前鋸筋の走行に沿って筋膜や深部筋をゆるめるイメージです。痛みを感じない範囲で、左右30秒ずつが目安。引用元:sakaguchi-seikotsuin.com
「ゆるめる」段階では、呼吸と動きを連動させることが大切です。息を吸う時に動きを準備し、吐く時に体を倒したり傾けたりして伸ばしていくと、より筋肉がほぐれやすくなると言われています。引用元: 湘南カイロ茅ヶ崎整体院
トレーニング — 筋力低下・強化に向けて
「ゆるめたあとは、使えるようにしていこう」というフェーズです。前鋸筋が弱かったり動きが鈍かったりすると、肩甲骨が浮き上がったり、腕を使って押す/引く動きで力が入りづらくなると言われています。引用元:NEIGHBORFIT | 運動で心と身体を整える |
以下のようなトレーニングがおすすめです:
-
プランク変形:通常のプランク姿勢でキープした後、肩甲骨を「背中から押し出す」ように意識します。胸を張るよりは、「肩甲骨を肋骨に貼りつける」感覚を持つと前鋸筋が使いやすいです。初めは10〜15秒キープから始めると良いと言われています。引用元: Smartlog
-
ウォールスライド(壁スライド):壁に背をつけて立ち、肘と手の甲を壁につけたまま、ゆっくり腕を上に滑らせます。肩甲骨の上方回旋を意識しながら行うことで、前鋸筋+僧帽筋下部の動きが改善されやすいと言われています。
-
パンチアウト動作:仰向けや立った姿勢で、ダンベルやペットボトルを持ち、腕を前方へ突き出すような動作を行います。肩甲骨が肋骨にしっかりついている感覚を意識しながら動くと、スポーツの動きにもつながりやすいです。引用元: Smartlog
これらのトレーニングを行う時は、「痛みが出ない動き」「姿勢を崩さないこと」「呼吸を止めないこと」がポイントです。痛みや違和感を感じたら無理を避け、専門家に相談することも選択肢の一つです。
実践時のポイント・注意点
この前鋸筋ケアを継続していくためには、次のような点を押さえておくとスムーズです:
-
姿勢を意識すること:背中が丸まったり、肩が内側に入りすぎていたりすると、前鋸筋がうまく使えていない可能性が高いと言われています。ストレッチ・トレーニング開始前に、まず「立ち姿」「肩甲骨の位置」をチェックしておきましょう。引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院
-
呼吸を止めないこと:深呼吸やゆったりとした息の流れを伴わせることで、筋肉がリラックスしやすく、効果が高まりやすいです。特にストレッチ時は「息を吐きながら伸ばす」ことが推奨されています。引用元: sakaguchi-seikotsuin.com
-
痛みがある場合は中止を検討:伸びている感覚=「気持ちいい」範囲で行うのが安全です。もし「鋭い痛み」「しびれ」「肩や腕がいつもと違う感じが強い」などがあれば、無理をせずケアを中断して、整形外科や理学療法士等の専門家に相談することが安心です。引用元: 湘南カイロ茅ヶ崎整体院
-
「ゆるめる」だけで終わらせず、「使える状態」にすることを忘れずに:ストレッチだけだと柔らかくなるだけで、筋肉が働ける状態=“使える筋肉”にはならないと言われています。強化動作を併用することで、姿勢改善や肩まわりの動きが実感しやすくなるとの報告があります。引用元: sakaguchi-seikotsuin.com
#前鋸筋ケア #肩甲骨トレーニング #巻き肩改善 #肩まわりストレッチ #姿勢改善習慣
5.前鋸筋を活かす日常・スポーツでの活用法と予防ケア

「ねえ、普段から“あ、この筋肉使えてるかな?”って思うことある?」なんて会話、ちょっと想像してみてください。ここでは、前鋸筋を 日常&スポーツで活かすコツ と 予防ケア習慣 を、会話形式でゆるく紹介しますね。
日常動作&スポーツでの「前鋸筋」活用シーン
「えっ、荷物を押す時にも前鋸筋って使うの?」と少し驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、実はすごく身近な動作で活躍します。
たとえば:
-
スーパーで買った荷物をカートで押す、扉を押して開ける、棚の上に手を伸ばして物を取る、といった“肩甲骨を少し前に出す・押す”ような動き。こうした動作では、前鋸筋が肩甲骨を胸郭(肋骨)にしっかり引きつけることで「安定した土台」が作られると言われています。
-
スポーツでは、パンチ・バドミントン・バレーボールなど「腕を前に突き出す」「上に振る」「押し込む」動作で、肩甲骨がしっかり機能していないと力が逃げやすいという報告があります。前鋸筋がその“肩甲骨と胸郭の橋渡し役”になっているという観点です。
こういう“日常&スポーツシーン”を思い浮かべるだけで、「あ、自分もこれ使えてないかも?」と気づくきっかけになるはずです。
前鋸筋をケアする習慣と専門家相談のタイミング
「じゃあ、どうやってケアしたらいいの?」という話です。前鋸筋を整えておくと、肩甲骨の動きがスムーズになり、肩まわりの不調が出にくくなると言われています。
具体的には:
-
定期的なストレッチ:例えば、壁を使って腕を出して肩甲骨を軽く押す/脇腹を伸ばすなど、“こまめに伸ばす”習慣をつくるのがポイントです。
-
肩甲骨まわりのセルフチェック:例えば鏡で肩甲骨の内側縁が背中から浮いていないか・腕を上げた時に肩甲骨がスムーズに動いているか・肩がすくんでいないか、などを時々チェックすると「おっ、使えてないかも」と気づきやすいです。
-
姿勢改善:長時間のデスクワーク・スマホ操作で肩が前に入ると、前鋸筋が機能しづらくなりやすいと言われています。
-
症状がある場合の専門家相談:「肩甲骨が背中から異様に浮いてる」「腕を上げると肩がギクッとする」「肩甲骨の動きに“ガクッ”とクセを自分で感じる」など、日常動作で明らかに違和感が出ているなら、整形外科・理学療法士・専門トレーナー等に相談するタイミングとも言われています。
「ほんの少しの意識」で、前鋸筋は“支える筋肉”から“活躍する筋肉”に変えられる可能性があります。日常動作をちょっと変えて、スポーツ動作にもうひと伸び加えて、肩甲骨を味方につけましょう。
ハッシュタグ:
#前鋸筋活用
#肩甲骨安定習慣
#日常動作ケア
#スポーツ肩甲骨トレ
#姿勢改善習慣
ステップ木更津鍼灸治療の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。




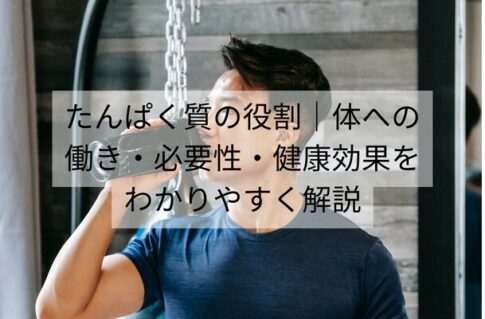



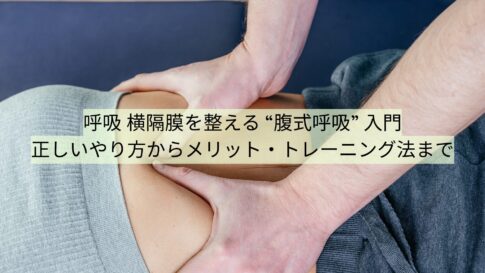
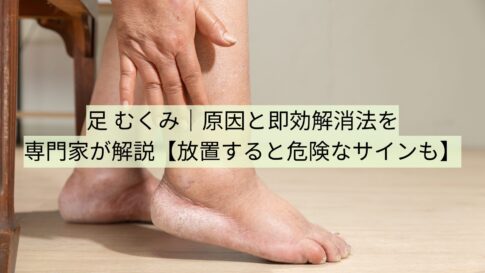
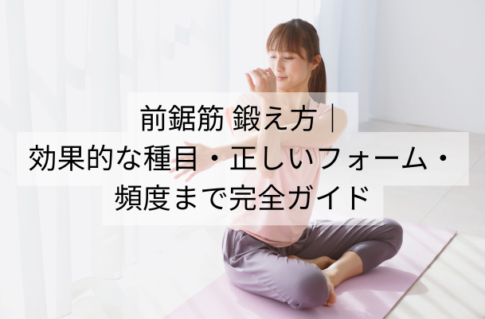

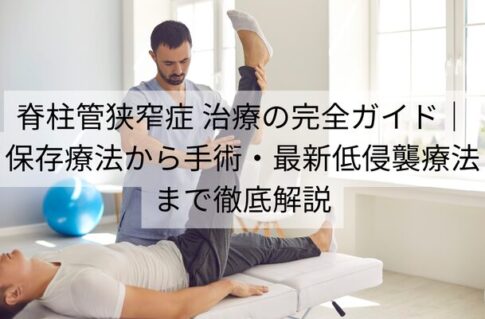
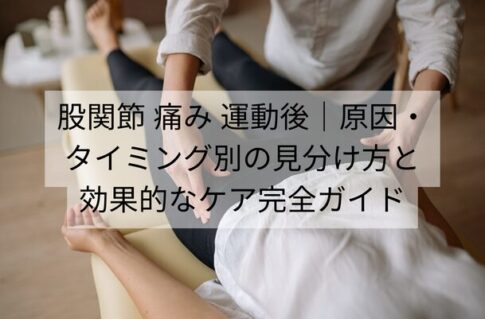
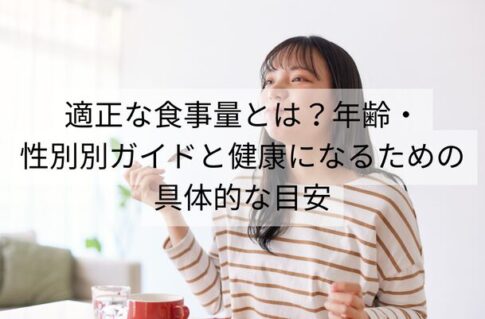
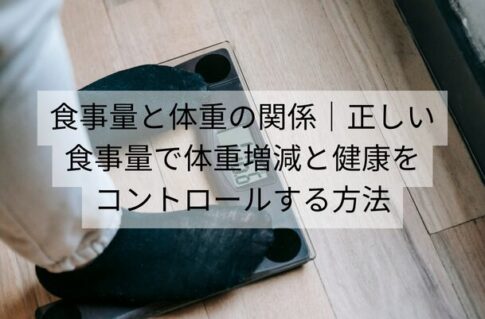
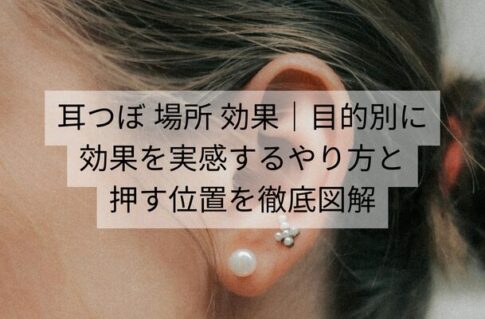




コメントを残す