
デスクワークでお尻が痛くなる仕組み・原因
「デスクワークをしていると、だんだんお尻が痛くなってくるんだけど…なんでだろう?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
実は、お尻の痛みにはいくつかの代表的な原因があり、それぞれに対策の方向性が少しずつ違うと言われています。ここでは、その主な要因をわかりやすく解説します。
長時間座ることによる血流の悪化と圧迫
まず一番多いのが「座りっぱなし」による血行不良です。
長時間、同じ姿勢で座っていると、お尻の筋肉や血管が圧迫され、血液の流れが滞りやすくなると言われています。その結果、じんわりとした重だるさや、鈍い痛みが出てくることがあります。「ずっと座っていて立ち上がるときにズキッとする」というのも、よくあるパターンです。
お尻・股関節まわりの筋肉の硬さ
座り姿勢が続くと、大臀筋・中臀筋・梨状筋など、お尻や股関節を支える筋肉が硬くなりやすいとされています。筋肉がこわばると、骨盤や背骨を支えるバランスが崩れ、ちょっとした動作でも違和感が出やすくなります。特に梨状筋は、坐骨神経の近くを通っているため、硬くなると神経を圧迫し、痛みやしびれを感じることもあるようです(引用元:https://stretchex.jp/5126)。
骨盤・姿勢のゆがみや傾き
「片方の足を組むクセ」や「背もたれに寄りかかりすぎる姿勢」は、骨盤や背骨を少しずつゆがませる原因になると考えられています。その状態が続くと、お尻の一部分に体重が集中して圧迫が強くなり、左右差のある痛みにつながることがあります。また、姿勢が前のめりになる人は、太ももの裏側や坐骨部に負担がかかりやすい傾向があるとも言われています。
既往症・神経圧迫の影響
坐骨神経痛や椎間板ヘルニアなど、既往症が背景にあるケースも少なくありません。デスクワークが長くなると、これらの症状が悪化しやすいとされており、片側のお尻や太もも、ふくらはぎまでしびれが出ることもあります。軽い違和感だからと放置せず、症状が続く場合は早めに専門機関に相談することが大切だとされています。
座面・椅子の問題
意外と見落とされがちなのが「椅子そのもの」の問題です。
硬すぎる・柔らかすぎる・高さが合っていないなど、座面が体に合っていないと、特定の部位だけに圧力が集中します。特に、坐骨の位置と椅子の形が合っていないと、数時間でジワジワと痛みが出てくることがあります。クッションや座布団で調整するだけでも負担が減る場合があると言われています。
まとめ
このように、お尻の痛みには複数の要素が関わっているケースが多く、単に「長く座っているから痛い」というだけではありません。自分の痛みの出方や生活習慣を振り返ることで、原因の手がかりが見つかることが少なくないと言われています。
#デスクワーク #お尻の痛み #骨盤のゆがみ #血行不良 #椅子選び
痛みの出方別チェックと対処の優先度
デスクワーク中のお尻の痛みは、人によって感じ方や出方が大きく異なると言われています。同じ「お尻の痛み」でも、その表現や状況によって対処法の優先度は変わってくるため、自分の症状を整理しておくことが大切です。
「ズキン」「チクチク」「重だるい」「しびれ感」などの表現パターン
痛みの種類を言葉にしてみると、自分の状態を理解しやすくなります。例えば、瞬間的に「ズキン」と走る鋭い痛みは神経や筋肉への急な負担が背景にあると考えられています。一方で「チクチク」と針で刺すような違和感は、血流の悪化や軽い神経圧迫が要因になることもあるそうです。
また「重だるい」と表現される痛みは、長時間座り続けて筋肉が硬直しているサインとされるケースが多いです。さらに「しびれ感」を伴う場合は、坐骨神経に関連した症状と結びつくことがあると報告されています(引用元:https://stretchex.jp/5126)。
左右差や片側だけに痛みが出るケース
お尻全体ではなく、片側だけが痛いケースも少なくありません。右だけ、あるいは左だけに痛みが集中する場合、骨盤の傾きや座る姿勢のクセが影響していると考えられています。例えば、脚を組む習慣や片方に体重をかけて座る癖がある人は、特定の筋肉に負担が集中しやすい傾向があるそうです。
また片側にだけしびれが広がるときは、坐骨神経や腰椎の影響を疑う見方もあります。こうした「左右差」は痛みの原因を見極める上で重要な手がかりになると言われています。
医療機関の来院を検討すべきサイン
「ただの疲れかな」と思って放置してしまう方も多いですが、以下のようなサインがある場合は専門機関に相談することがすすめられています。
-
痛みが強くて座っていられない
-
数日~数週間たっても改善の兆しがない
-
しびれが足先まで広がる
-
夜眠れないほど痛みが続く
これらは一時的な疲労ではなく、神経や腰椎などに関連する可能性があるため、早めに相談した方が安心だとされています(引用元:https://jp-hc.com/blog/hip-pain1703/)。
まとめ
お尻の痛みは「どんなふうに痛いのか」「左右差があるのか」を丁寧に確認することで、適切な対処法や受けるべきサポートが見えてきます。自分の体から出ているサインを見逃さず、状況に応じてケアや相談を進めていくことが重要だと言われています。
#デスクワーク
#お尻の痛み
#しびれ感
#片側の痛み
#対処の優先度

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

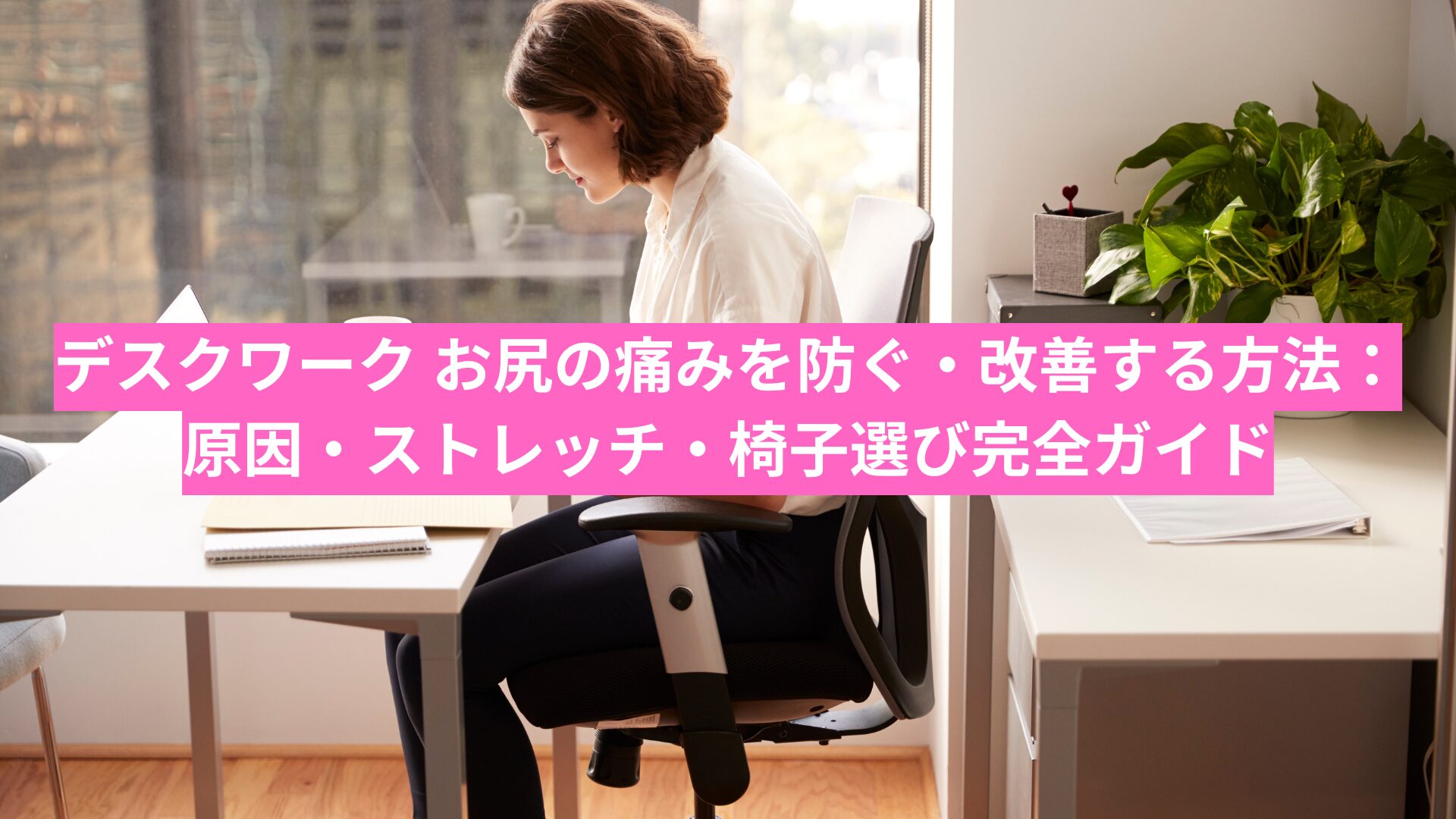





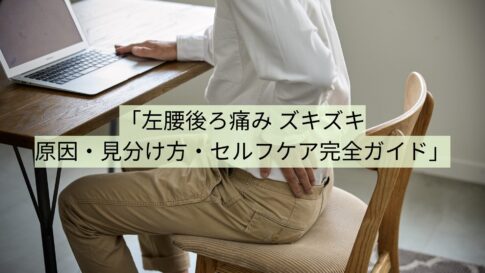
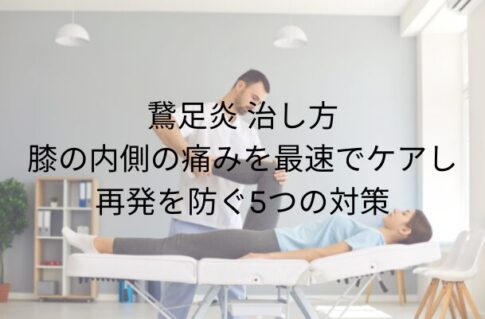
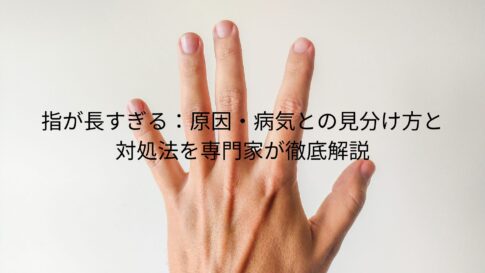

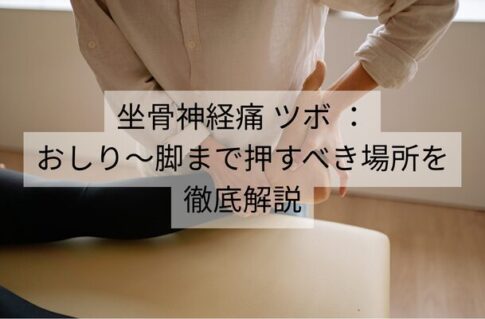
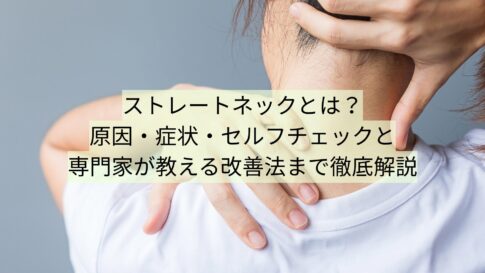













コメントを残す