1.慢性炎症とは

「慢性炎症」とは、体の中で炎症反応が長期にわたって続いている状態を指すと言われています。通常、体は何か異常が起きたときに炎症を起こして修復を図るのですが、炎症がしっかり終わらず“くすぶり続ける”ケースがあります。これはつまり、炎症が完全には鎮静せず、長期間にわたり体のさまざまな部分で影響を及ぼす状態です。 hatchobori.jp
急性炎症との違い
「急性炎症」は、怪我や細菌・ウイルスなどの侵入に対して、体が素早く反応して「発赤・腫脹・熱感・疼痛(痛み)」といった典型的な4つの徴候を示し、その後治癒に向かうものです。 hatchobori.jp
一方、「慢性炎症」は、こうした明らかな炎症のサイン(腫れ・熱・赤みなど)が目立たない場合が多く、症状が自覚しづらいゆえに放置されがちだと言われています。 hatchobori.jp
また、急性炎症が通常24時間~数日で収まり修復に至るのに対して、慢性炎症は数週間~数ヶ月、あるいはさらに長期間に及ぶことがあります。 マイナビコメディカル
なぜ「気づかれにくい」か
なぜ“気づかれにくい”かと言うと、慢性炎症では明確な局所症状が少ないからです。腫れや発赤がほとんど目立たず、痛みも軽かったり、繰り返しの倦怠感や軽い頭痛など“なんとなく不調”という形で現れることがあります。 stretchex.jp
そのため、「いつもより疲れやすいかな」「なんとなく体調が優れないな」という違和感があっても、炎症と結びつけずに見過ごされてしまうケースが少なくありません。さらに、血液検査や体調のチェックで異常が“明確に出る”まで進行してしまうこともあります。 stretchex.jp
この“静かに進行する”性質が、慢性炎症が「サイレント・キラー(静かな殺し屋)」と呼ばれることもある理由です。 hatchobori.jp
体内で何が起こっているのか(免疫反応・サイトカイン・組織変化等)
体内で慢性炎症が起きると、まず免疫システムが長期にわたって活発化します。本来、侵入してきた病原体や損傷組織を白血球などが除去し修復する「急性反応」が起こりますが、それが終わらず持続すると、マクロファージやリンパ球などの単核細胞が集まり、さらに新生血管の増生や線維化(組織が硬くなる変化)がみられるようになると言われています。 マイナビコメディカル
また、炎症性サイトカイン(例:TNF-α、IL-6、IL-1など)が血流に乗って全身を巡り、“局所だけ”でなく“全身的な”炎症反応を惹き起こす可能性があるとされています。 hatchobori.jp
さらにこのような持続的な炎症反応の中では、修復と炎症が繰り返されることで「組織リモデリング」と呼ばれる構造変化が起こり、元の柔軟な組織が硬くなったり、臓器の機能が低下したりする状況が生じ得ると説明されています。 hatchobori.jp
こうした流れを理解すると、なぜ“気づきにくい小さな炎症”が、長期的に見れば生活習慣病や老化、さまざまな慢性疾患の背景にあると考えられているのかが、なんとなく腑に落ちるかと思います。
#慢性炎症
#炎症対策
#健康習慣
#生活習慣病予防
#体の不調改善
2.慢性炎症がもたらす体への影響
疾患との関連:生活習慣病、がん、認知症など
「慢性炎症」という言葉を耳にしたとき、「ただの疲れやすさかな」と軽く考えてしまう人も少なくないでしょう。しかし、実はこの状態が放置されると、さまざまな重大な疾患との関連が指摘されていると言われています。例えば、血管の壁に炎症が慢性的に続くと、動脈硬化を進めて〈心筋梗塞〉や〈脳卒中〉のリスクが高まる傾向があるという報告があります。
また、最近の研究では「慢性炎症」が〈がん〉の発生や〈アルツハイマー型認知症〉などの神経変性疾患にも影響を与えている可能性があると言われています。
たとえば、「炎症性サイトカイン」という体内の炎症反応を促す物質が、長期間高く維持されると、細胞の修復機能が追いつかず、結果的に細胞レベルでの“傷の積み重ね”が生じるという仮説もあります。こうした背景から、私たちの日々の生活習慣が“慢性炎症を起こしやすい状態”をつくってしまっているとも考えられています。
ですから、ただ「なんとなく疲れた」「肌が荒れやすくなった」などの症状を流してしまうと、いずれ大きな病気とつながる“火種”を抱えている可能性がある――そんな視点が、慢性炎症の影響を考えるうえで重要だと言われています。
自覚しにくい症状・サイン(倦怠感、肌荒れ、集中力低下など)
では、「体に重大な影響がある」と言われても、自分では気づきにくいものなのがやっかいなところです。実際、慢性炎症は激しい痛みや明確な発熱といった“わかりやすいサイン”を伴わないことが多く、「なんとなくだるい」「眠りが浅い」「肌に艶がない」「集中力が続かない」といった漠然とした不調として現れるケースが少なくありません。
例えば、「毎朝起きても疲れが抜けない」「昼過ぎからすぐ眠気がくる」「顔色がくすんで、肌荒れも治りづらい」などがその例です。こうした自覚しづらい“くすぶる炎症”が、気づかぬうちに体の中に蓄積していく、というわけです。
さらに、一般的な血液検査や触診では異常と判断されないレベルで炎症が続いていると、「検査しても異常なし」と言われて安心してしまいがちですが、実はその背景に炎症が潜んでいるケースも報告されています。
このため、日々の小さな変化──「あれ、最近疲れが取れないな」「肌のハリが減ったな」「集中できていないかも」──といったサインを無視せず、体に目を向けることが“慢性炎症”への早めの視点につながると言われています。
#慢性炎症の影響
#生活習慣病リスク
#がん予防
#認知症対策
#体のサインに気づく
3.主な原因とリスクファクター

食事(加工食品・砂糖・トランス脂肪酸など)
「ねえ、最近なんとなく体が重いな…」って感じるとき、意外にもその背景に慢性炎症が潜んでいることがあると言われています。で、まず注目したいのが“食事”です。例えば、甘いお菓子や清涼飲料、そしてトランス脂肪酸や高度加工食品といったものを日常的に摂っている人は、炎症を起こしやすい食習慣を送っている可能性があると言われています。引用元:https://note.com/tkumashiro/n/ncac1766c0b0c
具体的には、「砂糖・ブドウ糖果糖液糖」「トランス脂肪酸」「超加工食品」「加工肉」などが、炎症のきっかけになりやすいと考えられています。引用元:https://note.com/tkumashiro/n/ncac1766c0b0c さらに、「糖質の過剰」「飽和脂肪・中性脂肪の偏り」「ビタミン・ミネラルの不足」などが、炎症を促進する条件になるとも指摘されています。
ですので、「食事=味わうだけ」ではなく、「炎症リスクを高めていないか」も少し意識しておくことが、慢性炎症を遠ざける第一歩になると言われています。
生活習慣(運動不足・睡眠不足・ストレス)
次に、“生活習慣”も重要なリスクファクターです。例えば、ほとんど体を動かさない日が続いたり、睡眠時間が明らかに短かったり、あるいは強いストレスを抱えっぱなしだったり――こうした状態では、体の中で炎症を促すスイッチが入りやすいと言われています。引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/%E6%85%A2%E6%80%A7%E7%82%8E%E7%97%87/%E6%85%A2%E6%80%A7%E7%82%8E%E7%97%87%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E6%94%BE%E7%BD%AE%E3%81%8C%E6%8B%9B%E3%81%8F%E4%B8%8D%E8%AA%BF%E3%81%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%B3%95%E3%82%92%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A
具体的に言うと、運動不足は筋肉量の低下や代謝の悪化を招き、免疫や炎症のバランスを乱す可能性があります。睡眠が十分でなかったり、質が悪かったりすると、交感神経が優位な状態が続き、“炎症性サイトカイン”という炎症を起こす物質が増えるという報告もあると言われています。
また、慢性的なストレスも、体の“休むべき仕組み”をうまく回せなくし、結果的に炎症傾向になりやすいとされています。つまり、生活習慣を整えることが、炎症のリスクを低めるための現実的かつ重要な手段のひとつだと言えるわけです。
腸内環境・環境因子(化学物質・たばこなど)
最後に、“腸内環境”および“外部環境因子”も見逃せないファクターです。腸は免疫機能の大部分を担っており、腸内のバランスが崩れると、炎症の温床になりやすいと言われています。引用元:https://flora-health.jp/immune/gut-environment-and-health%E2%86%92-chronic-inflammation/
例えば、悪玉菌が優勢になったり、腸壁のバリア機能が低下したりすると、腸内の物質が血流に入り込み、体が“異物を排除しよう”と炎症反応を起こすきっかけになるとも考えられています。さらに、たばこ・大気汚染・化学物質といった環境因子も、体にとって“慢性的な小さな刺激”となり得て、炎症反応を内側でくすぶらせる原因になるという報告もあります。引用元:https://chokenko.com/about-intestinal-environment/understanding-the-relationship-between-gut-microbiota-and-inflammation/
こうした背景を理解すると、「なんで自分だけ不調が続くんだろう…」という人ほど、意外なところに原因が潜んでいる可能性が高いと言えそうですね。
#慢性炎症 #炎症リスク #食生活改善 #生活習慣見直し #腸内環境ケア
4.セルフチェック&検査指標
家でできる“なんとなく”のサイン:見逃しがちな体の変化
「最近、疲れが抜けないな」「肌の調子がいつもより悪いかも」と感じたこと、ありませんか?実はこれ、慢性炎症の“火種”になっている可能性があると言われています。例えば、毎朝起きてもスッキリしない、集中力が落ちてきた、なんとなく体が重い、肌がくすむ・荒れやすい――そんな“なんとなく”の変化こそが、体内でくすぶる炎症のサインかもしれません。
もちろん、こうした症状だけで明確に慢性炎症だと決めつけるわけではありませんが、こうした“なんとなく不調”が続くときには、「もしかしたら炎症が関係しているのでは?」という視点を持つことが重要だと言われています。
さらに、普段から健康診断で「特に異常なし」と言われていても、実は炎症がゆるやかに続いているケースも報告されているのです。引用元:https://hirakata777.hatenablog.com/entry/20250701/1751363579
ですから、家で感じる小さなサインを軽視せず、「疲れとれてないな」「肌がいつもより…」「ちょっと集中が続かないな」という体の声に耳を傾けることが、慢性炎症リスクを意識する第一歩だというわけです。
医療機関で見られる指標(例:hs-CRP、A/G比など)
「自分ではひどくないから大丈夫」と考えがちですが、実際には血液検査の数値に“わずかな変化”として炎症の気配が出ることがあります。例えば、hs‑CRP(高感度C反応性タンパク質)は、0.2 mg/dL以上で慢性炎症や心血管リスクを示唆されるという報告があります。また、A/G比(アルブミン/グロブリン比)も近年、慢性炎症の指標として注目されており、「アルブミンが下がり、グロブリンが上がる」ことで比率が変化し、炎症傾向を捉えやすいとも言われています。ただし、こうした数値だけで「慢性炎症だ」と判断するのは難しいともされており、複数回の検査・生活習慣との関連を含めて総合的に評価されると言われています。
ですので、「検査ではなんともない」と言われたとしても、数値の“かすかな変化”や自覚症状と検査結果を照らし合わせる姿勢が、慢性炎症を見逃さないコツだと言えるでしょう。
“まだ異常なし”と言われても注意すべきポイント
医療機関で健康診断を受けて「特に問題なし」と言われても安心しきってはならない、というのが慢性炎症の難しいところです。なぜなら、炎症がゆるやかに進む「低悪性度慢性炎症(inflammaging)」のような状態では、検査値が基準範囲内であっても炎症が存在し得ると報告されているからです。例えば、体重が少しずつ増えてきた、寝起きがやや悪い、冷えやすくなった――といった変化を「年のせい」「仕事が忙しいせい」で片づけてしまうと、気づかぬうちに炎症がじわりと進む可能性があります。
だからこそ、「数値が正常範囲なら安心」と自分に言い聞かせるのではなく、日常の“なんとなく”を無視せず、定期的な検査+生活習慣の見直しをセットに考えることが大切だと言われています。
また、検査結果を見たときも「変化が小さいから大丈夫」と流さず、過去の自分と比べて「数値がわずかに上がっていないか」「生活習慣で改善できることはないか」を意識してみることが、慢性炎症を早期に“感じる力”につながるでしょう。
#慢性炎症 #炎症マーカー #hsCRP #AG比 #健康セルフチェック
5.慢性炎症を抑える生活習慣と実践ポイント

抗炎症を促す食材・食事パターン(青魚、野菜・果物、オリーブオイルなど)
「最近、何を食べたらいいんだろう?」って思うこと、ありますよね。実は、日々の“食事”こそが、慢性炎症 を抑える大きなカギだと言われています。例えば、色鮮やかな野菜・果物、青魚(サバ・イワシ・マグロなど)、そしてエキストラバージンオリーブオイル。これらは、体の中の炎症反応を和らげる方向に働く可能性があるそうです。引用元:イーヘルスクリニック新宿院「健康長寿の敵「慢性炎症」とは?100歳以上の高齢者に学ぶ食事と生活習慣」イーヘルスクリニック新宿院 –
具体的には、「トマト、緑の葉野菜、オリーブオイル、ナッツ、青魚、果物(リンゴ・ベリー類)」などが“改善につながる食事”とされています。引用元:同上 イーヘルスクリニック新宿院 –
それに対して、精製された炭水化物、揚げ物、砂糖たっぷりの飲料、加工肉、マーガリンなどは、炎症を促進しやすい食事パターンとしても紹介されています。引用元:イーヘルスクリニック新宿院「無理なダイエットは不要?体重5%減で炎症を抑える驚きの研究」イーヘルスクリニック新宿院 –
「でも、全部変えるのは無理…」と思ったら、まずは「今日は青魚を1品増やしてみる」「スープにカラフルな野菜を入れてみる」など、少しずつ始めるのが現実的だと言われています。
適度な運動・ストレッチ・日常動作から始める方法
「運動って何をしたらいいの?」と迷う人も多いでしょう。ここで大事なのは“適度に”“続けやすく”取り入れること。例えば、日常でちょっと早歩きする、階段を使う、テレビを見ながらストレッチをする――こうした“体を少し動かす習慣”が、慢性炎症の軽減に関係していると言われています。引用元:さかぐち整骨院「慢性炎症とは?〜放置が招く不調と対策法〜」 中山博之行政書士事務所
また、筋肉が減る・代謝が落ちる状態は炎症を起こしやすくする要素にもなるため、筋トレも軽く取り入れることが推奨される場合があります。引用元:同上 中山博之行政書士事務所
ポイントは「無理しない」「習慣に組み込む」ことです。例えば「朝起きたら5分だけストレッチ」「通勤時は駅二つ分歩く」という感じで、日常の動作に“運動のスイッチ”を忍ばせることで、継続しやすくなると言われています。
睡眠・ストレスマネジメント・社会的つながりの重要性
「寝不足だと何となく調子悪いな」と感じた経験、ありますよね。実は、十分な睡眠・ストレスの少ない生活・そして人とのつながりも、慢性炎症を抑える習慣のひとつだと言われています。引用元:イーヘルスクリニック新宿院「健康長寿の敵「慢性炎症」とは?100歳以上の高齢者に学ぶ食事と生活習慣」 イーヘルスクリニック新宿院 –
例えば、社会的な役割を持っている高齢者には、野菜中心の食事だけでなく「8時間以上の睡眠」「地域・家族・友人とのつながり」が共通点として挙げられており、これらが炎症レベルを低く保つ条件になっていたと言われています。引用元:同上 イーヘルスクリニック新宿院 –
ストレスが続くと、交感神経が優位になったり、睡眠の質が落ちたりして、炎症物質の分泌が増えると言われています。引用元: Hiroki
したがって、「今日は少し早めにベッドに入ろう」「スマホから離れる時間を作ろう」「友人にメッセージを送ろう」というような“ちょっとした行動”が、炎症を抑える日常の習慣として機能する可能性があります。
継続のコツ・習慣化のヒント(すぐできるステップ)
習慣化が苦手な人向けに、“すぐ始められる”ステップをご紹介します。
-
毎日の食事で「色の濃い野菜を1品+果物を1つ」追加してみる
-
通勤・家事・移動で「1日1000歩だけ多く歩く」よう意識してみる
-
夜22時〜23時にはスマホを手放し、ベッドに入る前に深呼吸2回だけする
-
友人・家族・近隣の人と週1回「雑談10分」や「散歩15分」など、交流の時間を設ける
こうした“小さな変化”を、まずは1週間続けてみて、「できた」「気持ち良かった」体験を蓄積することが、習慣化のポイントだと言われています。引用元:turn0search0
大きな変化を一気に目指すのではなく、「毎日10%良くする」くらいのペースで進めることで、無理なく続けられると言われています。
ケーススタディ・実践例(簡単なチェックリスト付き)
実際に「慢性炎症を抑える生活習慣」を取り入れた人の例です。
チェックリスト(1週間)
-
青魚(サバ・イワシ・鮭)を1回食べた
-
緑の葉野菜+果物を毎日1品以上摂った
-
通勤や移動で階段を使ったり、早歩きしたりした日が3日以上あった
-
夜22時にはスマホを手放し、深呼吸を2回した日が4日以上あった
-
友人や家族と“雑談・軽い運動・散歩”など交流した日が2日以上あった
このような実践を“継続する”ことで、炎症を抑える暮らしに近づく可能性が高いと言われています。引用元:turn0search6
もし、1週間終わった時「3つ以上できた!」というなら、次の週に「1歩レベルを上げる」形で継続するのがおすすめです。
#抗炎症生活
#健康的な習慣
#食事改善
#ストレスケア
#慢性炎症予防
ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。







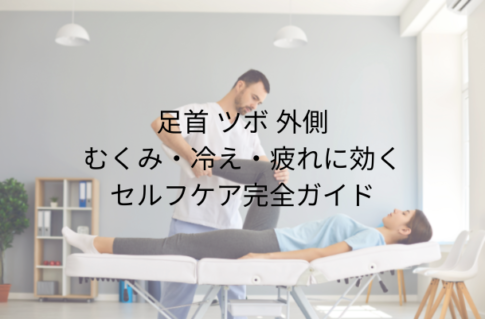
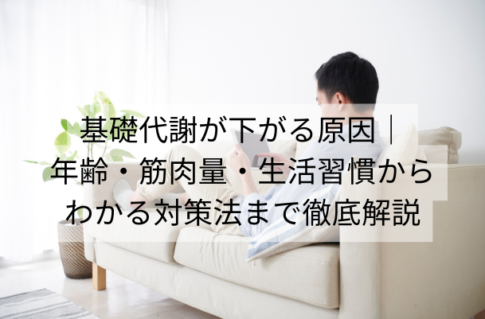

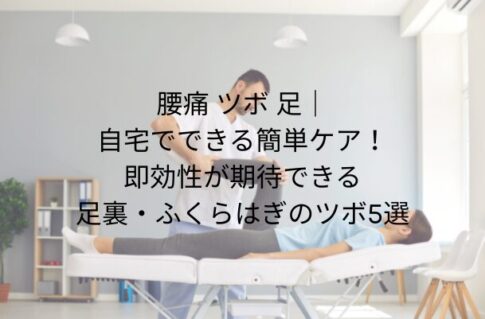

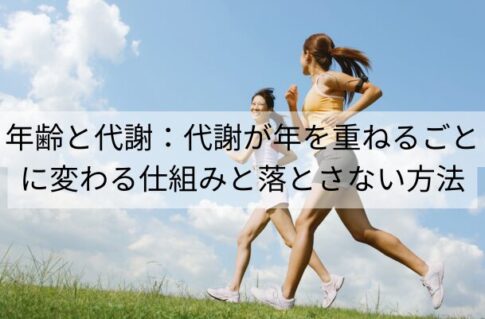
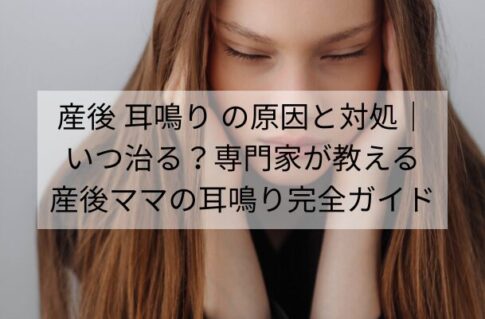
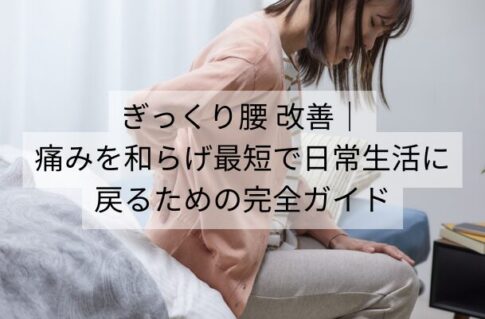
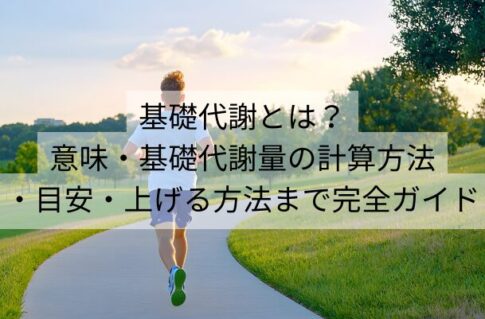




コメントを残す