1.肩甲挙筋とは?位置・役割・こりやすい原因を解説

筋肉の場所と役割
「肩甲挙筋ってどこにあるの?」と聞かれることがありますが、首の横から肩甲骨の上部につながる細長い筋肉のことを指すと言われています(引用元:https://stretchex.jp/5827)。肩甲骨を引き上げる働きがあるとされていて、首をひねったり肩をすくめたりするときに使われるそうです。日常生活でも意外と使用頻度が高い筋肉だと考えられています。
肩こり・首こりに関係する理由
この筋肉は首の後ろ側に近い位置にあるため、血流の低下や緊張が続くと首こりや肩こりにつながると言われています。「肩甲挙筋が固まると頭痛が出ることもあるって本当?」と心配される方もいますが、周囲の筋肉と連動しているので、張りやすい環境がそろうと不快感が広がるケースもあるとされています。特に同じ姿勢が続くと疲労がたまりやすいようです。
デスクワーク・スマホ姿勢との関係
「パソコンやスマホを触っていると肩が重くなる…」こんな経験はありませんか?前かがみの姿勢になると頭を支えるために肩甲挙筋に負担がかかると言われています。さらに、画面を見る時間が長くなると首が前に出るクセが定着しやすく、その状態が習慣化すると筋肉が緊張しっぱなしになりやすいそうです。座りっぱなしの仕事や家事の合間でも、肩まわりが固くなるのはこの筋肉が関係していると考えられています。
「気付いたら肩がガチガチなんだけど…」と感じる人は、無意識に力が入っている可能性もあります。こりが強くなる前に意識的に伸ばしたり、姿勢を変えたりすることで負担を減らせると言われています。
#肩甲挙筋とは
#肩こりの原因
#デスクワーク対策
#首こりと姿勢
#スマホ首ケア
2.肩甲挙筋がこると起こる症状
肩・首の痛み、可動域の制限
肩甲挙筋がこり固まると、まず感じやすいのが肩や首の痛みだと言われています。普段は意識しない小さな動きでも、筋肉が硬くなるとスムーズに動かせなくなることがあるそうです。たとえば首を左右に回そうとしたときに「ちょっと動かしづらいな」と感じるのは、筋肉の緊張が原因のひとつだと考えられています。さらに、可動域が狭まると姿勢もぎこちなくなり、他の筋肉に負担がかかるケースもあるとされています(引用元:https://stretchex.jp/5827)。
頭痛・姿勢の崩れ・自律神経への影響
肩甲挙筋のこりは、首周りの血流や神経に影響を与える可能性があると指摘されています。その結果、肩や首だけでなく頭痛として感じる人も少なくないようです。「デスクワークをしていたら急に頭が重い」といった感覚は、筋肉の緊張と関係していると言われています。さらに、筋肉のこわばりは姿勢を崩しやすく、猫背やストレートネックを招きやすいとの報告もあります。慢性的な緊張が続くと、自律神経のバランスにまで影響を及ぼすケースもあるとされています。
放置すると悪化するケース
「そのうち良くなるかな」と放置してしまう人もいますが、肩甲挙筋のこりは自然に和らがないこともあると言われています。固まった筋肉は他の部位まで負担を広げ、慢性的な肩こりや首こりにつながる可能性があると考えられています。さらに、可動域が狭くなると運動不足になり、悪循環が起きやすいそうです。早めのセルフケアや姿勢改善を取り入れることで、症状の悪化を防ぎやすいとされています。
#肩甲挙筋のこり
#首こりと肩こり
#頭痛の原因
#姿勢の崩れ
#放置は悪化のもと
3.自宅でできる肩甲挙筋マッサージのやり方

手で行うセルフマッサージ手順
肩甲挙筋をほぐす方法として、手を使ったセルフマッサージがよく紹介されています。やり方はシンプルで、片方の手を反対側の首から肩甲骨にかけて置き、親指や指先で硬さを感じる部分を探します。そのまま円を描くように軽く押しながらほぐすと、血流が促されやすいと言われています。力を入れすぎると逆に筋肉が緊張してしまうこともあるため、「痛気持ちいい」程度が目安になるそうです。肩の力を抜いて行うと、首まわりのストレッチ効果も得られるとされています(引用元:https://stretchex.jp/5827)。
テニスボール・フォームローラー活用法
「手で届きにくいところはどうしたらいいの?」という声もあります。そんな時に便利なのがテニスボールやフォームローラーです。壁と肩甲骨の間にボールをはさみ、体重をかけながらゆっくり上下に動かすと、ピンポイントで刺激できると言われています。床に寝転んで行うのも効果的とされていますが、慣れないうちは強い圧になりやすいので注意が必要です。フォームローラーの場合は肩甲骨の下に敷き、呼吸を合わせながら背中を転がすと、首から肩まで広い範囲をほぐせるとされています。
効果を高めるタイミングと圧のかけ方
マッサージのタイミングは体が温まっているときが良いと言われています。特に入浴後は血行が良くなっているため、筋肉が柔らかくなりほぐしやすいそうです。また、押す強さは「もう少し押されたいな」と感じる程度にとどめることが推奨されています。痛みを我慢して強く押すと逆効果になるケースもあるとされているため注意が必要です。呼吸をゆっくり整えながら行うとリラックス効果が高まり、筋肉の緊張も和らぎやすいと言われています。
#肩甲挙筋マッサージ
#セルフケア
#テニスボール活用
#フォームローラーケア
#効果的なタイミング
4.肩甲挙筋をほぐすストレッチ・エクササイズ
壁を使ったストレッチ
壁を使ったストレッチは、肩甲挙筋を狙いやすい方法として紹介されることが多いと言われています。やり方としては、まず壁に向かって立ち、両手を肩の高さに合わせてつきます。そこから上体を少し前に倒し、首を反対側に傾けると、肩から首にかけて心地よい伸びを感じやすくなるそうです。強く伸ばすのではなく、呼吸に合わせてじんわり伸ばすのがポイントとされています。特にデスクワークの合間など、固まりやすいタイミングで取り入れると緊張を和らげやすいと言われています(引用元:https://stretchex.jp/5827)。
座ったままできる簡単ストレッチ
「仕事中や家でも気軽にできる方法はない?」と聞かれることがあります。そんなときに便利なのが椅子に座ったままできるストレッチです。片手を背中側に回し、反対の手で頭を軽く斜め前に引くと、肩甲挙筋のラインが伸ばしやすいと言われています。目線をおへそ方向に向けると、首すじから肩甲骨にかけて伸びやすくなるそうです。無理のない範囲で10〜20秒ほどキープするとリラックスしやすく、深い呼吸を意識することで副交感神経も働きやすくなるとされています。
肩甲骨はがしとの組み合わせ
肩甲挙筋は肩甲骨に付着しているため、肩甲骨まわりを一緒に動かすと効率が良いと言われています。いわゆる「肩甲骨はがし」と呼ばれる動きでは、肩を前後に大きく回したり、両肘を引き寄せる動作が取り入れられることが多いそうです。壁や床を使うストレッチと組み合わせることで、深層の筋肉まで緩みやすくなるとされています。こりが強い人は、まず軽く肩を回してからストレッチに入ると負担を減らせると言われています。
#肩甲挙筋ストレッチ
#壁ストレッチ
#座ってできるケア
#肩甲骨はがし
#首肩リラックス
5.マッサージ効果を高める習慣・注意点

温めるタイミング・入浴との相性
「マッサージっていつやるといいの?」と聞かれることがありますが、体が温まっているタイミングが適していると言われています。特に入浴後は血流が良くなっていて、肩甲挙筋も緩みやすいそうです。お風呂でしっかり温めてから首や肩をほぐすと、負担をかけずに筋肉にアプローチできるとされています。逆に体が冷えた状態だと、筋肉がこわばって圧が入りづらくなるとの声もあります。お風呂上がりにタオルで軽く首を包んで温めながらマッサージする方法も紹介されているようです(引用元:https://stretchex.jp/5827)。
姿勢改善・デスク環境の見直し
「ほぐしてもすぐ戻る…」と感じる人は、姿勢の影響が大きいと言われています。肩甲挙筋は頭の重さを支える位置にあるため、長時間の前かがみ姿勢や猫背になりやすい環境だと、常に緊張が続くことになるそうです。デスクワークの場合、モニターの位置を目線の高さに合わせたり、肘や腰が安定する椅子を選んだりするだけでも負担を軽くしやすいと言われています。スマホを見るときは、画面を持ち上げて首を前に出しすぎないように意識すると良いとされています。
やってはいけないNG行動
肩甲挙筋のケアで気をつけたいのが、強く押しすぎたり、痛みを我慢して続けてしまうことです。無理に力を加えると筋肉がさらに緊張してしまうケースもあると言われています。また、長時間の同じ姿勢や、首を急に回す動作も負担になるとされています。寝転びながらスマホを見たり、肘をついた姿勢を続けたりするのも避けたほうが良いとされています。ストレッチやマッサージをしても違和感が強く残る場合は、専門家への相談を検討する人もいるそうです。
#マッサージ習慣
#入浴後ケア
#姿勢改善ポイント
#デスク環境見直し
#NG行動に注意
ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。




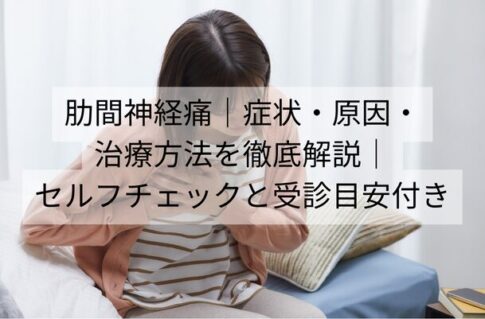



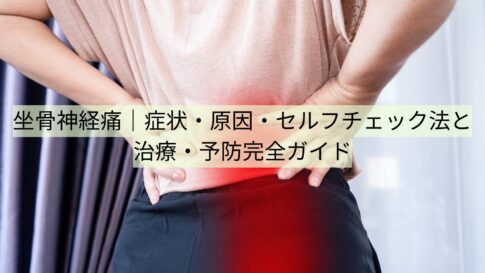


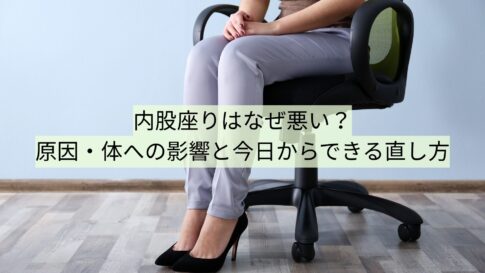









コメントを残す