
肩の付け根がズキズキ痛む:20代で起こる理由
20代にも起こるメカニズム(姿勢・筋疲労・習慣)
「肩の付け根がズキズキするなんて、まだ若いのに?」と驚く方も少なくありません。実際には、20代でも肩の付け根に痛みを感じるケースはよくあると言われています。大きな要因として、デスクワークやスマホ操作など、日常の姿勢や繰り返される動作が関係していると考えられています。例えば、長時間のパソコン作業では肩周りの筋肉が硬直しやすく、その負担が積み重なることで痛みへとつながることがあるそうです。
また、運動後の筋肉疲労や、同じ姿勢を続ける生活習慣もリスク要因になると言われています。特に20代は仕事や学業で不規則な生活になりがちで、体のケアを後回しにしやすい傾向があります。そのため、筋肉のバランスが崩れ、肩の付け根に違和感が出やすくなるとも考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4211/)。
痛みの性質(ズキズキ・夜間痛・動作時痛など)
「ズキズキする」という表現は、炎症や筋肉への負担が背景にある場合が多いとされています。安静にしていても痛む夜間痛や、腕を上げたときだけ強く出る動作時痛など、痛みの出方にはパターンがあると言われています。夜寝ている時に痛みで目が覚めてしまう場合や、片方の肩だけに集中する痛みなどは、体の使い方や炎症の程度が関わっている可能性があるそうです。
こうした痛みの特徴を把握することで、自分の体の状態を知る手がかりになると言われています。無理に放置せず、セルフケアや専門家への相談を早めに考えることが、改善への第一歩になると考えられています(引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_orthopedics/sy0983/)。
若年ならではの背景(スマホ・PC・運動習慣)
20代に特有の背景として、スマホやPCの長時間利用が挙げられます。下を向いた姿勢を続けると首から肩にかけての筋肉に負担がかかりやすく、それが肩の付け根の痛みに反映されると考えられています。また、運動不足や逆に激しいスポーツでの使い過ぎも影響するケースがあります。
「まだ若いから大丈夫」と思い込みやすい年代ですが、日常のちょっとした習慣が痛みのきっかけになることは少なくないと言われています。スマホの持ち方を工夫する、作業の合間にストレッチを取り入れるといった小さな心がけが、将来的な肩の負担を減らすヒントになるかもしれません(引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/五十肩撃退ブログ/shoulder-tukene-pain)。
#肩の付け根の痛み
#20代の体ケア
#ズキズキ痛み対策
#スマホ肩予防
#デスクワーク疲労


皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

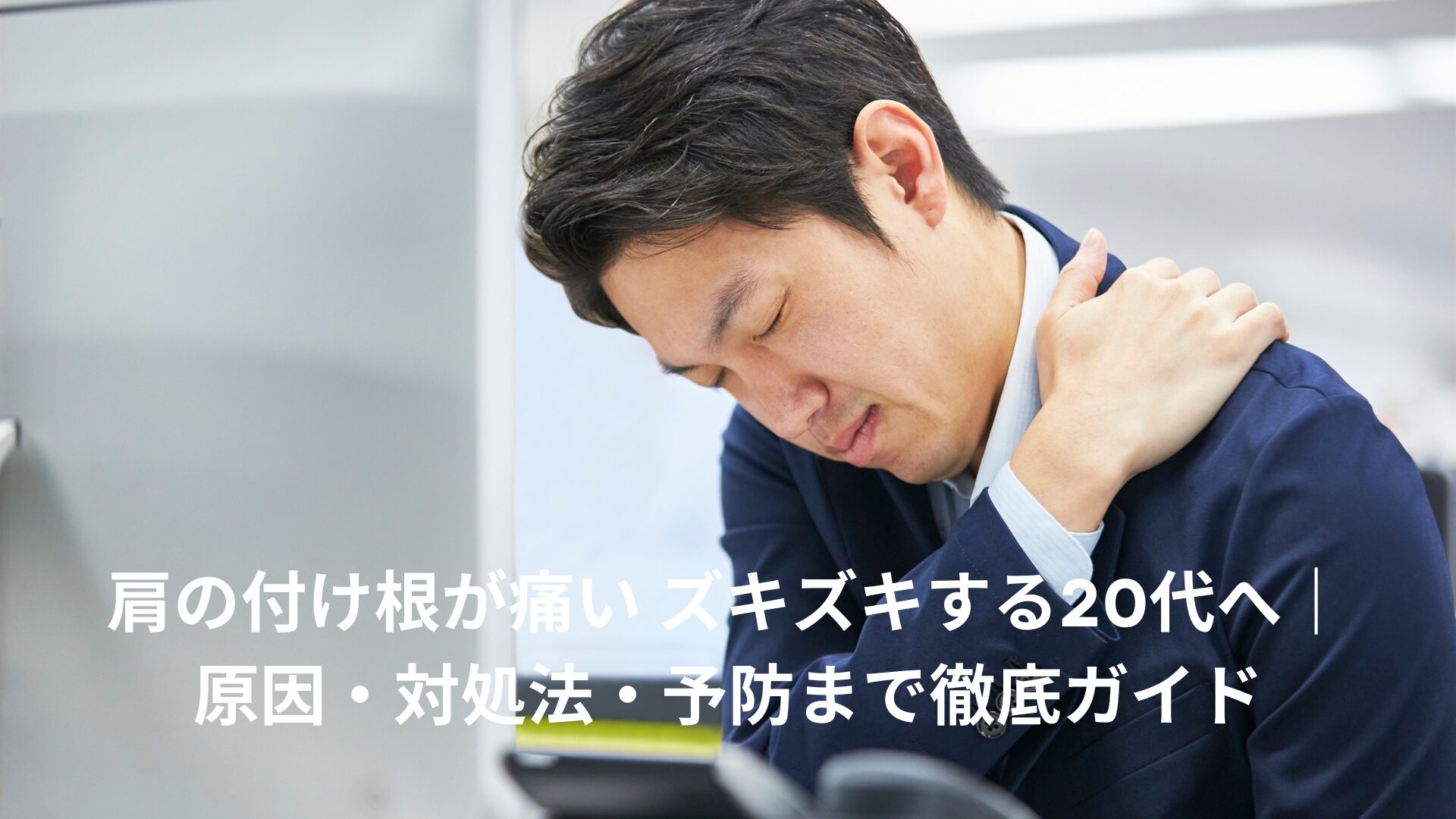



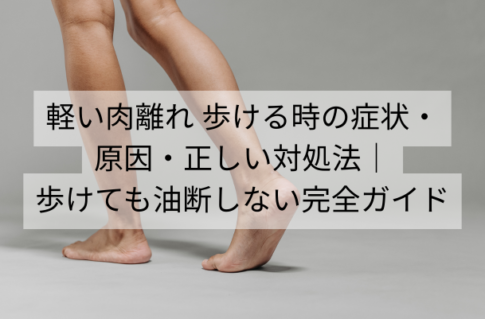
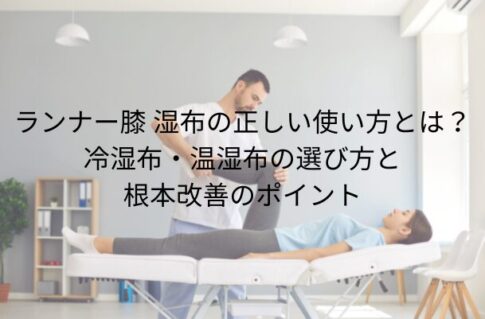

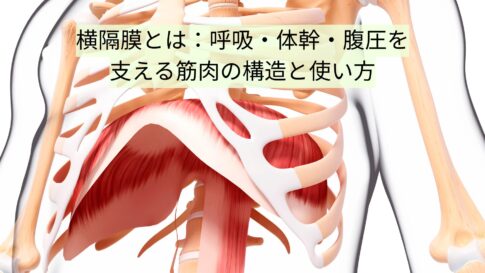
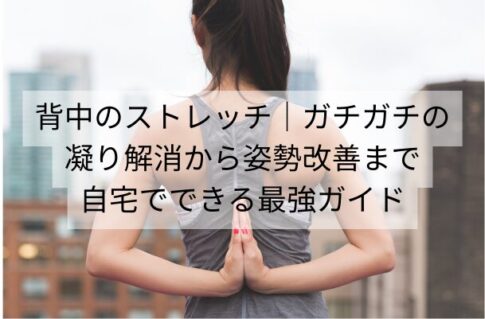
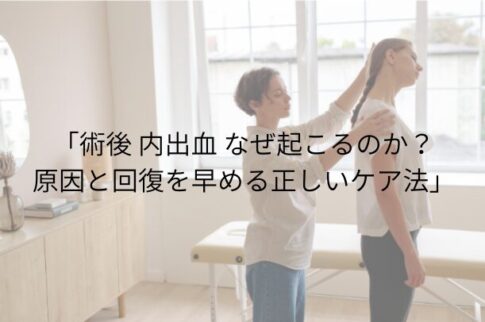














コメントを残す