4.専門治療の目安と内容
どんなときに来院を考えるべきか
鵞足炎は多くの場合、安静やストレッチ、セルフケアで改善していくことが多いと言われています。しかし、痛みが長引く場合や、歩行や階段の上り下りなど日常生活に支障が出るほど強くなった場合は、整形外科や整骨院への来院がすすめられています。特に「1〜2週間以上セルフケアを続けても改善が見られないとき」「夜間も痛みで眠れないとき」「膝に腫れや熱感が強いとき」などは、専門的な検査や施術が必要と考えられています(引用元:ライオンハート整骨院、マイナビコメディカル、武庫之荘駅前整骨院サキュレ)。
専門的な検査・施術の内容
来院すると、まずは膝の触診を中心に痛みの部位や可動域を確認することが多いと言われています。必要に応じてX線や超音波検査を行い、関節や腱に異常がないかを詳しく調べることもあるようです。そのうえで、症状の程度に合わせて施術内容が提案されます。
整形外科では、消炎鎮痛のための温熱療法や電気療法が取り入れられることがあります。さらに炎症が強いケースでは注射を使った対応が検討される場合もあると報告されています。一方、整骨院では鍼や手技による施術、筋膜リリースやテーピングなどが用いられることもあり、膝周辺の柔軟性を高めて再発を予防するアプローチがとられると言われています。
また、生活指導として姿勢や歩き方の改善をアドバイスされることも少なくありません。靴の選び方や日常動作の工夫など、セルフケアと併用することで回復をサポートする方法が取り入れられるとされています。
専門的な施術を受けるかどうかの判断は「日常生活への影響度」と「セルフケアでの改善度合い」が大きな目安になると言われています。無理に我慢を続けると慢性化のリスクがあるため、適切なタイミングで専門家の力を借りることが大切だと考えられています。
#鵞足炎
#膝の痛み
#専門治療
#整形外科
#整骨院

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

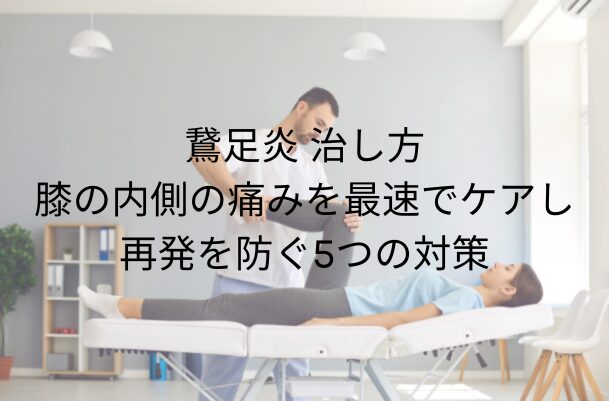



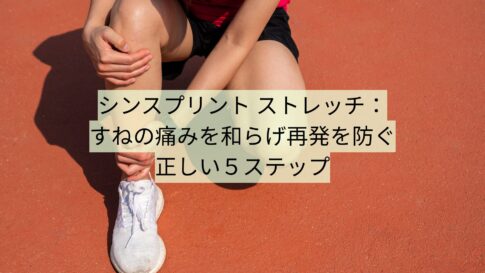
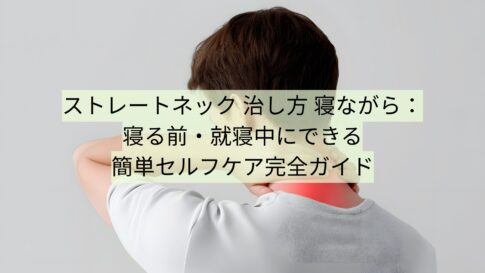

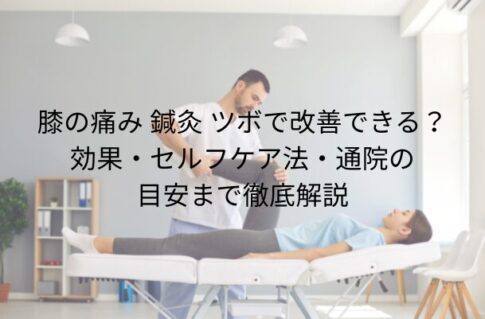
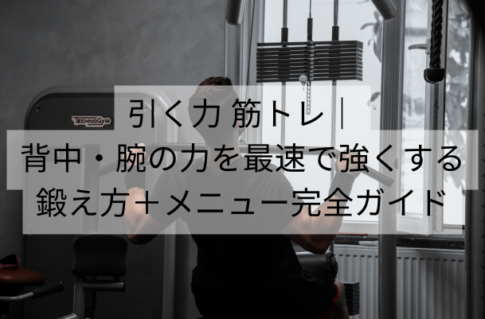
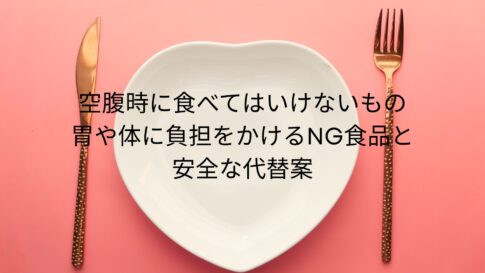
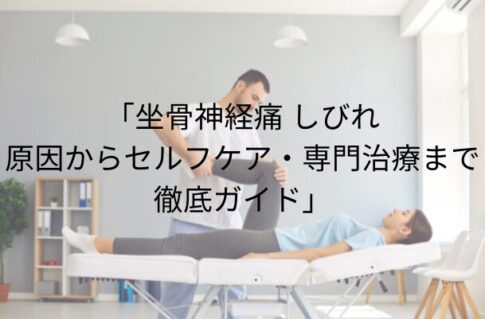











コメントを残す