1.内股座りとは?(アヒル座り/ぺたんこ座りとの違いも整理)
内股座りの姿勢を言語化
「内股座りって、どんな座り方のこと?」と聞かれたら、ざっくり言うと“膝を外に開いて、足先が体の内側に入る座り方”のことです。床にぺたんとお尻をつけ、左右の足が体の横に折れ曲がってWっぽく見えるので、W座りとも呼ばれます。本人はラクに感じやすい一方、股関節が内側にねじれやすい姿勢だと言われています。
呼び名の整理(アヒル座り・女の子座り・ぺたんこ座り)
呼び方はいろいろありますが、検索上はほぼ同じ姿勢を指すケースが多いです。「アヒル座り」「女の子座り」「ぺたんこ座り」などの名前は、足が外に流れてお尻がぺたっと床につく見た目から来ていると言われています。なので記事内では“内股座り=これらの別名”としてまとめておくと、読者の混乱が減りますよ。
起こりやすい年齢・タイプ
「なんで子どもがよくやるの?」というと、体幹の筋力がまだ育ち途中だと、背すじを立てる座り方より内股座りのほうが安定してラクだから、という見方があるようです。特に幼児期は股関節の柔らかさや骨の向きの個人差も大きく、自然にこの姿勢を選ぶ子もいると言われています。
一方、大人でも見られます。たとえば、股関節の内側が動きやすい人や、運動量が少なく外側の筋が使われにくい生活が続く人は、無意識に内股座りになりやすい傾向があるようです。女性に多いと言われるのも、骨盤まわりや関節の柔軟性の影響を受けやすいから、という説明がされています。
ただ「いつも内股座り=必ず問題」という話ではなく、痛みが出たり片側だけ極端だったりする場合は、体のクセとして一度チェックしてもらうと安心だと思います。
引用元: ひばりヶ丘にっこり整骨院
引用元:https://ashi-clinic.jp/cns/0005/
引用元:https://www.krm0730.net/blog/3089/
#内股座り #アヒル座り #ぺたんこ座り #子どもの姿勢 #座り方のクセ
2.内股座りのデメリット・体への影響(放置リスクを具体化)
骨盤・股関節のねじれ/ゆがみが起きやすいと言われています
「内股座りってラクだし、別にいいんじゃない?」と思う人もいますよね。だけど、あの姿勢は股関節が内側にねじれた状態になりやすく、骨盤も同じ方向へ引っ張られやすいと言われています。すると左右のバランスがくずれて、立ったときの重心がズレることがあるみたいです。実際、内股座りを続けると骨盤や股関節のねじれにつながる可能性がある、と複数の整骨院系記事でも説明されています。グレフル鍼灸接骨院 整体院 心斎橋 |
O脚・X脚、膝や腰の負担、冷え・むくみの悩みにつながる可能性
「脚のラインにも関係あるの?」って聞かれますが、内股座りは膝が内側に入りやすい体勢なので、脚の並び(アライメント)が乱れてO脚やX脚になりやすいと言われています。グレフル鍼灸接骨院
さらに、膝や股関節に不自然な力がかかりやすく、膝痛・股関節痛・腰痛のリスクが高まる可能性がある、という触れ方も多いです。 「最近ひざが気になるな…」とか「腰がだるいかも」と感じる人は、座りグセも一度見直したほうが安心かもしれませんね。
それともう一つ、見落とされがちなのが血行面。内股座りは下半身が折れ曲がって圧迫されやすいので、血液やリンパの流れが滞り、冷えやむくみが出やすくなる可能性があると言われています。「夕方になると足がパンパン」みたいな人は、座り方の影響もゼロじゃないかもしれません。
引用元:https://greful.com/column/ushimata-demerit/
引用元:https://okurayama.meu-seitai.biz/
引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/8318.html
#内股座りのデメリット #骨盤と股関節のねじれ #O脚X脚リスク #膝腰への負担 #冷えむくみ対策
3.内股座りになる原因(子ども/大人で分けて解説)

股関節のクセや筋バランスが関係する場合
「内股座りって、どうしてそうなっちゃうの?」とよく聞かれます。上位の記事では、股関節が内側に回りやすい(内旋しやすい)クセがあると、あの姿勢に入りやすいと言われています。さらに、内もも側の筋肉が働きやすく、お尻まわりや外側の筋が使われにくい状態だと、骨盤が安定しづらくて“ラクな座り方”として内股座りを選ぶこともあるようです。大人でも、無意識のうちに脚が内向きになりやすい人は要注意、という触れ方がされています。
引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/8318.html
子どもに多い理由(成長過程・柔軟性・骨格)
「子どもがよくやるのはなぜ?」という点については、成長途中で体幹の力がまだ弱いと、あぐらや正座より内股座りのほうがぐらつきにくいから、と説明されています。股関節が柔らかい子は、脚を外に逃がすこの座り方でも痛みを感じにくく、自然に身につきやすいとも言われています。つまり、発達や柔軟性の個人差が背景にあるケースがある、という見方ですね。
引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/
生活習慣と、注意が必要なケース
一方で、普段の座り方・歩き方・姿勢のクセが積み重なって内股座りが定着する場合もあるようです。たとえば、長時間座る生活で股関節まわりの外側の筋を使う機会が少ないと、脚が内に入りやすい状態になりやすい、といった指摘が見られます。
「じゃあ、放っておいても大丈夫?」と不安になりますよね。基本は“クセの一つ”として経過を見る考え方もありますが、痛みが出る、左右差が強い、歩き方が極端に気になるなどのときは、早めに専門家に相談したほうが安心だと言われています。
引用元:https://okurayama.meu-seitai.biz/
#内股座りの原因 #股関節の内旋 #子どものW座り #生活習慣のクセ #痛みがある時は相談
4.正しい座り方・やめるためのコツ(今すぐできる代替姿勢)
床での座り方の工夫(あぐら/長座/横座りなど)
「内股座りをやめたいんだけど、どう座ればいい?」と相談されることが多いのですが、まずは“骨盤が立ちやすい座り方”を選ぶことがポイントだと言われています。たとえば、あぐらは腰まわりのスペースが取りやすく、骨盤を起こしやすいので取り入れやすいですよ。長座(足を前に伸ばす座り方)も、背すじを伸ばす感覚をつかみやすいと言われています。「え、長座ってキツい…」という声もありますが、背中を壁に軽く当てて座るとラクになります。
「横座りってどうなの?」という質問もありますが、左右どちらかだけ長時間続けると偏りが出やすいので、左右を入れ替えながら短時間で取り入れるのがすすめられています。いろいろ試しながら“自分が無理なく姿勢を保てる座り方”を選ぶのが大事ですね。
(引用元:グレフル鍼灸接骨院 整体院 心斎橋|https://greful.com/column/ushimata-demerit/ )
椅子での正しい座り方(足裏接地・膝90度・骨盤を立てる)
椅子に座るときは、足裏がちゃんと床につくかどうかがまず大切なんです。ぶら下がってしまうと骨盤が後ろに倒れやすいので、足置きを使って調整する人もいます。「膝はどうすればいい?」と聞かれたら、だいたい90度前後になるよう意識すると姿勢が安定しやすいと言われています。
そして一番大事なのは骨盤。骨盤を軽く立てるように座ると、お腹や背中の力が自然に働くので、腰が丸まりにくくなります。「骨盤を立てるってむずかしい…」と思ったら、座面のやや前側に腰をかけたり、タオルを腰の後ろに挟むだけでも感覚がつかみやすくなるので試してみてください。
(引用元:薮下整骨院|https://www.krm0730.net/blog/3089/)
子どもへの声かけ・習慣化のコツ
子どもに「内股座りはダメ!」と言っても、正しい姿勢をキープするのはむずかしいんですよね。上位の記事でも、叱るより“遊びの中で姿勢を変える”アプローチが紹介されています。
たとえば、あぐらを「お山座り」と呼んでみたり、長座を「電車みたいに座ってみよう」と誘ったり、ゲーム感覚で姿勢を変える工夫をするとスムーズです。「こっちの座り方のほうが楽しくない?」と声かけするだけでも、子どもは自然と動いてくれます。
長時間の内股座りが続いてしまうときは、「ちょっとお水飲もうか」「一回立って伸びようか」と動くきっかけを作るのもおすすめです。大人の“さりげなく促す工夫”が、無理なく習慣化につながりやすいと言われています。
#正しい座り方
#内股座り改善
#椅子の座り方ポイント
#子どもへの声かけ
#姿勢を整えるコツ
5.内股座りを改善するストレッチ・エクササイズ(写真/手順/頻度)

骨盤リセット・股関節まわりのケアで土台を整える
「内股座りを直したいけど、何からやればいい?」って迷いますよね。参考記事では、まず骨盤まわりをゆるめて整える“骨盤リセット系”が入り口として紹介されています。たとえば仰向けで膝を立て、両膝を手で軽く押し合うようにして骨盤を締める動きは、短時間でも骨盤周辺を意識しやすいと言われています。次に、股関節の外側を支える外旋筋やお尻(殿筋)を使うエクササイズも大事。横向きで寝て上の脚を前に出し、股関節まわりをやさしく伸ばすストレッチは、大転子まわりの硬さケアに役立つ可能性があるようです。さらに、内もも(内転筋)やもも裏(ハムストリング)を伸ばして柔軟性を上げると、脚が内に入りにくい土台づくりにつながると説明されています。
(引用元:薮下整骨院|https://www.krm0730.net/blog/3089/)
続けやすい頻度と、変化チェックのコツ
「どれくらいやればいいの?」という声も多いですが、上位記事の流れだと“毎日ちょこっとが続けやすい”スタンスです。目安としては、1回5〜10分くらいを1日1回、できそうなら週に4〜5日をベースにする、くらいが無理なく続くと言われています。やる時間は朝でも夜でもOKで、テレビを見ながらでも続けば勝ちです。
変化のチェックはシンプルで大丈夫。①床に座ったとき内股座りになりづらくなったか、②脚の向きが前にそろいやすいか、③膝や腰に違和感が出ていないか、の3つをゆるっと見ていきましょう。「前よりラクにあぐらができるかも」みたいな小さい感覚が出たら、いいサインと言われています。
改善しにくい場合の来院目安
「頑張ってるのに変わらない…」ってときもあります。その場合、痛みが続く、左右差が強い、歩き方まで気になってきた、などがあれば専門家に相談する選択肢もあると言われています。整骨院や整体では、骨盤や股関節の動きを触診で確認しつつ、日常のクセに合わせた施術やセルフケア提案をしてくれるケースが多いようです。
(引用元:グレフル鍼灸接骨院|https://greful.com/column/ushimata-demerit/)
#内股座り改善ストレッチ
#骨盤リセット
#股関節外旋筋と殿筋
#内転筋ハムストリング柔軟性
#続けやすい頻度と来院目安
ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

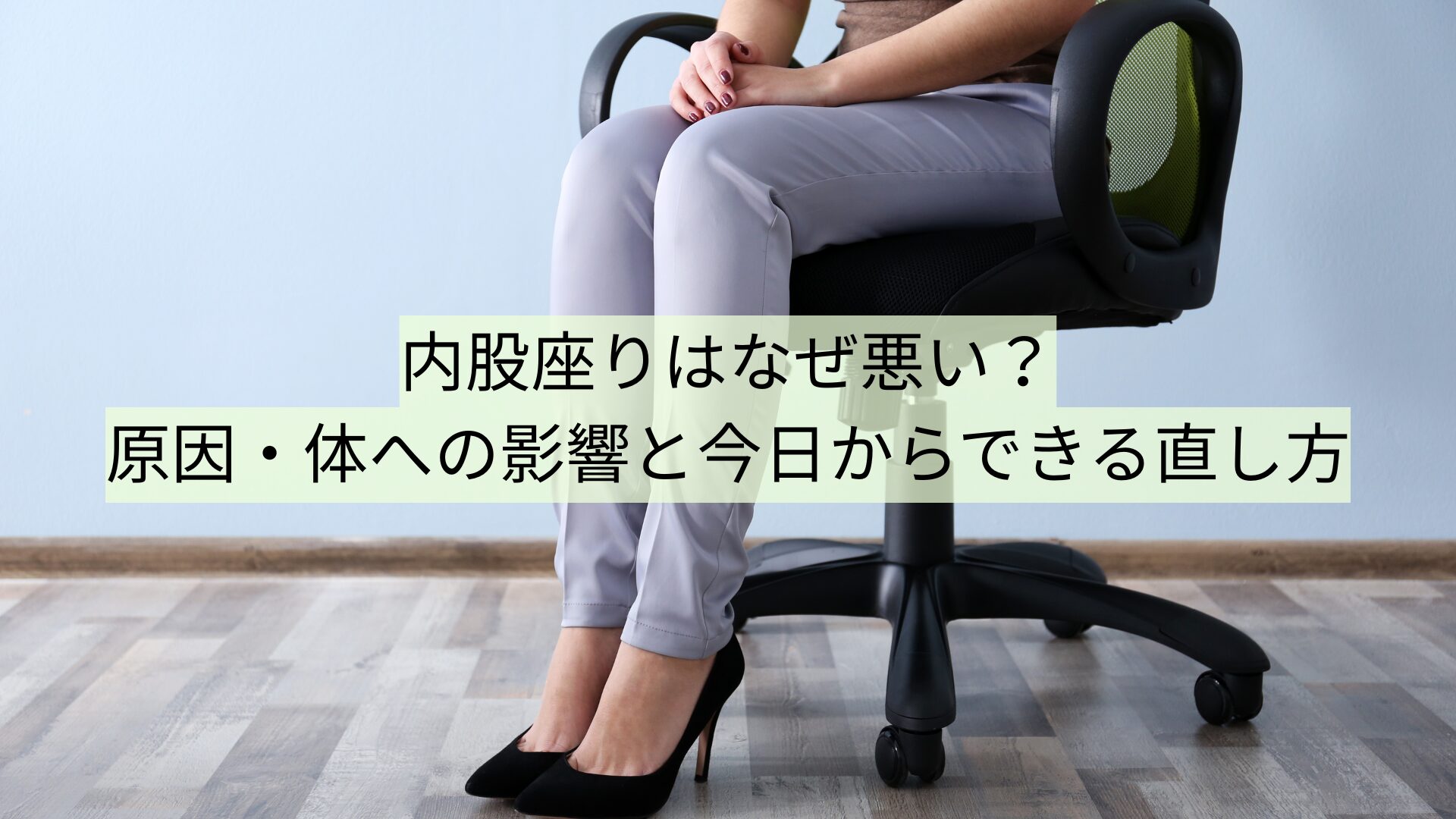


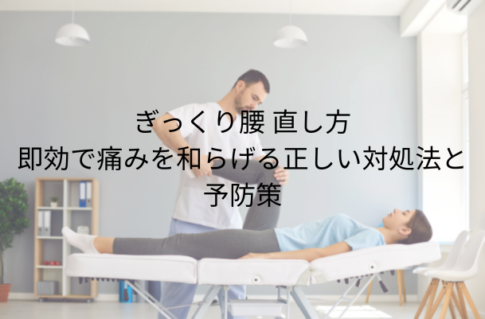
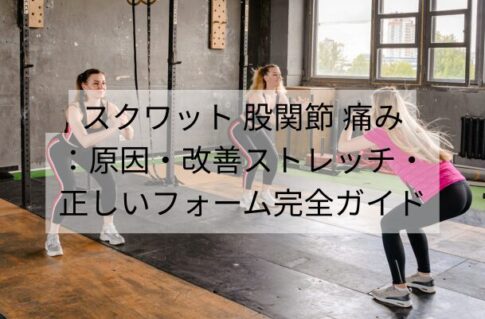
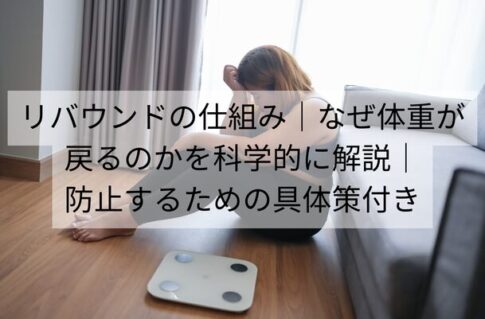

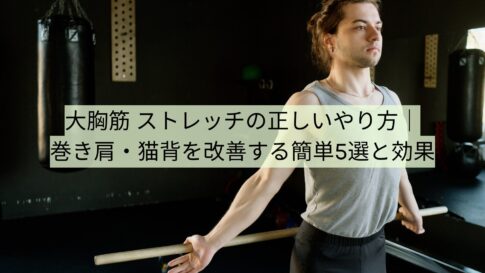



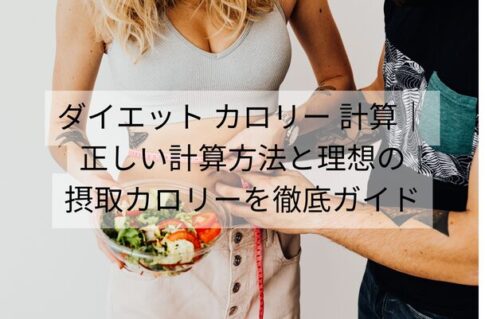
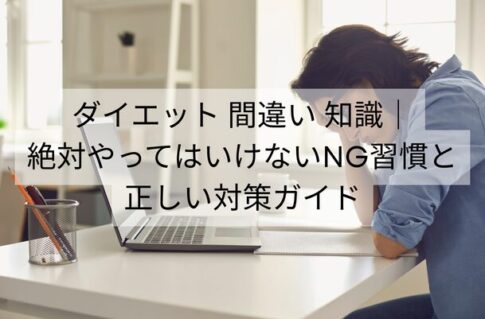
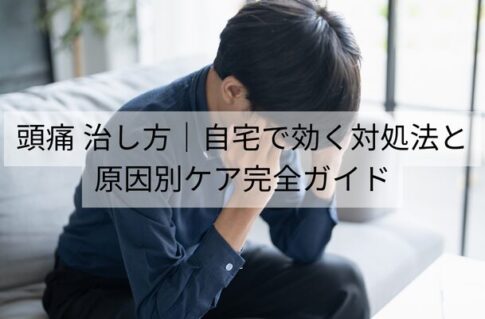
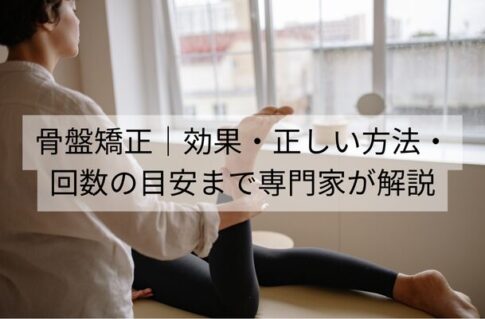
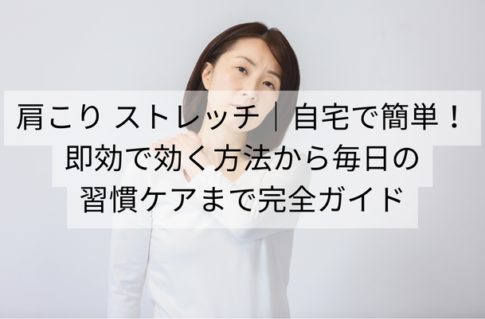




コメントを残す