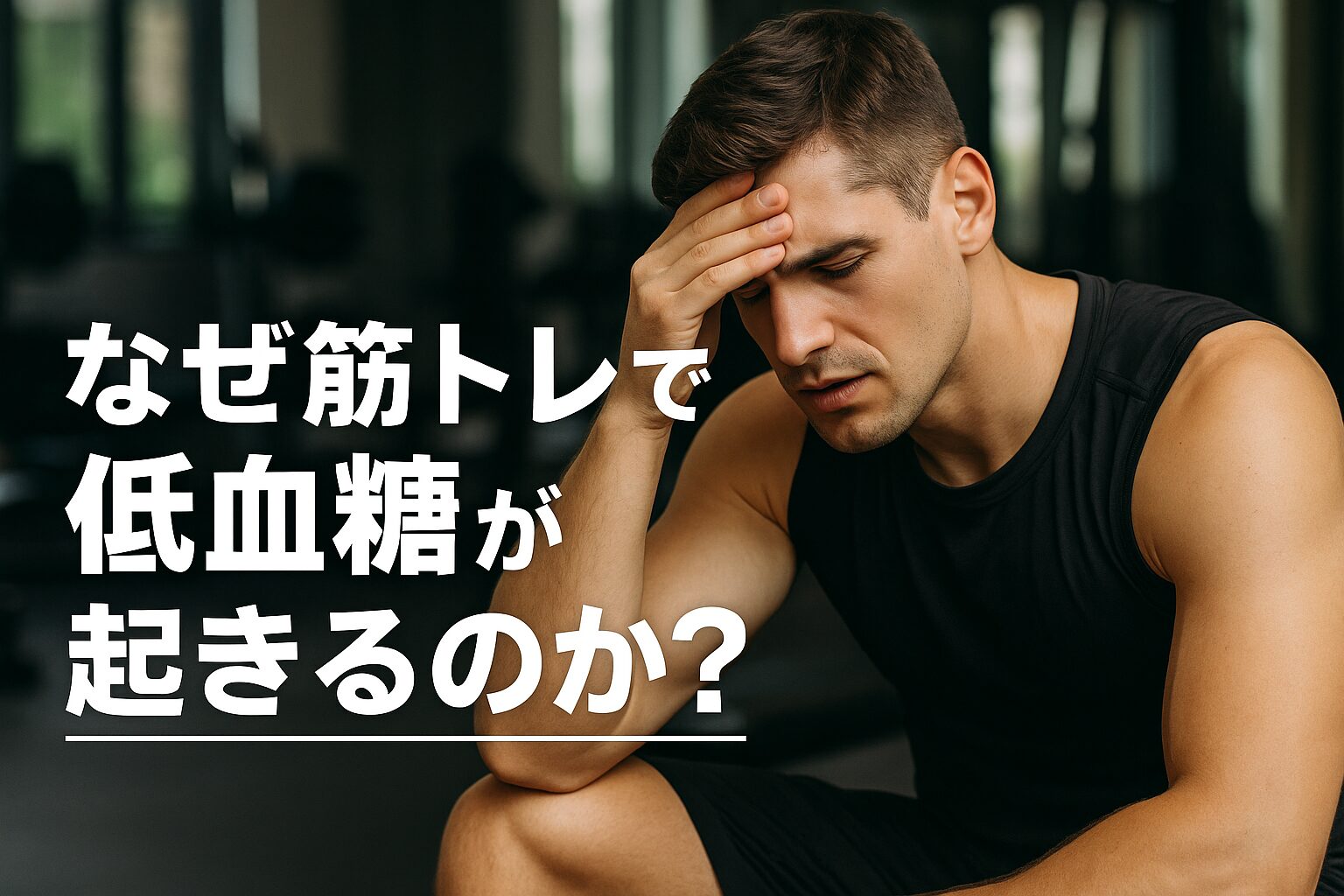
なぜ「筋トレで低血糖」が起きるのか?
筋トレ(特に無酸素運動)時の血糖値の動き
「筋トレをするとフラフラする…」なんて経験、ありませんか?実はこれは、トレーニング中に血糖値が急に下がる“低血糖”状態に近づいている可能性があります。無酸素運動(重めの筋トレや短時間高強度)では、体は主に筋肉内の貯蔵型エネルギーであるグリコーゲンや血中のブドウ糖を駆使して動こうとします。トレーニングの開始直後から、筋肉細胞はインスリンに頼らず「筋収縮刺激+AMPキナーゼ活性化」でグルコースを取り込むため、血中のブドウ糖および貯蔵グリコーゲンがあっという間に消費されやすいと言われています。分子栄養療法ナビ+1
そのため、筋トレ中に「急に力が入らなくなった」「頭がぼーっとする」などの症状が出るのは、血糖が筋肉へ・または肝臓でのグリコーゲンが分解されてブドウ糖として補充される量が追い付かなくなってきているサインとも捉えられています。
血糖が急激に消費・細胞に取り込まれるメカニズム
もう少し掘り下げると、筋トレ中は「筋細胞がグルコースをより多く使う」+「肝臓のグリコーゲン枯渇」の両方が重なり得ます。まず、食事などから取り入れられた炭水化物はブドウ糖になって血中を巡り、その一部が筋肉や肝臓に「グリコーゲン」として蓄えられています。分子栄養療法ナビ
運動中は、筋肉でのグリコーゲン分解・血中ブドウ糖の取り込み量が増えて、肝臓でもグリコーゲンを分解して補充しようとしますが、このストックが減ると「糖新生(たんぱく質や脂質からブドウ糖を作る)」に体が切り替えると言われています。分子栄養療法ナビ+1
この切り替えは、筋トレ直後では間に合わず、一時的に“使えるブドウ糖”が足りない状態、つまり低血糖傾向に陥りやすい状況を作ります。特に、筋トレを始めたばかり、または高強度・長時間で行っている場合はこのリスクが高まります。
空腹トレーニング・糖質制限との関連
加えて、食事タイミングや栄養摂取の状況も大きな影響を与えます。例えば「朝ご飯を抜いてそのまま筋トレ」「ダイエットのために糖質を極端に減らして筋トレ」という状況では、そもそもの血中ブドウ糖量・筋・肝のグリコーゲン量が不足しているため、筋トレ中に血糖が急速に消耗されやすいと言われています。分子栄養療法ナビ
さらに、糖質制限をしていると、筋肉内・肝臓内のグリコーゲン貯蔵量そのものが減少するため、トレーニング中の“取り込み量>補充量”のバランスを崩しやすいとの指摘もあります。結果として、筋トレ前後にふらつき・冷や汗・力が入らないなど、低血糖関連の症状が起きることがあるのです。
このように、「筋トレで低血糖が起きる」という現象は、単に運動だけの問題ではなく、『筋トレの種類・強度』『食事・栄養・グリコーゲンの蓄え』『空腹・糖質制限といった事前条件』が複雑に絡んで起きるものと言われています(引用元:上記)。“運動すれば血糖が下がる”というシンプルな図式ではなく、むしろ「ブドウ糖・グリコーゲンが足りないまま強い運動をしたとき」に低血糖傾向が生じる、というイメージが近いでしょう。
筋トレ時に「なんか調子が悪いな」「力が出ないな」と感じたら、まずはこの血糖・グリコーゲンの観点でチェックしてみるのがおすすめです。
#筋トレ低血糖 #無酸素運動血糖 #グリコーゲン消費 #空腹トレーニング危険 #糖質制限筋トレ注意
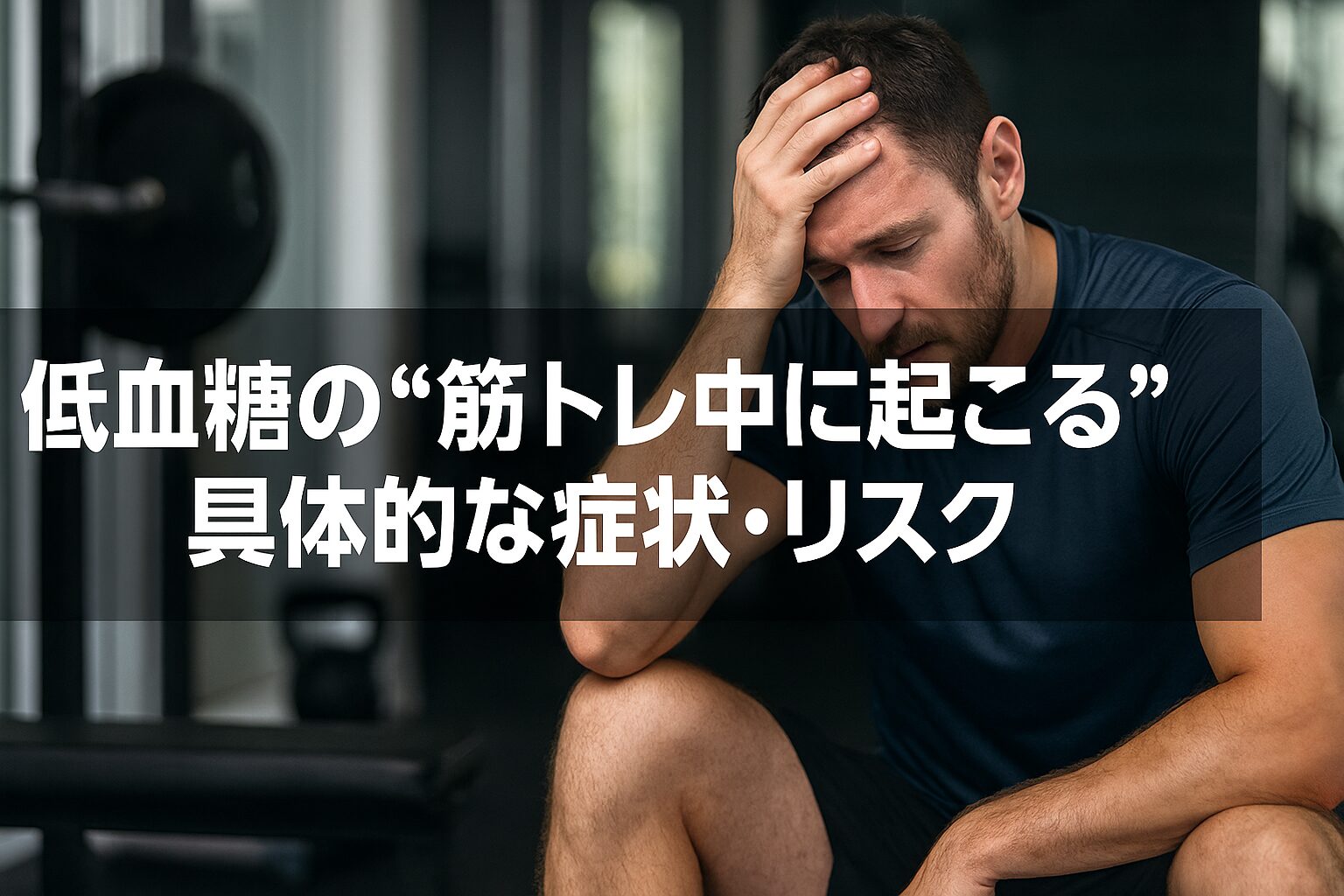
低血糖の“筋トレ中に起こる”具体的な症状・リスク
頭がぼーっとする/手足が震える/冷や汗が出るなど初期症状
――「あれ?今日ちょっと調子悪いな…」って、筋トレ中に感じるそのモヤっとした違和感――実はそれ、低血糖症のサインかもしれません。例えば「頭がぼーっとする」「手足が震える」「急に冷や汗が出る」といった症状が、筋トレ中やその直後に起こることがあると言われています。 さかぐち整骨院+1
無酸素運動や高強度なトレーニングをしていると、筋肉は大量のグルコース(血中のブドウ糖)を使い、さらには肝臓のグリコーゲン(糖貯蔵)を分解して補おうとします。ですが、その補充が追いつかないと、血中の“使える糖”が急速に減って、脳や筋肉が「燃料不足だよ」とSOSを出すことがあります。 分子栄養療法ナビ+1
しかも、糖新生(筋タンパク質や脂質から糖を作るプロセス)に切り替わるまでにはタイムラグがあります。つまり、トレーニング中にそのギャップが生じると、わたしたちの体は“糖が足りていない”状態=低血糖傾向に陥りやすいと言われています。 分子栄養療法ナビ
「ただの疲れかな?」と思って処理してしまいがちですが、単なる筋疲労とは違う“異質なだるさ”や“いつもと違う震え・冷や汗”を感じたときは、少し立ち止まって「血糖、足りてるかな?」と考えることが重要です。
進行した場合:意識障害・けいれんなどもありうること・単なる「疲労」との違いや見分け方・筋肉量低下・パフォーマンス低下につながる可能性
次に気をつけたいのは、初期症状を放置した場合に起こりうるリスクです。運動による低血糖傾向がさらに進行すると、「何かふわっと意識が飛びそう」「何をしているか分からなくなる」「けいれんを起こした」という報告もあります。これは、脳がエネルギー源としてのブドウ糖を十分使えなくなったことが関係していると言われています。 分子栄養療法ナビ+1
さらに「これはただ疲れてるだけかな?」という思い込みも危険です。疲労なら「筋肉が重い」「動きが鈍い」という感覚が主体ですが、低血糖による影響は「頭がぼんやり」「視界がぼやける」「急に手足が冷たくなる」「冷や汗が出る」といった“異なる”シグナルが伴うケースが多いと言われています。 さかぐち整骨院
また、長期的な影響として“筋肉量低下”や“筋トレのパフォーマンス低下”にまでつながる可能性も指摘されています。なぜなら、糖新生によって筋肉のタンパク質が糖に変換されてエネルギーとして使われてしまうと、筋肉を維持・成長させるための材料が不足し、結果として筋肉が減ってしまう可能性があるからです。 分子栄養療法ナビ
つまり、「筋トレをしてるのに力が出ない」「なんか痩せてきたけど筋肉が減った気がする」という場合、糖質・血糖の観点からも自分のトレーニング・栄養状況を見直す余地があるかもしれません。
どんな人が、どんな状況で“筋トレ 低血糖”になりやすいか?
糖質制限中/カロリー不足状態で筋トレをしている人・朝トレ/空腹トレ派・食事から時間が経っている状態
「最近、筋トレしてるのに途中でふらつくんだよね…」と感じるなら、それは“トレーニング中の低血糖リスク”が高まっているサインかもしれません。例えば、糖質を控えていて、カロリーも少なめ、という食事パターンを続けていると、トレーニング開始時点で“使える糖(ブドウ糖)”や“貯蔵形態のグリコーゲン”がそもそも不足している状態になりやすいと言われています。引用元:分子栄養療法ナビ「運動と低血糖症の関係とは」分子栄養療法ナビ
また、朝ご飯を抜いて筋トレ開始、もしくは食事から時間が経っている(例えば夕方前の誰も食べていない状態)という状況も要注意です。空腹状態では血中のブドウ糖が減り、肝臓・筋肉に蓄えられたグリコーゲンも減っていることが多く、筋トレのような運動負荷がかかる活動中、「糖の供給が追い付かない」リスクが上がると言われています。引用元:分子栄養療法ナビ分子栄養療法ナビ+1
このような「食事の量・質が少ない orタイミングが合っていない」+「トレーニングを実施している」状態は、低血糖傾向を作り出しやすい“条件”になるわけです。
筋トレ初心者・インスリン感受性が高まっている人・トレーニング強度・持続時間とリスクの関係
さらに注目すべきは、「筋トレ初心者」や「インスリン感受性(≒筋細胞がブドウ糖を使いやすい状態)が高まっている人」です。初心者は筋肉が運動による刺激を受けるたびにグルコースの取り込みが変化しやすく、また、インスリン感受性が高い状態では筋細胞がブドウ糖を取り込みやすく、結果として血中のブドウ糖が急速に減少する傾向があると言われています。引用元:分子栄養療法ナビ分子栄養療法ナビ
加えて、トレーニングの 強度が高い(例えば大きな負荷・短時間で筋肉を追い込む)・または 持続時間が長い(例えば休みなくセットを続ける、長時間行う)という状況も、低血糖につながる要因になります。なぜなら、筋肉が大量にグルコースを消費し、肝臓のグリコーゲン枯渇の起点が早まるからです。引用元:分子栄養療法ナビ分子栄養療法ナビ+1
つまり「初心者/インスリン反応が良い人」+「食事準備が不十分」+「強度や時間が高めのトレーニング」を組み合わせると、低血糖に陥りやすい“シナリオ”が出来上がると言えるわけです。トレーニング中に「急に力が抜けた」「動けなくなった」などを感じたら、このあたりをまずチェックするのがおすすめです。
#筋トレ低血糖リスク #糖質制限筋トレ注意 #空腹トレーニング危険 #初心者筋トレ血糖 #高強度持続筋トレ血糖消費
予防・対策:筋トレ中の低血糖を防ぐための実践的な方法
トレーニング前の糖質・タンパク質の摂取タイミングと量/補食・手軽に糖質を摂れる食品(バナナ・ゼリー・スポーツドリンク)
「よし、トレーニング始めよう!」というとき、実はその前の“栄養準備”が非常に大事です。例えば、トレーニング開始の30~60分前に、適量の糖質+タンパク質を摂っておくと、トレ中のブドウ糖供給が安定し、低血糖のリスクを抑えやすいと言われています。引用元:分子栄養療法ナビ「運動するとなぜ低血糖になりやすい?」(nutrinavi.com)
具体的には、バナナ1本+プロテイン20〜30 gといったシンプルな組み合わせや、ゼリー飲料・スポーツドリンクなど消化が早く糖質を補えるものを“補食”として活用するのがおすすめです。こういった補食を「トレーニング前ギリギリでも何も口にしない」よりも摂っておくことで、トレーニング中に「力が抜けた」「頭がぼーっとした」などの危険シグナルが出にくくなると言われています。引用元:さかぐち整骨院「筋トレで低血糖になる原因とは?」(sakaguchi-seikotsuin.com)
ただし、「糖質を大量に」「直前に重い食事を」というのは逆に胃腸に負担になりやすいため注意が必要です。摂取量やタイミングは体格・活動量・体調に応じて調整することが望ましいと言われています。
トレーニング時・トレーニング後の水分・ミネラル補給/空腹状態でトレーニングする場合の注意点・軽く食べてから行う選択肢/体調チェックリスト(眠り・前日の食事・体調など)/トレーニング中に異変を感じたらどうするか(中止・糖質補給・医療相談)
トレーニング中や終了直後のケアも、低血糖を防ぐカギです。まず、水分+ミネラル(ナトリウム・カリウムなど)を補給することで、血液循環がスムーズになり、糖が細胞に届きやすい状態を維持できると言われています。引用元:分子栄養療法ナビ(nutrinavi.com)
さらに、もし“空腹状態”でトレーニングする場合には、軽い補食をしてから始めるのが安心な選択肢です。例えば「起きてすぐ朝トレ」「食事から時間がかなり経っている状態でトレ」という状況では、血糖・グリコーゲンが不足気味になっているため、バナナ1本や小さめのゼリー飲料を摂っておくだけでも、トレ中のブドウ糖供給を安定させやすいと言われています。引用元:さかぐち整骨院(sakaguchi-seikotsuin.com)
最後に、“トレーニング前日の睡眠”、“前日の食事量・質”、“当日の体調・疲労具合”を簡単にチェックするリストを設けておくと安心です。例えば、「昨夜しっかり眠れた?」「前食から時間が経ちすぎてない?」「体がだるくない?」「手足が冷たくない?」という項目を設けておくことで、低血糖になりやすい“隠れた条件”を自覚しやすくなると言われています。引用元:さかぐち整骨院(sakaguchi-seikotsuin.com)
そして、もしトレーニング中に「なんかいつもと違うな」「視界がぼんやりする」「手足が震える」「冷や汗が出る」と感じたら、一旦動きを止めて座るか横になり、直ちに糖質+水分を補給するのが得策と言われています。改善が見られなかったり、こうした症状が頻繁に起こる場合は、無理せず専門機関での相談を視野に入れておくことが重要です。引用元:分子栄養療法ナビ(nutrinavi.com)
#筋トレ低血糖予防 #糖質補給筋トレ前 #空腹筋トレ注意 #水分ミネラル補給 #トレ中異変対処
実践プラン&Q&A:安心して続けられる筋トレ・低血糖ケアのために
朝/昼/夜トレ別の理想的な食事・補食プラン例/筋トレメニュー(例:高負荷 vs 低負荷)と血糖管理のヒント
「じゃあ、実際にどう食べてどう鍛えたらいいの?」という話をしましょう。まず、朝・昼・夜それぞれのトレーニング時間帯での理想的な食事・補食プランです。
-
朝トレ:起床後に軽めのバナナ1本+ホエイプロテイン20 g。トレーニング直後に玄米茶碗半分+鶏胸肉100 g+野菜たっぷり。
-
昼トレ:ランチ前後の時間に、主食150 g+サーモン100 g+サラダ。トレーニング30分前にゼリー飲料+スポーツドリンク。
-
夜トレ:夕食1〜2時間前に、パスタ(炭水化物70 g目安)+豆腐&卵、トレーニング直後にプロテイン+果物。
こうしたプランは、トレーニング前から “血糖・グリコーゲン” の備えをしておくことで、低血糖のリスクを減らせると言われています。
筋トレメニューについても触れておきましょう。高負荷(例えばスクワット5 RM×3〜4セット)なら消費糖量が大きく、血糖が急速に減る可能性が高いです。低負荷(例えばダンベルカール15〜20回×2〜3セット)なら消費は比較的緩やか。高負荷時にはトレーニング前にしっかり補食を、低負荷なら「軽く補食+通常の食事」で十分というヒントがあります。実際、適切な糖質補給がなければ“筋肉をつける”目的でも、逆に筋量が落ちてしまうリスクがあると言われています。
よくある疑問&回答/もし頻繁に低血糖症状が起きるならチェックすべきポイントと医療相談の目安
それでは、よくある疑問に口語風でお答えします。
Q1:「糖質を控えながら筋トレしても大丈夫?」
「糖質減らして体脂肪落としたいんだ」っていう意図は理解できます。ただ、筋トレ中の低血糖リスクを考えると、適量の糖質を摂ることが“筋トレを安全に続ける”ためにも重要だと言われています。
Q2:「血糖値を測っていないけど大丈夫?」
一般的な健康状態なら頻繁な血糖測定は不要かもしれませんが、「トレ中にふらつく・力が抜ける」と感じるなら、血糖の傾向を把握しておくのは安心材料になります。
Q3:「糖尿病等持病がある場合どうすれば?」
持病がある方は、運動前後の糖質補給・薬(インスリン等)調整など、専門家(医師・管理栄養士など)と相談しながら進めることが重要です。運動により低血糖・高血糖いずれも起こりうると言われています。
最後に、「頻繁に低血糖症状が起きるなら」チェックすべきポイントと医療相談の目安です。前日の睡眠不足・食事量の極端な減少・空腹トレーニング・トレーニング強度/時間の急増などが赤信号。こうした条件が重なって不調が頻発するなら、無理をせず専門機関で相談も選択肢です。
#筋トレ低血糖対策 #トレ前補食プラン #高負荷低糖リスク #糖質と筋トレ質問回答 #持病と運動血糖管理

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています





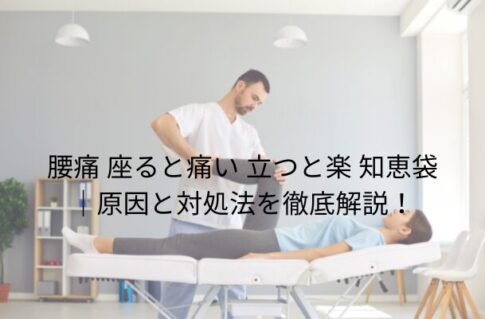



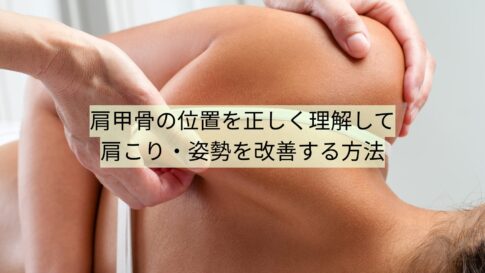
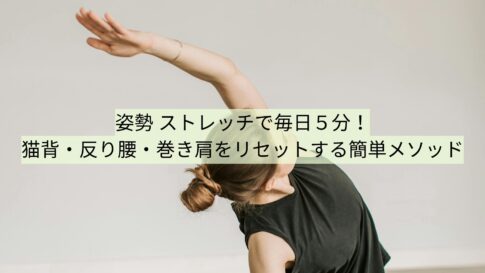




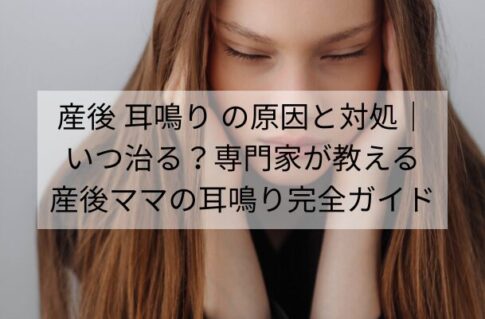
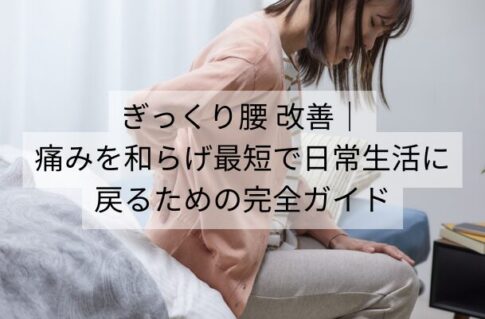
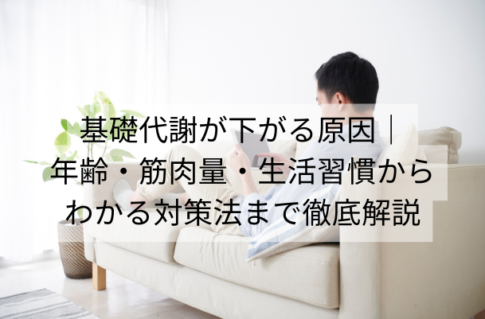
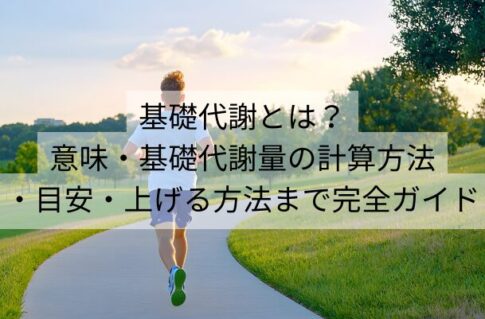
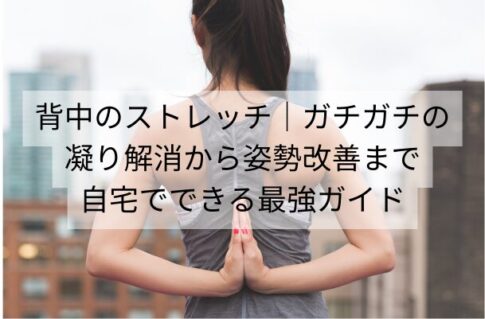




コメントを残す