体のしびれとは?—感覚異常の基本を知る
しびれの正体を理解する
「体のしびれ」と聞くと、多くの人が正座のあとに足がジンジンする感覚を思い浮かべるのではないでしょうか。実際、しびれという言葉には幅広いニュアンスがあり、感覚が鈍くなる「感覚鈍麻」や、針で刺されるような「ピリピリ感」、皮膚が焼けるような「灼熱感」、さらには力が入りづらい「脱力感」などが含まれると言われています。これらは一見似ているようでも、感じ方や現れる部位によって背景が異なることが多いとされています。
会話の中でわかる「しびれ」の感覚
たとえば、患者さんが「手がピリピリするんです」と話すと、医師は「それは感覚神経の異常かもしれませんね」と説明することがあります。別の人が「感覚がなくなって、物を触ってもよくわからない」と話した場合は、「感覚鈍麻」と表現されることがあるそうです。このように、しびれという一言でも、人によって感じ方や表現の仕方が違うため、丁寧に聞き取りながら状態を整理することが大切だと言われています。
異常感覚としてのしびれ
特に今回取り扱うのは「感覚が麻痺したように異常に感じるタイプ」です。これは単なる血流の一時的な停滞によるものだけではなく、神経や筋肉の働きに関連している場合もあります。長時間の同じ姿勢で神経を圧迫したときに出ることもあれば、体の中の別の要因が関係するケースもあるようです。こうした背景を知っておくことで、「一時的に出るしびれなのか」「改善が必要なサインなのか」を見分けやすくなると言われています。
#しびれの種類
#感覚異常の理解
#ピリピリ感と鈍麻
#脱力感の特徴
#日常と医療の視点
引用元:

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

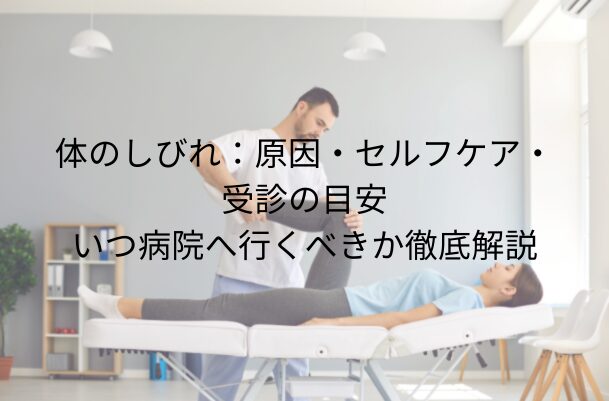


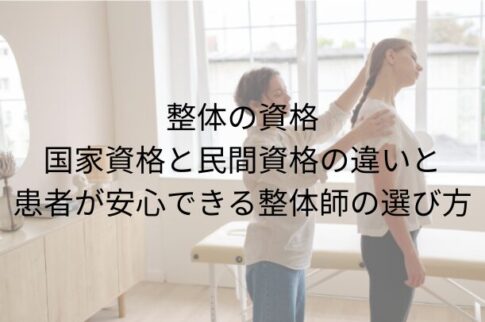

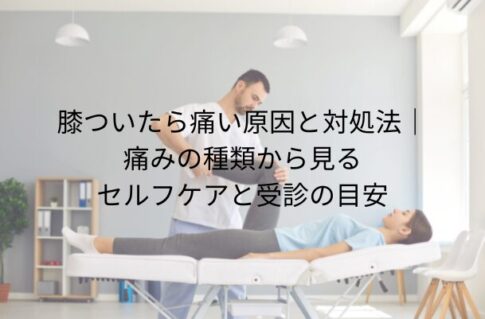

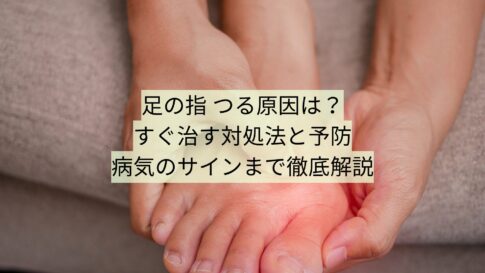
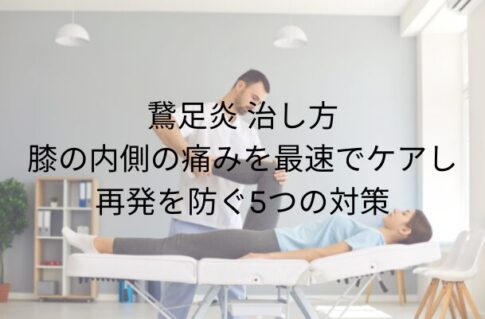

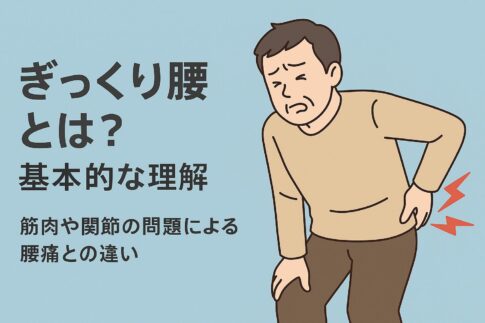





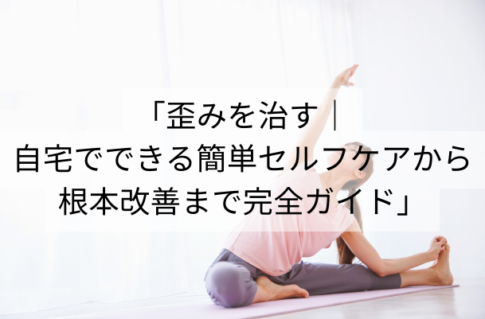

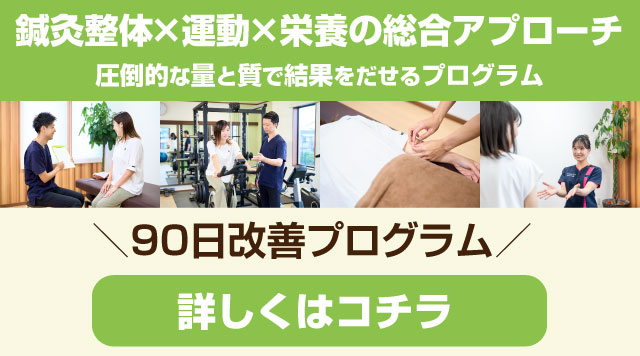



コメントを残す