1.僧帽筋上部とは?構造・役割・働きを解説

僧帽筋全体の中で「上部線維」がどこにあり、どんな働きをしているのか
「僧帽筋って背中の大きな筋肉でしょ?」と聞かれることがありますが、その中でも首の付け根から肩にかけて広がる部分が 僧帽筋上部 と呼ばれるところです。「ここが硬くなると肩こりを感じやすい」と言われています。
実際、僧帽筋上部は肩甲挙筋と一緒に肩をすくめる動きを担当していて、肩甲骨を上方向に引き上げるような作業が続くと負荷がかかりやすいんですね(引用元:https://muscle-guide.info/trapezius_upper.html)。
「なるほど、じゃあ普段どんな場面で使ってるの?」と聞かれることもあります。日常の中では、買い物袋を片側だけで持つときや、寒くて自然と肩をすくめてしまう場面でも僧帽筋上部は働いています。また、頭を支える役割もあるため、知らないうちに酷使しやすいと言われています。
なぜ僧帽筋上部だけが硬くなりやすいのか(姿勢・スマホ・PC作業)
「僧帽筋って上部だけ硬くなるの?」と思うかもしれませんが、スマホやパソコンの時間が長い人は特に影響を受けやすいと言われています。
というのも、前かがみ姿勢になると頭が前に出てしまい、その重さを支えるのが僧帽筋上部の仕事になるからです。「首が重い…」という感覚はこの筋肉が頑張っているサインかもしれません(引用元:https://postureram.com/what-is-trapezius/)。
また、「肩に力が入りやすいタイプなんです」と話す方もよくいますが、緊張状態やストレスでも肩をすくめる癖が出やすく、これも僧帽筋上部の張りにつながると言われています。
さらに、長時間同じ姿勢が続くデスクワークでは、筋肉が動かないまま固まりやすく、血流も低下してしまうため、コリを感じやすい状態になりやすいと言われています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog112/)。
#僧帽筋上部
#肩こり原因
#姿勢改善
#デスクワーク対策
#ストレートネック対策
2.なぜ僧帽筋上部がこる?原因と症状をチェック
肩こり・首こり・頭痛・巻き肩・いかり肩との関係
「最近、肩がずっと重いんですよね…」と相談されることがよくありますが、その背景には僧帽筋上部のこりが関係していると言われています。僧帽筋上部は首から肩にかけて広がっていて、この部分が緊張すると肩こりや首こりを感じやすくなるようです。
さらに、首から頭にかけて負担がかかると、頭痛を引き起こすきっかけになると言われています(引用元:https://kaori-yasuragi.com/column/488301.html)。
また、巻き肩やいかり肩の方は肩が前に出たり、肩が上方向に引っ張られた姿勢になりやすく、それが僧帽筋上部への負荷につながるとされています。「姿勢気になるんだけど、どうしても直らないんだよね」という方は、この筋肉がずっと力んでいる可能性があるんですね。姿勢と筋肉の関係は深いと言われています(引用元:https://postureram.com/what-is-trapezius/)。
典型的な生活習慣/姿勢の癖(肩をすくめる・片側荷物・前傾姿勢)
日常のちょっとした癖も僧帽筋上部がこる原因になりやすいと言われています。「荷物をつい片側だけで持っちゃうんですよね」という声はよく聞きますが、この習慣は肩が上がりやすく、筋肉に力が入りやすい状態が続いてしまいます。
また、スマホを長時間見ると前傾姿勢がクセになり、頭の重さを支えるために僧帽筋上部が常に緊張するとも言われています。気づいたら肩がすくんでいた、なんてこともありますよね。
放置するとどうなる?肩甲骨の動きが悪化し、可動域が狭くなる可能性
「忙しくてケアが後回しになってしまうんですよね…」という気持ちも分かるのですが、僧帽筋上部のこりを放置すると肩甲骨が動きづらくなり、腕の上げ下げなどがスムーズにいかなくなるとされています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog112/)。
肩甲骨が固まって可動域が狭くなると、さらに姿勢が悪化する悪循環につながりやすいと言われています。気づいたときには肩が上がったまま戻りづらい、そんなケースもあるようです。
#僧帽筋上部
#肩こり原因
#巻き肩改善
#デスクワーク疲労
#頭痛対策
3.自宅でできる!僧帽筋上部の効果的なストレッチ5選
椅子に座ったままの側屈ストレッチ(参考:湘南カイロ茅ヶ崎整体院)
「家で簡単にできるストレッチないですか?」という質問をよくいただきます。そんなときにまず紹介するのが、この側屈ストレッチです。
椅子に座り、片手で頭をゆっくり横へ倒し、反対側の肩を軽く下げながら僧帽筋上部を伸ばしていきます。「あ、ここ伸びてるな」という心地よさを感じるくらいがちょうど良いと言われています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog112/)。
タオルを使ったストレッチ(幅広い層に向けて)
タオルが1本あれば、さらに伸ばしやすいと言われています。
タオルを頭の横にかけて軽く引き、首を傾けると僧帽筋上部にじんわり広がる感覚があります。「手だけだと力加減が難しいんだよね」という方にもやりやすく感じてもらいやすいようです。
オフィスでもできる簡易ストレッチ
「仕事中でもできない?」という声も多いので、座ったまま肩をゆっくり下げて深呼吸する簡易ストレッチもおすすめされています。
長時間PCに向かっていると無意識に肩が上がっていることがあるので、「ふぅ〜」と息を吐きながら肩の力を抜くだけでも僧帽筋上部がゆるみやすいと言われています。
ストレッチ時のポイント(参考:ピラティススタジオBB)
ストレッチの効果を感じるにはコツがあると言われています。
・肩甲骨を下げて行う
・反動をつけない
・呼吸を止めない
この3つのポイントを守ると筋肉が素直に伸びてくれるようです(引用元:https://www.pilates-bb.com/topics/topic_20250201/)。
会話していると「つい息止めちゃうんですよね」と言われるのですが、呼吸が止まると筋肉も固まりやすくなるため、ゆったりとした呼吸を心がけると良いとされています。
頻度とタイミング(起床後・仕事の合間・就寝前)
「いつやればいいの?」という疑問も多いので、目安もお伝えしておきます。起床後は筋肉がこわばりやすいので軽めに伸ばすと体が動きやすくなると言われています。
仕事の合間は、固まった僧帽筋上部をリセットするチャンスです。1〜2分でも気分が変わりやすいようです。
そして就寝前は、リラックスのためにじっくり伸ばすタイミングとして向いていると言われています。
#僧帽筋上部ストレッチ
#肩こり対策
#デスクワーク疲労
#自宅ケア
#首こり改善
4.鍛えるべき?僧帽筋上部の筋トレ&姿勢改善アプローチ

上部線維を「過剰に使わない」ために中部・下部の働きが大事
「僧帽筋って鍛えたほうがいいんですか?」と聞かれることがありますが、僧帽筋上部はすでに日常生活で働きやすいと言われています。そのため、むしろ中部や下部の筋肉が使われていないことが、肩の緊張を引き起こす背景にあるとされています(引用元:https://postureram.com/what-is-trapezius/)。
例えば、巻き肩の方は上部だけが頑張ってしまい、肩甲骨が上に引っ張られた姿勢になりがちです。「肩が上がりっぱなしなんですよね…」と感じる方は、中部・下部を意識して使うことが姿勢の安定につながると言われています。
僧帽筋上部を鍛えるトレーニング(シュラッグ・ダンベル・バーベル)
とはいえ、「上部を鍛えちゃダメなの?」と思う方もいますよね。もちろん鍛えること自体が悪いわけではなく、バランスを考えることが大切だとされています。
代表的なメニューとして
・ダンベルシュラッグ
・バーベルシュラッグ
・軽負荷での肩すくめ動作
などがよく使われています(引用元:https://column.valx.jp/10578/)。
ただ、「やりすぎると肩がさらに上がる感じがするんですよね」と言われることも多いため、上部だけ集中的に鍛えるより、他の部位と合わせて行うほうが良いとされています。
トレーニング前後にストレッチを入れる理由と注意点
筋トレ前後にストレッチを入れると、動きやすさが変わると言われています。
・反動をつけない
・首をすくめない
・呼吸を止めない
この3つを守るだけでも、僧帽筋上部に余計な負荷をかけずに済みます。会話していると「無意識に肩が上がっちゃうんだよね」という声をよく聞きますが、首周りをリラックスさせてから動くと安定しやすいようです。
姿勢改善のための生活習慣(肩を下げる・肩甲骨を使う・スマホ位置調整)
最後に、「トレーニングしても姿勢が戻っちゃうんですよね…」と悩む方が多いため、日常で意識したいポイントもまとめておきます。
・肩を軽く下げることを意識する
・背中側の肩甲骨を寄せる感覚を思い出す
・スマホやPC画面を目線の高さに近づける
こうした小さな工夫が僧帽筋上部の緊張をやわらげると言われています。特にスマホの位置はすぐ下を向きやすいので、「少しだけ高く持つ」だけでも首肩の負担が変わるようです。
#僧帽筋上部
#筋トレ初心者
#姿勢改善
#肩こり対策
#肩甲骨エクササイズ
ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。
もう痛みを我慢する必要はありません。
一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。
ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。
何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。
一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

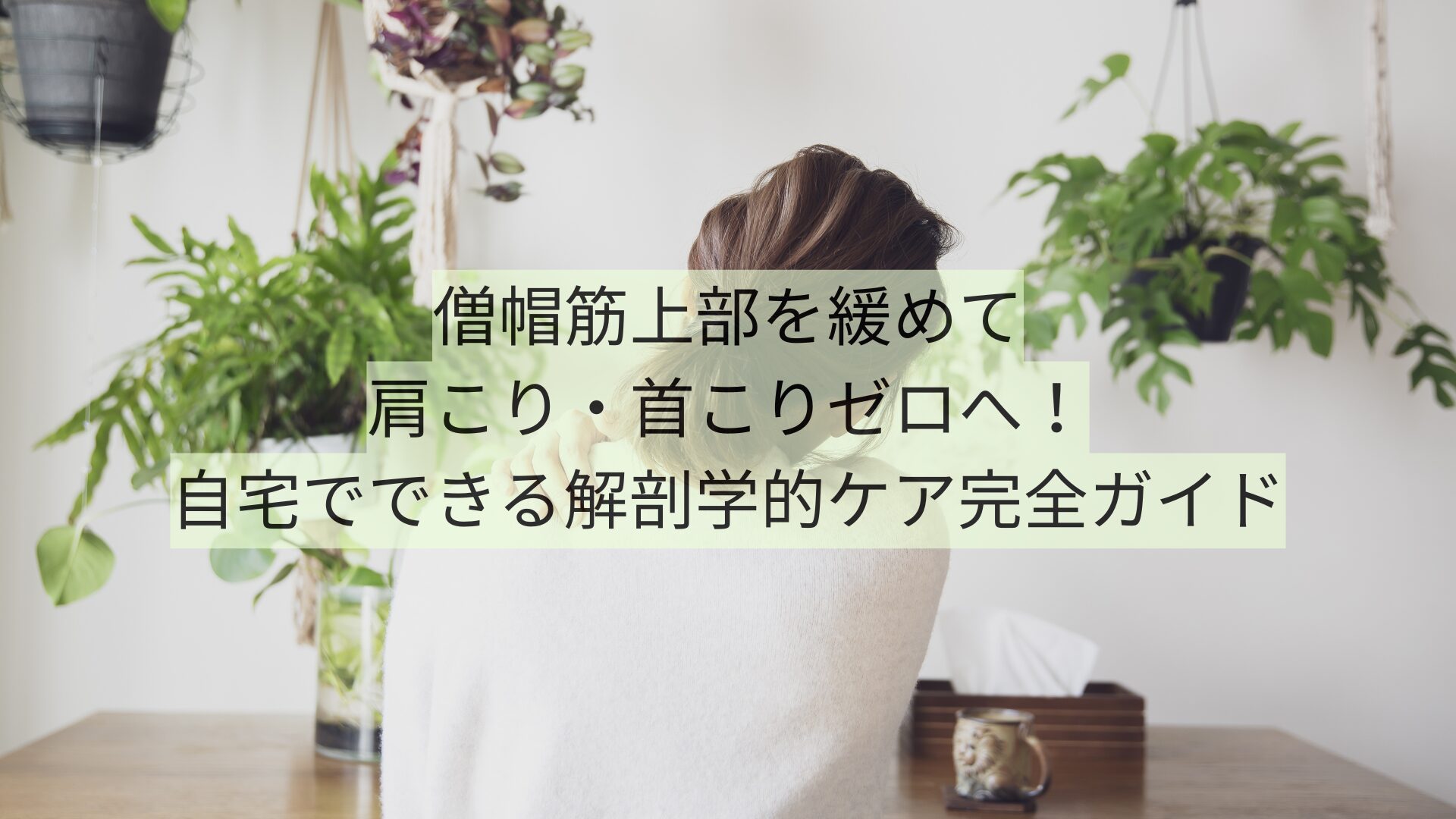
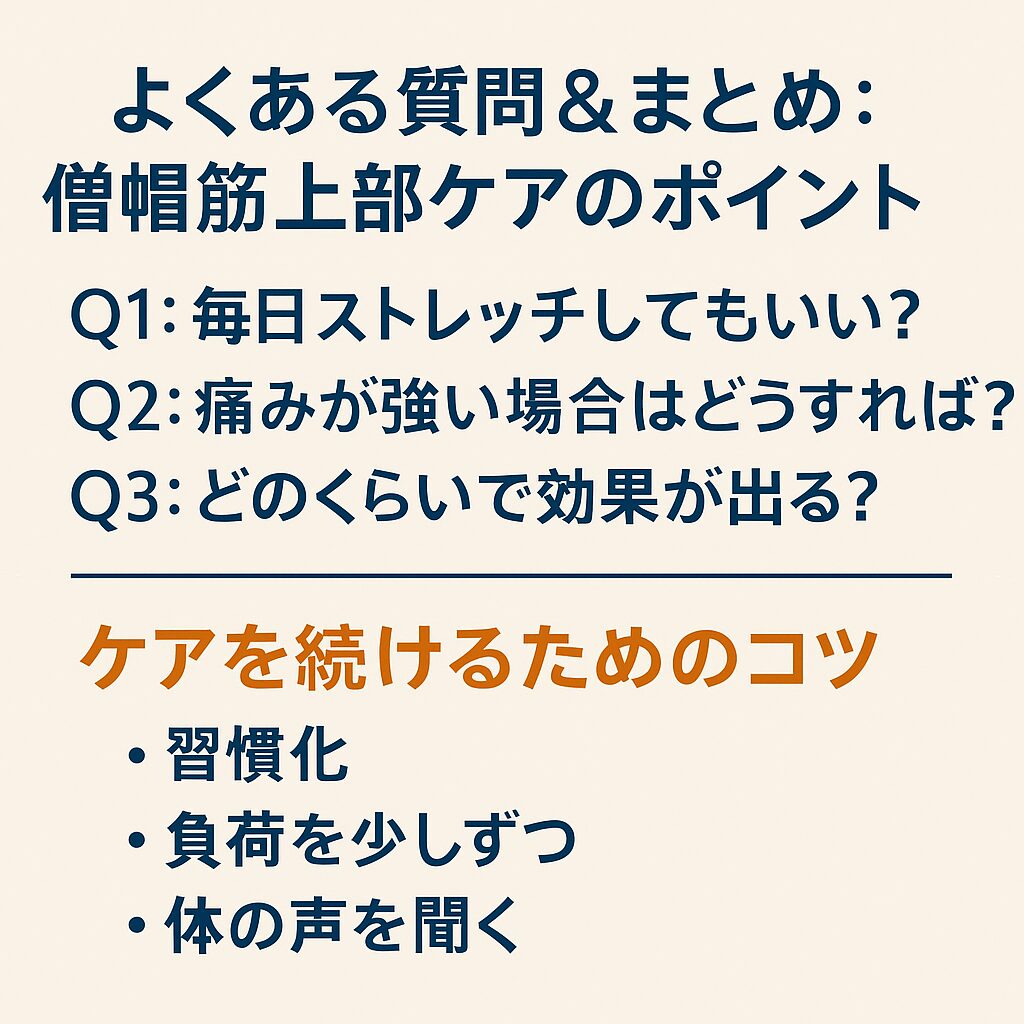


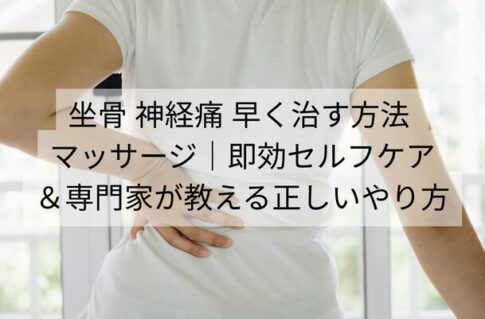
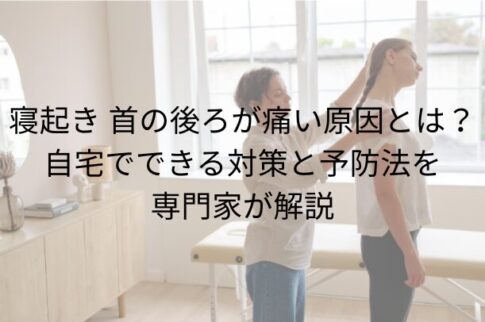

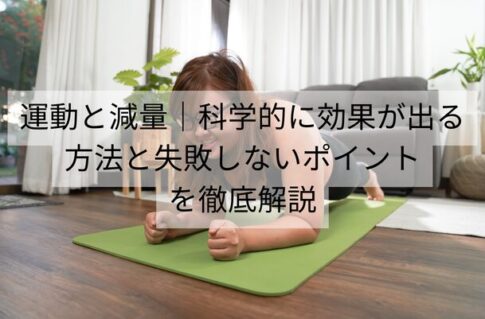


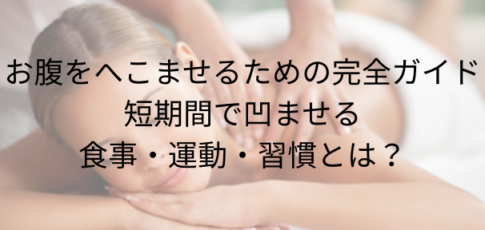










コメントを残す