*ステップ木更津鍼灸治療院は、幅広く症状に対応できるようにするため、『保険適用』は取り入れておりません。

鍼灸 保険適用とは?制度の概要と仕組み
健康保険制度下で「はり・きゅう」が給付対象となる条件
鍼灸が健康保険で認められるのは「療養費制度」と呼ばれる仕組みを通じてです。これは、医師による同意書をもとに一部の疾患に対して適用されるとされています。具体的には、腰痛症や神経痛、五十肩などの慢性的な症状が対象であるといわれています。こうした条件が整うことで、施術にかかる費用の一部を健康保険で補える可能性が出てきます。自費と比べて経済的な負担を軽減できる点が大きな特徴とされています。
引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
「受領委任払い」と「償還払い」の違い
鍼灸の保険利用では、「受領委任払い」と「償還払い」という2つの方法が存在します。受領委任払いは、患者さんが窓口で自己負担分だけを支払い、残りは施術所が直接保険者に請求する仕組みです。一方で償還払いは、いったん全額を支払ってから、患者さん自身が保険者に申請して払い戻しを受ける形です。一般的には、受領委任払いのほうが手続きが簡便で利用しやすいとされていますが、地域や保険者によって運用が異なる場合もあるといわれています。
保険適用が認められるまでの背景制度・法的根拠
鍼灸が公的保険に位置づけられるようになった背景には、古くからの臨床実績と、国民医療における役割があると説明されています。厚生労働省が定める療養費制度によって、特定の疾患に限り保険給付の対象とされているのです。これは国の法令に基づいた制度であり、自由診療と区別して運用されています。制度化の背景には、慢性疾患で悩む方々の負担を少しでも減らす狙いがあったといわれています。
#鍼灸
#保険適用
#療養費制度
#受領委任払い
#償還払い

対象疾患・条件:どの症状なら保険が使えるか?
国が定める対象疾患一覧
鍼灸が保険適用となるのは、厚生労働省が定める「療養費制度」に基づいた場合とされています。対象となるのは、神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頸椎捻挫後遺症、頸腕症候群など、慢性的で日常生活に支障をきたしやすい疾患だと言われています。これらの疾患に該当すれば、医師の同意書をもとに施術を受ける際、保険の利用が認められることがあります。
引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
対象とならない症状例
一方で、肩こりや美容目的の鍼灸、単なる疲労やリラクゼーションを目的とした利用は、保険の対象外とされています。例えば「仕事で疲れたから少し楽になりたい」というケースや「小顔や美容鍼をしたい」といった理由では適用できないといわれています。つまり、日常的な不調を和らげたい場合は自費での施術となることが多いようです。
医師の同意書が必要な理由・要件
保険を使って鍼灸施術を受けるには、医師の同意書が必要になります。これは、同じ症状に対して病院と鍼灸院の両方で二重に保険を利用してしまうことを避けるためと説明されています。また、同意書には症状や必要性が記載されるため、保険者が「適切な利用であるか」を判断する材料にもなるそうです。
併用不可ケースについて
医療機関で同じ疾患に対して検査や施術を受けている場合は、鍼灸での保険利用はできないとされています。たとえば腰痛で整形外科に通院中の場合、同じ腰痛に対して鍼灸で保険を併用することはできないという仕組みです。これは、制度が「補完的な施術」として位置づけられているためだと説明されています。
#鍼灸
#保険適用
#対象疾患
#医師同意書
#併用不可
手続きの流れと提出書類(ステップ別ガイド)
鍼灸院と相談 → 同意書様式入手
まずは通いたい鍼灸院に相談し、保険適用が可能かどうかを確認します。その際に必要となる「同意書様式」を受け取る流れが一般的だと言われています。鍼灸院によっては、書式をあらかじめ準備して渡してくれる場合もありますので、最初に確認しておくとスムーズです。
医師による触診・同意書発行
次に、医師の触診を受けて、保険適用が妥当か判断してもらいます。ここで重要なのが同意書の発行です。医師が「この症状に対して鍼灸施術が有効と考えられる」と認めた場合に限り、同意書が発行されるといわれています。これは制度上、二重での保険利用を防ぐ意味も持っているようです。
鍼灸院への提出・保険者への申請
同意書を受け取ったら、鍼灸院へ提出します。鍼灸院はその書類をもとに保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)へ申請を行います。患者さん自身が申請するケースもありますが、受領委任契約をしている院であれば、院が代行してくれることも多いと言われています。
有効期限と更新手続き
同意書には有効期限があります。一般的には6か月ごとに更新が必要とされています。期限が近づいた場合は再度医師の触診を受け、同意を得る流れになります。忘れずに更新を行わないと、保険適用外になってしまうこともあるため注意が必要と説明されています。
支払い方式選択(受領委任/償還)
支払い方法は「受領委任払い」と「償還払い」の2種類があります。受領委任払いは窓口で自己負担分だけを支払い、残りは鍼灸院が保険者に直接請求する仕組みです。償還払いは一度全額を支払ってから、患者さん自身が保険者に申請して払い戻しを受ける方式です。どちらを選ぶかは鍼灸院や患者さんの希望によって変わるといわれています。
引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
#鍼灸
#保険適用
#手続きの流れ
#同意書
#受領委任
費用・自己負担額の目安と最新相場
初回と再診の差分・料金構成
鍼灸を保険適用で受ける場合、料金は「初検料」と「施術料」に分かれているといわれています。初回は初検料が加わるため、再診時よりもやや高めになるケースが一般的です。施術料は施術部位の数によって変動し、複数箇所を対象とする場合には加算される仕組みです。そのため、初回と再診では費用に差が出ると説明されています。
自己負担割合(1割・2割・3割)のケース別例
自己負担額は加入している保険や年齢によって異なります。たとえば高齢者で1割負担の場合、施術料が1,000円なら100円前後の自己負担で済むとされています。一方、現役世代の3割負担では同じ施術料で300円程度になる計算です。具体的な負担割合は、保険証の種類や年齢区分に応じて決まる仕組みだと言われています。
地域差・保険組合による違い
鍼灸の保険適用は全国一律ではあるものの、実際の負担額や支払い方法は地域や保険組合によって細かな違いがあると説明されています。たとえば一部の組合では申請書式が独自に定められている場合もあり、必要書類や審査の厳しさに差が出ることもあるそうです。そのため、詳細は加入している保険者に確認することが大切だといわれています。
訪問鍼灸、加算適用時の注意点
体の状態によっては訪問鍼灸が利用できる場合があります。訪問施術には距離に応じた交通費や出張費が加算される仕組みとなっており、これも保険の範囲で取り扱われることが多いと説明されています。ただし、訪問が認められるのは歩行困難など一定の条件を満たすケースに限られるとされていますので注意が必要です。
明細の確認ポイント
鍼灸を保険で利用する際は、明細書を確認することが大切です。どの部位が施術対象となったのか、自己負担額が正しく計算されているかをチェックしておくと安心です。特に加算や訪問施術が入っている場合は、内訳を確認して疑問点があれば早めに鍼灸院や保険者へ相談すると良いといわれています。
引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
#鍼灸
#保険適用
#費用目安
#自己負担額
#訪問鍼灸
注意点・ケース別よくある質問と対策
保険適用外になりやすい落とし穴
鍼灸の保険適用には一定の条件があるといわれています。そのため、対象外になりやすいケースを知らずに利用すると「思っていたよりも費用が高かった」ということになりかねません。たとえば肩こりや疲労回復、美容目的などは保険の対象外とされています。また、病院で同じ症状の検査を受けている場合、鍼灸院での保険適用はできない仕組みです。この点を理解しておくことがトラブル防止につながるといわれています。
医師との関係性・同意取得が難しい場合
保険を使うためには医師の同意書が必要ですが、すべての医師が快く発行してくれるわけではありません。「鍼灸に効果があるのか疑問」と考える医師もおり、同意を得るのに時間がかかるケースもあるとされています。そうした場合は、鍼灸に理解のある医師を探す、または鍼灸院に相談して紹介を受けるなどの方法が現実的だといわれています。
保険者ごとの扱いの違い
協会けんぽ、組合保険、国保といった保険者によって、書類の書式や申請の流れに微妙な差があります。なかには独自の提出ルールを定めている組合もあるそうです。そのため「他の人はできたのに自分は通らなかった」ということもあり得ると言われています。利用を考えている方は、あらかじめ自身が加入している保険者に確認しておくと安心です。
保険適用と自費施術の混在について
鍼灸では保険適用となる施術と、自費扱いの施術を同時に行うこともあります。例えば腰痛は保険対象だが、美容目的の小顔鍼は対象外といった具合です。この場合、同じ日に両方を受けると「一部は保険」「一部は自費」と分けて支払いが発生するとされています。内容をきちんと確認しておくことがトラブルを避けるコツです。
Q&A形式でよくある質問
Q. 肩こりには保険が使えるの?
A. 一般的に肩こりだけでは対象外とされています。ただし頸腕症候群などに該当すれば認められることもあると言われています。
Q. 病院と鍼灸院を併用できる?
A. 同じ症状での併用は不可とされています。例えば腰痛で整形外科に通院中であれば、その腰痛で鍼灸保険を使うことはできないと説明されています。
Q. 更新はどのくらいの頻度?
A. 多くの場合、6か月ごとに医師の再同意が必要とされています。
引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
#鍼灸
#保険適用
#注意点
#よくある質問
#同意書

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています





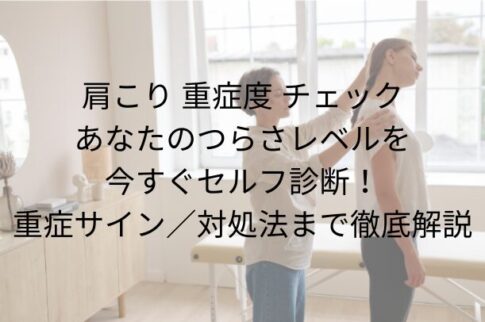




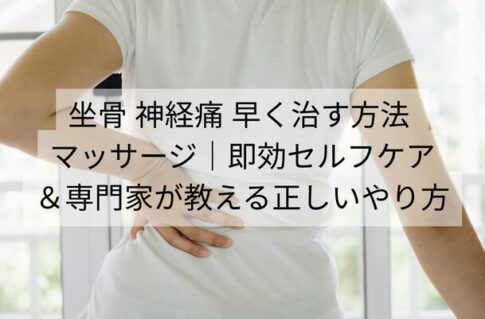














コメントを残す