筋肉痛のメカニズムとは?
筋肉痛の原因:筋繊維の微細な損傷と修復過程での炎症反応
筋肉痛は、運動やトレーニングによって筋繊維に微細な損傷が生じ、その修復過程で炎症反応が起こることが主な原因とされています。この炎症反応により、ブラジキニンやヒスタミンなどの発痛物質が生成され、神経を刺激して痛みを引き起こすと考えられています。
筋繊維自体には痛覚がないため、損傷直後には痛みを感じません。しかし、炎症が進行し、発痛物質が筋膜や周辺組織に到達することで、痛みとして認識されるようになります。このプロセスには時間がかかるため、筋肉痛が遅れて現れることがあります。
また、筋肉痛には「即発性筋痛」と「遅発性筋痛」の2種類があります。即発性筋痛は運動中や直後に感じる痛みで、乳酸の蓄積や筋肉の酸性化が関与しているとされています。一方、遅発性筋痛は運動後数時間から数日後に現れる痛みで、筋繊維の損傷とそれに伴う炎症が主な原因と考えられています。
これらの情報は、以下の参考記事を基にしています。
-
「筋肉痛の症状・原因|くすりと健康の情報局」
引用元:https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/symptom/39_kinnikutsu/アリナミン健康サイト+3第一三共ヘルスケア+3第一三共ヘルスケア+3 -
「筋肉痛の原因とは? 肩こり・腰痛・筋肉痛 トクホン 大正製薬」
引用元:https://brand.taisho.co.jp/tokuhon/body_pain/kinnikutsu001/Starter Kit+1大正健康+1 -
「筋肉痛があるとき筋トレはOK?痛みの原因や対策も解説 – アリナミン」
引用元:https://alinamin.jp/tired/musclepain-muscletraining.html疲れたあなたのカラダにアリナミン | アリナミン+1疲れたあなたのカラダにアリナミン | アリナミン+1アリナミン健康サイト+2疲れたあなたのカラダにアリナミン | アリナミン+2疲れたあなたのカラダにアリナミン | アリナミン+2
#筋肉痛の原因 #筋繊維の損傷 #炎症反応 #遅発性筋痛 #即発性筋痛
冷やすべきタイミングと方法
急性期(運動直後〜2〜3日以内)の炎症期には冷却が有効
筋肉痛が発生した直後から2〜3日以内の期間、いわゆる「急性期」では、患部を冷やすことが推奨されています。この時期は、筋肉の微細な損傷により炎症が起こり、痛みや腫れ、熱感が生じやすいとされています。
ただ、あくまでも冷やすのは患部のみです。大きめの氷嚢などで患部を覆いすぎると、正常な部位まで冷やすこととなり、治癒を阻害してしまいます。クリッカーなど局所的に冷やせるものを利用するのがおすすめです。
「昨日のトレーニングで筋肉痛が…」と感じたとき、患部が熱を持っている場合は、冷やすことが推奨されています。急性期とは、筋肉痛が発症してから約2〜3日以内の期間を指し、この時期は炎症反応が活発で、患部に腫れや熱感、痛みが生じやすいとされています。
患部が熱を持っている、腫れている場合の対処法
患部に熱感や腫れがある場合、冷却が有効とされています。冷やすことで血管が収縮し、炎症を抑える効果が期待できます。
「触ってみたら、いつもより熱いかも…」と感じたら、炎症が起きているサインかもしれません。このような場合、冷やすことで炎症を抑える効果が期待できます。逆に、温めてしまうと炎症が悪化し、痛みが増す可能性があるため、注意が必要です。
氷のうや冷却シートを用いた適切な冷却方法
冷却方法としては、氷のうや冷却シートの使用が一般的です。氷のうを使用する場合は、氷をビニール袋に入れ、空気を抜いて密閉し、直接肌に当てると凍傷のリスクがあるため、薄いタオルなどで包んで使用します。冷却時間は10分が目安とされています。
冷却シートを使用する場合は、メントールや水分が多く含まれており、1回貼ると6〜8時間ほど冷やせるとされています。運動後すぐや、シャワーを浴びた後に貼って、次のシートは寝る前に貼り替えて、朝起きて再び貼り直すといったケアが効果的とされています。
冷やしすぎは逆効果となる場合があるため、冷却時間や頻度には注意が必要です。
引用
miyagawa-seikotsu.com
New-HALE|ニューハレ+1FUNQ [ ファンク ]+1
#筋肉痛の冷却方法 #急性期の対処法 #氷のうの使い方 #冷却シートの活用 #炎症期のケア
温めるべきタイミングと方法
慢性期(炎症が治まり、こわばりや重だるさがある場合)には温熱療法が効果的
筋肉痛が発症してから数日が経過し、炎症が治まった後の「慢性期」では、患部を温めることが推奨されています。この時期には、筋肉のこわばりや重だるさが感じられることが多く、温熱療法によって血行を促進し、回復をサポートする効果が期待されています。
「昨日のトレーニングで筋肉痛が…」と感じたとき、患部が冷たく感じる場合は、温めることが効果的とされています。慢性期とは、筋肉痛が発症してから約2〜3日以降の期間を指し、この時期には炎症が治まり、筋肉のこわばりや重だるさが主な症状となります。
38〜40℃のぬるめの入浴や温湿布の活用
温熱療法の方法としては、38〜40℃のぬるめのお湯に15〜20分程度浸かる入浴や、温湿布の使用が一般的です。入浴は全身の血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果が期待されています。温湿布は、患部に直接貼ることで局所的に温めることができ、筋肉のこわばりを緩和するのに役立ちます。
「お風呂に入ってリラックスしたいな」と感じたときは、ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることをおすすめします。また、温湿布を使用する際は、低温やけどに注意し、長時間同じ場所に貼り続けないようにしましょう。
全身を温めることで血行を促進し、回復をサポート
全身を温めることで、血行が促進され、酸素や栄養素が筋肉に行き渡りやすくなります。これにより、筋肉の修復が進み、回復がサポートされるとされています。また、温熱療法にはリラックス効果もあり、ストレスの軽減にもつながると考えられています。
「最近、筋肉痛がなかなか取れないな」と感じたときは、全身を温めることで回復を促進することが期待されています。ただし、持病がある場合や体調が優れない場合は、医師や専門家に相談することをおすすめします。
引用
戸田はれのひ整骨院+1mother+1
戸田はれのひ整骨院
#筋肉痛の温熱療法 #慢性期の対処法 #ぬるめの入浴 #温湿布の活用 #全身の血行促進
冷やす・温めるの判断基準と注意点
患部の状態(熱感、腫れ、痛みの質)による判断
筋肉痛が発生した際、冷やすべきか温めるべきかの判断は、患部の状態に基づいて行うことが推奨されています。
-
熱感や腫れがある場合:患部が熱を持っていたり、腫れている場合は、炎症が起きている可能性があるため、冷やすことが推奨されています。
-
こわばりや重だるさがある場合:炎症が治まり、筋肉のこわばりや重だるさが感じられる場合は、温めることで血行を促進し、回復をサポートする効果が期待されています。
判断に迷った場合は、患部を触ってみて、熱感があるかどうかを確認することが一つの目安となります。
冷やしすぎや温めすぎによる逆効果のリスク
冷却や温熱療法は、適切に行うことで効果が期待されますが、過度に行うと逆効果となる可能性があります。
-
冷やしすぎ:長時間の冷却は、血行不良を引き起こし、筋肉のこわばりを増す可能性があります。
-
温めすぎ:炎症がまだ残っている状態で温めると、炎症反応が強まり、痛みが増す可能性があります。
冷却や温熱療法を行う際は、時間や温度に注意し、適切な方法で行うことが重要です。
自己判断が難しい場合は専門家への相談を推奨
筋肉痛の状態や症状は個人差があり、自己判断が難しい場合もあります。そのような場合は、整形外科や整骨院などの専門家に相談することが推奨されています。専門家の指導のもと、適切な対処法を選択することで、早期回復が期待されます。
引用
井尻整形外科|神戸市垂水区
みやがわ整骨院
246整體
#筋肉痛の判断基準 #冷やすタイミング #温めるタイミング #冷却と温熱の注意点 #専門家への相談
筋肉痛の予防と回復を促進する生活習慣
適切なストレッチや軽い運動による血行促進
筋肉痛を予防し、回復を早めるためには、日常的なストレッチや軽い運動が効果的とされています。運動前後にストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性が向上し、血行が促進されると考えられています。これにより、筋肉への酸素や栄養素の供給がスムーズになり、疲労物質の排出も促進されるとされています。
例えば、ウォーキングやヨガなどの軽い運動を日常的に取り入れることで、筋肉の緊張を和らげ、筋肉痛の発生を抑える効果が期待されています。また、運動後のクールダウンとしてストレッチを行うことで、筋肉の回復をサポートすると言われています。
「運動をする前と後にストレッチを行うと、ケガや筋肉痛を予防することができます。」
引用元:Starter Kit
たんぱく質やビタミンB群の摂取で筋肉の修復をサポート
筋肉の修復と成長には、たんぱく質とビタミンB群の摂取が重要とされています。たんぱく質は筋肉の主成分であり、運動後の筋肉の修復に必要不可欠です。また、ビタミンB群はエネルギー代謝やたんぱく質の合成に関与し、筋肉の回復をサポートすると考えられています。
具体的には、鶏肉、魚、大豆製品、卵などのたんぱく質を含む食品や、豚肉、レバー、バナナ、玄米などのビタミンB群を豊富に含む食品をバランスよく摂取することが推奨されています。
「筋肉の合成にも関わるビタミンDは魚やキノコに多く含まれますが、日光を浴びることでも体内で合成されます。筋肉疲労に効果的なビタミンB群は動物性食品に多く含まれています。」
引用元:Starter Kit
十分な睡眠と休息の重要性
筋肉の回復には、十分な睡眠と休息が欠かせないとされています。睡眠中には成長ホルモンの分泌が活発になり、筋肉の修復や再生が促進されると考えられています。また、適切な休息を取ることで、筋肉への過度な負担を避け、疲労の蓄積を防ぐことができます。
一般的に、成人は1日7〜8時間の睡眠が推奨されていますが、個人差があるため、自分に合った睡眠時間を確保することが重要です。また、睡眠の質を高めるために、就寝前のリラックスや規則正しい生活習慣を心がけることが効果的とされています。
「筋肉の修復は睡眠中に進行するため、十分な睡眠を取ることも大切です。」
引用元:leanomos.com
#筋肉痛予防 #ストレッチ習慣 #たんぱく質摂取 #ビタミンB群 #睡眠と休息

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。
怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。
体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

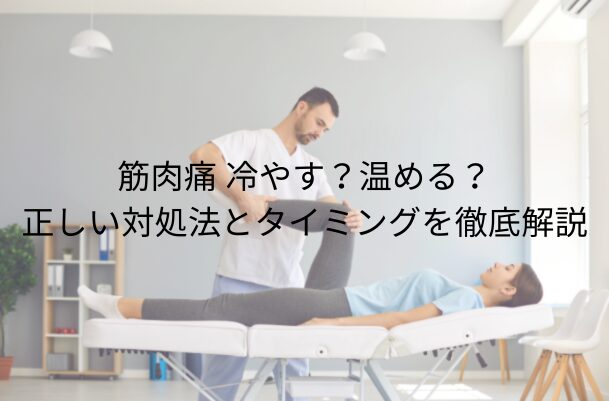



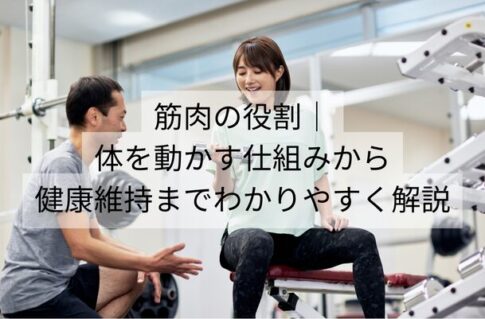




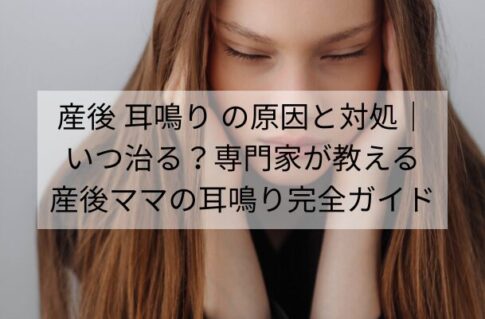





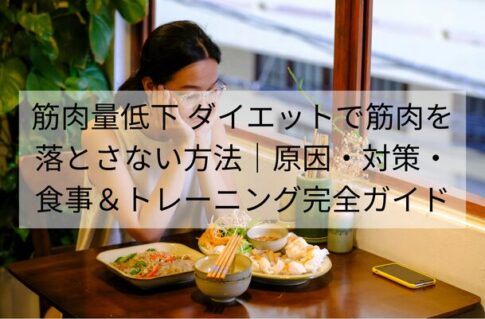
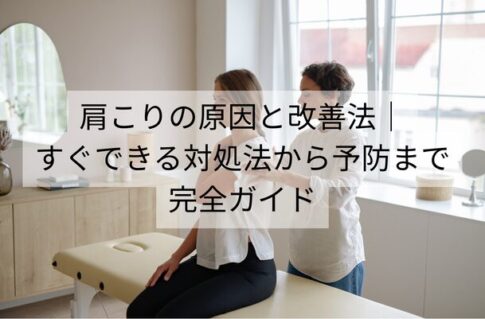
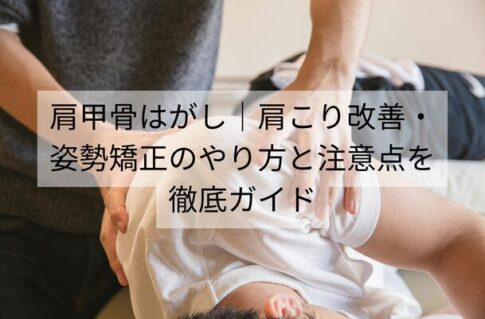
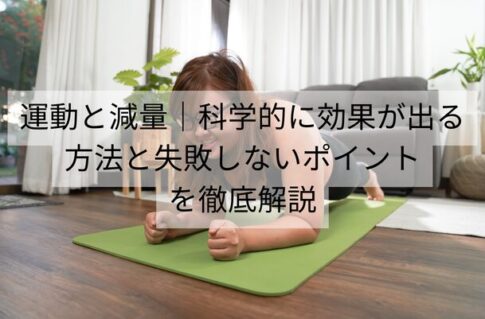




コメントを残す